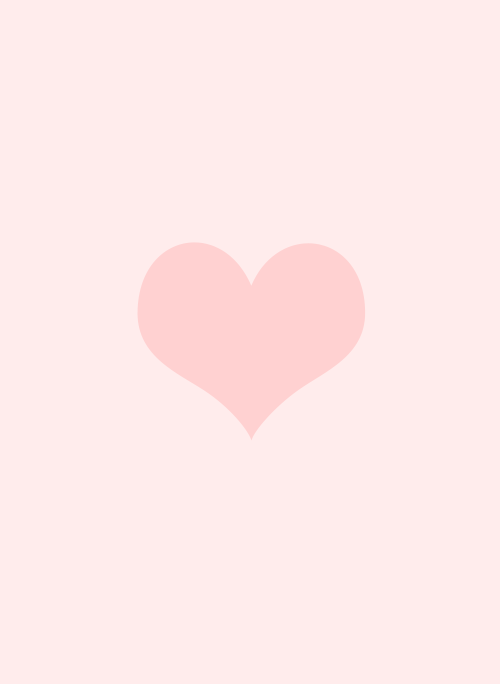【短】退屈なX'mas
「あっ、私の……!先輩、くれるって言ったじゃないですか」
先輩が例のケーキを、誰に断りもなく、頬張っていた。
「ああ、やるよ。半分。いいだろ、半分こ?」
「……」
先輩はどこまでもズルい気がした。
けれど、さっきまであれほど憎かった先輩の笑顔を、許したくなるからなんだか都合がいい。
だから先輩は、自然な“ワル”。
自然だからこそ許してしまう。
……だって、子供みたいに無邪気に笑うんだもん。
だから私もつられて笑った。
「顔赤いぞ、バカ」
「じゃあ先輩もバカですね」
「……」
先輩は何も言い返してこない。
それに私も、もうケーキにはこだわってない。
先輩とこうしてクリスマスイヴの夜に、こうして二人で憎まれ口だとしてでも喋っていることが、
すごく幸せだから。
――三時間前。
「あ、あのっ。もし、良かったら……メールアドレス、登録してください!」
先輩に対し、あきらかに私にもわかるような、
ありありな好意を持って近づいてくる、客。
きっと先輩も、この子の好意には気付いているんだろう。
勇気ある客。
もうやめて。どうか。と願っていた。
「ありがとうございました」
先輩は、どんなお客さんにも、丁寧な言葉と優しい笑顔で見送った。
メールアドレスの受けとりを先輩が、断った時点で、よし。としていたけれど。
この時も私はまだ、先輩への想いに気付かずに。
本当は、この時から恋の麻薬……“嫉妬”に、溺れてしまっていたのかも。
ほんの、三時間後に気づいたことでした。
Fin.