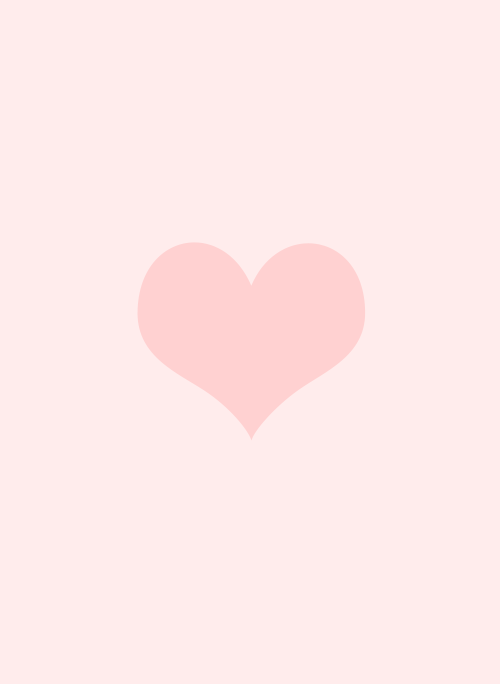下僕系男子
すっかり忘れていたけど、早坂くんは私のことが、好きなんだよね。
みやびのようなかわいい男子が自分なんかを好きになってくれるとは、泣き顔を見ても信じられない面がある。
「なぁ、俺帰ったほうがいいムード?これ」
侑が気まずそうな顔をして席を立とうとしたため、思い切り踵で足を踏みつけ、なんとか阻止した。
一人になってしまっては、昼休みの時のようにまた逃げ出してしまいそうだ。
侑は仕方ないな、とでも言いたげなため息をついて、視線を窓の外に広がる空へと移した。
相変わらず雲一つない、青い空。
「十瀬さんが好きです」
みやびの透き通った声が響き渡る。
その声は千夏の耳にも、侑の耳にもはっきりと届いた。
みやびはなぜ、自分を好きになったのだろう。
その疑問が、口を開こうとするたびにガムテープのように貼りつく。
「なんで千夏なんだ?」
千夏の代わりに侑が訊いた。
視線は空へ向けたまま。
「十瀬さんは、僕の憧れでした」
でした、ということは今は違うということだろうか。
それよりも、私のどこに憧れたんだろう。
謎は深まるばかりだ。
「取り柄が一つもないこいつのどこに憧れたんだよ」
かなり失礼なことを言っているけど、私の訊きたいことをすべて当てている。
時折思うが、侑はテレパシーを使えるのかもしれない。
「それは……」
みやびは照れたように俯いた。
恥ずかしがるようなところに憧れられたのかとこちらが心配になる。
「おまえ、そんなんだからかわいいって言われるんだよ」
「なっ。それとこれとは関係ありません!」
「大アリだっつの」
みやびはそのかわいさのあまり、本気で男子から告白をされたことがあるらしい。
あくまで噂だったが、この様子だと事実と受けとるのが妥当だろう。
「第一、なんで福丸くんに言わなきゃならないんですか」
「あ?俺は千夏の保護者だからな」
「身に覚えがないよ」
「バカ野郎。例えに決まってんだろ」
例えだとしても、侑が保護者なんて嫌だな。
どちらかといえば、私が保護者だよ。
――私がお母さんだね。
そんなような話をいつかしたことがあった気がする。
思い出しかけて、やめた。
「今日バイトなんだけど、帰っていいか」
大きなあくびをしながら、侑は次こそ席を立った。
おいて行くつもりなのか、というような視線を千夏が送ると、侑はその手を引いた。
「こいつも連れて帰るからな」
「ちょっ」
「まぁまぁいいじゃねーか。どうせ明日も学校はあるんだぜ」
「一つだけ」
みやびは、侑に腕を引かれる千夏の目を見つめた。
ただ見つめるのとは違って、瞳のさらに奥を見つめられている感じがする。
こちらの考えがすべて読まれてしまいそうだ。
「返事を、くれませんか」
少し強ばっているけど、まっすぐな声。
ここで何も言わないのはみやびの気持ちを踏みにじることと一緒だ。
もともと返事は一つだけ。
決して嫌いではない。
だけど、私はあまりにも早坂くんを知らない。
早坂くんは私に憧れを抱くようなのだから、少なからず私の何かを知っているのだろう。
でも私は何も知らない。
好きな物、誕生日、血液型、特技に趣味。
“クラスメートの友達”それ以上にもそれ以下にも思ったことはなかった。
だから知ろうともしなかったし、知りたいとも思わなかった。
この甘味処が早坂くんの家系が経営しているというのも、ついさっき知ったばかり。
なんていろいろ並べてみたけど、返事は何も変わらない。
「ごめんなさい」