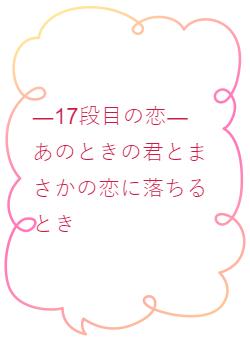心も体も、寒いなら抱いてやる
「私ね、俊がそのチョコレートをいつまでたっても食べないから、いらないのかと思って食べちゃったの。そしたら俊、すごい怒っちゃって。それこそ涙浮かべながら怒ったのよ。だからチョコぐらい買って返すわよって逆切れしたらよけいに怒って、それはみのりからもらったチョコなんだ!って」
そこで花蓮はその時の俊を思い返して、ふふっと笑った。
「みのりはね、俊の初恋の人なのよ」
「まじ……?」
「みのりはタンポポみたいなんだって、小学生の頃よく自慢してた。俊はね、タンポポの花が大好きなの」
強い風が吹き、花蓮の長い髪が舞い上がる。
「じゃあさ、俺も告白する。おれの初恋は花蓮さん」
「え?」と開きかけた唇を、太一が唇でふさいだ。
―――完―――
そこで花蓮はその時の俊を思い返して、ふふっと笑った。
「みのりはね、俊の初恋の人なのよ」
「まじ……?」
「みのりはタンポポみたいなんだって、小学生の頃よく自慢してた。俊はね、タンポポの花が大好きなの」
強い風が吹き、花蓮の長い髪が舞い上がる。
「じゃあさ、俺も告白する。おれの初恋は花蓮さん」
「え?」と開きかけた唇を、太一が唇でふさいだ。
―――完―――
< 209 / 209 >
この作家の他の作品
表紙を見る
にわかテニスファンの透子が会社のベネフィットを利用して通い始めた高級テニススクールはイケメンコーチで有名なスクールだった。
その中でなんといっても有名なのが、スクールの運営会社の御曹司でもある龍道新コーチ。
龍道グループの御曹司であり、モデルを超える容姿の新はスクールの広告塔でもあった。
常にキャンセル待ちの新のクラスに、なぜかすぐに入れることになった透子。
そしてなぜか強引に近づいてくる龍道コーチ。
”可能性がない男に気持ちは動かない”と思っていたはずなのに、いつの間にか期待し、気づけば望みのない恋に泣いていた。
「僕の警告をきかないからだよ」
同僚の田淵が透子の涙を指で拭って優しくなぐさめる。
と、そこに突如、新が登場。
「俺の彼女になにしてんの?」
「え?」
10年後に再会した君は、容姿端麗で金持ちで、口が悪いけど優しくて、そしてとんでもなく遠くなっていた、はずなのだけど――。
表紙を見る
「またか」
転校初日に気づいてしまった。
ここにも“いじめ”を楽しむ人がいることを。
いじめと言うイベントには誰も関わり合いたくなくて、
誰も見ないふり。
でも私は我慢できない。
なぜなら自分もさんざん「ターゲット」になってきたから。
知らん振りなんてできないし、しない――。
そんな勝ち気でまっすぐな妹が兄・強は心配でたまらない。
普段はロックアイスのように美しくクールな強だが、勝子にだけは溶けかける。
「勝子は俺が守る」と決めている強。
けれどそこにもう一人、勝子を見守るナイト――勇――が割り込んでくる。
「強さん、俺、勝子をかっさらっていいですか?」
勝子の幼い頃の過去、勇と勝子の意外な関係、そして兄・強の勝子への気持ち――。
勝子は本当のことを知ったとき、誰の心をつかむのか。
真田勝子(さなだかつこ)
17歳 私立女子高2年生
勝ち気で真っ直ぐな心を持つ。
幼い頃、ある悲惨な事件に巻き込まれたが、その自分の過去を
まだ知らない
真田強(さなだごう)
勝子の兄 25歳
冷静でロックアイスのようにクールな男。
ただし勝子のこと以外では。
神谷勇(かみやいさむ)
大学1年生 勝子の一番親しい男友だち。
友だちからの脱出を図る。
実は勝子と深いかかわりがある?
表紙を見る
それは同じ部署の青野君と一緒に少し遅めのランチをとってオフィスに戻るときのこと。
青野君は私より2つ年下、27歳の同僚だ。仕事はそつなくこなす。何でも頼んだことは「いいですよー」と緩く、快く、引き受けてくれる。
残業してれば手伝ってくれるし、荷物を運んでいれば「僕持ちますよ」と運んでくれて、ちょっと飲んで帰ろうよと言えばやっぱりたいていは「いいですよー」とつきあってくれる。
どんなシーンでもいつも「いいですよー」と言う感じ。
不潔には見えないので許されている、目にかかるほどのぼさぼさの髪と、今時あまりみかけない茶色の分厚いフレームの古臭い眼鏡。いつも着ているペラッとしたスーツはまるで制服のようだ。つまりもパッとしない感じなのだけど、それでもなぜかそれほどダサく見えないのは細身で頭が小さくて、目鼻立ちがすっとしているせいルックスのせいか。
「青野草汰」という苗字から、私は青野君を見ると野原でさわさわと風に揺れている野草を思い浮かべてしまう。どんなときでも風に身を任せて楽しんでいるような。
他の女子たちの評判も悪くない。ただ男っぽさが感じられない。
「青野くんて優しいし雰囲気も悪くないのに、パンチがないよね」
数日前、エレベータの前で一緒になった青野君にそう言ってみた。
「パンチ?」
「うん。なんかさ、もう少しグイッとしたところがあればすごいモテそうなのに」
今考えれば、自分のことを顧みず随分と身の程知らずなことを言ったものだと思う。青野君は気に留めた風もなく、ちょっと頬を緩めただけだったけど¥。
ひょうひょうとして優しくて、そばにいると安心できる青野君。
こんなに私のお願いを何でも聞いてくれるのは、もしかして私のこと好きだったりして。でも残念だけど彼氏には物足りないよね、なんて思っていた。
それなのに――
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…