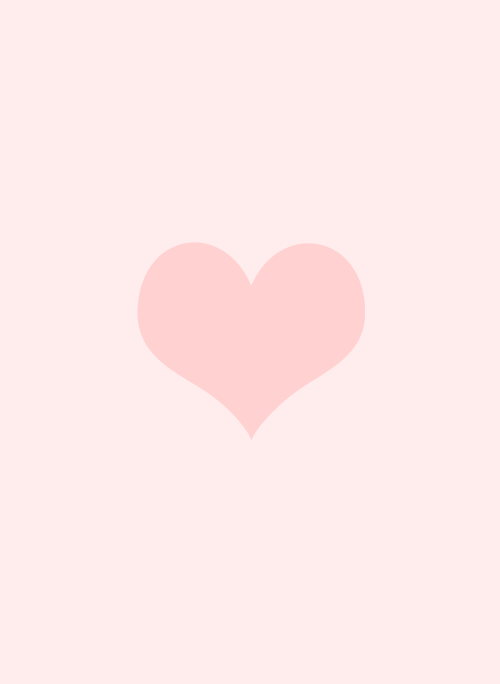切子のグラス
掌編
魚子と書いて、ななこ、というのが私の名前だ。
職人だった祖父がつけた、名。
私は手にした小さな紙片を見つめた。角が傷んで小さな皺を、目に見えないくらい小さな皺を蓄えている。私はそれを、右手の親指ですすすと、もう一度伸ばすように擦った。
その紙片は、名刺大の大きさで、── というか名刺で ── 東京とは名ばかりの鬱蒼とした山を彷彿とさせる住所と、工房主の名を一文字とった工房の名前「刻」、そして、工房の主の名「橋本刻奔 Tokiwa HASHIMOTO」とゴシック体で書かれていた。
彼は、祖父のお弟子さんだった人の息子さんで、私よりも一回も、いや、一回り以上年が下だ。雑誌の編集をしている友人に「若い職人さんを紹介して欲しい」頼まれて、確か橋本さんの息子さんが・・・と紹介し、祖父の命日には必ず心を配ってくださる橋本さんにご挨拶もしたいし、と工房へ訪問したときに初めて会った。初めて、というのはでも、実はそうではなかった、というのは後から知った話で、私が彼に初めて会ったのは彼がまだ赤ん坊で橋本のおじさんに抱かれていたのだと言う。でも、もう覚えてもいない。
魔が差した、と言う言葉が正しい。
一枚板のカウンターで、彼が切ったという切子は天井からあっちにこっちに向かう光を拾って輝いていた。杉の香りのする酒(ささ)が甘く、その切子に口づけるたびに彼がまるで私が彼自身に口づけたかのようにある種の熱を帯びた視線を向ける。
ああ、嘘ではなかったのだ、と、世渡り上手な橋本のおじさんの昔話がおべんちゃらな訳ではないと知りながらやはり心のどこかで嬉しくて、そして、彼が今でも私をそんな風に見るというのが嬉しかった。失ってしまったものをまだ手にしているようなそんな夢を見たのだ。
それと同時に、私は、丸ごと彼に差し出すほど、理性を失っていた訳ではなかった。かえってそれがいけなかったのだ、と今は思う。思わせぶりな言葉だけを紡いでそして、逃げた。
ほんの一年半ほど前に、私が彼に最後に言った言葉と、彼が私に言った言葉が何度も何度も私の脳裏を行き来する。
「わたしがもっと若くて・・・・。あなたが欲しがるなにかを満足に与えられたならよかったのに・・・・。」
「僕は、何も欲しくないよ。でも、たとえば僕が、あなたから何かを欲しがったとして、それを、若かったあなたよりもいまのあなたから欲しいのだと言っても?」
彼の熱を帯びた視線が私の唇を捉えた瞬間を何度も思い出す。この一年半の間に、もう何度も何度もその言葉も、その一瞬の彼のモーションも、何度も何度もリフレインして、私は記憶というのは擦り切れるものだとずっと信じてきたけれど、一生擦り切れない記憶というものがもしかしたら存在するかもしれないと、ほとんど信じ始めていた。けれども、一年半という期間がどれほど短い期間なのかを、私はもう、十分に知ってもいる。
角の傷んだ紙片を私は今一度左手で撫でた。それから、何事もなかったように、大きな仕事用のトートバッグのモバイル用ポケットにしまった。
彼の幼き日に、彼の目に、どんな風に私が映っていたのか。
けれどももう、私は、あの頃のように若くはない。
叶えたことよりも、喪ったことの方が多い人生で、自分がどんなにくたびれてしまったのかを、誰よりも知っているのだ。
「いまのあなたから欲しいのだと言っても?」
いまの私が彼に、この先にいくらも叶えなければいけないことがある彼に、何を与えられるというのだろう。
あの後、
「ななこ」
と、彼の唇は動いた。
彼が「魚子」と私を呼ぶとき、どんな声で呼ぶのだろう。
きっと、叶うことのない、小さな夢を抱く。
「魚子」と、私は、自分を呼んでみる。
彼の声を、何度も思い出しながら、「ななこ」と自分を呼んでみる。
月明かりは、魚子模様に揺らいでいる。
彼の切った美しいグラスは、酒(ささ)も、水も、抱くことはなく、ただ、月明かりをうけて静かに揺らぎだけを生んでいる。
「切子のグラス」終わり
職人だった祖父がつけた、名。
私は手にした小さな紙片を見つめた。角が傷んで小さな皺を、目に見えないくらい小さな皺を蓄えている。私はそれを、右手の親指ですすすと、もう一度伸ばすように擦った。
その紙片は、名刺大の大きさで、── というか名刺で ── 東京とは名ばかりの鬱蒼とした山を彷彿とさせる住所と、工房主の名を一文字とった工房の名前「刻」、そして、工房の主の名「橋本刻奔 Tokiwa HASHIMOTO」とゴシック体で書かれていた。
彼は、祖父のお弟子さんだった人の息子さんで、私よりも一回も、いや、一回り以上年が下だ。雑誌の編集をしている友人に「若い職人さんを紹介して欲しい」頼まれて、確か橋本さんの息子さんが・・・と紹介し、祖父の命日には必ず心を配ってくださる橋本さんにご挨拶もしたいし、と工房へ訪問したときに初めて会った。初めて、というのはでも、実はそうではなかった、というのは後から知った話で、私が彼に初めて会ったのは彼がまだ赤ん坊で橋本のおじさんに抱かれていたのだと言う。でも、もう覚えてもいない。
魔が差した、と言う言葉が正しい。
一枚板のカウンターで、彼が切ったという切子は天井からあっちにこっちに向かう光を拾って輝いていた。杉の香りのする酒(ささ)が甘く、その切子に口づけるたびに彼がまるで私が彼自身に口づけたかのようにある種の熱を帯びた視線を向ける。
ああ、嘘ではなかったのだ、と、世渡り上手な橋本のおじさんの昔話がおべんちゃらな訳ではないと知りながらやはり心のどこかで嬉しくて、そして、彼が今でも私をそんな風に見るというのが嬉しかった。失ってしまったものをまだ手にしているようなそんな夢を見たのだ。
それと同時に、私は、丸ごと彼に差し出すほど、理性を失っていた訳ではなかった。かえってそれがいけなかったのだ、と今は思う。思わせぶりな言葉だけを紡いでそして、逃げた。
ほんの一年半ほど前に、私が彼に最後に言った言葉と、彼が私に言った言葉が何度も何度も私の脳裏を行き来する。
「わたしがもっと若くて・・・・。あなたが欲しがるなにかを満足に与えられたならよかったのに・・・・。」
「僕は、何も欲しくないよ。でも、たとえば僕が、あなたから何かを欲しがったとして、それを、若かったあなたよりもいまのあなたから欲しいのだと言っても?」
彼の熱を帯びた視線が私の唇を捉えた瞬間を何度も思い出す。この一年半の間に、もう何度も何度もその言葉も、その一瞬の彼のモーションも、何度も何度もリフレインして、私は記憶というのは擦り切れるものだとずっと信じてきたけれど、一生擦り切れない記憶というものがもしかしたら存在するかもしれないと、ほとんど信じ始めていた。けれども、一年半という期間がどれほど短い期間なのかを、私はもう、十分に知ってもいる。
角の傷んだ紙片を私は今一度左手で撫でた。それから、何事もなかったように、大きな仕事用のトートバッグのモバイル用ポケットにしまった。
彼の幼き日に、彼の目に、どんな風に私が映っていたのか。
けれどももう、私は、あの頃のように若くはない。
叶えたことよりも、喪ったことの方が多い人生で、自分がどんなにくたびれてしまったのかを、誰よりも知っているのだ。
「いまのあなたから欲しいのだと言っても?」
いまの私が彼に、この先にいくらも叶えなければいけないことがある彼に、何を与えられるというのだろう。
あの後、
「ななこ」
と、彼の唇は動いた。
彼が「魚子」と私を呼ぶとき、どんな声で呼ぶのだろう。
きっと、叶うことのない、小さな夢を抱く。
「魚子」と、私は、自分を呼んでみる。
彼の声を、何度も思い出しながら、「ななこ」と自分を呼んでみる。
月明かりは、魚子模様に揺らいでいる。
彼の切った美しいグラスは、酒(ささ)も、水も、抱くことはなく、ただ、月明かりをうけて静かに揺らぎだけを生んでいる。
「切子のグラス」終わり