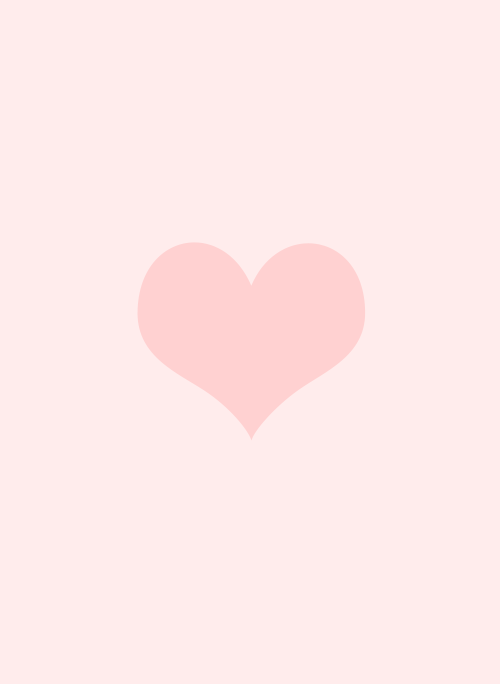悪人きどり
先生は困った顔で私を椅子に座らせた。
「…地道。お前いじめられているのか?」
「…はぁ…」
何時の話をしているのか。
困っただとか評価がどうのと先生はぶつぶつ呟く。
「俺もなぁ…ボーナス時期にこんなの困るんだよ」
< 7 / 7 >
この作家の他の作品
表紙を見る
虚勢を張ることでしか、自分を保てない全ての私に。
大丈夫と甘く溶かして、固まった心を抱きとめて。
そんな都合の良い夢を見ては目が覚めて、悪夢のような現実を生きる。
そんな日々をあなたは知っていますか。
表紙を見る
その昔、一人の男が怒りに我を忘れ、剣をとった。
村が鮮血に染まった理由は、男の腕ではなく飢饉に体が弱りきった者が多かった為であるが。
刃から肘へ滴る鮮血に、男はその刀身を眺め、浸ってしまった。
肉を断つ、その快感に。
仇の隣家へ、長い刃を地に引きずり、赤い血を顔につけ。
二件、三件、悲鳴が男を高揚させた。
逃げ惑う女の足を、命乞いする老人の腕を。
血しぶき舞うそこは、まさに地獄か。
橋を越え、隣村へ、山を越えさらに遠くへ。
いつしか男は狂った鬼、狂鬼(くるいおに)と呼ばれた。
悦が飽きへと変わる頃、なまくらとなりかけた刀身を、踏み付け、二つに裂いた。
刀を磨くという知識がない為であった。
奇しくもその行為が、すでに邪剣となったその刀の覚醒への引き金になってしまった。
二つになった刀は意思を持ち、いつしか男は刀の意思のまま人を切る真の鬼になってしまった。
邪剣が妖刀となるほど、人の血を吸った頃、男の生が終わりを迎えかけていた。
ほとんど不眠不休で人を狩る鬼となったが、その器はまだ、かろうじて人の姿をしていたた為であった。
だが、妖刀は持ち主の生が終わり、その役目を終えることを嫌がった。
あまりにも血を吸いすぎた妖刀は、次々に人の手にわたっては辺りを血に染め、持ち主を鬼へと変貌させていった。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…