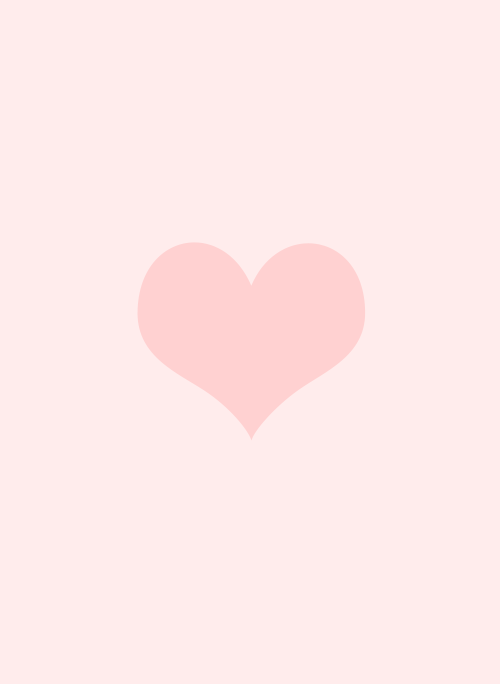チョコレートよりも。
真っ先に向かったのは体育館だった。全力で走ったせいで息が乱れたまま中に入る。
ボールの音はしない。どこかに行ってしまったのか、別のところを探したほうがいいのか見渡したその時。
入口と反対側の開いてるドアの隙間から人がもたれているのが見える。
「富永…」
間違いない。名前を口にすると競り上がる気持ちに足が体育館の裏口へと向かう。
走ったから脈が速いのか、緊張によるものなのかも分からない。
心臓の音が耳から頭までこだましている。
体育館の反対側まで来るとドアの前に座り込んでいる富永の姿がはっきりと見えた。
ボールを抱えて前を見据えているようにも見える。
「三宅…」
近づいてきた私に気づくと富永は少し驚いた顔をした。
「何してるの…」
「…練習」
「してないじゃん」
突っ込みを予想していたように富永はばつの悪い表情で頭をかいた。
「三宅こそ。こんなとこまでどうしたんだよ」
今度は私が狼狽える番だった。こっちを見る富永と目が合わせられない。
でも、もうここまで来てしまったら言うしかない。
「これ!」
あぁもう。どうして私はこんな言い方しかできないの。
意気地なし。ちゃんと言わないと後悔すると思ったから来たんでしょ。
自分を叱りつけるように富永の前まで歩いていく。
ドアから続く階段の下。少し見上げるように顔を上げると、若干緊張したような富永の顔。
「…作ったから、ビターのやつ」
「…おれに?」
「富永が言ったんでしょ、ビターがいいって」
「おう。言ったな」
「だから、これはあんたの」
早く受け取って欲しい。手が震えていることに気づかれたくない。
富永は立ち上がって私の正面まで降りてくる。
「これ、あいつに渡してたのと違うんだけど」
「…一緒なわけない…」
「なんで」
なんなの。もう、恥ずかしくて死にそうなのに。私の顔が赤いの気づいてるくせに。
「…これが本命だからっ」
耐え切れなくて左手の甲で顔を隠す。もう富永がどんな顔でこっちを見ているのかも見ていられない。
「…可愛すぎんだろ」
富永の小さい呟きを聞き返す間もなくチョコと一緒に引っ張られた。
どうやら富永の腕の中にいるらしいと分かった瞬間、体温が二度ほど上昇したのではないかと思うくらい一気に熱くなる。
「あ、の…」
「うるせぇ。びびらせやがって」
これだめだ。
抱きしめられるとこんなに体格差を感じるものなのかとか、心臓のどきどきがどっちのものか分からないとかどうでもいいこと考えてしまうくらいに富永の体温と声が近すぎてオーバーヒートしそう。
「言っとくけど、チョコのリクエストなんてお前にしかしないから」
「そう、なの」
ちょっと擦れ気味にそんなこと呟かれたら心臓もたないってば。
反射的に適当な相槌を返すとそれが気に食わなかったのか、富永は少し身体を離して至近距離で目を合わせた。
「好きな女にしか言うわけねーだろ」
チョコレートよりも甘い言葉に私は完全に打ち抜かれてしまうのだった。
-fin-
ボールの音はしない。どこかに行ってしまったのか、別のところを探したほうがいいのか見渡したその時。
入口と反対側の開いてるドアの隙間から人がもたれているのが見える。
「富永…」
間違いない。名前を口にすると競り上がる気持ちに足が体育館の裏口へと向かう。
走ったから脈が速いのか、緊張によるものなのかも分からない。
心臓の音が耳から頭までこだましている。
体育館の反対側まで来るとドアの前に座り込んでいる富永の姿がはっきりと見えた。
ボールを抱えて前を見据えているようにも見える。
「三宅…」
近づいてきた私に気づくと富永は少し驚いた顔をした。
「何してるの…」
「…練習」
「してないじゃん」
突っ込みを予想していたように富永はばつの悪い表情で頭をかいた。
「三宅こそ。こんなとこまでどうしたんだよ」
今度は私が狼狽える番だった。こっちを見る富永と目が合わせられない。
でも、もうここまで来てしまったら言うしかない。
「これ!」
あぁもう。どうして私はこんな言い方しかできないの。
意気地なし。ちゃんと言わないと後悔すると思ったから来たんでしょ。
自分を叱りつけるように富永の前まで歩いていく。
ドアから続く階段の下。少し見上げるように顔を上げると、若干緊張したような富永の顔。
「…作ったから、ビターのやつ」
「…おれに?」
「富永が言ったんでしょ、ビターがいいって」
「おう。言ったな」
「だから、これはあんたの」
早く受け取って欲しい。手が震えていることに気づかれたくない。
富永は立ち上がって私の正面まで降りてくる。
「これ、あいつに渡してたのと違うんだけど」
「…一緒なわけない…」
「なんで」
なんなの。もう、恥ずかしくて死にそうなのに。私の顔が赤いの気づいてるくせに。
「…これが本命だからっ」
耐え切れなくて左手の甲で顔を隠す。もう富永がどんな顔でこっちを見ているのかも見ていられない。
「…可愛すぎんだろ」
富永の小さい呟きを聞き返す間もなくチョコと一緒に引っ張られた。
どうやら富永の腕の中にいるらしいと分かった瞬間、体温が二度ほど上昇したのではないかと思うくらい一気に熱くなる。
「あ、の…」
「うるせぇ。びびらせやがって」
これだめだ。
抱きしめられるとこんなに体格差を感じるものなのかとか、心臓のどきどきがどっちのものか分からないとかどうでもいいこと考えてしまうくらいに富永の体温と声が近すぎてオーバーヒートしそう。
「言っとくけど、チョコのリクエストなんてお前にしかしないから」
「そう、なの」
ちょっと擦れ気味にそんなこと呟かれたら心臓もたないってば。
反射的に適当な相槌を返すとそれが気に食わなかったのか、富永は少し身体を離して至近距離で目を合わせた。
「好きな女にしか言うわけねーだろ」
チョコレートよりも甘い言葉に私は完全に打ち抜かれてしまうのだった。
-fin-