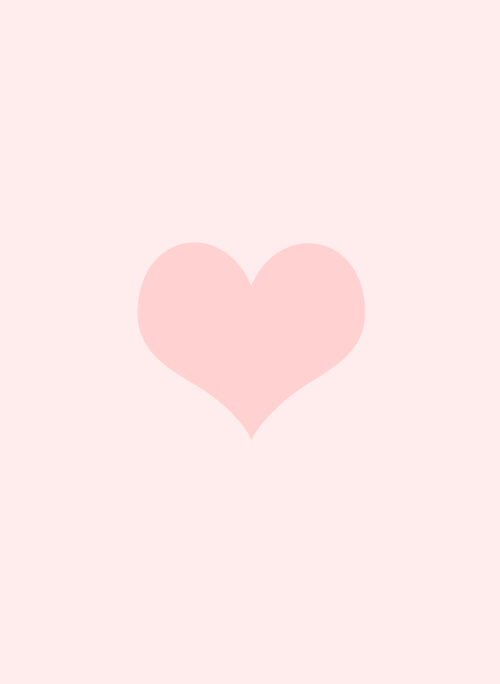散りゆく恋、はらはら
1
聞き慣れた足音。
振り向かなくたって、もうわかる。
彼が来た。
私の待ち人、杉崎雄大(すぎさきゆうだい)だ。
「そろそろ来る頃だと思った」
ニカッと笑ってみれば、彼はバツが悪そうに舌打ちをした。
これは照れ隠しだ。
(ふふ。かわいい)
ポケットに手を突っ込み、私の隣で少し微妙な距離を保ち歩みを止めた。
いつものことながら思う。
絶妙な距離感だ、と。
心地良くてもどかしくて、心が疼く。
そんな距離感。
「この間の、アレ。すごかったね」
「ホント、余(あまり)って遠慮ねえのな」
仏頂面をさらに極める彼、杉崎雄大。
私は構わず笑った。
「だって、杉がここに来たのはそれのためでしょ?」
「ふん……」
そっぽを向かれてしまった。
だから私はつい謝った。
「ごめんごめん。調子に乗った」
「つか、余もここにいるってことは、そういうことなんじゃねえの?」
そういうこと、というのは彼と同じ理由で、ここーー校舎裏の二人だけの秘密の場所にいる、ということ。
そしてその理由とは“傷心”に他ならない。
私と彼には、お互い思い人がいた。
もちろん、お互い片想い中で多分、失恋中だ。
ハートブレイクな出来事があった日には、こうしてこの場所へ来て、互いの傷を舐め合っていた。
「あ、白いお月さまが出てる!」
夜になれば灯籠のような色で輝くのに、明るいうちは白いだなんてまったく不思議だ。
「余……話そらしてんじゃねえよ」
少し離れた隣にいたはずの杉崎雄大が、いつの間にか向かいにいた。
私はドキッとした。
「言いたくないなら無理には聞かないけど。
でも俺だけ知らないのは、やっぱり不公平だよな」
それから空を見上げた。
今彼の目にも、あの白い月が映っているのだろうか。
だったら、少し切ない気がした。
同じ時に同じものを見ているのに、気持ちは別々なのだ。
同じにはなれないのだ。
それはすごく切ないことだ、と思った。
「うーん。不公平か。
でもさ、杉も自分から話したわけじゃないでしょ。あれはバレて当然。
なんせ、杉の顔に書いてたもん。百合(ゆり)さんが好き、ってね」
「か、書いてねえし! そんなの、ただのバカだろ……」
「うん。杉はバカだ」
「うるせ。余だってそうだろ。ここにいる時点で、そうじゃん」
「確かに……その通りだ」
私も往生際が悪くて意気地がなくて、バカだ。
そして私は、ありきたりで単純な質問を彼にしていた。
「杉はやめないの? 百合さんを好きでいるの」
「やめられたら、ここに来てないっての」
“だよね”
力なく笑いながら、やっぱりそうなんだ、と思った。
彼が百合さんを諦めるか、もしくは両想いになれば、彼はもうここへは来なくなる。
来る必要はなくなってしまう。
その時期はーー終わりはもう近づいていた。
そしてその音は、私の耳にしっかりと届いていた。
「そう言う余もそいつのこと、やめねえの?」
仏頂面がなくなり、真剣な面持ちで彼は尋ねた。
彼に同じ質問をしながら、思えば私自身そんなことは一度も考えたことがなかった。
“諦める”なんて、ありきたりで簡単な選択肢なのに。
「確かにそうだ。そうしたら、楽だよね」
「なんだそれ。その程度なのに、ここに通いつめてたのかよ。ヘンなやつ」
切れ長の冷たい目が、笑うと少し垂れ下がるそんな笑顔が好きだった。
仏頂面も拗ねるところも、照れ屋なところも、もちろん一途なところも、憎いくらい好きだった。
(そっか。杉を諦めればもう、この苦しみからも解放されるんだ)
そして杉崎雄大は百合さんを諦めない。
つまりは両想いになることを望んでいる。
複雑だとばかり思っていた迷路が今、きれいに照らしだされた。
「余?」
「へ? なに?」
「なに、じゃねえじゃん。それはこっちの台詞だよ」
「あれ……」
視界が霞んでいく。
目が熱くて、頬が濡れていく。
私、今おかしい。
「ったく、ためすぎなんだよ。余はいっつも。
俺がいるときくらい、気抜けよな」
涙のわけを、彼は決して聞こうとはしなかった。
私が導きだした答えはとても簡単で、あまりにもつらすぎた。
そう。
私はもうとっくに知っていた。
杉崎雄大と百合さんが両想いであることを。
知らないのは、多分彼だけ。
百合さんは熱烈なアプローチに根負けした結果、同じ学年の男の子と付き合いはじめた。
しかし、それは本心ではなかった。
百合さんの視線の先には何故か、いつも杉崎雄大がいた。
はじめは不思議だった。
だけど、彼氏がいるのに他の男子を見つめる理由なんて、きっとひとつしかない。
ーー好きだから
杉は本当はすごく優しい。
だから、私を独りにしないでいてくれた。
そしていつも側にいてくれた。
彼が百合さんと両想いになれば、もしくは彼女を諦めれば、私はこの場所で独りぼっちになる。
だから彼は、理由を見つけてはここへ来てくれた。
こんなことを彼に言えば“自惚れんな”なんて毒づかれると思うから、言わない。
だけど、多分そうなのだ。
だから私が、彼を解放してあげなければならない。
私が諦めさえすれば、彼はもう気兼ねなく、百合さんの元へいけるのだ。
今のままでは彼は、百合さんを諦めることも、百合さんに告白することもできない。
私が彼を縛りつけていたのだ。
「はは。自分のバカさ加減に呆れる」
「余ーー」
「杉の言う通り、諦めれば良かったんだよね」
「いや。はじめにそれ言ったの、余だけどな」
「こら。そこ、冷静につっこまないの」
グーで軽く殴るふりをした。
その時の彼の笑顔はとても印象的だった。
そしてふと思った。
彼はもう何もかもわかっているのではないか、と。
「さあて、と。じゃあ、これにて終わりにしますか」
「終わり?」
「そう。私は今日で、この恋を諦めるの。
もうおしまい」
いつもの笑顔で、いつもの調子で私は告げた。
「余。それは、本当に本心か?」
それなのに彼は見慣れない表情で、知らない声で私を掻き乱した。
「やだなもう。そんな辛気くさい顔しないでよ。本心だから」
おどけるしかできない私は本物の弱虫だった。
「わかった。ならもう、最後だな」
掴んでいた私の手を離した。
しかし、その部分は熱を帯びたままだ。
彼は決心を固めた目で、私をしっかりと見据えた。
「俺、百合に告白しようと思う。派手に当たって砕けてくるわ。
そしたらさ、その時はいつもみたいに笑ってくれよな。頼んだぜ、余」
「あ……あったりまえでしょ。任せなさいよ!」
泣きたくて、泣きたくてたまらなかった。
彼は本当にバカだった。
ただのお人好しだった。
大好きな彼をしあわせにできるのは、私しかいないのに片時の温もりがほしくて、私は彼を縛りつけていた。
手放す勇気がなかった。
諦める、というありふれた方法を見失うほど、私は臆病者になっていた。
「大笑いしてあげるからね! 泣くのもバカらしいくらいバカ笑いしてやる!」
「なんだよそれ。もはやただのバカじゃん」
最後だから、笑いたかった。
私の目に映るのも、彼の目に映るのも、互いの笑顔が良かった。
たとえ痛くて苦しくて、今にもつぶれてしまいそうだったとしても。
この足で立ってまた歩いていくために、私は笑おう。
心の底から高らかに笑おう。
杉が、百合さんと両想いになったその時、本物の笑顔で
“おめでとう”
そう言えるように。
(おしまい)