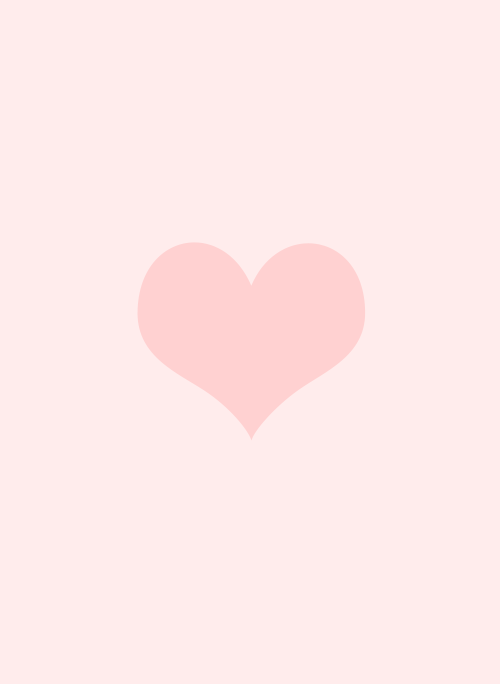ぜんぶクリスマスのせいだ。
慌てて口元を手で覆ってくしゃみをした私に、三宅は耐えられないというように吹き出した。
「お前、このタイミングでくしゃみするか普通」
「だ、だって寒かったんだから仕方ないでしょ!」
お腹を抱えて笑い続ける三宅に、恥ずかしくなって、自然と顔に熱が集まる。
あー、もう!こんな失態を三宅に晒すなんて、屈辱。
なんでもうちょっと耐えられなかったの私!
寒さと恥ずかしさでぷるぷると体は震えだし、尚も笑い続ける三宅にイラッとして、私は“もう帰る!わざわざ付き合ってくれてありがとう!”と捨て台詞として叫び、踵をかえして帰路につこうとする。そんな私の手をつかんだ。
「待て待て。笑って悪かった。
こんな夜道に女一人でいたら、物好きが寄ってくるかもしれないって言っただろ」
笑いすぎて目尻に滲んだ涙を拭いながら、さりげなく掴んだ手を引いて、三宅は歩き出す。
彼が進んでいる方向は紛れもなく私の家の方だ。残業で残っていた私をほぼ毎日送ってくれていた道。
いつの間にそんな優しさが日常になってたんだろう。
つながれた手を見ながらそんなことを思っていると、三宅がくるりと振り返った。
「な、なによ」
「またあの色気のないくしゃみしたいのか」
ふっと笑って私の首にかけた自分の青いマフラーを、三宅は丁寧にぐるぐると巻いてくれた。きゅっと右側で結んで、最後に寒さで赤くなった頬にちゅっとかわいらしい音をだしてその唇で触れた。
……三宅って実はかなりのキス魔なんじゃない?
触れた頬を、つないでいない方の手でバッと押さえてから三宅を睨む。すると三宅は悪びれることもなく、楽しそうに笑った。
「流されて、そのまま俺のこと、
好きになっちゃえばいいのに」
いつもならむかつくその笑顔に、その言葉に、どうしようもなくときめいてしまうのも、思いがけないいつもの優しさに鼓動が騒ぐのも、ぜんぶ、クリスマスのせいだ。