溺愛彼氏
「喜んで」
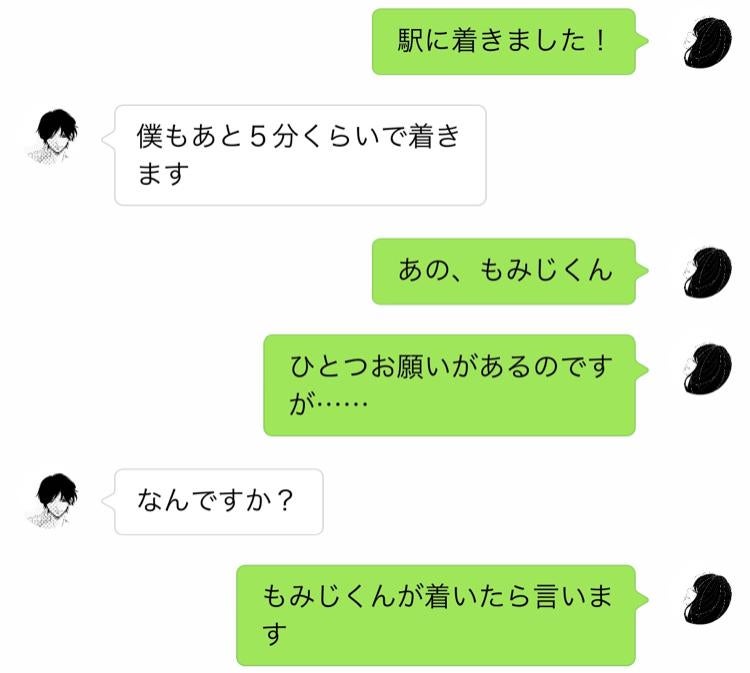
「お待たせしました」
改札を出てすぐのところで待っていれば、甘めの声音が私に向かって飛んできた。
「お疲れ様です」
「で、あんずのお願いってなんですか?」
会っていきなり開口一番に、それですか。ですよね。と、もみじくんの顔をじっと見つめる。
「なんですか?かっこいいですか?」
「え、あ、かっこいいですよ、いつも」
「え、なにごとですか。そんなストレートに言われたら照れるのですが」
自分から、かっこいい?と聞いてきたのに照れないで、いただきたい……。私のほうがもっと恥ずかしいのに。
なんて思いながら、もみじくんのスーツの袖口を少し遠慮がちに握った。
「どうしたの?あんず」
「あの……」
「うん」
「手を……」
「手?」
「手を繋いで帰りたいの、ですが」
「え、」
「ダメですか……?」
勇気を振り絞って、熱くなる顔を隠すように俯けば、
「なんだ、そんなこと」
そんなこと。なんて言われてしまった……。
私の勇気を、そんなこと呼ばわり……。
と、袖口を握っていた指先がもみじくんの体温に包まれる。
するりと顔を上げれば、いつもよりちょっぴり顔を赤らめた もみじくんの顔が私の顔に近づいて、耳元で吐息と共に甘い言葉を囁いた。
絡まった指先も、甘く囁かれた耳も、溶けてしまいそうなくらいに熱い。

