溺愛彼氏
「一目惚れって信じますか?」
ーー4年前。もみじくんとの出会いのお話。
仕事が終わりいつものように、いつもの駅へ向かう。
ホームで電車を待っていれば、ドンッと、突然背中になにかがぶつかった。振り返ったその先にはチャコールグレー色のスーツに身を包んだ高身長の男性。
『あ、あのすみません』
『いえ、私は大丈夫です』
『あ、あの、本当にすみません。ぶつかった拍子に僕のコーヒーがかかってしまったようで』
少し低めの甘い声音を響かせるその人。自分の着ていた白色のワンピースに視線を落とせば盛大に裾に着いてしまった茶色のシミ。
あらら。でも仕方がない。
『このくらい大丈夫ですよ。それにこのワンピース安ものですし、私これから帰るだけなので』
『いえ、本当に申し訳御座いません。クリーニング代をお支払いしますので』
『いえ、そこまでしてくださらなくても』
『ダメですよ。せっかくの可愛いワンピースなのに』
さらりと、スマートにそう言った彼は持っていた鞄から手帳を取り出しスーツの胸元に差していたペンでさらさらと文字を綴っていく。
手帳からその1枚を破り差し出されまそれを見れば名前と電話番号が綴られていて。
『本当にすみません。今度お詫びも兼ねてなにかご馳走させてください』
『いえ、本当に結構ですので』
『でも、それでは僕の気が治りませんので』
律儀な人だなと思いつつ、差し出された紙を受け取った。
綺麗な筆跡で綴られた彼の名前と電話番号。彼の綺麗な顔立ちにその文字も、書かれていた名前もとてもよく似合っていて。
『お時間ある時にでも連絡ください。美味しいものでも食べに行きましょう』
『すみません、ありがとうございます』
『あ、あの迷惑でなければお名前お伺いしてもよろしいでしょうか?』
『あ、すみません。私、美森 杏と申します』
『瀧 紅葉と申します。美森さんこの度は大変失礼致しました。ではまた今度近いうちに』
『はい』
これがもみじくんとの出会いだった。
けれど私はもみじくんに連絡をしなかった。
コーヒーを溢されたことには怒っていないし。そんなことでご飯をご馳走になるなんておこがまし過ぎる。
第一、なんて連絡をしたらいいのか分からない。
私は彼に連絡先を教えてなどいなかったから向こうから連絡が来ることもなく。
でも毎日、駅に着くとちらちらと周りを確認して。もしかしたら彼がいるのではないかと探している自分がいた。
そんなある日、偶然にも帰りの駅のホームで彼を見つけて。
じっと目で追っていれば、彼の瞳がこちらに向く。
どきりと、心臓がうるさく鳴って、まるで私の心臓は彼のことを好きだと言っているみたいだ。
『偶然ですね』
と、彼のあの優しい甘い声音に包まれた。
脳と体が甘く痺れる。彼しか見えなくて。
どきどきがバレないように、きっと真っ赤であろう顔を隠すようにするりと俯く。
『全然、連絡くれないんですね』
『え、あ、あのすみません……』
『待ってました。ずっと』
『え、』
『あなたからの連絡』
その言葉に驚いて顔を上げれば、眉尻を下げて少し困ったように微笑む彼の顔。
どういう意味だろう。からかわれてるのかな。あの汚れたワンピースのことをまだ気にしてくれているのだろうか……?
『あ、あのすみません、本当にあのワンピースは大丈夫でしたので、そんな気にしていただかなくても』
『いや、あのそうではなくて』
『え、』
『あれは、わざとというか……』
『わざ、と……』
ん?あれ、わざととは……?
彼から溢れた言葉を瞬時に処理できない私はフリーズする。
私は、わざと、コーヒーをかけられたというのか……?
ぽかんとした顔で彼を見つめれば申し訳なさそうに唇を開く。
『コーヒーがかかってしまったのは想定外なのですが、ぶつかったのはわざとで』
『……』
『なんなら、いまこうして、偶然会ったのも偶然ではなくて』
『えーと、』
『ちなみに、あのぶつかった日が初めましてでもないです』
綺麗な顔の男の人が、甘い声音でよく分からない言葉を口にする。
『僕のこと覚えてませんか?』
『えーと、すみません……』
記憶を遡る。けれどこんなイケメンと知り合いだったら忘れることなどないだろうなと思いつつ誰だ、誰だと検索するけれどヒットしない。
誰か別の人と、私を間違えているじゃないかな。
『通勤ラッシュの駅のホームで人混みの中、貧血で倒れそうになってる男を助けた記憶はありませんか?』
え。そのひと言でヒットした。
“あの、顔色悪いですけど大丈夫ですか?”
“あ、すみません”
“貧血ですかね?私もたまになるので、しんどいですよね。これお水。買ったばかりで新しいものなので飲んで少し座ってたら落ち着くと思いますよ”
「その顔は思い出してくれました?」なんておどけた口調で彼が言うから「あの時の」と呟けば目を細めて嬉しそうに微笑んだ。
『ふらふらだった僕に誰も気がつかなかったというか誰も興味なんてない中で、あなただけが声をかけてくれたんです』
『なんでですかね、ふと目がいってしまったというか』
『名前聞こうと思ったら居なくなってしまっていて』
『すみません、あの時は会社に遅れそうで急いでいて』
『だからずっと、あなたを探していました』
「見つけたけれどなんて声をかけていいか分からなくて、わざとぶつかって接点を作ろうとしました。すみません」と頼りなく呟いた彼を私は愛おしいと思ってしまった。
『連絡先、聞いてもいいですか?』
『……はい』
スマホを取り出し自分のQRを彼に差し出す。と、送られてきたメッセージ。
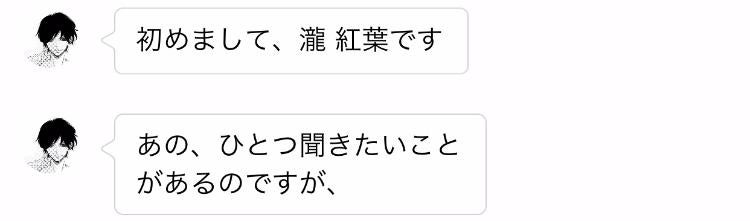
するりと、指先を絡められ初めて彼の体温に触れる。
顔を熱くして、私はこくりと小さく頷いた。

