溺愛彼氏
「心配なんだよ」
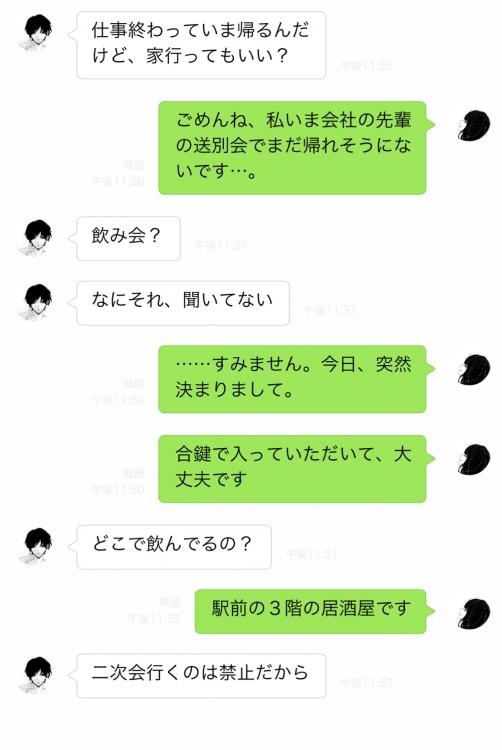
飲み会が終わり、ひとり駅の改札をくぐった。腕時計を見つめ終電ギリギリなことに気づき少し早足になる。
もみじくんは家にいるだろうか。
と、
「遅い」
「……もみじくん」
私に向かって飛んできた言葉。スーツを着て両腕を組んだ彼が階段下で立っていた。
あれ、どうして彼がここにいるんだろうか。
もしかして合鍵がなくて入れなかった……?いやでもそうしたら自分の家に帰るよね……?
「あの、」
「合鍵がなかったわけじゃないから」
「え、」
「合鍵がなくて入れなかったのかな?って顔してた」
どうやら、私の思考は筒抜けらしい。
けれど、私ももみじくんのことなら大抵のことは分かる。いまはとりあえず、機嫌が悪い。
「はやく帰るぞ」
「……はい」
口調がいつもと、違う。命令口調になるのはいつだって少し怒っているとき。
「……ごめんなさい。」
「なんで謝るの?」
「……だってもみじくんが怒っているので」
「怒ってないだろ」
ほら、怒ってる……。
「あんずがこんな時間まで飲み会なんか参加してるから」
「……今度からはちゃんと報告します」
「そうしてくれると助かります」

