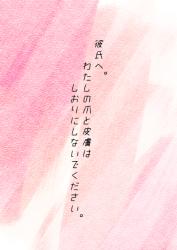やってきた秋に、舌打ちをした。
――腕を折り曲げ、抱きしめてくれた。
「日菜乃、日菜乃」
何度も名前を囁いて。
眉を震わせて。
「千秋くん、千秋くん」
瞼を閉じても、目を開けても、彼の熱を感じる。
もう、感じられないはずだったのに。
「だいすき」
私たちは、どちらからともなくこぼした。
伝わっているかは、わからない。
千秋くんの熱は確かに感じるけれど、腕はすり抜けてしまう。
千秋くんが抱きしめてくれるけれど、それも生きていた頃とは違う。
それでも。
伝わるかはわからなくとも、言いたくなったのだ。
そのくらい、千秋くんがすきなの。
千秋くん、だいすき――。
千秋くんの濡れた瞳が、燃える橙の空を映し出す。
儚い命を映すかのように綺麗で、キラキラと輝いていて、私の恋に終わりがないことを示しているようだった。
END.