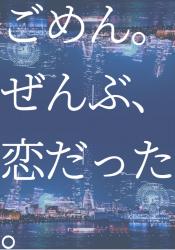きみはやっぱり林檎の匂いがする。
会計を済ませて、外に出ると空には満月が浮かんでいた。
「ねえ、零士くんは幸せにならなきゃダメよ」
千鳥足で危ない綾子さんのことをおんぶしてあげると、彼女はいつもこの言葉を言う。
「綾子さんと飲めて幸せですよ」
「そうじゃなくて、人生的にもっともっと幸せに……う」
「もう、日本酒は禁止ですからね」
風に乗って、身体に染み付いた焼き鳥屋の香りが漂ってくる。
誰といてもなにかが違うような気がして、笑っていても心だけは見せなかった。
でも彼女といると、俺は自然体でいられる。
決して恋愛関係にならないことが、実はものすごい強みなんじゃないかと前に綾子さんに話したら『それって最強かも』と笑ってくれた。
「ねえ、零士くん。お嫁さんになるって夢は遠退いてるけど、それ以上に私には叶えたい夢があるのよ」
呂律が回っていない声で、綾子さんがぽつりと言う。
「いつかね、海が見える街に住みたいの。大きな時計台があって、レンガ造りの街並みを歩きながら、私はバスケットを持ってフルーツとパンを買うのよ。それでね、夕暮れにはピンク色の空に鳩が飛んでる。そんな絵本みたいな街に住むことが今の夢」
それは十年、二十年、三十年と先のことかもしれないけど、贅沢はしないで真面目に仕事をしてお金を貯めたら、自分の好きなように生きたいと、話してくれた。
「それ、俺の夢にもしてもいいですか?」
「ふふ、いいわよ」
そんな返事が返ってきたあと、背中で綾子さんの寝息が聞こえてきた。
彼女の家まで続く道を、ゆっくりと歩く。
俺たちを照らしている満月が、綺麗な林檎に似ていた。
END