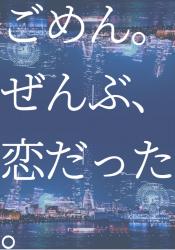首筋に、甘噛み。
「多分、いてーぞ。痕も残るかも」
俺は彼女の髪の毛を掻き分ける。
そこから露になった白い首筋。ゴクリと、生唾が口いっぱいに広がっていく。
「大丈夫です。先輩につけられる痕ならちっとも怖くありません」
吉光はそう言って、ニコリと笑った。
俺は指先で首筋をなぞる。一瞬だけビクッとした彼女の身体を支えるように、背中に手を回した。
「あと、噛んだらきっと我慢できねーから、どうなっても怒るなよ」
顔を近づけて、牙を肌に当てた。
……ガリッ。
きみの味を覚えてしまっても、
この気持ちだけは恋と呼ばせてほしい。
†END†