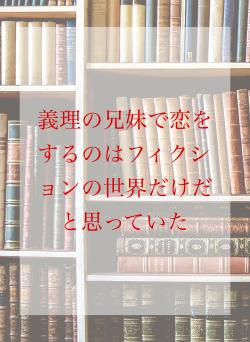小説家の妻が溺愛している夫をネタにしてるのがバレまして…
密壺に、ゆっくりゆっくり欲望を挿入していった。
「ハッ…はぁ…ぁ…」
僕のソレを嬉しそうに、味わうように柔らかく解(ほぐ)した媚肉が吸いついてきた。抜けるかどうかギリギリのところまで腰を引き、次の瞬間、ズンっと奥深くまで突く。それを数回繰り返したのち、ゆっくりとグラインドすると熱く擦れて、詩乃ちゃんは気持ち良さそうな声を漏らす。
「はぁ…ッ……きもちぃ…」
「……」
(あぁ…もう敬語プレイとか…どうでもいいや…。)
余裕がなくなる。
トロけた詩乃ちゃんの表情を見ると、理性が吹っ飛ぶ。
「っ…はぁ……子宮…降りてきた…。僕との子…欲しい…?」
「うんっ……ぁんっ…」
腰の奥底からグワッと快楽が押し寄せて苦しくなる。体温が上昇し、息も上がった。
「奥っ……奥に…出して…」
「んっ……イくよ…。イくっ……」
「私もっ……はぁ…あぁッ!!」
大きく膣壁がうねる。それが恐ろしいくらいにきもちよくて…。
《ドプッ…》
最奥で、僕は果てた。
クタクタになった詩乃ちゃんを甘やかすのもひっくるめて営みだと思っている。
「休んでて。ピーマンの肉詰め、僕が作る」
「……うぅ………」
「ごめんって。」
テーブルに突っ伏して脱力している妻に謝ると、彼女は顔を上げてプクッと頬を膨らませた。
「郁人くん……突然敬語で…びっくりした…」
「いつも以上に濡れてたね。興奮しすぎ。」
「っ…もぉ…」
照れ隠しで膨らませた頬を人差し指で突くと、やわらかい弾力で癖になりそうだった。
「………好きだよ?」
「そうやってご機嫌とろうとして…」
「………愛してる」
「……………知ってる」
END