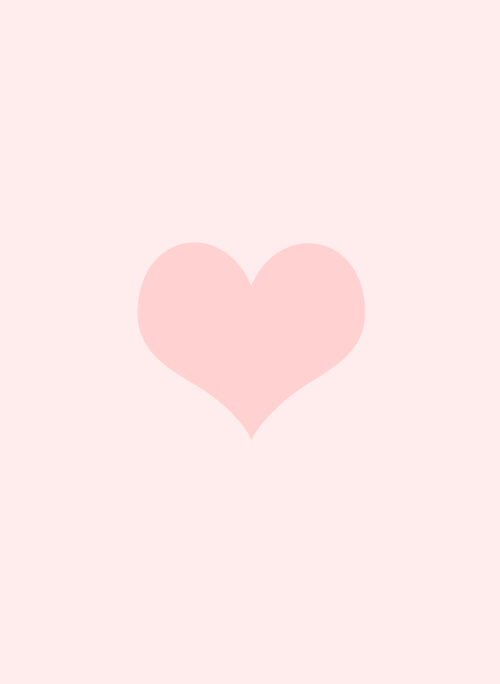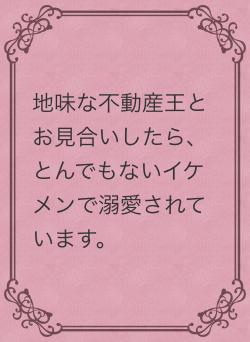ポロン星のクッキー
ジグニーに、僕の気持ちを伝えるべきなのか、迷った。
付き合って欲しい、というような気持ちはない。
30年以上、彼女の気持ちに気づかなかった僕である。
今さら何かを期待するのも、違うだろうと思った。
家の前まで帰ると、隣の家でジグニーがポーチではなく降りて待っていた。
「少し、話がしたいんだ」
ジグニーはそう言って、僕をポーチに誘った。
今日はソファーの他に、イスが一つ用意されていた。
ジグニーは僕にソファーを勧め、自分はイスのほうに座った。
「これ、返しておくよ」
ジグニーはそう言って、テーブルの上に銀のクッキー箱を置いた。
驚くことに、黒く焦げ付いた箱は、ピカピカになっていた。
「これは・・・」
「銀はね、変色しやすいんだ。少し時間はかかったけど磨いてやると治ったよ」
まったく信じられないほど、綺麗になっていた。
ジグニーは「少し」と言っていたが、ここまで磨くのにどれほどの時間と労力がかかったんだろう。
「この前、自分のせいかもしれない、と言ってただろう?それは本当に間違いで、あの日、アタシは家に自分のクッキー箱は持って帰ったんだ。それは覚えている」
そうなのか?ではどこで?と思って、銀の箱からジグにーに目を移すと、ジグニーが続けて言った。
「あの後さ、また、あんたが言い出すんじゃないかと思って、いつも持って歩いてたんだ。そりゃ、そんな事してたら、いつか無くすよ。だから、あんたのせいじゃない」
「それは・・・」
僕は言葉に詰まった。
銀のクッキー箱を見つめた。
それは、ある意味、僕のせいではないか?
「ジグニー……」
僕がいいかけたのを、ジグニーがさえぎった。
「アタシが好きだったからって、それも気にしなくていんだ。これは貰えない、それを言いたかっただけなんだ」
そう言って、ジグニーも、銀のクッキー箱に目を落とした。
しばらくの間、じっとクッキー箱を見ていた。
「僕は」
言いかけて、止まった。
これほど言いづらい言葉だったのか、と心のなかで唸っていた。
ジグニーが立ち上がりかけた。
「好きなんだ」
あわてて言った。
「え?」
「僕はジグニーのことが好きなんだ」
立ち上があろうとしていたジグニーは、ゆっくりイスに座り直した。
ジグニーのベッドで目を覚ました時、一瞬、どこか解らなかった。
かなり深く眠ってしまったらしい。
隣りに寝ているジグニーを見て、安心した。
ポーチでしばらくの間、何かしどろもどろに話したが、あまり覚えていない。
いや、あの、うん、といった言葉とも言えないような会話をした気がする。
その後、ジグニーの家に入って、ワインを少し飲んだ。
少し安心して、昔の話をした。
二人で話をしだすと、子供の頃の色々な事を思い出した。
僕が忘れていた事もあるし、ジグニーが覚えていない事もあった。
ジグニーの料理も食べた。
思ったより美味しくて、びっくりした。
「母親が病気がちだっから、ハイスクールの時から作ってるからね」
ジグニーはそう言った。
知ってることは多いが、知らないことも多い。
ジグニーのことが好きだ、そう解っても、付き合いとか結婚したいとは思わなかった。
でも、話をしていると、僕たちは一度は結ばれるべきなんじゃないか?という思いが膨らんできた。
「一度でいい、いつか、君を抱かせてくれないか?」
思わず、そう言ってしまった。
ジグニーが抱きついてきた。
儀式のような行為になるかもしれない。そう思ったが、まったく違った。
僕らは、どちらも上手とは言えない二人だったが、夢中になった。
僕の想いをぶつけ、ジグニーが身体いっぱいに受け止める。
どれだけ近づいても、もっと近くに寄りたかった。
その思いは、ジグニーの中に果てる瞬間、一つになった。
これまでの行為は何だったんだろう?と思うほど、ジグニーとの交わりは違った。
これが恋なのか!という思いと、あのジグニーを抱いた!という思いも交錯する。
背中を向けて寝ているジグニーに目をやる。
布団から出ている肩がつややかだった。
これほどジグニーが可愛く見えるのも、不思議だった。
でもそうだ、木登りで上を登っていたジグニーが振り返った時、後ろから日が差した。
あの時、笑顔を見て、なんて可愛いんだ!と思ったっけ。
木登り!
僕は、がばっと起き上がった。
ジグニーが僕の音で目を覚ました。
「グラント?」
「千年杉、覚えてるかい?」
ジグニーは思い出そうするが、覚えてないようだった。
「二人で、あの下にありったけの宝物を埋めた!」
あっ!とジグニーも思い出したようだ。
「あの時、君はリュックの中の物を全部入れた。もし、クッキー箱が紛れていたら……」
僕らは急いで服を着て、懐中電灯を持った。
父の大きなスコップを持ち出し、森に入る。
千年杉はすぐ解った。
掘り始めると、小雨がパラついてきた。急がないと!
予想より深くまで掘ると、やっとカツンと金属に当たった音がした。
土を除けて行くと、フタの部分が見えてきた。
エンジンオイル20Lの大きな缶のフタだ。
フタは錆びついていて、スコップを差し込んで力まかせに開けた。
中に色々な物が入っている。
戦闘機の模型、バッジ、野ネズミの頭蓋骨をビンに入れたもの。
その下に、ちらりと見えた紫色の箱、これだ。
取り出すと、間違いなくクッキー箱だった。
ジグニーに渡し、笑いながら聞いた。
「紫だったっけ?」
「アタシも驚いてる」
彼女も笑った。
雨が、いよいよ本格的に振り始めてきた。
クッキー箱とスコップだけ持って走る。
家に入ると両親を起こしてしまいそうなので、車庫にとりあえず入った。
息が切れている。年を考えないと。
ジグニーも息を切らしていた。
白髪まじりの髪が、顔に張り付いていて、僕は爪でそっと払った。
「ありがとう」
彼女は、そう言って笑った。
僕はポケットから自分のクッキー箱を出す。
笑っていた彼女の顔が曇った。
「グラント、それはいいことだとは思わない。少し冷静になってから考えたほうが……」
僕は首を振った。
「今まで、自分のクッキーがなんだったか、気になってた。」
「それは、アタシも覚えているよ」
「でも、今はどうでもいいんだ。ただただ、君の箱を開けたい。だめかい?」
彼女は満面の笑みを浮かべて言った。
「だめも何も、30年前からオーケーだよ」
彼女が、僕にクッキー箱を差し出す。
僕は彼女にクッキー箱を渡した。
二人で、箱の側面を合わせる。
カチリ、と鍵が開く音が聞こえた。
ジグニーが思わず、息を大きく吸い込んだ。
僕はうなずく。
彼女のクッキー箱を開けた。
出てきたクッキーはハート型だった。
「意外だ!ジグニーはハート型だったのか!」
びっくりしてジグニーを見ると、彼女も驚いた顔をしていて、箱をくるりとこちらに向けた。
僕のクッキーもハート型だった。
「ハートなんて作った覚えない!」
「アタシもだよ!」
二人して、クッキーを見つめた。
これはいったい……
「エポートル、奇跡の麦、やっぱり知らなかったか」
誰かと思えば、車庫の入口に父が立っていた。
「父さん!起きてたの?」
父は笑いながら入ってきた。
「物音に目が冷めたら、お前がスコップを持って森に行くのが見えた。待っていると、なにやら、かつての二人が車庫にコソコソ入っていくじゃないか」
僕とジグニーは、思わず互いを見た。
そうだ、昔に開けようとしたのもここだった。
「父さん、これってどういうこと?」
父は、うーんと少し考えて、静かに話し始めた。
「エポートル、という麦は不思議な成分があってな。触った人の精神にリンクして形を変える、半永久的に」
「触った人……あ!だから親が横から指示は出すけど、手伝わないのか!」
ジグニーが思い出したかのように言った。
僕は作った時の様子は覚えていないが、父はうなずいた。
「だから、箱の中のクッキーはたえず形を変える。まれに、こういった同じ形になる場合がある」
「父さんたちも?」
「私たちの時は、星型だった。夜空を見て感動した後だったからかもしれない」
「教えてくれればいいのに」
思わず言った。
こんな秘密があるなら、もっと早く知りたかった。
父は困った顔で頭をかいた。
「それは難しくてな。同じ型になると本当の恋だという者もいるが、その本当の恋というやつは、なった者にしか解らぬものだしな。海を見たことがない者に、海を説明するように」
父の言葉は、今なら解る気がする。
確かに、若いころの僕に説いても無駄だろう。
まさに海と同じで、いくら説明を聞いても無駄で、初めて海を見た時に「これが海か」と思うだろう。
「よく、噂が広まらないな」
「そうだな、同じ形になるのは、ひじょうに少なくてな。声高に人に喋る気にはなれん。違う形になった恋人でも、幸せになった者は多いのでな」
なるほど、それもそうだ。
しかし、昔の彼女で僕のクッキーを見た途端、泣き出した女性の理由がわかった。
おそらく、僕のクッキーはいびつな形だったのだろう。
「おじさん、このクッキー、食べれるのですか?」
ジグニーが父に聞く。
「まあ、美味しくはないが、食べれんことはない」
ジグニーと見合った。
でも、食べないなんて考えられない。
父が僕たち二人を見てため息をついた。
「まさか、何十年も後にこうなるとはなぁ。私が怒ったのは、余計なことだったのかもしれん」
ジグニーと僕は苦笑いを浮かべた。
「おお、母さんがな、もしクッキーだったなら、ホットミルクがいるだろうと言ってな。さっき作り始めたところだ。飲むかね?」
僕もジグニーも大きくうなずいた。
父の後に付いて、家に帰る。
雨はやんだようだ。
少し後ろを歩くジグニーの手を取った時、月明かりに照らされた彼女の顔は、とても綺麗だった。
終
付き合って欲しい、というような気持ちはない。
30年以上、彼女の気持ちに気づかなかった僕である。
今さら何かを期待するのも、違うだろうと思った。
家の前まで帰ると、隣の家でジグニーがポーチではなく降りて待っていた。
「少し、話がしたいんだ」
ジグニーはそう言って、僕をポーチに誘った。
今日はソファーの他に、イスが一つ用意されていた。
ジグニーは僕にソファーを勧め、自分はイスのほうに座った。
「これ、返しておくよ」
ジグニーはそう言って、テーブルの上に銀のクッキー箱を置いた。
驚くことに、黒く焦げ付いた箱は、ピカピカになっていた。
「これは・・・」
「銀はね、変色しやすいんだ。少し時間はかかったけど磨いてやると治ったよ」
まったく信じられないほど、綺麗になっていた。
ジグニーは「少し」と言っていたが、ここまで磨くのにどれほどの時間と労力がかかったんだろう。
「この前、自分のせいかもしれない、と言ってただろう?それは本当に間違いで、あの日、アタシは家に自分のクッキー箱は持って帰ったんだ。それは覚えている」
そうなのか?ではどこで?と思って、銀の箱からジグにーに目を移すと、ジグニーが続けて言った。
「あの後さ、また、あんたが言い出すんじゃないかと思って、いつも持って歩いてたんだ。そりゃ、そんな事してたら、いつか無くすよ。だから、あんたのせいじゃない」
「それは・・・」
僕は言葉に詰まった。
銀のクッキー箱を見つめた。
それは、ある意味、僕のせいではないか?
「ジグニー……」
僕がいいかけたのを、ジグニーがさえぎった。
「アタシが好きだったからって、それも気にしなくていんだ。これは貰えない、それを言いたかっただけなんだ」
そう言って、ジグニーも、銀のクッキー箱に目を落とした。
しばらくの間、じっとクッキー箱を見ていた。
「僕は」
言いかけて、止まった。
これほど言いづらい言葉だったのか、と心のなかで唸っていた。
ジグニーが立ち上がりかけた。
「好きなんだ」
あわてて言った。
「え?」
「僕はジグニーのことが好きなんだ」
立ち上があろうとしていたジグニーは、ゆっくりイスに座り直した。
ジグニーのベッドで目を覚ました時、一瞬、どこか解らなかった。
かなり深く眠ってしまったらしい。
隣りに寝ているジグニーを見て、安心した。
ポーチでしばらくの間、何かしどろもどろに話したが、あまり覚えていない。
いや、あの、うん、といった言葉とも言えないような会話をした気がする。
その後、ジグニーの家に入って、ワインを少し飲んだ。
少し安心して、昔の話をした。
二人で話をしだすと、子供の頃の色々な事を思い出した。
僕が忘れていた事もあるし、ジグニーが覚えていない事もあった。
ジグニーの料理も食べた。
思ったより美味しくて、びっくりした。
「母親が病気がちだっから、ハイスクールの時から作ってるからね」
ジグニーはそう言った。
知ってることは多いが、知らないことも多い。
ジグニーのことが好きだ、そう解っても、付き合いとか結婚したいとは思わなかった。
でも、話をしていると、僕たちは一度は結ばれるべきなんじゃないか?という思いが膨らんできた。
「一度でいい、いつか、君を抱かせてくれないか?」
思わず、そう言ってしまった。
ジグニーが抱きついてきた。
儀式のような行為になるかもしれない。そう思ったが、まったく違った。
僕らは、どちらも上手とは言えない二人だったが、夢中になった。
僕の想いをぶつけ、ジグニーが身体いっぱいに受け止める。
どれだけ近づいても、もっと近くに寄りたかった。
その思いは、ジグニーの中に果てる瞬間、一つになった。
これまでの行為は何だったんだろう?と思うほど、ジグニーとの交わりは違った。
これが恋なのか!という思いと、あのジグニーを抱いた!という思いも交錯する。
背中を向けて寝ているジグニーに目をやる。
布団から出ている肩がつややかだった。
これほどジグニーが可愛く見えるのも、不思議だった。
でもそうだ、木登りで上を登っていたジグニーが振り返った時、後ろから日が差した。
あの時、笑顔を見て、なんて可愛いんだ!と思ったっけ。
木登り!
僕は、がばっと起き上がった。
ジグニーが僕の音で目を覚ました。
「グラント?」
「千年杉、覚えてるかい?」
ジグニーは思い出そうするが、覚えてないようだった。
「二人で、あの下にありったけの宝物を埋めた!」
あっ!とジグニーも思い出したようだ。
「あの時、君はリュックの中の物を全部入れた。もし、クッキー箱が紛れていたら……」
僕らは急いで服を着て、懐中電灯を持った。
父の大きなスコップを持ち出し、森に入る。
千年杉はすぐ解った。
掘り始めると、小雨がパラついてきた。急がないと!
予想より深くまで掘ると、やっとカツンと金属に当たった音がした。
土を除けて行くと、フタの部分が見えてきた。
エンジンオイル20Lの大きな缶のフタだ。
フタは錆びついていて、スコップを差し込んで力まかせに開けた。
中に色々な物が入っている。
戦闘機の模型、バッジ、野ネズミの頭蓋骨をビンに入れたもの。
その下に、ちらりと見えた紫色の箱、これだ。
取り出すと、間違いなくクッキー箱だった。
ジグニーに渡し、笑いながら聞いた。
「紫だったっけ?」
「アタシも驚いてる」
彼女も笑った。
雨が、いよいよ本格的に振り始めてきた。
クッキー箱とスコップだけ持って走る。
家に入ると両親を起こしてしまいそうなので、車庫にとりあえず入った。
息が切れている。年を考えないと。
ジグニーも息を切らしていた。
白髪まじりの髪が、顔に張り付いていて、僕は爪でそっと払った。
「ありがとう」
彼女は、そう言って笑った。
僕はポケットから自分のクッキー箱を出す。
笑っていた彼女の顔が曇った。
「グラント、それはいいことだとは思わない。少し冷静になってから考えたほうが……」
僕は首を振った。
「今まで、自分のクッキーがなんだったか、気になってた。」
「それは、アタシも覚えているよ」
「でも、今はどうでもいいんだ。ただただ、君の箱を開けたい。だめかい?」
彼女は満面の笑みを浮かべて言った。
「だめも何も、30年前からオーケーだよ」
彼女が、僕にクッキー箱を差し出す。
僕は彼女にクッキー箱を渡した。
二人で、箱の側面を合わせる。
カチリ、と鍵が開く音が聞こえた。
ジグニーが思わず、息を大きく吸い込んだ。
僕はうなずく。
彼女のクッキー箱を開けた。
出てきたクッキーはハート型だった。
「意外だ!ジグニーはハート型だったのか!」
びっくりしてジグニーを見ると、彼女も驚いた顔をしていて、箱をくるりとこちらに向けた。
僕のクッキーもハート型だった。
「ハートなんて作った覚えない!」
「アタシもだよ!」
二人して、クッキーを見つめた。
これはいったい……
「エポートル、奇跡の麦、やっぱり知らなかったか」
誰かと思えば、車庫の入口に父が立っていた。
「父さん!起きてたの?」
父は笑いながら入ってきた。
「物音に目が冷めたら、お前がスコップを持って森に行くのが見えた。待っていると、なにやら、かつての二人が車庫にコソコソ入っていくじゃないか」
僕とジグニーは、思わず互いを見た。
そうだ、昔に開けようとしたのもここだった。
「父さん、これってどういうこと?」
父は、うーんと少し考えて、静かに話し始めた。
「エポートル、という麦は不思議な成分があってな。触った人の精神にリンクして形を変える、半永久的に」
「触った人……あ!だから親が横から指示は出すけど、手伝わないのか!」
ジグニーが思い出したかのように言った。
僕は作った時の様子は覚えていないが、父はうなずいた。
「だから、箱の中のクッキーはたえず形を変える。まれに、こういった同じ形になる場合がある」
「父さんたちも?」
「私たちの時は、星型だった。夜空を見て感動した後だったからかもしれない」
「教えてくれればいいのに」
思わず言った。
こんな秘密があるなら、もっと早く知りたかった。
父は困った顔で頭をかいた。
「それは難しくてな。同じ型になると本当の恋だという者もいるが、その本当の恋というやつは、なった者にしか解らぬものだしな。海を見たことがない者に、海を説明するように」
父の言葉は、今なら解る気がする。
確かに、若いころの僕に説いても無駄だろう。
まさに海と同じで、いくら説明を聞いても無駄で、初めて海を見た時に「これが海か」と思うだろう。
「よく、噂が広まらないな」
「そうだな、同じ形になるのは、ひじょうに少なくてな。声高に人に喋る気にはなれん。違う形になった恋人でも、幸せになった者は多いのでな」
なるほど、それもそうだ。
しかし、昔の彼女で僕のクッキーを見た途端、泣き出した女性の理由がわかった。
おそらく、僕のクッキーはいびつな形だったのだろう。
「おじさん、このクッキー、食べれるのですか?」
ジグニーが父に聞く。
「まあ、美味しくはないが、食べれんことはない」
ジグニーと見合った。
でも、食べないなんて考えられない。
父が僕たち二人を見てため息をついた。
「まさか、何十年も後にこうなるとはなぁ。私が怒ったのは、余計なことだったのかもしれん」
ジグニーと僕は苦笑いを浮かべた。
「おお、母さんがな、もしクッキーだったなら、ホットミルクがいるだろうと言ってな。さっき作り始めたところだ。飲むかね?」
僕もジグニーも大きくうなずいた。
父の後に付いて、家に帰る。
雨はやんだようだ。
少し後ろを歩くジグニーの手を取った時、月明かりに照らされた彼女の顔は、とても綺麗だった。
終