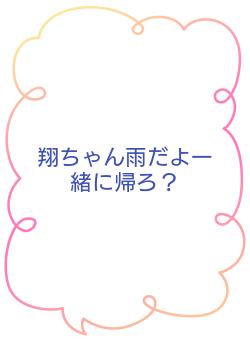きみが空を泳ぐいつかのその日まで
いつかのその日まで
「長くなるから、疲れたら言うんだよ」
運転席でお父さんが気遣ってくれたけど、耳に入ってこなかった。
「小説? 文庫か。最近の高校生はスマホで本を読むんだろう?」
「そんなことないよ。本でしか読めないものも、まだまだいっぱいあるんだよ」
「そうか、つぼみも大人びたことを言うようになったね」
お父さんはそこで言葉を止めて、泣いてるような笑っているような顔をした。
「お弁当、ありがとう。上手にできてた」
その声はどこか懐かしい、リラックスした声だった。
「そっか。よかった」
これからだってちゃんと二人分、作るつもりだよ。
バイクの免許取得について調べようとスマホを手にしたけれど、思い直してお父さんに声をかけた。
「お父さんあのね、バイクの免許って何歳でとれるの? 中免ってなに? 」
「中免っていうのは、普通自動二輪免許。16歳から取れるはずだよ。排気量400CCまでの大きな単車に乗ることができるけど、まさかとるつもりなのか?」
「いや……ううん、わかんないけど」
いつものお父さんならここで話を終わらせる。案の定、少し怖い声になった。
「まとまったお金も必要だし、教習所にも通わないといけないし、それにバイクは危ないし、つぼみに乗りこなせるとは……」
「それは、私が決めることだよ」
反対されることなんてわかってた。
だからムキになったて意見したら、お父さんは気の抜けたように苦笑して、言葉を足してくれた。
「そうだな、いいんじゃないか。どこにだって行けるし、誰にだって会える。それがきっと生きてるってことなんだろう」
私はもう、四月に16歳になっていた。
久住君の誕生日はいつなんだろう。彼のことをなんにも知らないけれど、きっとそう遠くはない未来だ。
大きなバイクに跨がっている自分を想像してみた。お父さんの言うとおり乗りこなせるとは到底思えないし、少しも似合わない。
だけどまっすぐな道を、風を切り走ることができたら、どんなに素敵だろう。辿り着いた先に、ずっと会いたかった人が待っていてくれたなら、どれほどに。
車は高速に乗ったばかりで、抑揚のない平べったい景色がびゅんびゅん後ろへ飛んでいった。
お父さんにみつからないようそっと本を胸に押し当てると、それを伝って鼓動が次々あふれ、手に取ってしまえるようだった。
その想いになんて名前をつけたらいいのか、今はまだわからない。
見上げると、一羽の鳥が公団の上を渡る姿があった。気流に乗る鳥は堂々と優雅で、そのうち美しい夕景に吸い込まれてしまった。
その光景を目の奥に焼き付けると、宝物に触れるよう、そっと表紙をめくった。
「きみが空を泳ぐいつかのその日まで」
タイトルを目に焼き付けて、また胸にしっかり抱いた。大切な人に泣いてもいいよって、私もいつか、そう言えるようになるために。
完
運転席でお父さんが気遣ってくれたけど、耳に入ってこなかった。
「小説? 文庫か。最近の高校生はスマホで本を読むんだろう?」
「そんなことないよ。本でしか読めないものも、まだまだいっぱいあるんだよ」
「そうか、つぼみも大人びたことを言うようになったね」
お父さんはそこで言葉を止めて、泣いてるような笑っているような顔をした。
「お弁当、ありがとう。上手にできてた」
その声はどこか懐かしい、リラックスした声だった。
「そっか。よかった」
これからだってちゃんと二人分、作るつもりだよ。
バイクの免許取得について調べようとスマホを手にしたけれど、思い直してお父さんに声をかけた。
「お父さんあのね、バイクの免許って何歳でとれるの? 中免ってなに? 」
「中免っていうのは、普通自動二輪免許。16歳から取れるはずだよ。排気量400CCまでの大きな単車に乗ることができるけど、まさかとるつもりなのか?」
「いや……ううん、わかんないけど」
いつものお父さんならここで話を終わらせる。案の定、少し怖い声になった。
「まとまったお金も必要だし、教習所にも通わないといけないし、それにバイクは危ないし、つぼみに乗りこなせるとは……」
「それは、私が決めることだよ」
反対されることなんてわかってた。
だからムキになったて意見したら、お父さんは気の抜けたように苦笑して、言葉を足してくれた。
「そうだな、いいんじゃないか。どこにだって行けるし、誰にだって会える。それがきっと生きてるってことなんだろう」
私はもう、四月に16歳になっていた。
久住君の誕生日はいつなんだろう。彼のことをなんにも知らないけれど、きっとそう遠くはない未来だ。
大きなバイクに跨がっている自分を想像してみた。お父さんの言うとおり乗りこなせるとは到底思えないし、少しも似合わない。
だけどまっすぐな道を、風を切り走ることができたら、どんなに素敵だろう。辿り着いた先に、ずっと会いたかった人が待っていてくれたなら、どれほどに。
車は高速に乗ったばかりで、抑揚のない平べったい景色がびゅんびゅん後ろへ飛んでいった。
お父さんにみつからないようそっと本を胸に押し当てると、それを伝って鼓動が次々あふれ、手に取ってしまえるようだった。
その想いになんて名前をつけたらいいのか、今はまだわからない。
見上げると、一羽の鳥が公団の上を渡る姿があった。気流に乗る鳥は堂々と優雅で、そのうち美しい夕景に吸い込まれてしまった。
その光景を目の奥に焼き付けると、宝物に触れるよう、そっと表紙をめくった。
「きみが空を泳ぐいつかのその日まで」
タイトルを目に焼き付けて、また胸にしっかり抱いた。大切な人に泣いてもいいよって、私もいつか、そう言えるようになるために。
完