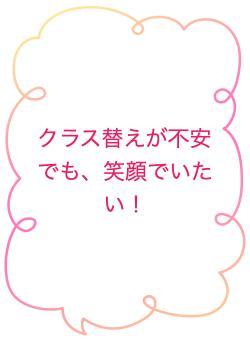青春・友情
syu.syu/著

- 作品番号
- 1624012
- 最終更新
- 2020/12/16
- 総文字数
- 0
- ページ数
- 0ページ
- ステータス
- 未完結
- PV数
- 0
- いいね数
- 0
「こちら、並行世界です」
これは私の、普通が普通でなくなってしまう話だ。
私の日常。朝、けたたましいアラーム音と共に起床。朝食を食べ、歯磨き。念入りに身支度を整えて、あり得ないほど低い自分の自己肯定感を少しでも上げていく。(どうせ学校に着いて鏡を見れば無かっことになってしまうのだが。)時間に追われつつ登校、学校着。そして私の苦痛な学校生活が始まるのだ。
「ねーねー!昨日の嵐にしやがれみた?」
クラスメイトとの何気ない会話。
「あー!見た!めっちゃ面白かった!」
当たり障りなくやり過ごす。愛想笑いがバレないように。自然に。
私は学校生活が一番嫌いだ。なぜこうもして学校に通って、機会的に毎日を送っているのか。そして周りの人がなぜ毎日こうも楽しそうなのか、私には全く理解できない。こうやって愛想笑いでやり過ごすのは楽じゃない。全くもって楽じゃない。
だから私は唯一の一人の時間を作る為に昼食は屋上で一人で食べる。ここなら誰にも邪魔されず、日頃のストレスを忘れられるからだ。
屋上。ここは最高の場所。誰にも邪魔されない。自分だけの、至福の時間。
(あー、やっと午前が終わったなー)
「なぁ」
不意に声がした。
「…?」
いつも誰もいないのに、話しかけられるなんて聞いてない。
姿を現したのは同じクラスの進藤カケルだった。
「何?カケル?」
何故かカケルは怒ったような、悲しんでいるような顔をしながらこちらを見据えていた。
「お前さ、友達と話してても大して楽しくないんだろ?」
なんなんだ。いきなり。
「なんで?そんなことないよ」
「分かるんだよ。態度で」
なんなんだ、本当に。
「もしそうだったとして、カケルには関係ないでしょ?変に突っかかってこないで」
ほんとうに意味が分からなかった。いきなりカケルは何を言い出すのだろう。放っておいてほしかった。
「お前、…それで後悔しないのかよ」
顔をあげても、今カケルがどんな表情をしているのか私からは見えなかった。
キーンコーンカーンコーン
昼休みが終わるチャイムが鳴ると、カケルはその場から消えていた。
これは私の、普通が普通でなくなってしまう話だ。
私の日常。朝、けたたましいアラーム音と共に起床。朝食を食べ、歯磨き。念入りに身支度を整えて、あり得ないほど低い自分の自己肯定感を少しでも上げていく。(どうせ学校に着いて鏡を見れば無かっことになってしまうのだが。)時間に追われつつ登校、学校着。そして私の苦痛な学校生活が始まるのだ。
「ねーねー!昨日の嵐にしやがれみた?」
クラスメイトとの何気ない会話。
「あー!見た!めっちゃ面白かった!」
当たり障りなくやり過ごす。愛想笑いがバレないように。自然に。
私は学校生活が一番嫌いだ。なぜこうもして学校に通って、機会的に毎日を送っているのか。そして周りの人がなぜ毎日こうも楽しそうなのか、私には全く理解できない。こうやって愛想笑いでやり過ごすのは楽じゃない。全くもって楽じゃない。
だから私は唯一の一人の時間を作る為に昼食は屋上で一人で食べる。ここなら誰にも邪魔されず、日頃のストレスを忘れられるからだ。
屋上。ここは最高の場所。誰にも邪魔されない。自分だけの、至福の時間。
(あー、やっと午前が終わったなー)
「なぁ」
不意に声がした。
「…?」
いつも誰もいないのに、話しかけられるなんて聞いてない。
姿を現したのは同じクラスの進藤カケルだった。
「何?カケル?」
何故かカケルは怒ったような、悲しんでいるような顔をしながらこちらを見据えていた。
「お前さ、友達と話してても大して楽しくないんだろ?」
なんなんだ。いきなり。
「なんで?そんなことないよ」
「分かるんだよ。態度で」
なんなんだ、本当に。
「もしそうだったとして、カケルには関係ないでしょ?変に突っかかってこないで」
ほんとうに意味が分からなかった。いきなりカケルは何を言い出すのだろう。放っておいてほしかった。
「お前、…それで後悔しないのかよ」
顔をあげても、今カケルがどんな表情をしているのか私からは見えなかった。
キーンコーンカーンコーン
昼休みが終わるチャイムが鳴ると、カケルはその場から消えていた。
- あらすじ
- これは女子高生の私の、普通が普通でなくなってしまう話だ。
この作品をシェア
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…