真紅の花嫁
●Prologueー夢ー●
幼い頃の夢を見る。
夏休みに祖父母の家に遊びに来てた時の、ほんの少しの夏の間。
私には、大切な友達がいた。
1人は、大きい瞳の女の子みたいにキレイな男の子。私のお兄ちゃんみたいな人だった。おままごとにも付き合ってくれるし、私のお話を聞いてくれる。
もう一人は、冷たい性格の男の子。運動神経がよくて、森の中でもたくさん走り回ってた。不器用な男の子。
私たちは3人でいつも森の中で探検をした。
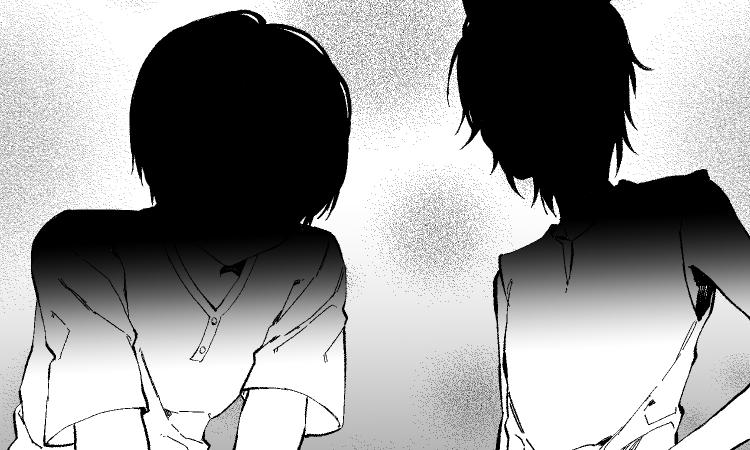
「いたっ」
「…おい、結羽?」
「大丈夫?」
森の中で走って、走って、速い二人に追いつきたくていつも無理をしていた。そうして私は毎回転んでしまう。
前にいた二人がすぐに駆け付けてくれる。嬉しいけれど、膝が痛い。
「血が出てる」
大きい瞳を痛々し気に歪めて、私の膝を見る男の子。大丈夫だよ、って言いたいけれど、痛いモノは痛い。
自然と涙が滲んでしまう。
「泣かないで、ほらおいで」
綺麗な顔をしているけれど、私たちの中で一番背が大きいお兄ちゃん。私を抱きかかえてくれるのはいつも彼の役目。
「…何泣いてんだ。弱虫」
「おい」
私を見て、悪態をついてくる子。彼は私に・・・いや、周りの人みんなに冷たい。
でも知ってるの。悪くいったりするけど、私のそばに絶対に彼はいてくれる。
二人は遊んでる間中私をずっと気遣ってくれるのがわかっていた。
幸せだった。休みの間中ずっと3人一緒だった。
夏休み最後の日。いつも通り待ち合わせの場所い行くと、そこにいたのは冷たい彼。
「■■くんは?」
「…しらねー」
もう一人の居場所を聞くと、ぶっきらぼうに返される。機嫌が悪いのだろうか。
ちらちらとこちらを見てくる。よくわからないけれど、冷たい印象の彼は、今日は少し違っていた。
「…え、帰る?」
「うん…」
私は夏休みが終わることと、家に帰ることを話した。
ここに来るのはきっと次の長い休みの日になるかもしれない。私が住んでいるところは、ここより遠いから。
「……」
彼は黙り込んでしまった。何を言ったらいいかわからないけど、最後はいっぱい遊んでお別れがしたかった。
「…お前も、俺から離れてくんだな」
「え?」
沈黙を破った彼の声は重く沈んでいた。幼い彼が出したとは思えない、すごく切ない声だった。
彼がかわいそうになった。
私にとって大切な友達だったから。
「また遊びに来れるよ。次の長いお休みがある時に」
少年の耳がぴくっと動く。そして、伏せていた顔を上げた。
今まで3人でいるときはこんな近くで、しっかりと見つめることがなかった彼の瞳。
大きくて、赤い瞳。その瞳は心なしか潤んでいた。不安そうな顔がかわいそうで…
「■■、また遊ぼう。絶対戻ってくるから」
私は約束を口にしてしまった。
「…うん…」
彼がこくりと頷いた。頬が赤く、目がさらに潤んでいる。
――泣いちゃうのかな?
そんな風に少し焦る私に、彼の顔が近づいてくる。彼の綺麗な顔に見とれてしまう。
近づいてくる彼の顔に自然と目が閉じてしまう。
そうして、私と彼は小さな唇を重ねた。
ほのかに、花の香りがした。

幼い頃の夢を見る。
夏休みに祖父母の家に遊びに来てた時の、ほんの少しの夏の間。
私には、大切な友達がいた。
1人は、大きい瞳の女の子みたいにキレイな男の子。私のお兄ちゃんみたいな人だった。おままごとにも付き合ってくれるし、私のお話を聞いてくれる。
もう一人は、冷たい性格の男の子。運動神経がよくて、森の中でもたくさん走り回ってた。不器用な男の子。
私たちは3人でいつも森の中で探検をした。
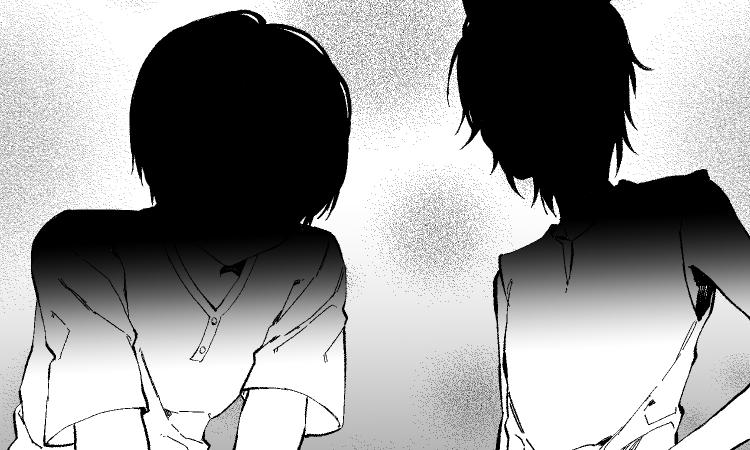
「いたっ」
「…おい、結羽?」
「大丈夫?」
森の中で走って、走って、速い二人に追いつきたくていつも無理をしていた。そうして私は毎回転んでしまう。
前にいた二人がすぐに駆け付けてくれる。嬉しいけれど、膝が痛い。
「血が出てる」
大きい瞳を痛々し気に歪めて、私の膝を見る男の子。大丈夫だよ、って言いたいけれど、痛いモノは痛い。
自然と涙が滲んでしまう。
「泣かないで、ほらおいで」
綺麗な顔をしているけれど、私たちの中で一番背が大きいお兄ちゃん。私を抱きかかえてくれるのはいつも彼の役目。
「…何泣いてんだ。弱虫」
「おい」
私を見て、悪態をついてくる子。彼は私に・・・いや、周りの人みんなに冷たい。
でも知ってるの。悪くいったりするけど、私のそばに絶対に彼はいてくれる。
二人は遊んでる間中私をずっと気遣ってくれるのがわかっていた。
幸せだった。休みの間中ずっと3人一緒だった。
夏休み最後の日。いつも通り待ち合わせの場所い行くと、そこにいたのは冷たい彼。
「■■くんは?」
「…しらねー」
もう一人の居場所を聞くと、ぶっきらぼうに返される。機嫌が悪いのだろうか。
ちらちらとこちらを見てくる。よくわからないけれど、冷たい印象の彼は、今日は少し違っていた。
「…え、帰る?」
「うん…」
私は夏休みが終わることと、家に帰ることを話した。
ここに来るのはきっと次の長い休みの日になるかもしれない。私が住んでいるところは、ここより遠いから。
「……」
彼は黙り込んでしまった。何を言ったらいいかわからないけど、最後はいっぱい遊んでお別れがしたかった。
「…お前も、俺から離れてくんだな」
「え?」
沈黙を破った彼の声は重く沈んでいた。幼い彼が出したとは思えない、すごく切ない声だった。
彼がかわいそうになった。
私にとって大切な友達だったから。
「また遊びに来れるよ。次の長いお休みがある時に」
少年の耳がぴくっと動く。そして、伏せていた顔を上げた。
今まで3人でいるときはこんな近くで、しっかりと見つめることがなかった彼の瞳。
大きくて、赤い瞳。その瞳は心なしか潤んでいた。不安そうな顔がかわいそうで…
「■■、また遊ぼう。絶対戻ってくるから」
私は約束を口にしてしまった。
「…うん…」
彼がこくりと頷いた。頬が赤く、目がさらに潤んでいる。
――泣いちゃうのかな?
そんな風に少し焦る私に、彼の顔が近づいてくる。彼の綺麗な顔に見とれてしまう。
近づいてくる彼の顔に自然と目が閉じてしまう。
そうして、私と彼は小さな唇を重ねた。
ほのかに、花の香りがした。

< 1 / 4 >
