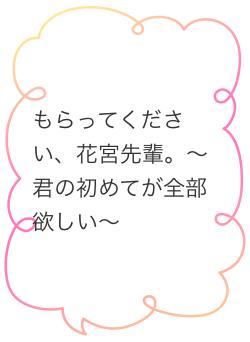織原くんの秘密
「なぁ、何持ってるのそれ」
────それは、突然の出会いだった。
あれは中学2年生の冬。早朝、私は吹奏楽の朝練に参加する為、空気の澄んだ田んぼに囲まれた田舎道を、学校に向かい歩いていた。
普段は学生以外誰も歩いていない時間帯。近所に友達は住んでいない。なのに、後ろから声がして、私は驚き手に持ったトランペットのケースを落としそうになった。
振り返ると、そこには短髪にジャージ姿の男子が、自転車に跨りこちらを興味深げに見つめていた。その視線の先には私のトランペットのケースが。
「……えっと、トランペット」
「へぇ、かっけーな」
「う、うん。ありがとう」
「吹部、いつも頑張ってるよな」
「えっと……誰?」
「あぁ!ごめん。5組の織原」
「織原くん」
「急に声掛けて驚いたよな。けど、いつも大切そうに抱えてるから、それが何か気になって」
織原くんはニッと口角を上げ、自転車のペダルに足を掛ける。
「じゃあな、小林」
そう言い残し、織原くんは自転車に乗って去って行ってしまった。呆気に取られていたが、一つだけ不思議なことに気が付いた。
「何で、私の名前知ってるの?」
※※※
それから、織原くんは朝練に向かう私を見かける度に声を掛けてくれるようになった。
最初こそ緊張していたものの、織原くんの優しく懐っこい人柄のおかげで、すっかり打ち解けることが出来た。
寒い早朝の田舎道を、トランペットケースを抱えた私と、自転車を押す織原くんは並んで歩く。
織原くんは野球部らしく、聞かせてくれる部員達のおふざけエピソードが面白くて、朝からお腹を抱えて笑った。
「あはははっ…!!それで、先生にバレなかったの?」
「バレなかった。あの時はマジで冷や冷やした」
「運が良かったねぇ」
「確かに」
織原くんは私が笑うと、何故かとても満足そうに口角を上げた後、決まって俯く。
織原くんの明るい性格の裏に、何かを抱えているんじゃないか。そう思ってしまう程、織原くんは時折、きゅっと唇を噛み締め私から目を逸らした。
何か悩んでいるのかな。聞きたい、けど、私と織原くんの関係は、朝こうやって一緒に学校が見えるまで登校するだけの関係。学校では恥ずかしくて、どうしても織原くんをみることが出来ない。
「小林、指先真っ赤だな」
「あ、ほんとだ。寒いもん」
「手袋ねぇの?」
「うん、ない。失敗したなぁ」
「…………」
私の手をじっと見つめていた織原くんは、自転車を停め、自分がしていた手袋を脱いだ。そして、私に差し出す。
「これ、してていいよ」
「え、なんで?織原くん寒いでしょ?」
「俺は全然平気。それより小林の手のが可哀想」
「……いいの?」
「うん」
そう頷いた時の織原くんの頬は少し赤らんでいて、声は少し掠れていた。私より少し背の高い織原くんを見上げ、手袋をぎゅっと握りしめた私の心臓は、どきんと大きく脈打った。
────私、織原くんのことが好きだ。
そう、自覚した。
※※※
部活帰り、もう日はとっぷりと沈んでいた。下駄箱で友達と別れ、夜空に煌めく星を見上げながら校門を抜けた時。
「小林」
その声に勢いよく振り返ると、校門に寄り掛かる織原くんがいた。今日は自転車がない。いつも朝会うのに、放課後会うのは初めてだ。驚きのあまり無言で目を大きくしていると、織原くんはこちらに駆け寄ってくる。
「暗いから送る」
「ま、待っててくれたの?」
「……うん。まぁ、そう」
「……ありがとう」
嬉しくて、何だか少しだけ泣きそうになった。織原くんは頬を赤くし、頭を掻く。
いつもの田舎道を、家に向かって並んで歩く。今日の織原くんの口数は、いつもより少なかった。
「……なぁ」
「なに?」
「この前、小林が練習してるの見た。すげーかっこよかった」
「…ありがとう。嬉しい」
「俺さ、ずっと応援するから」
「あはは、何を?」
「……小林のトランペット」
「……織原くん?」
いつの間にか、私の家の前に着いていた。けど、なんだかその日だけは、織原くんと別れるのがどうしても惜しかった。
妙な違和感を感じた。冬の冷たい夜風が、私達の間を吹き抜けていく。
織原くんは俯いた後、ゆっくりと私の顔を見る。そして、口角をニッと上げた。
「────じゃあな、小林」
髪の毛をくしゃりと撫でられる。私は違和感を言葉にすることが出来ず、織原くんの背を見送った。
※※※
織原くんが転校したと聞いたのは、数日後の事だった。
織原くんの部活のチームメイトが、私のクラスを訪ねてきて知った。呆然とする私に、尋ねてきた彼は言った。
「織原、部活やってる小林さんのこと、ずっと見てたんだよ」
それじゃあ織原くんは、私に話し掛ける口実を作る為、全部知っていて私に初めて声を掛けたんだ。それを知り、胸がいっぱいになった。
織原くんの引っ越しは、彼が私に声を掛けたくらいに決まったことだったらしい。
知っていたなら教えてほしかった。何一つ伝えることが出来ずに、織原くんは居なくなってしまった。
織原くんは俯く度、何を考えていたんだろう。どんな気持ちで、私と会話をしていたんだろう。少しでもいい、教えて欲しかった。残り少ない時間を、もっともっと大切に過ごしたかった。
「織原、くん」
あの瞬間、私達は想い合っていたはずだ。
だけど、伝えずに居なくなると決めたのは、織原くんだ。それが、答えなんだ。
だけど、私はずっとずっと忘れないよ。あの、澄んだ冷たい空気の中、一緒に歩いた田舎道を。
織原くんの、優しい笑顔を。