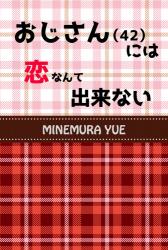とある企業の恋愛事情 -受付嬢と清掃員の場合-
後日。秘書課の業務を挟んだ次の日、受付に行くと詩音達がずいぶん喜んでいた。
どうやら美帆がいない間に文也が来て、カフェのドリンクやお菓子を差し入れしてくれたらしい。
しかし、どうして自分がいない時に限って、と美帆は憤慨した。
「津川さん太っ腹ですねえ。うふふ、さすが美帆さんの彼氏さんですね」詩音はニマニマ笑っている。よほど差し入れが嬉しかったのだろう。
「ずるいじゃない。なんで私がいない時に来るの?」
「たまたま寄ったんですって。美帆さんの分もありますよ。ほら、このお菓子です」
詩音は受付に置かれた箱の中から個包装のクッキーを取り出した。別にクッキーが羨ましかったわけではない。ただ、ちょっと会えたらと思っただけだ。そこまで食い意地は張っていない。
それからいつも通り業務を始めた。
今日の総合受付担当は詩音と美帆だ。仕事は特別変わったことはない。ややこしい来客もないし、落ち着いた一日になるだろう。
やがてお昼時を迎えて、ロビーは若干混み始めた。混んでいるといってもコンビニぐらいだ。あとは社員食堂に行く人間と外に食べに行く人間。この時間は受付も手が空く。
「しばらく予定も空いてるし────私お昼行ってこようかな」
「えっ!?」
美帆が立ち上がると、詩音がやたら驚いた声をあげた。
「どうしたの?」
「あの、私先にお昼に行っちゃ駄目ですかね」
「え? うん。いいけど……じゃあ、私あとから行くね」
「あの、受付にちょっと私の知り合いが来るかもしれなくてですね」
「うん?」
「だからもうちょっとだけ、待ってもらってもいいですか」
詩音はなんだか必死だ。よほど大事な用事なのだろう。
────ははぁ。もしかして、彼氏が会いに来るのかな?
詩音も彼氏と仲良くやっているようだし、一緒にランチに行きたいのかもしれない。
「お腹空いてないし大丈夫だよ。気にしないで」
「ありがとうございます」
お昼の時間帯が多少前後しても問題ない。きっかり十二時に昼休憩を取ることの方が珍しいし、受付では飲み物を飲んでもオーケーということになっている。時間がずれるぐらいなんてことはない。
────それにしても、彼氏が来るならそういえばいいのに。もしかしてまだ遠慮してるのかな。
彼氏がいない時間が長かったから受付の皆にはずいぶん苦労をさせた。だが、今は文也という彼氏がいる。恋人の話を聞いても羨ましいと思うことはない。
思い出すと会いたくなってきて、チラリとスマホの画面に視線を向けた。この間会ったばかりだが、夕食に誘ってみようか。文也がいいと言ったらそのまま家に行って────。なんて妄想を頭の中で繰り広げる。
連絡しようとスマホの電源を入れた時だった。なんだかロビーがざわついてふっと視線を上げた。
「えっ」
声をあげたのは美帆だけではなかった。小さな声はロビーのあちこちから聞こえてきたが、それどころではない。エントランスから入ってきた人物を見て、美帆はぽかんと口を開けた。
とにかく驚いた。だから隣にいた詩音が珍しく大人しくしていることにも気が付かなかった。
文也はやたら大きな荷物を抱えて自動扉から一直線に総合受付まで向かってくる。焦っているのは美帆だけだ。
やがて文也は受付の前まで来ると立ち止まった。
文也が来るのは珍しい話ではない。今日はなんの予約もされていないが、たまたま近くに来て立ち寄ることは多々あった。だが、問題はそんなことではない。
「ふ……文也さん……?」
文也の手に抱えられた大きな花束を見て、ロビーにいる人間は美帆同様驚きを隠せない様子だ。受付に花が届けられることはあるが、お祝いはお祝いでもそれが表すものがビジネス関係でないと皆分かるのだろう。美帆も、それを見てすぐに察した。
今更ながら、詩音が自分を休憩に行かせなかったわけがわかった。
文也は大きな薔薇の花束を抱えていた。随分恥ずかしそうな顔をしている。
そうだろう。見ている美帆ですら恥ずかしいと思っているのだから、こんな人だらけの場所で巨大な花束を持って来た文也が恥ずかしくないわけがない。そんな性格でもないのだから。
文也は花束を抱えたまま、器用にポケットから小さな箱を取り出した。大きな花束を持っているから開けにくそうだ。思わず手を差し出してしまいそうになる。なんとか不格好ながらにそれを開けて、美帆に見せた。言うまでもなく指輪が入っていた。
やがて落ち着いたのか、ようやくやっと文也は口を開いた。
「杉野美帆さん。俺と結婚してくれますか」
文也はいつになく真面目だ。緊張しているのだろう。以前は唐突に言ったから今度はちゃんとしようと思っていたのだろうか。美帆は次第に冷静さを取り戻し始めていた。
薔薇は一体何本買ってきたのだろうか。数えられないし重たそうだし、ロビーにいる人間は自分達のことを見つめている。情報量が多くて混乱しそうだ。そして何よりも恥ずかしい。
こんなところでプロポーズするなんて、もう少し場所を選べなかったのだろうか。
けれど、悪い気はしない。会ったばかりの頃なら仕事中ですと跳ね除けるところだけれど、今日ばかりは許そう。二人にとってとても大事なことなのだから。
答えはずっと決めている。文也が言った時に、今度こそちゃんと返事しようと思っていた。
「喜んで」
そろそろ花束が重そうだから受け取った方がいいだろう。ギャラリーも文也の腕を心配しているようだし、受け取れば結果が分かるだろう。
美帆が花束を受け取ろうとすると、文也はすいっと花束を持ち上げた。
「ちょっと、私にくれるんじゃないんですか」
「返品不可やで。ほんまにええんやな。やっぱやめますとか絶対になしやで」
「なっ……さっき言ったじゃないですか!」
「受け取ったからには絶対に逃さへんからな。途中で愛想尽かさんといてや」
「もう! 注文が多いですね! ちゃんと一緒にいますから────」
やっと美帆の腕の中に花束が渡った。かなりずっしりして重かった。見た目はゴージャスだが、持っている方は重さの印象の方が勝つ。
そしてそのまま、花束を持つ指にするりと何かが嵌った。確認するようにそれを覗き込む。先ほど文也が見せていた指輪だ。
「美帆、幸せ?」
そこは「幸せにするよ」でしょうと心の中でツッコミを入れる。けれどこれも紆余曲折を経たからだろうか。
もし文也が不安なら、自分がすべきことは一つだけだ。困ったことは二人で解決したらいいし、寂しい時は寄り添ってあげればいい。自信がない時はたくさん愛してあげればいい。
これからずっと一緒にいるのだから。
「とっても」
完
どうやら美帆がいない間に文也が来て、カフェのドリンクやお菓子を差し入れしてくれたらしい。
しかし、どうして自分がいない時に限って、と美帆は憤慨した。
「津川さん太っ腹ですねえ。うふふ、さすが美帆さんの彼氏さんですね」詩音はニマニマ笑っている。よほど差し入れが嬉しかったのだろう。
「ずるいじゃない。なんで私がいない時に来るの?」
「たまたま寄ったんですって。美帆さんの分もありますよ。ほら、このお菓子です」
詩音は受付に置かれた箱の中から個包装のクッキーを取り出した。別にクッキーが羨ましかったわけではない。ただ、ちょっと会えたらと思っただけだ。そこまで食い意地は張っていない。
それからいつも通り業務を始めた。
今日の総合受付担当は詩音と美帆だ。仕事は特別変わったことはない。ややこしい来客もないし、落ち着いた一日になるだろう。
やがてお昼時を迎えて、ロビーは若干混み始めた。混んでいるといってもコンビニぐらいだ。あとは社員食堂に行く人間と外に食べに行く人間。この時間は受付も手が空く。
「しばらく予定も空いてるし────私お昼行ってこようかな」
「えっ!?」
美帆が立ち上がると、詩音がやたら驚いた声をあげた。
「どうしたの?」
「あの、私先にお昼に行っちゃ駄目ですかね」
「え? うん。いいけど……じゃあ、私あとから行くね」
「あの、受付にちょっと私の知り合いが来るかもしれなくてですね」
「うん?」
「だからもうちょっとだけ、待ってもらってもいいですか」
詩音はなんだか必死だ。よほど大事な用事なのだろう。
────ははぁ。もしかして、彼氏が会いに来るのかな?
詩音も彼氏と仲良くやっているようだし、一緒にランチに行きたいのかもしれない。
「お腹空いてないし大丈夫だよ。気にしないで」
「ありがとうございます」
お昼の時間帯が多少前後しても問題ない。きっかり十二時に昼休憩を取ることの方が珍しいし、受付では飲み物を飲んでもオーケーということになっている。時間がずれるぐらいなんてことはない。
────それにしても、彼氏が来るならそういえばいいのに。もしかしてまだ遠慮してるのかな。
彼氏がいない時間が長かったから受付の皆にはずいぶん苦労をさせた。だが、今は文也という彼氏がいる。恋人の話を聞いても羨ましいと思うことはない。
思い出すと会いたくなってきて、チラリとスマホの画面に視線を向けた。この間会ったばかりだが、夕食に誘ってみようか。文也がいいと言ったらそのまま家に行って────。なんて妄想を頭の中で繰り広げる。
連絡しようとスマホの電源を入れた時だった。なんだかロビーがざわついてふっと視線を上げた。
「えっ」
声をあげたのは美帆だけではなかった。小さな声はロビーのあちこちから聞こえてきたが、それどころではない。エントランスから入ってきた人物を見て、美帆はぽかんと口を開けた。
とにかく驚いた。だから隣にいた詩音が珍しく大人しくしていることにも気が付かなかった。
文也はやたら大きな荷物を抱えて自動扉から一直線に総合受付まで向かってくる。焦っているのは美帆だけだ。
やがて文也は受付の前まで来ると立ち止まった。
文也が来るのは珍しい話ではない。今日はなんの予約もされていないが、たまたま近くに来て立ち寄ることは多々あった。だが、問題はそんなことではない。
「ふ……文也さん……?」
文也の手に抱えられた大きな花束を見て、ロビーにいる人間は美帆同様驚きを隠せない様子だ。受付に花が届けられることはあるが、お祝いはお祝いでもそれが表すものがビジネス関係でないと皆分かるのだろう。美帆も、それを見てすぐに察した。
今更ながら、詩音が自分を休憩に行かせなかったわけがわかった。
文也は大きな薔薇の花束を抱えていた。随分恥ずかしそうな顔をしている。
そうだろう。見ている美帆ですら恥ずかしいと思っているのだから、こんな人だらけの場所で巨大な花束を持って来た文也が恥ずかしくないわけがない。そんな性格でもないのだから。
文也は花束を抱えたまま、器用にポケットから小さな箱を取り出した。大きな花束を持っているから開けにくそうだ。思わず手を差し出してしまいそうになる。なんとか不格好ながらにそれを開けて、美帆に見せた。言うまでもなく指輪が入っていた。
やがて落ち着いたのか、ようやくやっと文也は口を開いた。
「杉野美帆さん。俺と結婚してくれますか」
文也はいつになく真面目だ。緊張しているのだろう。以前は唐突に言ったから今度はちゃんとしようと思っていたのだろうか。美帆は次第に冷静さを取り戻し始めていた。
薔薇は一体何本買ってきたのだろうか。数えられないし重たそうだし、ロビーにいる人間は自分達のことを見つめている。情報量が多くて混乱しそうだ。そして何よりも恥ずかしい。
こんなところでプロポーズするなんて、もう少し場所を選べなかったのだろうか。
けれど、悪い気はしない。会ったばかりの頃なら仕事中ですと跳ね除けるところだけれど、今日ばかりは許そう。二人にとってとても大事なことなのだから。
答えはずっと決めている。文也が言った時に、今度こそちゃんと返事しようと思っていた。
「喜んで」
そろそろ花束が重そうだから受け取った方がいいだろう。ギャラリーも文也の腕を心配しているようだし、受け取れば結果が分かるだろう。
美帆が花束を受け取ろうとすると、文也はすいっと花束を持ち上げた。
「ちょっと、私にくれるんじゃないんですか」
「返品不可やで。ほんまにええんやな。やっぱやめますとか絶対になしやで」
「なっ……さっき言ったじゃないですか!」
「受け取ったからには絶対に逃さへんからな。途中で愛想尽かさんといてや」
「もう! 注文が多いですね! ちゃんと一緒にいますから────」
やっと美帆の腕の中に花束が渡った。かなりずっしりして重かった。見た目はゴージャスだが、持っている方は重さの印象の方が勝つ。
そしてそのまま、花束を持つ指にするりと何かが嵌った。確認するようにそれを覗き込む。先ほど文也が見せていた指輪だ。
「美帆、幸せ?」
そこは「幸せにするよ」でしょうと心の中でツッコミを入れる。けれどこれも紆余曲折を経たからだろうか。
もし文也が不安なら、自分がすべきことは一つだけだ。困ったことは二人で解決したらいいし、寂しい時は寄り添ってあげればいい。自信がない時はたくさん愛してあげればいい。
これからずっと一緒にいるのだから。
「とっても」
完