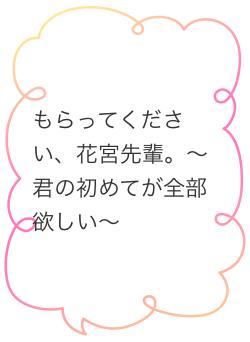キスで捕らえて許さない。
「みっちゃん、いかないで、やだよぉ」
「まな、ぼくおおきくなったら、まなのことむかえにくるからね、つよくなるから」
「うん。まってる……!」
「だから、そのときは────」
ガバッ!!
そうだ、あの時だ。夢を見た。あの時私は、みっちゃんと離れ離れになる悲しさのあまり、その約束に大きく頷いたんだ。
だって、子供のする約束なんて時効だもん。年齢を重ねるごとに忘れてしまう。今はカーテンの外が真っ暗なことからきっと深夜。
私は路地裏でみっちゃんに助けられ、そのまま馬鹿でかいマンションの一室に連れ込まれた。
私が寝かされていたのはやけに寝心地のいいキングサイズのベッドで、私が帰る帰ると騒いだから、みっちゃんに抱き込まれて寝かしつけられてしまったんだった。
昔から変わらないみっちゃんの子供体温に、私は一発で夢の中だった。危機感がないとかそんなことは分かっている、けど眠ってしまったものは仕方ない。眠剤とかは飲まされてない、はず……。
「みっちゃんは……いない。よし」
いつの間にかみっちゃんはいなくなっていた。私はベッドから降りて、ひたひたと大理石の床を進む。寝室のドアを開けて、リビングには誰もいない。そろそろと足を進める。
みっちゃんには申し訳ないけど、私は普通に学校に行きたいし普通の暮らしがしたい。それに、路地裏で会ったみっちゃんの仲間…?明らかに不良だった。多分平々凡々な私が関わったらいけない人達。
だからあの楽しかった過去は、過去として思い出に変えてね。きっとみっちゃんみたいにかっこよくて優しい人なら素敵な恋人ができるよ。
心の中で言い訳をしながら、私はリビングから玄関に続くドアを開こうとドアノブに手を掛ける。
────しかし、ドアが開くことはなかった。
「愛菜、なにしてるの」
耳元で、恐ろしいほど冷えた声が響く。
いつの間にか私の身体を包む様に、背中にピッタリとみっちゃんの身体がくっ付いている。そして伸ばされた手がドアをしっかり押さえている。
こ、これは死んだ。やばいやばいやばい。
逃げようとしたけど、ドアを押さえている手とは逆の腕が私の腰に巻きつき、まるで子供に言い聞かせる様なゆっくりとした声が耳元に吹き込まれる。
「お腹すいた?何か欲しかった?」
「い、いや……あのね、みっちゃん。私やっぱり帰り」
「あぁ、お風呂か。まだ入ってないもんね」
「違う違う、聞いてみっちゃん、ちょっとおかしいよ」
「────なに?じゃあまさか、逃げようとか考えてたの?」
そうです逃げようとしてましたえへへ。なんていえないほど、私の背中の気配が恐ろしいことになっている。多分今振り返れば私はボコボコにされてしまうのではないか。
私がみっちゃんの問いに答えずにいると、肩にぽすんとみっちゃんの額が乗った。
「えっと……あの」
「許さないよ」
「っ……」
「俺から逃げるなんて、俺は愛菜がいないと生きていけないのに。絶対に離れるなんて許さない」
「みっちゃん」
「愛菜の親には、俺から連絡したよ。ちゃんと説明したら、これからよろしくお願いしますだって」
「え?!うそでしょ……そんなっ」
「学校だって一緒に行こうね。俺の学校に転校届けも出してあるからね」
恐ろしい執着だ。なにがみっちゃんをここまで突き動かすんだろう。
けど、これで私の自由は全てみっちゃんの手のひらの上だ。昨日までの平穏は、全て崩れ去ってしまった。
するりとみっちゃんの手が私の顎を掴み、上を向かされる。そして視線が合い驚いた。
やることはこんなに強引なのに、こちらが悲しくなるほど切ない表情をしていたから。
「愛菜も、俺なしでは生きていけないくらいに溺れて」
上を向かされたまま、苦しい体制でのキス。唇をぴったりと塞がれ、呼吸を奪われるほど重ねては角度を変え、熱を移される。
溺れてしまう、苦しい、熱い。こんなの、おかしい。
やっと唇を解放され、私が膝から砕け落ちるとそのまま抱えられた。みっちゃんは満足そうに腕の中の私を見下ろすと、優しく微笑む。
「大丈夫、また寝かせてあげるからね」
「……頼んでないよ。っていうか、どこにいたの?」
「ベランダで電話してたら、愛菜がこっそり寝室から出てきたからしばらく見てたんだ」
「へっ」
「今度逃げようとしたら、キスどころじゃ済まさないからね」
「……うう」
逃走は失敗。知らず知らずのうちに周りも固められた。
こんなに強引で、最低なのに。
どうしてもみっちゃんを憎めないのは、なんでなんだろう。