政略結婚を前提に恋愛しています
昨日までは疑似兄妹、今日からは新婚夫婦
【Side:花嫁B】
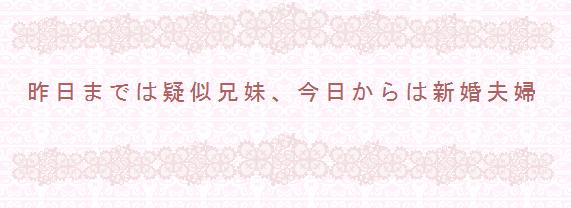
いつか、この日が来るのを、ずっと待ち望んでいた。
大好きなこの人の、お嫁さんにしてもらえる、今日のこの日を。
この人は、私のことを妹のようにしか扱ってくれない。
私も戯れに「兄様」なんて呼んだりしていたけれど……兄だなんて、思ったことは一度も無い。
兄妹のような関係ではなく、ちゃんとした夫婦になれる日を、ずっとずっと待っていたのだ。
許嫁という関係性は、相手が理想の人であるなら、とても便利で都合の良いものだと思う。
想いを告げなくても、恋仲になる努力をしなくても、時が来れば自然と“夫婦”になれるのだから。
この人は、私にとって理想そのものだった。
……いいえ。むしろ、物心も満足につかない幼いうちに、この人と出逢ったものだから、私の理想そのものが、この人を基準に形成されていったという方が正しいのかも知れない。
それは刷り込みのような恋だった。
けれど、私にとっては、ちゃんと恋だった。
初めて会ったその日から大好きで、その気持ちをずっと、大切に育み続けてきた。
幼い頃は、ただその気持ちを、この人にぶつけることしかできなかった。
はしゃいで、甘えて、まとわりついて……。
一緒にいてくれなければ嫌だと、泣いて駄々をこねた日もあった。
今にして思えば、この人を困らせてばかりだった気がする。
けれどこの人は、そんな子どものワガママにも、苦笑してつき合ってくれていた。
だから私はますます、そんなこの人のことが大好きになったのだ。
成長するにつれ、夫婦という関係が、必ずしも愛によって結ばれたものではない、という事実を知るようになった。
形だけの夫婦、愛の無い政略結婚――そんなものが世の中に溢れているのだと、知るようになった。
そうして私たちの関係性を振り返ってみた時、私は衝撃を受けた。
私とこの人の関係もまた、政略のための結婚を前提としていることに気づいて。
正直、焦ったし、正直、ちょっとしたパニックになった。
このまま大人になって結婚すれば、無条件で幸せになれると思っていたのに……そもそも自分が、彼に想われているのかどうかも分からないという、その事実に打ちのめされた。
許嫁という関係性は、時にとても不便で不都合なものだと思う。
想いを告げなくても、恋仲になる努力をしなくても、関係が成立してしまうということは、そこに恋愛感情があっても無くても関係ない、ということだ。
この人が私のことを、好きだと思ってくれているのかどうか……確かめたい気持ちと、確かめるのが怖い気持ちが半分半分で、結局ちゃんと訊けないまま、今日まで来てしまった。
だけど、何もして来なかったわけじゃない。
もし私のことが好きじゃないなら、好きになってもらえるように……もし私のことを既に好きなら、もっと好きになってもらえるように、できる限りの努力をしてきたつもりだ。
経験値の低い私には、男の人の恋愛心理なんて分からない。
だから、ただ“私がされて嬉しいこと”を実行しただけだ。
いつでも笑っていて欲しいから、私もいつでも笑いかける。
一番の味方でいて欲しいから、私も、この人の一番の味方でいる。
愛情を示して欲しいから、私も精一杯の愛情を示す。
「兄様、大好き」「世界で一番、兄様が好き」
何回、何十回、何百回言ったか分からない。
だけど、この人は微かに笑って頷くだけで、ただの一度も「好きだ」と言ってくれない。
昔は簡単に言えた「好き」も、そのうちだんだん、口にするのが難しくなっていった。
口にしようと彼を見上げるたびに、甘酸っぱい何かが胸に詰まって、上手く言えない。
心臓が震えて、きゅっとなる。
きっと「好き」の中身が複雑になってしまったんだ。
切ないような、怖いような、苦しいような、嬉しいような……とても一言で表せない気持ち。
昔はもっと単純で、簡単なものだった気がするのに。
昔から、話しかけるのはいつも私が先で、私ばかりがおしゃべりしているようなものだったから、私が言葉を出せずにいると、会話が続かなくなってしまう。
物も言えずにもじもじする私を、この人は困ったような顔で見つめてくる。
そうすると私は不安になって、一層何も言えなくなってしまう。
会うのを拒否されることも、婚約を破棄されることもなかったから、結婚自体を望まないなんてことは無いはずだけど……この人の気持ちが、分からない。
分からないまま結婚するのが、怖くて、不安で堪らない。
だけど、そんな私の心などお構いなしに、婚姻の準備は着々と進んでいった。
そして、今日、私はこの人の花嫁になった。
もう子どもではないから、結婚がどういうものなのか、ちゃんと知っている。
これから為される未知のあれこれが、怖くないと言えば嘘になる。
だけど、それでも……ずっとこの日を待っていた。
もしかしたら、形だけのことなのかも知れなくても……この人が、私だけの特別な人になるこの日を、ずっとずっと待っていたのだ。
新床の上、二人向かい合い、三つ指ついて挨拶を済ませ……私はただ、事が始まるのを待っていた。
だけど……この人は、なかなか動き出さない。
怖いくらいの眼差しで、じっと私を見据えたまま、微動だにしない。
「あの……旦那様……?」
声を掛けたは良いものの、何を問えば良いか分からない。
あまりあからさまなことを訊くのは、何だか恥ずかしい気がする。
「あの……私は……どうしたら……?」
おずおずと、彼の俯いた顔を覗き込む。
次の瞬間、私は手を引かれ、彼の広い胸に抱き寄せられていた。
「分かっているのか、お前は。これから何をされるか」
その囁きは、何故だかとても苦しげに聞こえた。
私は戸惑いながらも、問われたことに答えを返す。
「……はい。知識だけは、ちゃんと教わって来ましたから」
その答えに、彼はフッと笑う。
笑われたのかと身構えたが、彼は、慈しむような瞳で、優しく私を見つめていた。
「出逢ったばかりの頃は、あんなに小さかったのに……」
「それは……ほんの幼子でしたもの。でも、今はもう大人です」
「腕も腰も、まだこんなに華奢なくせに……」
言いながら、つ……と腰骨の辺りを撫で下ろされ、ビクリと身を竦ませる。
彼はその厚い手のひらで、私の両頬を挟み込み、じっと目を覗き込んでいた。
「俺は、お前を壊してしまうのが怖い。俺は酷い男だ。それでもお前は、俺を愛してくれるか?」
気弱な問いを口にしながらも、その両手は私の頬を捕え、逃がさないとでも言いたげに固定して放さない。
それなのに、その目には迷いや、怯えにも似た色が滲んで、揺れていた。
思いきって、私の方からも手を伸ばし、強張った彼の頬に触れてみる。
「……怖がらないで、兄……旦那様。私、一方的にされるばかりじゃありません。だって、これは、二人で探って、深めて、育んでいくものでしょう?」
今、何となく、分かった気がする。
怖いのは、不安なのは、私だけじゃなかった。
この人も、怖さと不安を抱えていたんだ。
相手が大事であればあるほど生まれる怖さを、この人も抱えてくれていたんだ。
想われていないわけじゃなかった。
私は、ちゃんとこの人に大事に想われていた。そのことが伝わってきて、どきどきした。
「大好きです……旦那様」
昔のように素直な言葉を、震える唇から絞り出す。
促すように、ねだるように、彼の頬を指でなぞると、その唇がゆるゆると開いた。
「ああ。俺も……お前が好きだ」
ずっとずっと聞きたかった言葉が、やっと聞けた。
けれど、じんわり感慨に浸っている暇など無かった。
初めての夜が、始まる。
これまでの関係が、決定的に変わっていく。もう、戻れない。
初めての感覚に翻弄され、我を失いそうになりながら、頭の片隅で思う。
本当の本当に好きだという、この気持ちが、この人の胸に、ちゃんと届いているかな、と。
疑われることなく、勘違いされることなく、そのままの形で伝わっているかな、と。
できれば彼の心臓の真ん中に、真っ直ぐ突き立って、抜けずに残り続けて欲しい。
肉体だけでなく、心までちゃんと、しっかり結ばれるように。
だって、この人は今日から私の旦那様。
唯一無二の、人生を共に行く伴侶なのだから。
