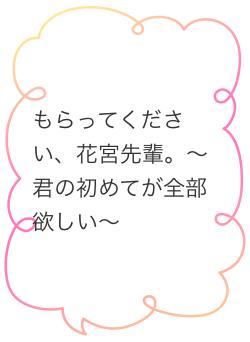雨の日、しゅわしゅわ。
「もう、最悪」
────梅雨なんて大嫌いだ。
何故かって聞かれたら、それはもう理由なんてたくさんある。なんかジメジメして蒸し暑いし、髪の毛はアイロンしても唸るし、ローファーの中がびしょびしょになるし、空は毎日どんよりしてるし。
私は放課後、昇降口の外で、そんなどんよりとした空を睨みながら突っ立っていた。だって傘がないんだもん。
今日の朝の予報は、梅雨の合間の晴れ間とか言ってたし、空も快晴。私はお母さんの折りたたみ傘を持って行きなさいと言う言葉を無視して、家をるんるんスキップして出てきた。そして今、目の前は突然の土砂降りなわけ。もう泣きそう。
「委員会なんて聞いてないし」
そう、委員会なんてなければこんな土砂降りに巻き込まれることなんてなかったはず。最悪、ほんっっとうに運が悪い。
けど、空の向こう側が晴れてるから、通り雨かもしれない。止むまで気長に待とうと、下駄箱に寄りかかりスマホをポケットから出すと、後ろから妙に大きな声が聞こえた。
「最悪だ」
その声と同時に、ドサリと鞄が床に落ちる音がする。チラリと横目で見ると、運動部の男子が持っているエナメルバックが床に置かれていて、そのすぐ側で男子がしゃがみ込み空を睨んでいた。
あ、この人知ってる。サッカー部で一番元気な三波くんだ。身長は男子の中では小さな方なのに、結構可愛い顔をしているからなかなモテる方だ。話したことはないけど、クラスの女子が噂してたことがあるから知ってる。
けど、私は一度も話したことがないし、声を掛けることもなくスマホに視線を移した。横から視線を感じた気がしたけど、知らないふりをしてSNSに夢中になる。
「(今日のトレンドの若手俳優、結婚してたのか〜)」
「なぁ」
「(まぁ、これだけかっこいいし、女は放っておかないよね)」
「なぁって!」
「ひっ!」
「なんで無視すんの」
「え?……えっ?無視?」
いつの間にか、人一人分空けたすぐ隣に三波くんが立っていた。小さいとはいっても女子よりは普通に背が高いから、私は見上げる形になる。
それにしても、無視って言われても私三波くんと話したことないし。頭の上に?マークを浮かべていると、何かを差し出される。
「腹減らね?飴あげる」
「い、いいの?」
「いいよ。たくさんあるから」
そう言って、三波くんは私にカバンの中身を見せる。そこには飴の大袋が入っていて、確かにこれなら私に分けてもたいしたことないな、とホッとする。
けど、なんで突然三波くんは話しかけてきたんだろう。コミュ力が高い人はこれが普通なのかな?
「……私達、話したことないよね?」
「ないな」
「じゃあ、なんで飴くれたの?」
「えー、雨宿り仲間じゃん」
「雨宿り仲間?」
「梅雨に折りたたみ傘も持たず歩いてる時点で、なんか俺たち似てそうじゃね?」
「えー、そうかなぁ。私はたまたまだよ」
「そうですかー」
三波くんの会話のテンポはどこか心地いい。これは人気者な理由も頷ける。
貰った飴の包みを開けて、パクリと食べると私の一番好きなサイダー味だった。口の中でしゅわしゅわが広がって幸せな気分になる。
甘みに浸っていると、再び話しかけられた。
「亜美さんだよな?名前」
「え、何で名前知ってるの」
「同じ部活に安野がいる。アイツ幼馴染なんだろ?」
「あー、陽太ね。幼馴染だよ」
「アイツさ、よく部活で亜美さんのこと話してて」
「ちょっと待って、どんなこと?」
「カレーの日は決まっておかわりするとか」「アイツありえない……」
陽太は私の幼馴染で、よく晩御飯を一緒に食べる。明るくてお兄ちゃん気質でお世話になってはいるが、まさかそんなことを部活で話しているなんて……!!
私はすぐさまスマホのメッセージアプリを開き、陽太に後で殺すと送った。
「いいじゃん、カレー俺も好き」
「……カレー嫌いな人なんていないでしょ」
「確かにな。おかわりしたくなる気持ちも分かる」
「ねぇ!忘れてよそれ!」
「無理だろ。そんなに細いのにカレーおかわりしてるとかギャップがやばい」
「細いって言われるのは嬉しいけど、ほんと忘れてほしい」
「そんなに?」
私が恥ずかしさのあまり両手で顔を覆っていると、影が顔に掛かった。
何だろうと両手を外すと、至近距離で顔を覗き込まれていて驚き、背後の壁に頭を思い切りぶつけてしまった。
「いったい!!」
「わ!悪い!」
「な、何でそんなに近くにいるの?!」
「いや、泣いてるのかと思って……!!」
「泣かないよこんなくだらないことでっ」
「そ、それならよかった」
「…………」
私達の間に妙な雰囲気が流れる。三波くんは何故か話さなくなってしまった。
けど、近くで見た三波くんの顔、かっこよかったな……。二度目だがモテるのも頷ける。今更顔が赤くなってきた。
私達が無言でいると、後ろからおーいと声が聞こえた。振り返ると、そこには陽太が立っていた。私は瞬時に陽太に近付き、脛を蹴る。
「いてぇ!!!」
「天罰だよ」
「……なんだよ、亜美はよく分かんねーな。三波もまだ帰ってなかったのか、傘は?」
「ない」
「亜美は?」
「ありませーん」
「馬鹿二人」
陽太の手にはビニール傘がある。そして、片手で鞄を漁るとそこからは折りたたみ傘が。
「陽太、それ三波くんに貸してあげて。それで私は入れて帰ってよ」
「えー……」
私の言葉に、陽太は何故か三波くんを見つめ歯切れの悪い返事をする。
すると、何を思い立ったのか、三波くんにビニール傘を渡し、折りたたみ傘をさして雨の中に飛び出した。
「は!ちょっと陽太!」
「お前はそれで一緒に帰れよ!じゃーなっ!」
「ふざけんな!」
「三波!後でコーラ奢れよ!」
ビシャビシャと雨の中傘をさし、陽太は走り去って行ってしまった。
私は陽太の背中を見つめ、深いため息をつく。何なのアイツはマジで……。
すると、横で三波くんが傘を開いた。
「んじゃ、帰るか」
「え、でも」
「俺的にはラッキー、なんて」
「……ラッキー?」
「だって俺、飴準備してタイミング伺ってたし」
グイッと手を引かれ、傘の中に入れられる。至近距離で見上げた三波くんの頬は真っ赤だった。
つられるように私も赤くなる。
その数週間後、あっという間に三波くんの彼女になった私は、彼の初恋が私だと知る。
『雨の日、しゅわしゅわ。』おわり