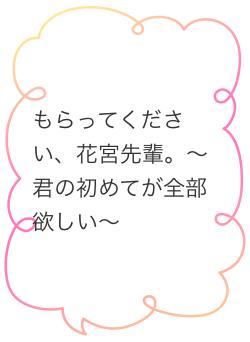爪先のワンフレーズ
今日は、自分で言うのもなんだけど、いつもと違った。
何度も何度も、本当に何度も練習したフレーズ。楽譜を見なくても、何も考えていなくても、身体に染み込んだ、染み込ませた大切なソロのある曲が今から始まる。
あの数小節を得るために、二年なのに生意気だと陰口を叩かれても、朝から晩まで練習して自分の手で掴み取った努力の証。
大丈夫、いつも通り吹ける。トランペットのメンテナンスも完璧だし。ピカピカに磨いたじゃん。いい音出るって。練習で先生に褒められたじゃん。
────なのに。
「────ぁ」
目が眩むほど眩しい舞台、満員の客席、曲の始まりに指揮者がお辞儀をし、会場が割れんばかりの拍手に包まれる。
指先が痺れるように震えて、冷たい。そんなことは関係なしに指揮者の指揮棒は振られ始める。
今日は、二年生になって初めてのスプリングコンサートだ。
曲はどんどん進み、木管と金管が激しく入り乱れる美しい音の圧が消え、伴奏が木管楽器の柔らかで静かなものになる。そして、私は震える手で楽器を構えた。指揮者と視線が合う。
大丈夫、大丈夫だから、お願い、いつも通り。
そして、深く深く腹式呼吸をして────。
「っ────」
私は、音を出すことが出来なかった。
指揮者は目を見開き、口パクで何かを言っている。けど、ダメ、なんで。
どうして私は────。
吹奏楽の名門中学に入学し、一年のうちは毎日基礎練基礎練、楽譜を貰えても全てがサード。勿論コンクールには出られない。上下関係も厳しい。
自分が先輩達と比べて下手くそなことは分かっていた。けど、それでも悔しくて、認めて欲しくて。毎日毎日泣きながら練習していた。
「おー宮野、今日も早いな」
「相沢先輩、おはようございます」
私が一年の時に同じパートの三年生に、相沢先輩という男子がいた。
明るくさっぱりとした性格で面倒見がよく、男女問わず人気がある。コンクールメンバーの先輩だった。
けど、相沢先輩がコンクールメンバーに選ばれたのは三年生になってかららしい。メンバー層の厚いこの部でコンクールメンバーをもぎ取るのには、並大抵の努力では足りない。きっと想像を超える努力したんだろう。
それを裏付けるように、先輩の音は厚みがあって、中低音は美しく響き、高音は華やかでよく通る。
相沢先輩は、いつも一番に登校し、朝練を始める私のすぐ後に来ていた。
だから、二人で会話をする機会もたくさんあった。
「お前さぁ、構えが下すぎるんだよ。それじゃあ音が飛ばなくてもったいねーだろ」
「えっ……ありがとうございます気を付けます」
「後、さっきの音少しピッチ高いかも。気持ちもう少し管抜いた方がいい」
「……少し聴いただけなのに、よく分かりますね」
「伊達に練習してねーからな。それに俺、耳だけはいいんだよ」
相沢先輩は自分の耳朶を掴み、へらりと笑う。
そして、ケースからトランペットを取り出してマウスピースに息を吹き込んだ。
三年生なのに、毎日学年で一番に音楽室に来て朝練をして、こうやって後輩の面倒まで見てくれて、楽器だって私なんかよりもずっとずっと上手で。
────私は来年、再来年、相沢先輩に追いつけるくらい上手になれているんだろうか。
何だか不安になって楽器を下ろすと、先輩は不思議そうに私の顔を覗き込む。
「どうした? 体調悪いのか?」
「……いえ、あの」
「なんだ」
「私、先輩みたいに上手になれますか? いつか、コンクールメンバーになれますか?」
「は」
「先輩みたいに、舞台でソロを吹きたいです」
まっすぐに見つめ思いの丈を吐き出すと、先輩はとても驚いた表情をした後、にやりと笑った。
「それはなぁ、お前次第だろ」
「うっ……そうですよね」
「けどな、アドバイスがあるとしたら」
「はい」
「何度失敗しても、何度心が折れそうになっても、思い出せ。練習はお前を裏切らない」
「…………」
「こうやって、毎日一番にここに来て練習をしていることは絶対に無駄じゃない。だから、どんなに大きな失敗をしても、進み続けろよ」
相沢先輩は私の頭に大きな手を乗せ、わしゃわしゃとかき混ぜる。
「未来のことは分からないけど、俺はお前の音が好きだよ。頑張れ、俺はお前の努力を信じてる」
──相沢先輩が卒業してからも、あの日の言葉は私の糧だった。
演奏会の一部が終わり、舞台袖にはける。
部員のみんなが励ますように声を掛けてくれたけど、それが聞こえないくらいに私の心は深く沈んでいた。
ぐわんぐわんと視界が揺れて、今にも膝から崩れ落ちそうだった。
────練習しても、無駄じゃん。本番で失敗したら、意味なんてない。
だったら、今までの私は……。
「宮野」
「っ」
その声で弾かれるように振り返る、そこには卒業した相沢先輩が立っていた。
そっか、演奏会だから先輩方が手伝いで来てくれてるんだ。
相沢先輩は真っ青であろう私の顔を見て、あろうことかにやりと笑うと背中をばしりと叩いてきた。
「痛いっ!」
「おいおい落ち込んでるな」
「……そんなの、当たり前」
「何度失敗しても、心が折れても、進むんだよ」
「……えっ」
「大丈夫だ。お前の努力は無駄になったわけじゃない」
「せ、んぱい」
「こうやって失敗重ねて成長するんだよ。まだこれはスプリングコンサートだから、平気だ」
先輩の言葉でじわりと涙腺が緩む。けど、泣けない。まだコンサートは終わってない。
そうだ、まだ私の努力の日々も終わったわけではない。
「コンクールメンバーになったんだろ? 今年」
「はい。頑張りました」
「俺より昇格早いじゃねーか。すげーな」
「相沢先輩よりも上手になりたいので」
「ははは、そうかよ。だったら俺も、高校で沢山練習しないとな」
相沢先輩が私の背中を押す。そしてあの日と同じような、明るく安心する声が後ろから聞こえた。
「頑張れ、俺はお前の努力を信じてる」
『爪先のワンフレーズ』おわり