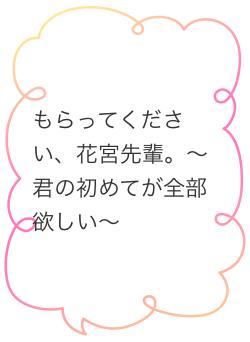もっと、甘く縛って厳しく躾けて
「先輩、私はもう怒りました」
「何に」
「自分の心に聞いてみてください」
「何も身に覚えがない」
「犯罪を犯した人も最初はそう言うんです」
「冤罪だ」
「え、えんざい……?」
「ほら、世理はお馬鹿なんだから無理しなくていいよ。何に怒ってるのか言ってみな」
「キィー!」
私の怒りにはちゃんと原因がある。
放課後、花夏先輩の家で、今日の私はお利口だったから怖い躾もなく、ただ甘やかされていた。
ベッドに座る花夏先輩に手を引かれ、向かい合うように膝に乗せられた。肩に顔を埋められる。そのまますんすんと匂いを嗅がれ、私は花夏先輩の髪の毛が頬にふわふわ当たってくすぐったくて身を捩る。
「ふふふ、くすぐったい」
「可愛い、シャンプーの匂いも可愛い。俺だけの世理」
「えへへ、嬉しい。もっとぎゅうしてください」
「何それ、あざと過ぎて心配になるんだけど」
「あざと……?」
「ごめんね世理には難しかったね。ほら、ぎゅう」
ぎゅむぎゅむと抱きしめられ、すりすりと頬ずりをされて、ちゅ、ちゅ、と目尻や額、唇に優しくキスしてもらえる。その甘く柔らかな感覚に、思考がとろりと溶けて、私はへたりと花夏先輩に体重を掛けた。
怖くないキスは大好きだ。ぽやぽやして、胸があったかくなって、幸せな気持ちになるから。
なのに、花夏先輩はそんな私を見て目を細めると、キスをするのをやめてしまった。
「……んう、なんで……?」
「もうおしまい」
「もっとしたい……」
「もっとしたら、怖くなるよ」
「へ?」
「躾、怖いでしょ。あんな感じになる」
「……なんでそうなるんですか……?」
「無知って怖いよね」
「むち」
「何も知らないってこと。大丈夫、俺が全部教えるから。安心して世理はお馬鹿なままでいな」
私が首を傾げると、花夏先輩は私のオデコに自分のオデコをこつりとくっ付ける。そんなに至近距離にこられると、余計にまたキスしたくなっちゃう。
けど、我慢我慢。私は花夏先輩のお利口な彼女になりたいから、我慢する。
それに、躾は怖い。イヤイヤしてもやめてもらえないから。
私は花夏先輩の膝から下ろされ、ベッドに座る先輩を床にペタリと座り見上げる。先輩はそんな私を見て、艶やかに微笑む。
「可愛いなぁ、世理を見てるとほんと支配欲を駆り立てられる」
「これ以上支配されたら私身動き取れません」
「支配欲は分かるんだね」
「えへへ」
「うーん、俺的にもっと身動き取れなくさせたいところなんだけど」
「へっ」
「もうさ、こんなにお馬鹿で無知で可愛くて、よく俺に見つかるまで無事でいたよね。はぁ、もっと早く見つけたかった。そしたら問答無用で女子校に行かせたのに。本当に他の男の目に触れさせたくない、会話させたくない、閉じ込めたい。閉じ込めて良いかな?」
「花夏先輩、私閉じ込められるのは窮屈で嫌です。運動はしたいもん」
「うーん、運動は好きなだけしてもらっていいんだけど」
見上げる私のほっぺをすりすり撫で撫でする花夏先輩の言葉を聞きながら、私は唇をとがらせる。
男子と話せないのは全然いい。花夏先輩がいればいいから。けど、体育大好きスポーツ大好きな私にとって、閉じ込められるのはちょっとだけ嫌。それは無理。
そう考えているうちに、私はハッと嫌なことを思い出し、顔をくしゃっとしてしまう。それを見た花夏先輩は目を大きくした。
「どうしたの世理。ブサイクやめて? ほら、可愛い顔に戻って」
「花夏先輩、今度、球技大会あるじゃないですか」
「ああ、うん」
「先生に、お前は教室で補習って言われたんです」
「へぇ」
「……私、球技大会、楽しみだったのに。バレーしたかった」
三度のご飯より花夏先輩と運動が好きな私から球技大会を取り上げるなんて、先生酷いと抗議したけど、先生は顔を青くして首を横に振るだけだった。
私の目にうるうると涙が溜まるのを見て、花夏先輩はぎゅっと抱きしめてくれた。嬉しい、慰めハグだ。けど悲しい。
悲しむ私を他所に、花夏先輩は次の瞬間爆弾を落とした。
「クラス単位の体育はまだしも、世理の体操着姿が全校生徒の目の前に晒されるのは我慢できなかったから、学校の対応には感謝だね」
「へ、え? 先輩?」
「世理を球技大会に出さない代わりに、学校のパンフレットに俺のこと載せるのを承諾したんだ。ダメだよ、球技大会なんてダメ。絶対」
──そして、冒頭に戻る。
キーキー怒る私を見た花夏先輩は、悩ましげに首を傾げた。
「だって世理、去年バレーの決勝出たよね。俺それで世理を見つけたんだから。すごく目立ってて可愛かったけど、同時に他の男子にエロい目で見られる場だよあれは」
「花夏先輩、今日ちょっと脳みその調子悪い?」
「絶好調だから。ハラチラとか汗で火照る身体とか、男は欲の塊なんだよ。そんなもの他の男に見せるわけにいかない」
「じゃ、じゃあ長いジャージ着るから」
「ダメ」
「それなら、花夏先輩のお願いなんでも聞くからっ」
ぴくり、花夏先輩が動いたのが分かる。
私はなんとしても球技大会に出たい。だったら、花夏先輩のパシリでもなんでもやってみせる。お願い、どんとこいだ。
すると、突如グイッと両脇を持たれ、再び花夏先輩の膝に乗せられてしまった。至近距離に、目をギラギラさせた花夏先輩。
あれ? ちょっと、これ、なんか嫌な予感。
「それなら、お願い聞いてもらおう」
「は、はい……」
「躾の怖いキス、世理は嫌いだよね」
「やだ」
「俺、ずっと我慢してたんだ。お馬鹿で無知な世理の為に」
「え」
「最後までは無理だろうから、ワンステップ進んだ怖いことをします」
「なにそれっ、やだやだっ」
「球技大会」
「それとこれとはっ、ひっ」
ガブリと首筋を甘噛みされ、プチプチとワイシャツのボタンを手早く外される。私の悲鳴は花夏先輩の唇に食べられてしまった。
怖い、怖い。けど、本当はその中に気持ち良いが含まれているのを私は知ってるから、強く拒めない。結局、最後はとろとろに溶かされ甘やかされ、これが気持ちいいことだと躾けられるだけ。
数日後、花夏先輩のお願いを叶えた私は、一人だけ長袖長ズボンという異質な格好で、球技大会のバレーに参加することに成功した。