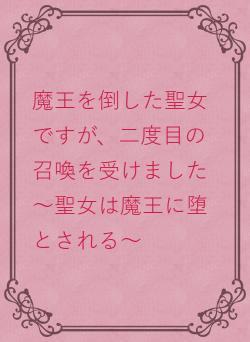猫耳少女は森でスローライフを送りたい
エピローグ
「私、は……」
次の言葉を出そうと、私はアルの腕を掴んだ。
アルがみんなに指示すると、みんながきちんとまとまった。
頼りになる人だなって思った。
時々憂いを帯びる少年の横顔は、何故なのだろうと気を揉ませられた。
けれど、殻を破ったアルは、急に大人になっちゃって。
彼を少年だと思おうと言い聞かせていた、私の思考が追いつかなくなった。
一度手を繋いだきりの彼の大きな手は、たくましく、温かだった。
二人で並んで仰ぎ見る空は明るく、空は青く空気も澄んでいた。
彼と一緒にいるだけでーー世界は、私の心は、幸福に満たされたの。
「私は、あなたのことが嫌なわけじゃない」
「うん」
「多分、好き……なんだと思う」
「……チセ」
私が掴んでいたのは、片方だけだったから、もう片方の手も彼の腕に添えた。
そうして、一つ息を吐いて、大きく吸い込んだ。
「私は、あなたが好き。……でも、それは求婚だとか、いきなりじゃなくて、ゆっくり考えさせて欲しいの」
何もかもが、私には急すぎる。
だから、ゆっくり考える、自分を言い聞かせる時間が欲しかったのだ。
「大丈夫。驚かせたり、急に驚かせたりしないよう、配慮するよ。……でも、俺が君のそばにいることを許して欲しいんだ」
「私こそ……アルに、そばに……」
「……うん」
言葉尻は小さくなってしまったけれど、私は今の想いを頑張って伝えた。
急に目の前が暗くなって、私よりもだいぶ背が高くなったアルが、私の方へ屈んだのだと気が付いた。そして気づいたその瞬間、額に柔らかく温かいものが触れた。
……キスだ。
私は額に口付けを受けていた。
「驚かせないって、いったそばから……」
私は、その感触に全く嫌な感じを感じなかったから、その口付けを受けながら瞼をそっと閉じて笑った。
目を閉じると、アルの息遣いを感じた。
「そうだな」
アルの唇がそうっと離れていって、その温もりが離れていくことに、私は少しの寂しさを感じる。
「そうだよ」
「じゃあ、抱きしめるのは許してほしい」
「仕方がないなぁ」
くすくすと笑い合いながら、私は体の重さを彼に預け。
そして、アルがその体重を受け止めて、ふんわりと抱きしめてくれたのだった。
私たちの抱擁がしばらく続いた後、「ゴホンゴホン」と咳払いの音が聞こえた。
ご両親の前じゃない!
私は、ぎゅうっと両手でアルを押しやって、熱くなった頬を両手で覆う。
憎たらしいことにアルは余裕なようで、お父さまに「まあまあ」なんて言っている。
「アルは、これからどうするつもりなんだ? 今の話だと、彼女と一緒にいたいんだろう?」
お兄さまがアルに尋ねた。
恥ずかしいことに(当たり前か)、私たちの会話はご家族に丸聞こえだったらしい。
「これからも、ルルド村……チセのアトリエに住み続けたいと思っています」
あれ?
国を守護する聖竜さまがうちにいていいんだっけ?
私は驚いてアルに確かめるように、彼を見上げた。
「ならば、ルルド村を聖竜の里として聖地に認定しよう。聖竜がそこにいたいというのであれば、この国の民も一生に一度はその姿を見たいと巡礼に赴くだろう」
「でしたら、王都から聖地までの道を整備しないといけませんね!」
お父さまとお兄さまがやる気満々といった様子で頷き合っていた。
「まあ、それは素敵。いっそ神殿でも作ったらどうかしら。アルの力を目覚めさせてくださったのなら、チセさんを巫女に認定してもいいかもしれませんね」
「おお。どちらもいい案だな!」
お母さまとお父さまが盛り上がっている。
でも、今欲しいのは巫女だの神殿じゃなくて、焼け落ちた家の修復よね。
(そして丁重に巫女は辞退したい。)
「聖地となって、道が整備されれば、人の往来も増えて村も次第に潤うことでしょう。私たちは、道が整備されてゆく間に、村を綺麗に整えたいと思います。先日の件で、焼けた家も直さなければなりません」
「ああ、そうだったな。焼け落ちたままでは生活も立ち行くまい。早々に手筈を……」
「父上。兵士に私が以前赤竜だった時の剥がれ落ちた鱗を預けております。あれを国に買い取っていただきたいのです。村人たちの生活のために必要なものの、資金が欲しいのです」
「ならば、財務卿に話を通しておこう」
「ありがとうございます」
結局、神殿云々はまだあとにして(それでも、そのうちできるらしい……)、村の復興を優先することになった。
そうして、私たちは換金手続きが済むまで王城に滞在することになったのだ。
「ねえ、アル。あれはなあに?」
私たちは今、アルの案内で王都で街歩きをしている。
そして私が指差した先には、良い匂いのする屋台のようなものがあったのだ。
「ああ、あれは獣の肉を金属の串に刺して焼いた、屋台料理だな」
やはり、あれは焼き鳥の屋台のようなものだったらしい。
「食べてみるか? 美味いぞ?」
アルが懐から袋を取り出す。
多分、奢ってくれるというのかなあ?
でも自分で言い出しておいてどうなのかな、と思って自分も懐からお金の入った袋を取り出そうとした。
「こら、チセ。ここでは全部奢ると言っただろう」
つん、とアルに額を人さし指で軽く押された。
「だって、自分で言っておいて奢ってもらうなんて、『奢ってほしい』ってねだっているみたいじゃない」
ぷう、と私は頬を膨らませる。
「ねだるくらいでいいんだよ」
アルがそう言って私の膨らんだ頬をつん、と押す。
私は、頬が熱くなるのを感じながら、押された方の頬を手のひらで隠す。
ーーなんか、これってデートっぽくないかな?
そう思ったら、途端に頬が熱くなったのだ。
そうして歩いているうちに、屋台の前に到着した。
「ほら、どれにする? ピグ豚に、コック鶏、珍しいな、こっちはカウ牛だ」
何だか、前の世界で聴いたのと似たような獣の名前をアルが説明してくれた。
私はコック鶏、アルはカウ牛を選んで、近くにある噴水のそばのベンチに並んで座る。
「ん! 美味しい!」
「だろう?」
私たちは顔を見合わせて笑う。二人とも、目は美味しさにまんまるになって、お揃いだ。
「んーー!」
横からもう一切れ噛み取って、その肉を咀嚼しながら空を仰ぎ見る。
空はどこまでも澄んだ青空。
そして隣には、多分、大好きな人。
ーーずっと、仲良く一緒にいられたらいいな。
神さまの思惑はどうであれ、私はこの世界で大切な人を見つけ出した。
もし神さまが天にいるのだとしたら、任務を達成した私たちには、この後幸せな人生を揃って送らせてくれてもいいんじゃない?
私はそう思って、笑いながら空を眺めるのだった。
次の言葉を出そうと、私はアルの腕を掴んだ。
アルがみんなに指示すると、みんながきちんとまとまった。
頼りになる人だなって思った。
時々憂いを帯びる少年の横顔は、何故なのだろうと気を揉ませられた。
けれど、殻を破ったアルは、急に大人になっちゃって。
彼を少年だと思おうと言い聞かせていた、私の思考が追いつかなくなった。
一度手を繋いだきりの彼の大きな手は、たくましく、温かだった。
二人で並んで仰ぎ見る空は明るく、空は青く空気も澄んでいた。
彼と一緒にいるだけでーー世界は、私の心は、幸福に満たされたの。
「私は、あなたのことが嫌なわけじゃない」
「うん」
「多分、好き……なんだと思う」
「……チセ」
私が掴んでいたのは、片方だけだったから、もう片方の手も彼の腕に添えた。
そうして、一つ息を吐いて、大きく吸い込んだ。
「私は、あなたが好き。……でも、それは求婚だとか、いきなりじゃなくて、ゆっくり考えさせて欲しいの」
何もかもが、私には急すぎる。
だから、ゆっくり考える、自分を言い聞かせる時間が欲しかったのだ。
「大丈夫。驚かせたり、急に驚かせたりしないよう、配慮するよ。……でも、俺が君のそばにいることを許して欲しいんだ」
「私こそ……アルに、そばに……」
「……うん」
言葉尻は小さくなってしまったけれど、私は今の想いを頑張って伝えた。
急に目の前が暗くなって、私よりもだいぶ背が高くなったアルが、私の方へ屈んだのだと気が付いた。そして気づいたその瞬間、額に柔らかく温かいものが触れた。
……キスだ。
私は額に口付けを受けていた。
「驚かせないって、いったそばから……」
私は、その感触に全く嫌な感じを感じなかったから、その口付けを受けながら瞼をそっと閉じて笑った。
目を閉じると、アルの息遣いを感じた。
「そうだな」
アルの唇がそうっと離れていって、その温もりが離れていくことに、私は少しの寂しさを感じる。
「そうだよ」
「じゃあ、抱きしめるのは許してほしい」
「仕方がないなぁ」
くすくすと笑い合いながら、私は体の重さを彼に預け。
そして、アルがその体重を受け止めて、ふんわりと抱きしめてくれたのだった。
私たちの抱擁がしばらく続いた後、「ゴホンゴホン」と咳払いの音が聞こえた。
ご両親の前じゃない!
私は、ぎゅうっと両手でアルを押しやって、熱くなった頬を両手で覆う。
憎たらしいことにアルは余裕なようで、お父さまに「まあまあ」なんて言っている。
「アルは、これからどうするつもりなんだ? 今の話だと、彼女と一緒にいたいんだろう?」
お兄さまがアルに尋ねた。
恥ずかしいことに(当たり前か)、私たちの会話はご家族に丸聞こえだったらしい。
「これからも、ルルド村……チセのアトリエに住み続けたいと思っています」
あれ?
国を守護する聖竜さまがうちにいていいんだっけ?
私は驚いてアルに確かめるように、彼を見上げた。
「ならば、ルルド村を聖竜の里として聖地に認定しよう。聖竜がそこにいたいというのであれば、この国の民も一生に一度はその姿を見たいと巡礼に赴くだろう」
「でしたら、王都から聖地までの道を整備しないといけませんね!」
お父さまとお兄さまがやる気満々といった様子で頷き合っていた。
「まあ、それは素敵。いっそ神殿でも作ったらどうかしら。アルの力を目覚めさせてくださったのなら、チセさんを巫女に認定してもいいかもしれませんね」
「おお。どちらもいい案だな!」
お母さまとお父さまが盛り上がっている。
でも、今欲しいのは巫女だの神殿じゃなくて、焼け落ちた家の修復よね。
(そして丁重に巫女は辞退したい。)
「聖地となって、道が整備されれば、人の往来も増えて村も次第に潤うことでしょう。私たちは、道が整備されてゆく間に、村を綺麗に整えたいと思います。先日の件で、焼けた家も直さなければなりません」
「ああ、そうだったな。焼け落ちたままでは生活も立ち行くまい。早々に手筈を……」
「父上。兵士に私が以前赤竜だった時の剥がれ落ちた鱗を預けております。あれを国に買い取っていただきたいのです。村人たちの生活のために必要なものの、資金が欲しいのです」
「ならば、財務卿に話を通しておこう」
「ありがとうございます」
結局、神殿云々はまだあとにして(それでも、そのうちできるらしい……)、村の復興を優先することになった。
そうして、私たちは換金手続きが済むまで王城に滞在することになったのだ。
「ねえ、アル。あれはなあに?」
私たちは今、アルの案内で王都で街歩きをしている。
そして私が指差した先には、良い匂いのする屋台のようなものがあったのだ。
「ああ、あれは獣の肉を金属の串に刺して焼いた、屋台料理だな」
やはり、あれは焼き鳥の屋台のようなものだったらしい。
「食べてみるか? 美味いぞ?」
アルが懐から袋を取り出す。
多分、奢ってくれるというのかなあ?
でも自分で言い出しておいてどうなのかな、と思って自分も懐からお金の入った袋を取り出そうとした。
「こら、チセ。ここでは全部奢ると言っただろう」
つん、とアルに額を人さし指で軽く押された。
「だって、自分で言っておいて奢ってもらうなんて、『奢ってほしい』ってねだっているみたいじゃない」
ぷう、と私は頬を膨らませる。
「ねだるくらいでいいんだよ」
アルがそう言って私の膨らんだ頬をつん、と押す。
私は、頬が熱くなるのを感じながら、押された方の頬を手のひらで隠す。
ーーなんか、これってデートっぽくないかな?
そう思ったら、途端に頬が熱くなったのだ。
そうして歩いているうちに、屋台の前に到着した。
「ほら、どれにする? ピグ豚に、コック鶏、珍しいな、こっちはカウ牛だ」
何だか、前の世界で聴いたのと似たような獣の名前をアルが説明してくれた。
私はコック鶏、アルはカウ牛を選んで、近くにある噴水のそばのベンチに並んで座る。
「ん! 美味しい!」
「だろう?」
私たちは顔を見合わせて笑う。二人とも、目は美味しさにまんまるになって、お揃いだ。
「んーー!」
横からもう一切れ噛み取って、その肉を咀嚼しながら空を仰ぎ見る。
空はどこまでも澄んだ青空。
そして隣には、多分、大好きな人。
ーーずっと、仲良く一緒にいられたらいいな。
神さまの思惑はどうであれ、私はこの世界で大切な人を見つけ出した。
もし神さまが天にいるのだとしたら、任務を達成した私たちには、この後幸せな人生を揃って送らせてくれてもいいんじゃない?
私はそう思って、笑いながら空を眺めるのだった。