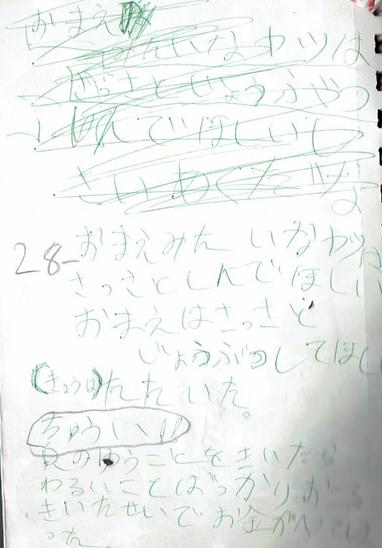丸いサイコロ
車の中
どうやら、まつりは再びぼんやりしてしまったらしい。まつりのいう《お兄さん》というのは、三人称みたいなもので、ぼくの兄だと理解しての発言とは思えなかったが……。
「質問、答えてもらってないけど」
ぼくはもう一度聞いた。
「あのおばさんが呼んだ、迎えだよ」
兄はそう言いながら、三人の間に視線をうろつかせた。しばらくキョロキョロしていた目は、やがて、弟に向けられる。初対面の人物がいるため、挙動不審、と取るべき反応なのだろうか。
「……乗って」
それぞれ、考えることがあるのか、三人とも黙ってしまうと、兄はそう声をかけ、後部座席の、ぼくの側のドアを開けた。
ぼんやりしていたまつりに声をかけ、肩をそっと叩いて押し、先に押し込む。それから、自分もぼんやりしていたと気がつく。後ろから声をかけるな、と何度も注意されたのに。
──一瞬、身構えたが、何も起こらなかった。まつりはぼくにさえ、気が付いていないのだろうか?
続いてケイガちゃんが乗った。いつの間にかまつりの手を握っていたらしい。
「……嘘つき」
表情は見えなかったが、彼女の口から、小さな呟きが聞こえた。誰に向けられたものなのかはわからないが、誰にしたって、もちろん、ぼくにだって、心当たりがある台詞だった。
「おい、ナナト、早く乗れよ!」
兄の声がかけられて、慌ててぼくも乗り込む。どこに行くのか、とか、いきなりこうなるのはなぜだ、とか、兄はいつ帰ってきた、だとか、考えることは、たくさんあったはずなのだ。
──なのに、なぜかぼくは、そのとき、どれも聞く気になれなかった。本当は、その意味に、理由に、気が付いている気さえした。
座席もふかふかで、高そうな車であることがうかがえる。みんな無言になったらどうしようと思ったが、あまり心配はいらなかったようだ。
兄は始終喋り続けていた。
「なぁちゃん、行きたいところある? あ、俺が免許取ったの、知ってた知ってた~? つーか、コンビニとか寄る?」
頭の中がぐらぐらする。免許、という言葉は、昔を思い出すから、嫌な気分だ。彼が学生の時に取ろうとして遊んでしまって2回も30万を借金していたところまでは記憶している。
ぼくなんて、運転するなんてとんでもない、誰かを殺すに決まっているとまでと言われて家族中の大笑い者だったというのに、兄が教習所に通うのは許していた。なんだかんだ言っても、あの家は兄にだけ甘い。
――跡を継げない子どもには、価値など無いのだから。
それでいて、自分より優位に立ちそうなことがあれば、全力で暴力を振るって泣きわめいていた。
こいつが傍にいると、昔からぼくに自由はなかった。
甘やかされたなんて言う勘違いもよくされていたけれど、
実質は『幼いから』という、手加減があるだけで、なんの価値もないぼくには30万をぽんと貸してくれたりはしないと思う。
いや、べつに車に乗らないけど……。
しかも、その権限を、親だから当然としか思っていない。
そんな当然があるわけない。今だってそうだ。
「話、聞こえてる?」
絶えずこんなことをぼくに囁き続けても、『彼だけが』
、唯一、あの家で許された。
感情を持つことも、立場を持つこと。
人生を揺るがすようなことをやらかしても、勘違いしても、
どこまで、他人を殺しても。