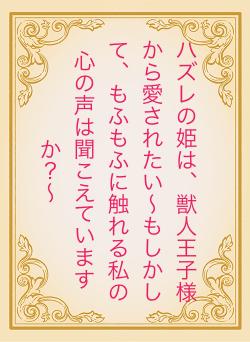ちょっと不運な私を助けてくれた騎士様が溺愛してきます
「いやぁ、凄いね、こんなに早く目覚めるとは思わなかったよ。それに二人とも元気そうだ」
屋敷にやって来たジークさんは、かなり疲れた顔をしていた。
実験をする為に魔獣を数十頭呼び出して、魔力が枯渇しているとヘラヘラと笑いながら言った。
「ヴィクトール閣下はすごいよ、それは認める。でも、あの人は我慢が出来ない……だから大変だったのさ」
何となく察したエスターが、ジークさんに「コレを食べるといい」と飴の入った瓶を渡す。
(……あれは、バート侯爵から頂いた元気になる飴……まだあんなにあったのね……)
ジークさんはそれを一つ口にしながら、話をした。
「実験の結果、シャーロットちゃんが、魔獣に吹き飛ばされた理由が分かったよ」
「吹き飛ばされた理由?」
「そう、魔獣にとっては、天敵とも言える存在が竜獣人だ。それを更に強くする存在が『花』だ。さらに『花』は竜獣人を生み出す。その上、食うことも出来ない。何故なら『花』は魔獣にとっては、例えるなら『毒』になるからだ。そう、俺は結論を出した」
「毒? どうして『花』が毒になるの?」
不思議に思って聞いた私を見て、ジークさんは目を細めた。
(ん? 私、おかしな事を聞いた?)
「『花』が魔獣にとって『毒』になるのは、竜獣人と結ばれた後なんだと思う。だから竜獣人は見つけたらすぐに、本能で体を結ぶ。大切な人を守る為に。その事を知らなかったとはいえ、エスターくん、シャーロットちゃんは危なかったね」
「危なかった?」
「そうだよ、竜獣人の『花』となって印がついただけの普通の女の子が外に出ていたら、その子を見つけた魔獣は真っ先に食べるんじゃない? だってその子は毒にもなってないし、竜獣人を何倍も強くする事が出来るほどの力、つまりは栄養を持っているって思うんじゃないかな」
ハッとしたエスターは、横に座る私の手をギュッと握った。
「君が迎えに行くまで、彼女が結界の強い城の中にいた事と、運良く防御魔法のかけてある城の馬車に乗って帰った事、男爵家に戻ってから外に出なかった事がよかったよ」
私がエスターと出会ったのは城だ。城には結界が張ってあった。私はそこから城の馬車で男爵家まで帰って……確かに外には出ていない。
「その事は、父上も知らなかったのか……」
「そう、知ってたらすぐにでも君にシャーロットちゃんを攫いに行かせたさ。ヴィクトール閣下にこの事を教えたら、かなり驚いていたからね。……まぁ、俺も昨日分かったんだけど……魔獣術師に代々伝わる日誌があって、それに書いてあったんだ。
今度見せてあげるよ、レイナルド公爵もガイア公爵も知らない事が書いてあると思う。ただ、すごく字が汚くて読み辛いけどね」
ジークさんは飴をガリガリ噛むと、もう一つ口にした。
「ま、俺が教えてやれる事はこれぐらい。簡単に言うと『毒』だから食べずに吹き飛ばされたんだ。何か魔獣にしか分からない匂いがあるのかな? まぁ、何にしろ危ないよね。これからはエスターくんが一緒じゃないなら、外に出ない方がいいよ。魔獣は何処から出てくるのか、魔獣術師の俺達にすら、まだ分からないんだから。それから……この飴まだあるならくれる?」
一通り話終えると、ジークさんはバート侯爵の『元気になる飴』と、あの『媚薬入りクッキー』をエスターから受け取り城へと戻って行った。
ジークさんを見送った玄関で、私はエスターに抱きしめられた。
「どうしたの?」
エスターは、私の肩に顔を埋める
「僕はちっともシャーロットを守れていないな……」
「どうして? いつもエスターは私を助けてくれているわ」
「そうかな?」
「私に体力まで分けて、助けてくれたじゃない」
エスターは顔を上げ、私を麗しい青い目で見つめた。
「そんなの、当たり前だ」
見つめ合う彼の瞳が一瞬で金色に変わり、私を甘く蕩けさせる。
「エスター……」
息がかかるほど近づくと、それは当たり前のように二人の唇は重なった。
ーーーーーー*
あの氷祭りから一年後。
今年の祭りの警護は第二騎士団だ。
あれからエスターは頻繁に町へ向かうようになり(もちろん仕事で……ヴィクトール様が『お前が外に出ないから余計に目立つのだ』と、第二騎士団の管轄地域を町中に変えてしまった)以前ほど人に囲まれる事はなくなったらしい。
私は……あれ以来ほとんど外に出ていない。
あんな話を聞いたら出ようとも思わないけど……。
それにまだ、魔獣に吹き飛ばされて体が冷たくなった原因は分かっていなかったから。
屋敷の玄関にはいつものように、主人を見送る私とジェラルドさん達が並ぶ。
「ジェラルド、ドロシー分かってるね」
黒い隊服に身を包み、聖剣を腰に下げたエスターは二人をしっかりと見て告げる。
「はい、分かっております。エスター様」
「何があっても決してお出し致しません」
二人の言葉を聞くと、端麗な顔で頷く。
「ダンとクレアも頼んだよ」
「もちろんです。あんな事は懲り懲りですから」
「ちゃんと見ておきます」
「うん、頼むよ」
エスターは私の頭に手を乗せた。まるで子供をあやす様だ。
「僕がお菓子を買ってきてあげるから、絶対にどこにも行かないで……シャーロット」
頭に乗せられた手は、頬に移りスリスリと撫でられる。
「……はい、ちゃんとまっ」
エスターの人差し指が私の唇を押さえて言葉を止めた。
「シャーロット、その言葉はダメだ、信用出来ない」
……?
どうしてか、皆も頷いていた。
唇を塞ぐ彼の手を取り、甘えたように見上げる。
「……無事に、早く帰って来てね」
そう言うとエスターは微笑んで私にキスをした。
「…………」
声を出してはいけない。
キスが長くなっちゃうから……でも……。
「……んっ……」
深い口づけは続く。
また少し背が伸びて、少年から青年の体つきへと変わってきた彼の強い腕が私を抱きしめる。
「んっ……はっ……」
んんっ、とジェラルドさんの咳払いが聞こえた。
そっとエスターは唇を離し「続きは帰ってからね」と耳に囁いて警護へと向かった。
*
私達が住むこの屋敷は一年で随分変わった。
彼は私が外に出なくても退屈しないように、レイナルド公爵邸より広い庭を、屋敷を増築して造ってくれた。
公爵邸の家の中に庭が造られていたのは、こういう理由だったのか……
レイナルド公爵閣下も、ガイア公爵閣下も『花』の基本的な事しか知らなかったが、本能で外に出そうとしなかったようだ。
ここには、ジークさんが強い結界を張ってくれている。私はこの屋敷にいる限り、魔獣に襲われる事はない。
だからエスターは安心して騎士の仕事へと向かう。
夜遅くに氷祭りから帰って来たエスターは、買ってきたお菓子を私にくれた。
あの日、夜空に散った花飾りと、同じ花の小さなブーケも買って来てくれた。
エスターの凄艶な青い目が、瞬き一つで色をかえる。
私を見つめる彼の瞳は、蕩けるような金色に輝いていた。
「愛してるよ、シャーロット」
「私も愛してます。エスター……」
……今宵も注がれる彼の愛に、私は溺れていく。
これからも、ずっと……
《the end》
屋敷にやって来たジークさんは、かなり疲れた顔をしていた。
実験をする為に魔獣を数十頭呼び出して、魔力が枯渇しているとヘラヘラと笑いながら言った。
「ヴィクトール閣下はすごいよ、それは認める。でも、あの人は我慢が出来ない……だから大変だったのさ」
何となく察したエスターが、ジークさんに「コレを食べるといい」と飴の入った瓶を渡す。
(……あれは、バート侯爵から頂いた元気になる飴……まだあんなにあったのね……)
ジークさんはそれを一つ口にしながら、話をした。
「実験の結果、シャーロットちゃんが、魔獣に吹き飛ばされた理由が分かったよ」
「吹き飛ばされた理由?」
「そう、魔獣にとっては、天敵とも言える存在が竜獣人だ。それを更に強くする存在が『花』だ。さらに『花』は竜獣人を生み出す。その上、食うことも出来ない。何故なら『花』は魔獣にとっては、例えるなら『毒』になるからだ。そう、俺は結論を出した」
「毒? どうして『花』が毒になるの?」
不思議に思って聞いた私を見て、ジークさんは目を細めた。
(ん? 私、おかしな事を聞いた?)
「『花』が魔獣にとって『毒』になるのは、竜獣人と結ばれた後なんだと思う。だから竜獣人は見つけたらすぐに、本能で体を結ぶ。大切な人を守る為に。その事を知らなかったとはいえ、エスターくん、シャーロットちゃんは危なかったね」
「危なかった?」
「そうだよ、竜獣人の『花』となって印がついただけの普通の女の子が外に出ていたら、その子を見つけた魔獣は真っ先に食べるんじゃない? だってその子は毒にもなってないし、竜獣人を何倍も強くする事が出来るほどの力、つまりは栄養を持っているって思うんじゃないかな」
ハッとしたエスターは、横に座る私の手をギュッと握った。
「君が迎えに行くまで、彼女が結界の強い城の中にいた事と、運良く防御魔法のかけてある城の馬車に乗って帰った事、男爵家に戻ってから外に出なかった事がよかったよ」
私がエスターと出会ったのは城だ。城には結界が張ってあった。私はそこから城の馬車で男爵家まで帰って……確かに外には出ていない。
「その事は、父上も知らなかったのか……」
「そう、知ってたらすぐにでも君にシャーロットちゃんを攫いに行かせたさ。ヴィクトール閣下にこの事を教えたら、かなり驚いていたからね。……まぁ、俺も昨日分かったんだけど……魔獣術師に代々伝わる日誌があって、それに書いてあったんだ。
今度見せてあげるよ、レイナルド公爵もガイア公爵も知らない事が書いてあると思う。ただ、すごく字が汚くて読み辛いけどね」
ジークさんは飴をガリガリ噛むと、もう一つ口にした。
「ま、俺が教えてやれる事はこれぐらい。簡単に言うと『毒』だから食べずに吹き飛ばされたんだ。何か魔獣にしか分からない匂いがあるのかな? まぁ、何にしろ危ないよね。これからはエスターくんが一緒じゃないなら、外に出ない方がいいよ。魔獣は何処から出てくるのか、魔獣術師の俺達にすら、まだ分からないんだから。それから……この飴まだあるならくれる?」
一通り話終えると、ジークさんはバート侯爵の『元気になる飴』と、あの『媚薬入りクッキー』をエスターから受け取り城へと戻って行った。
ジークさんを見送った玄関で、私はエスターに抱きしめられた。
「どうしたの?」
エスターは、私の肩に顔を埋める
「僕はちっともシャーロットを守れていないな……」
「どうして? いつもエスターは私を助けてくれているわ」
「そうかな?」
「私に体力まで分けて、助けてくれたじゃない」
エスターは顔を上げ、私を麗しい青い目で見つめた。
「そんなの、当たり前だ」
見つめ合う彼の瞳が一瞬で金色に変わり、私を甘く蕩けさせる。
「エスター……」
息がかかるほど近づくと、それは当たり前のように二人の唇は重なった。
ーーーーーー*
あの氷祭りから一年後。
今年の祭りの警護は第二騎士団だ。
あれからエスターは頻繁に町へ向かうようになり(もちろん仕事で……ヴィクトール様が『お前が外に出ないから余計に目立つのだ』と、第二騎士団の管轄地域を町中に変えてしまった)以前ほど人に囲まれる事はなくなったらしい。
私は……あれ以来ほとんど外に出ていない。
あんな話を聞いたら出ようとも思わないけど……。
それにまだ、魔獣に吹き飛ばされて体が冷たくなった原因は分かっていなかったから。
屋敷の玄関にはいつものように、主人を見送る私とジェラルドさん達が並ぶ。
「ジェラルド、ドロシー分かってるね」
黒い隊服に身を包み、聖剣を腰に下げたエスターは二人をしっかりと見て告げる。
「はい、分かっております。エスター様」
「何があっても決してお出し致しません」
二人の言葉を聞くと、端麗な顔で頷く。
「ダンとクレアも頼んだよ」
「もちろんです。あんな事は懲り懲りですから」
「ちゃんと見ておきます」
「うん、頼むよ」
エスターは私の頭に手を乗せた。まるで子供をあやす様だ。
「僕がお菓子を買ってきてあげるから、絶対にどこにも行かないで……シャーロット」
頭に乗せられた手は、頬に移りスリスリと撫でられる。
「……はい、ちゃんとまっ」
エスターの人差し指が私の唇を押さえて言葉を止めた。
「シャーロット、その言葉はダメだ、信用出来ない」
……?
どうしてか、皆も頷いていた。
唇を塞ぐ彼の手を取り、甘えたように見上げる。
「……無事に、早く帰って来てね」
そう言うとエスターは微笑んで私にキスをした。
「…………」
声を出してはいけない。
キスが長くなっちゃうから……でも……。
「……んっ……」
深い口づけは続く。
また少し背が伸びて、少年から青年の体つきへと変わってきた彼の強い腕が私を抱きしめる。
「んっ……はっ……」
んんっ、とジェラルドさんの咳払いが聞こえた。
そっとエスターは唇を離し「続きは帰ってからね」と耳に囁いて警護へと向かった。
*
私達が住むこの屋敷は一年で随分変わった。
彼は私が外に出なくても退屈しないように、レイナルド公爵邸より広い庭を、屋敷を増築して造ってくれた。
公爵邸の家の中に庭が造られていたのは、こういう理由だったのか……
レイナルド公爵閣下も、ガイア公爵閣下も『花』の基本的な事しか知らなかったが、本能で外に出そうとしなかったようだ。
ここには、ジークさんが強い結界を張ってくれている。私はこの屋敷にいる限り、魔獣に襲われる事はない。
だからエスターは安心して騎士の仕事へと向かう。
夜遅くに氷祭りから帰って来たエスターは、買ってきたお菓子を私にくれた。
あの日、夜空に散った花飾りと、同じ花の小さなブーケも買って来てくれた。
エスターの凄艶な青い目が、瞬き一つで色をかえる。
私を見つめる彼の瞳は、蕩けるような金色に輝いていた。
「愛してるよ、シャーロット」
「私も愛してます。エスター……」
……今宵も注がれる彼の愛に、私は溺れていく。
これからも、ずっと……
《the end》