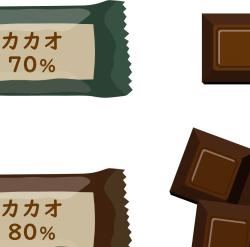愛を知るまでは★イチゴキャンディ編★
初めてをあげる
鹿内さんの新しい住まいであるマンションは、最寄り駅から15分ほど歩いた住宅地にある。
駅前の商店街に美味しそうな洋菓子が並ぶ「パティスリーSAKURA」というケーキ屋さんがあったので、そこでショートケーキを二つ買った。
鹿内さんの好きなケーキは一位がショートケーキ、二位がチーズケーキ、三位がミルフィーユだということはもう調査済みだった。
鹿内さんと付き合い始めて早3ヶ月目。
もうすぐ鹿内さんの誕生日。
そして、初めて行く、鹿内さんの新居。
もっと早く訪ねて行きたかったけど、鹿内さんは
「そのうちな」
と言ったきり、なかなか私を部屋には招いてくれなかった。
私を部屋に入れたくない理由があるのだろうか?
そんな風に不安に思わないでもないけれど、きっと鹿内さんなりの理由があるのだろう、と信じていた。
「今度、俺の部屋に来る?」
そう言われたとき、私は頬を桃色にして頷いた。
部屋は片付いているのだろうか。
食事はちゃんととれているのだろうか。
私はサプライズで、突然鹿内さんの部屋を訪ねることにした。
今日は折しも週末の土曜日だ。
ラインで部屋を訪ねることは連絡しておいたけれど、ちゃんと見てくれているかな?
仕事で疲れて寝ている可能性も大だ。
晴れて恋人同士になったとはいえ、男の人の一人暮らしの部屋を訪ねることに緊張していた。
戸建ての住宅が立ち並ぶ路地の一角にある黄色いマンションに、前にもらっておいた地図を見ながら歩き、ようやくたどり着く。
オートロックのボタンを押すと、寝起きのようにかすれた鹿内さんの返事が聞こえて来た。
「つぐみです。」
そう告げると、オートロックが外れ、透明なガラスドアが開いた。
エレベーターの扉を開け、5のボタンを押す。
506号室が鹿内さんの部屋番号だった。
部屋の前まで来ると、震える指先でインターホンのチャイムを押す。
しばらくしてドアが開いた。
鹿内さんは寝ぼけまなこを手でこすり、目を大きく見開いた。
でもすぐに目を細めて、私を玄関の中に招いてくれた。
「驚いた。でもこんなサプライズなら大歓迎だよ。」
突然の訪問に鹿内さんは少しとまどっているようだった。
上は白い肌着のTシャツ、下はグレーのスエット姿という寝巻のようないで立ち。
髪は寝癖が付いていて、無精ひげも生えている。
「突然来てごめんなさい!びっくりさせたくて・・・寝ていたんですか?」
私は玄関で靴を脱ぎながら、鹿内さんのものである投げ出されているスニーカーを揃えながら尋ねた。
「ん。今さっき起きたとこ。」
フローリングの中央には黒い足のガラステーブルが置かれ、1リットル水のペットボトルや空のカップラーメンの容器、煙草とライターと灰皿が乱雑に置いてある。
テレビ、本棚、そして窓際にはベッドがあり、うちにいた時よりもさらに殺風景な部屋だ。
「まあ、座って。」
私は座布団もないフローリングの床に、腰を下ろした。
鹿内さんは寝起きの一服を吸うために、煙草に火をつけ、美味しそうに最初の煙を深く吸い込んだ。
私は窓の外の景色が見たくて、すぐに立ち上がった。
「やっぱり男の人の部屋って感じしますね。空気が淀んでいる。」
私はレースのカーテンを開き、サッシ窓を開けて空気の入れ替えをした。
「そうか?これでも綺麗にしているつもりだけどな。」
そう言いながら、鹿内さんはTシャツの裾をまくりあげ、
お臍を見せながら脇腹をぼりぼりと掻く。
「私の他に女の子を部屋に入れたりしました?」
「するわけないだろ?女を部屋にいれるのはつぐみが最初で最後。」
鹿内さんは私の頭をコツンと軽くこづいた。
「ならいいけど。鹿内さんモテるから。」
「なに?架空の女にジェラシー感じているの?」
「そうジェラシーですよ!鹿内さんがなかなか私を部屋に呼んでくれないから。」
観念した私はそう認め、ケーキの入った小さな箱を鹿内さんに差し出した。
「はい!これ。鹿内さん、ショートケーキ好きでしょ?」
「つぐみからのジェラシーなら大歓迎だな。」
鹿内さんはそう言ってにんまりした。
「お茶いれるので、一緒に食べましょう。」
「おう。サンキュ。」
私はキッチンにあったお茶っぱを急須に入れ、ポットのなかにあったお湯を入れ、
二人分のお茶を入れた。
鹿内さんは皿を出し、ケーキを取り分けた。
二人でケーキを食べていると、ふいに鹿内さんが私に尋ねた。
「つぐみ、その・・君のママに今日、ここに来ることは?」
「言っていません。言うとパパに告げ口するから。
パパ、デートの度にどこに行ったかとか、何をしたかとか、しつこく聞いてくるからうざったくて」
「そう」
私だってパパやママに、ひとつくらい秘密を持ったっていいよね?
「つぐみ。口にクリームがついている。」
「え?ハンカチ・・・」
「俺が取ってやるよ。」
鹿内さんはそういうと、私の口についたクリームを舐めるように唇を重ねて来た。
私と鹿内さんは抱き合いながらその場に倒れ込んだ。
私は鹿内さんの背中に腕を回しながら、長いキスを受け止めていた。
舌と舌が絡まって唾液が混ざり、息が苦しくなる。
でもそれは幸福な息苦しさだ。
「つぐみ。男の部屋にひとりで来るってどういう意味だかわかっていて来たの?」
「え?」
私はきょとんと口を半分開けて、鹿内さんをみつめた。
「なにそれ?」
私は不思議な思いで微笑むと、さらに鹿内さんの首に回した手をぎゅっと強めた。
「そうやって煽るなよ。」
鹿内さんは少し怖いくらいの強さで、私の唇を吸った。
その唇は首から鎖骨へと移動し、私の胸元近くまで到達した。
私は、思わず笑い声を上げた。
「鹿内さん。くすぐったいよ。」
「あーもう!海が見えるペンションに連れて行って、優しく奪うつもりだったのに。
つぐみがそんなに可愛い仕草を見せるから・・・ごめん。もう止めてあげられそうにない。」
「え?」
「つぐみの全てを、俺のものにしてもいい?」
それは高貴なものに懇願するような、それでいて切迫しているような男の目だった。
そんなに切ない目でみつめられたら、私にそれを拒むことは出来なかった。
私は小さくこくりと頷いた。
行為そのものは漫画や小説などの知識で知ってはいた。
でもいざ現実の男の人の前で、どうやって振舞っていいのかわからない。
まるで未知の領域だ。
「今の鹿内さん、ちょっと怖い。」
私は正直な気持ちを述べた。
「怖がらないで。つぐみは何も考えなくてもいい。ただ俺に身体を委ねて。」
そう言うと鹿内さんはいきなり私をお姫様抱っこしてベッドに運んだ。
仰向けに寝かされた私は、いきなり大きな体に抱きすくめられる。
さっきまで鹿内さんが眠っていたベッドの寝具は、煙草の匂いがした。
実はもしかしてこんな展開があるのかもしれないと覚悟はしていたので、真っ白なシルクにフリルのついた一番お気に入りの下着を付けてきた。
でもいざとなると身体が強張る。
そんな私の髪を優しくなでたあと、鹿内さんは私のブラウスのボタンをゆっくり外していく。
「・・・嫌か?嫌ならやめるけど。」
私は首を振った。
「ううん。鹿内さんなら・・・後悔しない。
初めては海が見えるペンションより、鹿内さんの匂いに包まれたこの部屋がいい。」
私は大きな鹿内さんの胸に抱きすくめられた。
「つぐみ・・・好きだよ・・・ずっと俺だけのつぐみでいて・・・」
☆
「鹿内さん・・・キスして」
私達は繋がったまま、お互いを狂おしく求めあい、口づけをかわし、両足を絡ませた。
「鹿内さんじゃなくて、弘毅だろ?何回言えばわかるの?」
「だって・・・。」
「罰として俺が喜ぶ言葉、三つ言って?・・・あの言葉は使っちゃ駄目だよ。」
どうして愛しているって言っちゃいけないの?
でもそれが鹿内さんと私の暗黙のルール。
「・・・・弘毅、大好き。」
「うん。」
「・・・・ずっと弘毅のそばにいる。」
「うん。」
「・・・・私はずっと弘毅だけのもの。」
「・・・俺もずっとつぐみだけのものだよ。」
鹿内さんは満足そうにそう言うと、私の鼻先にキスをした。
「それと敬語はナシ。もう俺とつぐみの立場はイーブンなんだから」
「違う。私の方がずっと鹿内さんのこと好きだもん。
いつまでたっても私の方が負けっぱなし。
でも・・・言わせて?
弘毅・・・好き。大好き。
素直に気持ちを伝えられるだけでもこんなに嬉しいの。」
「ん。今のところはそれで合格。」
再び鹿内さんの唇が私の唇と重なり合う。
「今のところは?私これ以上、思いを伝えるすべを知らない。」
でも私は鹿内さんに想いを告げるだろう。
何度でも何度でも・・・。
私は少しでも大人な鹿内さんに追いつけているのだろうか。
優しく頬を触れられて、私は鹿内さんの熱い体温に身を任せていた。
行為が終わり、私は大きな鹿内さんの胸に身を委ねながら、
常々疑問に思っていたことを初めて口にした。
「ねえ。鹿内さんは、いつ私を好きになってくれたの?」
「・・・・それは内緒。」
「意地悪!もう教えてくれたっていいでしょ?」
私は鹿内さんに背中を向けた。
そんな私の腰を後ろから抱きしめてから、
鹿内さんは少し迷ったように沈黙して小さな声で言った。
「初めてつぐみを見たときから。ずっと。」
「初めて?鹿内さんが初めて家に来た時から?」
「うーん。どうだろ。」
「なんだ。やっぱり一目惚れしてくれたわけじゃないんだ?」
「一目惚れだよ。」
鹿内さんは私の髪にくちづけながら、そうつぶやいた。
そしてさりげなく、私に尋ねた。
「・・・・つぐみは?いつ俺を好きになったの?」
「うーん。いつだろう。気が付いたら好きになっていたの。魔法にかかったように。」
「・・・・俺が魔法をかけたんだよ。」
「そうなの?」
私はクスクスと笑った。
「でも今はきっと私の方が鹿内さんのことを好きよ。
だって鹿内さんはいまでも愛がわからないんでしょ?」
「・・・・・でも一生ずっとつぐみの側にいたい。それは絶対的に変わらない感情なんだ。信じてくれるかな?」
私は自分の体をくるりと鹿内さんの方へ向け、鹿内さんの頭を、自分の胸の谷間に抱き寄せてその髪を優しくなでた。
まるであどけない赤子に乳を与えるように。
「いいの。鹿内さんは愛なんて知らなくていいのよ。
そのままでいいの。
私の想いを受け止めてくれれば、それで私は満足なの。」
鹿内さんは「愛している」って絶対に言ってくれない。
だから私も「愛している」なんて言ってあげない。
でも愛なんて言葉を使わなくても、私にはわかる。
その瞳、その表情、その言葉、その行動・・・その全てで私を愛してくれているってことを。
それを愛という言葉で表現するのを怖がっていることも。
でも、もう鹿内さんは私だけのもの。
私も鹿内さんだけのもの。
「好き・・・弘毅・・・好き。大好き。」
鹿内さん。これが愛するってことよ。
「うん。知ってる。・・・俺も。」
鹿内さんはまた優しいキスをくれた。
鹿内さん・・・ううん弘毅。
弘毅が私への愛を知るまでは・・・いつか愛を知っても・・・ずっとそばにいてね。
Fin
駅前の商店街に美味しそうな洋菓子が並ぶ「パティスリーSAKURA」というケーキ屋さんがあったので、そこでショートケーキを二つ買った。
鹿内さんの好きなケーキは一位がショートケーキ、二位がチーズケーキ、三位がミルフィーユだということはもう調査済みだった。
鹿内さんと付き合い始めて早3ヶ月目。
もうすぐ鹿内さんの誕生日。
そして、初めて行く、鹿内さんの新居。
もっと早く訪ねて行きたかったけど、鹿内さんは
「そのうちな」
と言ったきり、なかなか私を部屋には招いてくれなかった。
私を部屋に入れたくない理由があるのだろうか?
そんな風に不安に思わないでもないけれど、きっと鹿内さんなりの理由があるのだろう、と信じていた。
「今度、俺の部屋に来る?」
そう言われたとき、私は頬を桃色にして頷いた。
部屋は片付いているのだろうか。
食事はちゃんととれているのだろうか。
私はサプライズで、突然鹿内さんの部屋を訪ねることにした。
今日は折しも週末の土曜日だ。
ラインで部屋を訪ねることは連絡しておいたけれど、ちゃんと見てくれているかな?
仕事で疲れて寝ている可能性も大だ。
晴れて恋人同士になったとはいえ、男の人の一人暮らしの部屋を訪ねることに緊張していた。
戸建ての住宅が立ち並ぶ路地の一角にある黄色いマンションに、前にもらっておいた地図を見ながら歩き、ようやくたどり着く。
オートロックのボタンを押すと、寝起きのようにかすれた鹿内さんの返事が聞こえて来た。
「つぐみです。」
そう告げると、オートロックが外れ、透明なガラスドアが開いた。
エレベーターの扉を開け、5のボタンを押す。
506号室が鹿内さんの部屋番号だった。
部屋の前まで来ると、震える指先でインターホンのチャイムを押す。
しばらくしてドアが開いた。
鹿内さんは寝ぼけまなこを手でこすり、目を大きく見開いた。
でもすぐに目を細めて、私を玄関の中に招いてくれた。
「驚いた。でもこんなサプライズなら大歓迎だよ。」
突然の訪問に鹿内さんは少しとまどっているようだった。
上は白い肌着のTシャツ、下はグレーのスエット姿という寝巻のようないで立ち。
髪は寝癖が付いていて、無精ひげも生えている。
「突然来てごめんなさい!びっくりさせたくて・・・寝ていたんですか?」
私は玄関で靴を脱ぎながら、鹿内さんのものである投げ出されているスニーカーを揃えながら尋ねた。
「ん。今さっき起きたとこ。」
フローリングの中央には黒い足のガラステーブルが置かれ、1リットル水のペットボトルや空のカップラーメンの容器、煙草とライターと灰皿が乱雑に置いてある。
テレビ、本棚、そして窓際にはベッドがあり、うちにいた時よりもさらに殺風景な部屋だ。
「まあ、座って。」
私は座布団もないフローリングの床に、腰を下ろした。
鹿内さんは寝起きの一服を吸うために、煙草に火をつけ、美味しそうに最初の煙を深く吸い込んだ。
私は窓の外の景色が見たくて、すぐに立ち上がった。
「やっぱり男の人の部屋って感じしますね。空気が淀んでいる。」
私はレースのカーテンを開き、サッシ窓を開けて空気の入れ替えをした。
「そうか?これでも綺麗にしているつもりだけどな。」
そう言いながら、鹿内さんはTシャツの裾をまくりあげ、
お臍を見せながら脇腹をぼりぼりと掻く。
「私の他に女の子を部屋に入れたりしました?」
「するわけないだろ?女を部屋にいれるのはつぐみが最初で最後。」
鹿内さんは私の頭をコツンと軽くこづいた。
「ならいいけど。鹿内さんモテるから。」
「なに?架空の女にジェラシー感じているの?」
「そうジェラシーですよ!鹿内さんがなかなか私を部屋に呼んでくれないから。」
観念した私はそう認め、ケーキの入った小さな箱を鹿内さんに差し出した。
「はい!これ。鹿内さん、ショートケーキ好きでしょ?」
「つぐみからのジェラシーなら大歓迎だな。」
鹿内さんはそう言ってにんまりした。
「お茶いれるので、一緒に食べましょう。」
「おう。サンキュ。」
私はキッチンにあったお茶っぱを急須に入れ、ポットのなかにあったお湯を入れ、
二人分のお茶を入れた。
鹿内さんは皿を出し、ケーキを取り分けた。
二人でケーキを食べていると、ふいに鹿内さんが私に尋ねた。
「つぐみ、その・・君のママに今日、ここに来ることは?」
「言っていません。言うとパパに告げ口するから。
パパ、デートの度にどこに行ったかとか、何をしたかとか、しつこく聞いてくるからうざったくて」
「そう」
私だってパパやママに、ひとつくらい秘密を持ったっていいよね?
「つぐみ。口にクリームがついている。」
「え?ハンカチ・・・」
「俺が取ってやるよ。」
鹿内さんはそういうと、私の口についたクリームを舐めるように唇を重ねて来た。
私と鹿内さんは抱き合いながらその場に倒れ込んだ。
私は鹿内さんの背中に腕を回しながら、長いキスを受け止めていた。
舌と舌が絡まって唾液が混ざり、息が苦しくなる。
でもそれは幸福な息苦しさだ。
「つぐみ。男の部屋にひとりで来るってどういう意味だかわかっていて来たの?」
「え?」
私はきょとんと口を半分開けて、鹿内さんをみつめた。
「なにそれ?」
私は不思議な思いで微笑むと、さらに鹿内さんの首に回した手をぎゅっと強めた。
「そうやって煽るなよ。」
鹿内さんは少し怖いくらいの強さで、私の唇を吸った。
その唇は首から鎖骨へと移動し、私の胸元近くまで到達した。
私は、思わず笑い声を上げた。
「鹿内さん。くすぐったいよ。」
「あーもう!海が見えるペンションに連れて行って、優しく奪うつもりだったのに。
つぐみがそんなに可愛い仕草を見せるから・・・ごめん。もう止めてあげられそうにない。」
「え?」
「つぐみの全てを、俺のものにしてもいい?」
それは高貴なものに懇願するような、それでいて切迫しているような男の目だった。
そんなに切ない目でみつめられたら、私にそれを拒むことは出来なかった。
私は小さくこくりと頷いた。
行為そのものは漫画や小説などの知識で知ってはいた。
でもいざ現実の男の人の前で、どうやって振舞っていいのかわからない。
まるで未知の領域だ。
「今の鹿内さん、ちょっと怖い。」
私は正直な気持ちを述べた。
「怖がらないで。つぐみは何も考えなくてもいい。ただ俺に身体を委ねて。」
そう言うと鹿内さんはいきなり私をお姫様抱っこしてベッドに運んだ。
仰向けに寝かされた私は、いきなり大きな体に抱きすくめられる。
さっきまで鹿内さんが眠っていたベッドの寝具は、煙草の匂いがした。
実はもしかしてこんな展開があるのかもしれないと覚悟はしていたので、真っ白なシルクにフリルのついた一番お気に入りの下着を付けてきた。
でもいざとなると身体が強張る。
そんな私の髪を優しくなでたあと、鹿内さんは私のブラウスのボタンをゆっくり外していく。
「・・・嫌か?嫌ならやめるけど。」
私は首を振った。
「ううん。鹿内さんなら・・・後悔しない。
初めては海が見えるペンションより、鹿内さんの匂いに包まれたこの部屋がいい。」
私は大きな鹿内さんの胸に抱きすくめられた。
「つぐみ・・・好きだよ・・・ずっと俺だけのつぐみでいて・・・」
☆
「鹿内さん・・・キスして」
私達は繋がったまま、お互いを狂おしく求めあい、口づけをかわし、両足を絡ませた。
「鹿内さんじゃなくて、弘毅だろ?何回言えばわかるの?」
「だって・・・。」
「罰として俺が喜ぶ言葉、三つ言って?・・・あの言葉は使っちゃ駄目だよ。」
どうして愛しているって言っちゃいけないの?
でもそれが鹿内さんと私の暗黙のルール。
「・・・・弘毅、大好き。」
「うん。」
「・・・・ずっと弘毅のそばにいる。」
「うん。」
「・・・・私はずっと弘毅だけのもの。」
「・・・俺もずっとつぐみだけのものだよ。」
鹿内さんは満足そうにそう言うと、私の鼻先にキスをした。
「それと敬語はナシ。もう俺とつぐみの立場はイーブンなんだから」
「違う。私の方がずっと鹿内さんのこと好きだもん。
いつまでたっても私の方が負けっぱなし。
でも・・・言わせて?
弘毅・・・好き。大好き。
素直に気持ちを伝えられるだけでもこんなに嬉しいの。」
「ん。今のところはそれで合格。」
再び鹿内さんの唇が私の唇と重なり合う。
「今のところは?私これ以上、思いを伝えるすべを知らない。」
でも私は鹿内さんに想いを告げるだろう。
何度でも何度でも・・・。
私は少しでも大人な鹿内さんに追いつけているのだろうか。
優しく頬を触れられて、私は鹿内さんの熱い体温に身を任せていた。
行為が終わり、私は大きな鹿内さんの胸に身を委ねながら、
常々疑問に思っていたことを初めて口にした。
「ねえ。鹿内さんは、いつ私を好きになってくれたの?」
「・・・・それは内緒。」
「意地悪!もう教えてくれたっていいでしょ?」
私は鹿内さんに背中を向けた。
そんな私の腰を後ろから抱きしめてから、
鹿内さんは少し迷ったように沈黙して小さな声で言った。
「初めてつぐみを見たときから。ずっと。」
「初めて?鹿内さんが初めて家に来た時から?」
「うーん。どうだろ。」
「なんだ。やっぱり一目惚れしてくれたわけじゃないんだ?」
「一目惚れだよ。」
鹿内さんは私の髪にくちづけながら、そうつぶやいた。
そしてさりげなく、私に尋ねた。
「・・・・つぐみは?いつ俺を好きになったの?」
「うーん。いつだろう。気が付いたら好きになっていたの。魔法にかかったように。」
「・・・・俺が魔法をかけたんだよ。」
「そうなの?」
私はクスクスと笑った。
「でも今はきっと私の方が鹿内さんのことを好きよ。
だって鹿内さんはいまでも愛がわからないんでしょ?」
「・・・・・でも一生ずっとつぐみの側にいたい。それは絶対的に変わらない感情なんだ。信じてくれるかな?」
私は自分の体をくるりと鹿内さんの方へ向け、鹿内さんの頭を、自分の胸の谷間に抱き寄せてその髪を優しくなでた。
まるであどけない赤子に乳を与えるように。
「いいの。鹿内さんは愛なんて知らなくていいのよ。
そのままでいいの。
私の想いを受け止めてくれれば、それで私は満足なの。」
鹿内さんは「愛している」って絶対に言ってくれない。
だから私も「愛している」なんて言ってあげない。
でも愛なんて言葉を使わなくても、私にはわかる。
その瞳、その表情、その言葉、その行動・・・その全てで私を愛してくれているってことを。
それを愛という言葉で表現するのを怖がっていることも。
でも、もう鹿内さんは私だけのもの。
私も鹿内さんだけのもの。
「好き・・・弘毅・・・好き。大好き。」
鹿内さん。これが愛するってことよ。
「うん。知ってる。・・・俺も。」
鹿内さんはまた優しいキスをくれた。
鹿内さん・・・ううん弘毅。
弘毅が私への愛を知るまでは・・・いつか愛を知っても・・・ずっとそばにいてね。
Fin