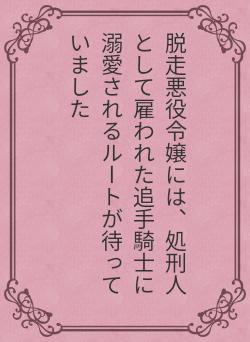愛でて育てたあの子は、いつしか私に優しい牙を剥く
7.夢の続きはディナーのあとで
「ねえ、抱かせて?」
熱に浮かされたように瞳を潤ませて、息を荒げる龍斗に押し倒された。
「ちょっ…待って、まだそこまでは覚悟できてなっ…」
「俺、もう限界だよ、遥ちゃん…」
龍斗の熱い吐息と舌の感触が首筋に触れた。
「あっ、龍っ!!それは待っ…ダっ、ダメーーーーーっ!!!」
パチリと目を開くと、明るくなり始めた自室の天井が見えた。
枕元のスマホが起床時間を知らせるために、必死でアラームを鳴らしている。
「この歳になって、こんな夢オチって………」
アラームを止めて、上体を起こした。
「どんな夢見てんのよ、私は。なんか寝た気がしないし…」
龍斗に対する感情の変化に気付いたあの雨の日から、少しずつ私が変になっていっている気がする。
「遥ちゃん、起きた?朝ごはんできてるよ!」
「龍斗、ノックぐらいしなさいってば」
今目の前にいる龍斗はこんなにもほがらかで、いつものように優しい笑顔を向けてくれるのに。
夢の中で見た龍斗は、ただ一人の男でしかなくて、身体を熱くさせ、息を荒げ、射るような瞳で私を見つめている。
そして、女としての私を必死に求めてくる。
それが私の願望なのか、それとも恐れているのか分からない。
「あれ?遥ちゃん、シャンプー変えた?」
すれ違いざまに、龍斗が耳元に顔を寄せた。
「なんか、いつもと香りが違う」
そのまま龍斗が、すんすんと髪に近付けた鼻を鳴らす。
耳元で話す龍斗の吐息や、首筋に触れるか触れないかのところで動く唇の気配に、夢の余韻なのか、ぞわっと甘い感覚が押し寄せ、思わず首を押さえて、サッと龍斗から身体を離した。
「あ、これね、シャンプーじゃなくて、ドライヤーする前にヘアオイル使ったの!香りが気に入って即買いしちゃって!」
急に身体を離されて、私の行動に違和感を覚えたのか、龍斗がきょとんとこちらを見つめた。
「そう…なんだ」
「朝ごはん作ってくれたんだ!先に顔洗ってから食べるね」
部屋を出て、洗面台へと向かった。
なんか、龍斗の顔がまともに見れない!
初めて恋愛をするわけでもないっていうのに、この歳で!!!
夕方、仕事から帰宅すると、カレーのいい匂いがキッチンから漂っていた。
「ただいま!夕飯も作ってくれたんだ!」
「おかえり。うん、今日はバイトもなかったし。カレーの材料なら冷蔵庫にありそうだったから」
鍋に浸かったレードルを回しながら龍斗がにこりと笑った。
その横から鍋を覗き込んだ。
「私の好きなきのこカレーだ!あの食感が好きなのよね」
「あ、ネックレスの留め具が前にきてる」
そう言って龍斗が首に手を伸ばした瞬間、思わずその場から飛び退いた。
「あっ、いや、自分でなおすから大丈夫!あ、ありがとう」
慌てて取り繕ったが、龍斗にはそう何度もこういうことは通用しない。
「…ねえ、遥ちゃん。俺のことまた避けてる?」
「え?!い、いや、そんなことないけど、仕事持ち帰ってきてるから、夕飯はあとでにしようかなって思っただけだよ」
「ふうん…でもとにかく夕飯は先に食べて!サラダも用意してるし、冷めないうちに!」
「分かった。とりあえず着替えてくるね」
足早に自室へと逃げ込んだはずが、閉めようとした扉を強い力で押さえられてしまった。
「そんなあからさまに避けなくてもいいじゃん。俺はこないだ遥ちゃんと両思いになれたと思って、浮かれてたんだけど、違うの?」
部屋に入り込まれて、そのまま壁に押し付けられた。
龍斗が鼻と鼻がついてしまうぐらいの至近距離に顔を寄せてくる。
「それはっ、違わないというか…まだしっくりときてないというか…龍斗をそういう目で見るのに慣れなくて…」
思わず目を伏せて、しどろもどろになってしまった。
「キスしたい」
ふいにそう言われて、胸がドキリと鳴った。
若くて、たるんだ皺一つない整った顔立ちのまま真顔でそんなことを言われたら、思わず頭がグラつきそうになる。
少し前までは、どんなに近付かれても、絶対にそんなこと感じなかったのに。
と、こんな状況なのにそこでふと思った。
あれ?そういえばここ数年こんな間近で龍斗の顔なんて見ていなかった気がする。
最近は、近付いてさえなかったような…
私の返事など聞く間もなく、近付く龍斗の唇を思わず押さえた。
「え!や、ちょっとっ、待って!何してんの?!」
こうやって迫られると、二十歳の誕生日の夜に、無理やりされたキスの感触を思い出して、身体が勝手に熱くなる。
「ねえ、俺以外とキスしたのっていつ?」
自分の唇を押さえていた私の手をそっと剥がしてから、龍斗が聞いた。
「急に何でそんなこと聞くの?!」
聞いても理由は答えない。
「もう、そんなの覚えてないわよ!覚えてないぐらい昔!」
「嘘だね!少なくとも5年前と3年前は男いたじゃん!」
いじけたように龍斗が顔を背けた。
「え、ちょっと何でそんな年数まで覚えて…」
「気付いてないとでも思った?」
龍斗の瞳が急に熱を帯びたことに気付いた。
あ、夢と同じ。
「5年前は中3。3年前は高2。健全な男子にひどい仕打ちだよね」
「だってそんなの知らないしっ…それに、あのときは龍斗にも父親的な存在が必要なのかもと思って…」
「俺がどれだけ嫉妬したと思ってんの?」
そう言って、龍斗が私の言葉を遮った。
責めるような言葉とは裏腹に、悲しげに下がる目尻がどうにも愛しくてたまらない。
そう思って、そっと龍斗の頬を両の手のひらで包んだ。
ああ、そっか。
私がなんとも思っていない間も、この子は男として悩み、人知れず傷付いてきたんだ。
そう思うとますます愛しさが込み上げ、どうしても男としての龍斗を欲しくなった。
龍斗の顔を引き寄せ、そのまま深く口唇を重ねた。
誕生日の夜に龍斗が私にしたように。
背中に伝う冷たい壁の感触が、どうにか理性を保たせてくれている。
唇を離すと互いの口から熱い吐息が漏れた。
「ベッド行きたい」
ねだるような濡れた瞳に理性が崩壊しそうになったが、我慢してぐいーっと龍斗の胸を押し離した。
「ダメ!それはまだダメ!!」
「何で?!!ここまでしといて!!!遥ちゃんだって行きたいくせに、ベッド!!」
「そんなことない!!!行きたくない!!」
「嘘つき!遥ちゃんの意地っ張り!朝からいい香りなんかさせちゃってさ!」
「いや、それ、そんなつもりじゃないから!」
「ムリ!もうムリ!我慢も限界!10年我慢したんだからね!!」
そう言うと、龍斗が軽々と私を担ぎ上げた。
「ちょっ…やめて、おろしなさい!いつの間にそんなに力つけたのよ!カレーは?!冷めるんじゃなかったの?!ねえ!」
「カレーはまた温めればいい」
そのままベッドに寝かされてしまえば、わずかに残っていた理性などあっという間に意味を失ってしまった。
ああー…ついに…
体を起こして頭を抱えた。
遅かれ早かれ、こうはなるだろうと思ってはいたけど。
「…おはよう、遥ちゃん」
でも隣で優しく微笑む龍斗が愛しくて、後悔はしない。
そう思えた。
射し込む朝の陽光で、色白の龍斗が余計に綺麗に見えて、色気を感じてしまう。
こんな朝がくるなんて…
「お、おはよ」
はにかむように挨拶を返すと、急にぎゅーっと身体を抱き締められた。
「ああー、目覚めたら隣に遥ちゃんがいるなんて、夢みたいな朝だよ」
「そんな恥ずかしいこと言わないの!」
ああ、でもなんて可愛いこと言うのかな。
思わず私も、色素の薄い龍斗の柔らかい髪の毛ごと
ぎゅっと頭を抱き締めた。
「ねえ、…またしたい。いい?」
「え?」
髪を掻き分けて、龍斗が首元に唇を落としてくる。
「いやっ!ちょっ、何言ってんの!てか、そんな見えるとこに跡とかつけちゃダメだからね!」
「うん、分かってる」
聞いているのかいないのか、生返事の龍斗の胸を押し返す。
「…ちょっと!ねえ、待って!龍斗てば!夕べあれだけしてまだ…??!」
可愛らしくねだられて、下腹部が熱くなってしまう自分もちょっと腹立たしい。
「だって朝だし、もうこうなっちゃってるし」
布団を捲る龍斗の手を押さえた。
「ぎゃー!分かったから!朝から見せなくていい、見せなくて!!!てか、あんた引っ越すんじゃなかったの?!」
「んー…保留?」
そこから先は二人の秘密ということで。
恐るべし二十歳…。
一緒に暮らしてて私、これから大丈夫かな?
私たちの関係は変わっても、多難な前途は変わらず続いていくようだ。
熱に浮かされたように瞳を潤ませて、息を荒げる龍斗に押し倒された。
「ちょっ…待って、まだそこまでは覚悟できてなっ…」
「俺、もう限界だよ、遥ちゃん…」
龍斗の熱い吐息と舌の感触が首筋に触れた。
「あっ、龍っ!!それは待っ…ダっ、ダメーーーーーっ!!!」
パチリと目を開くと、明るくなり始めた自室の天井が見えた。
枕元のスマホが起床時間を知らせるために、必死でアラームを鳴らしている。
「この歳になって、こんな夢オチって………」
アラームを止めて、上体を起こした。
「どんな夢見てんのよ、私は。なんか寝た気がしないし…」
龍斗に対する感情の変化に気付いたあの雨の日から、少しずつ私が変になっていっている気がする。
「遥ちゃん、起きた?朝ごはんできてるよ!」
「龍斗、ノックぐらいしなさいってば」
今目の前にいる龍斗はこんなにもほがらかで、いつものように優しい笑顔を向けてくれるのに。
夢の中で見た龍斗は、ただ一人の男でしかなくて、身体を熱くさせ、息を荒げ、射るような瞳で私を見つめている。
そして、女としての私を必死に求めてくる。
それが私の願望なのか、それとも恐れているのか分からない。
「あれ?遥ちゃん、シャンプー変えた?」
すれ違いざまに、龍斗が耳元に顔を寄せた。
「なんか、いつもと香りが違う」
そのまま龍斗が、すんすんと髪に近付けた鼻を鳴らす。
耳元で話す龍斗の吐息や、首筋に触れるか触れないかのところで動く唇の気配に、夢の余韻なのか、ぞわっと甘い感覚が押し寄せ、思わず首を押さえて、サッと龍斗から身体を離した。
「あ、これね、シャンプーじゃなくて、ドライヤーする前にヘアオイル使ったの!香りが気に入って即買いしちゃって!」
急に身体を離されて、私の行動に違和感を覚えたのか、龍斗がきょとんとこちらを見つめた。
「そう…なんだ」
「朝ごはん作ってくれたんだ!先に顔洗ってから食べるね」
部屋を出て、洗面台へと向かった。
なんか、龍斗の顔がまともに見れない!
初めて恋愛をするわけでもないっていうのに、この歳で!!!
夕方、仕事から帰宅すると、カレーのいい匂いがキッチンから漂っていた。
「ただいま!夕飯も作ってくれたんだ!」
「おかえり。うん、今日はバイトもなかったし。カレーの材料なら冷蔵庫にありそうだったから」
鍋に浸かったレードルを回しながら龍斗がにこりと笑った。
その横から鍋を覗き込んだ。
「私の好きなきのこカレーだ!あの食感が好きなのよね」
「あ、ネックレスの留め具が前にきてる」
そう言って龍斗が首に手を伸ばした瞬間、思わずその場から飛び退いた。
「あっ、いや、自分でなおすから大丈夫!あ、ありがとう」
慌てて取り繕ったが、龍斗にはそう何度もこういうことは通用しない。
「…ねえ、遥ちゃん。俺のことまた避けてる?」
「え?!い、いや、そんなことないけど、仕事持ち帰ってきてるから、夕飯はあとでにしようかなって思っただけだよ」
「ふうん…でもとにかく夕飯は先に食べて!サラダも用意してるし、冷めないうちに!」
「分かった。とりあえず着替えてくるね」
足早に自室へと逃げ込んだはずが、閉めようとした扉を強い力で押さえられてしまった。
「そんなあからさまに避けなくてもいいじゃん。俺はこないだ遥ちゃんと両思いになれたと思って、浮かれてたんだけど、違うの?」
部屋に入り込まれて、そのまま壁に押し付けられた。
龍斗が鼻と鼻がついてしまうぐらいの至近距離に顔を寄せてくる。
「それはっ、違わないというか…まだしっくりときてないというか…龍斗をそういう目で見るのに慣れなくて…」
思わず目を伏せて、しどろもどろになってしまった。
「キスしたい」
ふいにそう言われて、胸がドキリと鳴った。
若くて、たるんだ皺一つない整った顔立ちのまま真顔でそんなことを言われたら、思わず頭がグラつきそうになる。
少し前までは、どんなに近付かれても、絶対にそんなこと感じなかったのに。
と、こんな状況なのにそこでふと思った。
あれ?そういえばここ数年こんな間近で龍斗の顔なんて見ていなかった気がする。
最近は、近付いてさえなかったような…
私の返事など聞く間もなく、近付く龍斗の唇を思わず押さえた。
「え!や、ちょっとっ、待って!何してんの?!」
こうやって迫られると、二十歳の誕生日の夜に、無理やりされたキスの感触を思い出して、身体が勝手に熱くなる。
「ねえ、俺以外とキスしたのっていつ?」
自分の唇を押さえていた私の手をそっと剥がしてから、龍斗が聞いた。
「急に何でそんなこと聞くの?!」
聞いても理由は答えない。
「もう、そんなの覚えてないわよ!覚えてないぐらい昔!」
「嘘だね!少なくとも5年前と3年前は男いたじゃん!」
いじけたように龍斗が顔を背けた。
「え、ちょっと何でそんな年数まで覚えて…」
「気付いてないとでも思った?」
龍斗の瞳が急に熱を帯びたことに気付いた。
あ、夢と同じ。
「5年前は中3。3年前は高2。健全な男子にひどい仕打ちだよね」
「だってそんなの知らないしっ…それに、あのときは龍斗にも父親的な存在が必要なのかもと思って…」
「俺がどれだけ嫉妬したと思ってんの?」
そう言って、龍斗が私の言葉を遮った。
責めるような言葉とは裏腹に、悲しげに下がる目尻がどうにも愛しくてたまらない。
そう思って、そっと龍斗の頬を両の手のひらで包んだ。
ああ、そっか。
私がなんとも思っていない間も、この子は男として悩み、人知れず傷付いてきたんだ。
そう思うとますます愛しさが込み上げ、どうしても男としての龍斗を欲しくなった。
龍斗の顔を引き寄せ、そのまま深く口唇を重ねた。
誕生日の夜に龍斗が私にしたように。
背中に伝う冷たい壁の感触が、どうにか理性を保たせてくれている。
唇を離すと互いの口から熱い吐息が漏れた。
「ベッド行きたい」
ねだるような濡れた瞳に理性が崩壊しそうになったが、我慢してぐいーっと龍斗の胸を押し離した。
「ダメ!それはまだダメ!!」
「何で?!!ここまでしといて!!!遥ちゃんだって行きたいくせに、ベッド!!」
「そんなことない!!!行きたくない!!」
「嘘つき!遥ちゃんの意地っ張り!朝からいい香りなんかさせちゃってさ!」
「いや、それ、そんなつもりじゃないから!」
「ムリ!もうムリ!我慢も限界!10年我慢したんだからね!!」
そう言うと、龍斗が軽々と私を担ぎ上げた。
「ちょっ…やめて、おろしなさい!いつの間にそんなに力つけたのよ!カレーは?!冷めるんじゃなかったの?!ねえ!」
「カレーはまた温めればいい」
そのままベッドに寝かされてしまえば、わずかに残っていた理性などあっという間に意味を失ってしまった。
ああー…ついに…
体を起こして頭を抱えた。
遅かれ早かれ、こうはなるだろうと思ってはいたけど。
「…おはよう、遥ちゃん」
でも隣で優しく微笑む龍斗が愛しくて、後悔はしない。
そう思えた。
射し込む朝の陽光で、色白の龍斗が余計に綺麗に見えて、色気を感じてしまう。
こんな朝がくるなんて…
「お、おはよ」
はにかむように挨拶を返すと、急にぎゅーっと身体を抱き締められた。
「ああー、目覚めたら隣に遥ちゃんがいるなんて、夢みたいな朝だよ」
「そんな恥ずかしいこと言わないの!」
ああ、でもなんて可愛いこと言うのかな。
思わず私も、色素の薄い龍斗の柔らかい髪の毛ごと
ぎゅっと頭を抱き締めた。
「ねえ、…またしたい。いい?」
「え?」
髪を掻き分けて、龍斗が首元に唇を落としてくる。
「いやっ!ちょっ、何言ってんの!てか、そんな見えるとこに跡とかつけちゃダメだからね!」
「うん、分かってる」
聞いているのかいないのか、生返事の龍斗の胸を押し返す。
「…ちょっと!ねえ、待って!龍斗てば!夕べあれだけしてまだ…??!」
可愛らしくねだられて、下腹部が熱くなってしまう自分もちょっと腹立たしい。
「だって朝だし、もうこうなっちゃってるし」
布団を捲る龍斗の手を押さえた。
「ぎゃー!分かったから!朝から見せなくていい、見せなくて!!!てか、あんた引っ越すんじゃなかったの?!」
「んー…保留?」
そこから先は二人の秘密ということで。
恐るべし二十歳…。
一緒に暮らしてて私、これから大丈夫かな?
私たちの関係は変わっても、多難な前途は変わらず続いていくようだ。