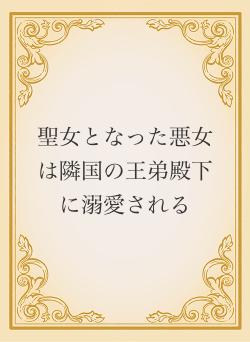わがまま聖女の世話係公爵令嬢は、年下ワンコ系王子に溺愛される
わがまま聖女の世話係公爵令嬢は、年下ワンコ系王子に溺愛される
なんとなく、こうなることは分かっていた。
「ルシア・プリエーミャ。今この時をもってお前との婚約は破棄させてもらう!」
第一王子であるダニエル・フォン・クライフが、婚約者である私に『今日からお前は‘‘聖女’’の世話をしろ!』なんて言ったあの日から、もしかしたらこんな日が来るのかもしれないと感じていた。
「アンから全て聞いた。お前は聖女の力を持つ彼女に嫉妬し、酷い嫌がらせをしていたようだな!」
二人の距離が近づくのは側にいたから嫌でも分かった。
4歳の時に婚約者となり、彼と初めて会ったあの日から12年。
その積み重ねた日々は、私にはない可愛らしさを持ち、コロコロと表情を変え誰にでも分け隔てなく接する愛らしい同い年の少女にたった1ヶ月で上書きされた。
つまり私は負けたのだ。
「王妃になれるとでも思っていたのか? ハッ、残念だったな! 王妃になるのは聖女であるアンだ!! 今すぐ俺の前から消えろ! もう二度と俺の前へ姿を見せるな!!」
私はもう用済みだ。そして、公爵令嬢としての立場やプライドもズタズタに引き裂かれ傷つけられた。
「……かしこまりました」
最後くらいは気高くいよう。感情を表に出さないことなど慣れている。
私は目の前で顔を真っ赤にさせ怒りを顕にしている‘‘元’’婚約者と、そんな彼の腕にぴったりと自身の体をつけ潤んだ瞳で彼を見上げる少女──聖女・アンに一礼して……──。
◇ ◇ ◇
「……ふぅ」
部屋を出て周りに響かないように小さく溜息を吐く。
本来なら溜息なんて吐いてはいけないことは重々承知だが、今は吐かずにはいられなかった。それほど私は辟易としていた。
──ことの始まりは数日前。この世界で最も身分の高い女性である‘‘聖女’’が発見された。
前の聖女が天寿を全うして以来何百年という長い期間新しい聖女は現れていなかったため、いつしか聖女は幸福な夢物語となって貴族平民関係なく愛され語り継がれていた。
聖女は16歳になるとその力を身に宿し、その存在一つで国を豊かにするという。そのため16歳になると王国に住む全ての女性は聖女式に参加し力の有無を確認するのがいつからか恒例となった。
しかし、当たり前だが簡単には見つからないまま数百年という月日が経った──のだが、なんと今年の聖女式で突然聖女が発見されたのだ。
「ルシア! 今日からお前は‘‘聖女’’の世話をしろ!」
「……かしこまりました」
「なんだ? 何か文句でもあるか?」
「……いいえ、申し訳ございません」
「ハッ、つまらんな。お前は俺のおかげで王妃になる女だ。対して相手は聖女である。どちらの方が上かわからんお前ではなかろう」
その言葉が皮肉だとわからない私ではなかった。
彼が国王となることで王妃になれる私と、自身の能力によってその地位を手に入れた聖女。そのどちらの方が上かと問われれば誰もが聖女様だと答えるだろう。国を豊かにしてくれる存在なのだから当たり前だ。
「承知しております」
だから私は感情なく頭を下げ彼の指示に従った。
その日から私は聖女の‘‘世話’’をするようになった。世話と言っても内容は身の回りの世話ではなく、上に立つ者の立ち振る舞いや礼儀作法などを教える教師のような役目。
彼女は平民の出。話し方も振る舞いも、何一つとしてできなくてもしょうがないことなど誰もがわかっている。だから彼女のペースに合わせて私は丁寧に教えていた──はずだった。
「あたしこんなのしたくなーい!」
「なんであたしばっかりこんなに大変な思いしなくちゃいけないのっ!?」
「別に勉強なんてしなくていいでしょ!! あたしには聖女の力があるんだから、それだけで十分なの!!」
足元に投げ捨てられた礼儀作法の教本や筆ペンにインク瓶。使用中だったインク瓶の蓋が閉められているわけもなく、投げた先にいた私のドレスの裾をゆっくりと黒く染める。
「ですが聖女様も今後国の祭事や夜会に出席していただくこととなります。その際にご挨拶していただく機会もございますので、最低限マナーについては身に付けていただけませんとお相手の方へ失礼に……」
「失礼? あたしは聖女なんだけど? あたしが話してあげるだけでも感謝して欲しいくらいなんですけど!」
彼女はそう言うと、ふんっ! と鼻を鳴らす。そして私を睨み付けると近くの棚においてあった本を手に取り振りかぶる。
「あんたってマジで空気読めないしうざいんだけど!」
そして私に向けて投げられた本はかなりの分厚さで重たかったこともあり、私にぶつかることはなく私と彼女の真ん中あたりに鈍い音を立てて落ちる。
しかし、彼女はそれすらも気に食わなかったのだろう。
「むかつくっ!! いいから早く出てってよ!」
聖女となってから全て自分の思い通りとなる生活が始まった。欲しいものは簡単に手に入り、命令すれば人をも自由に動かせる。何もかもが彼女の思うがまま。
だから彼女は、やりたくないと言っているのに引き下がらない私にも、私にぶつけるために投げた本がかすることもなくあっけなく地面に落ちたことにも腹を立てたのだ。
顔を真っ赤にさせて怒りを顕にし「出てけッ!!」と声を荒げ私を部屋から追い出すほどに。
一礼して廊下に出た私は、周りに人がいないのを確認してから静かな廊下に響かないように小さく溜息を吐く。
私だってできるのならばもう彼女の世話なんてしたくない。
毎日のように投げられる物や飛んでくる罵声。いったい誰が喜んでそんな状況を受け入れるだろうか。それでも私がやめないのは婚約者であり第一王子のダニエル様の命だからだ。
私は彼がいるからこそ次期王妃候補となれた身。私自身には公爵令嬢という肩書きしかあらず、それすらもご先祖様のおかげで手にした物であり私が手に入れたものではない。だからこそ私は彼に従い、彼の望むように行動する。
しかしそれももう限界だった。
最初はまだよかった。渋々、と言った感じではあったが彼女はちゃんと椅子に座り教科書を開いてくれていた。途中で飽きてしまう様子も見られたが、お菓子休憩を挟めば頬杖をつきながらでも静かにページを捲ってくれていた。
しかし、日が経つにつれてその態度はどんどん悪い方へと変わっていった。
『疲れたから休憩させて』から始まった言葉は次第に『やりたくない』へと変化し、そして今では椅子に座ることもなく、机の上に用意されたそれらを私に向かって投げつけ部屋から追い出す始末。
私以外の誰もこの現実を知らない。私が毎日物を投げられていることも、毎日罵声を浴びせられていることも、毎日部屋から追い出されていることも。このことを知るものは誰もいない。
代わりに知られていることといえば、第一王子の婚約者である私が聖女を虐めているという噂話。
プライドの高い私が平民の出である聖女の世話をしなければならないことの腹いせに虐めているだとか、婚約者である自分よりも聖女の方が第一王子によくしてもらってるのが気に食わなくて虐めてるだとか。そんな噂話がこの王城で広まっているのを私は知っている。
「……くだらないわ」
虐めなんてそんなことして一体何になるのか。世話係から解放される? それとも今すぐに王妃になれる? そんなわけがない。確かに世話係からは外れるかもしれない。しかしそれは私が次期王妃になれないことを意味する。
「昔はあんな方じゃなかったのに……」
記憶の中の婚約者はもっと純粋で可愛い人だった。『ルシアっ!』と、優しい笑顔を浮かべて私の名を呼ぶ彼はいつも私の手を引いてくれていた。彼と一緒にいるのが楽しくて、ただ純粋に心から幸せだと思えた。
……なのに、いつからだろうか。彼が変わったのは。そして、私が変わったのは。
「ルシア様っ!」
静かで長く豪華な廊下を視線を下げて歩けば、私の名を呼ぶ声が聞こえ足を止める。そして落ちていた視線を上げればそこには私に笑顔を向ける一人の男性が小走りで近づいてきた。
「ゼン殿下……。お久しぶりでございます」
「はいっ、お久しぶりです! ルシア様は今日も変わらずお美しいですね」
「……ありがとうございます。ですがゼン殿下、私に‘‘様’’など身に余ります。ですので他のご令嬢と同じようにお呼びください」
「では、ルシア様も僕のことは‘‘ゼン’’と呼んでください!」
「それは……できませんわ、ゼン殿下。自国の王子殿下を呼び捨てするなど公爵令嬢である私は許されません」
私がそうキッパリと断ると、彼──ゼン・フォン・クライフ第二王子殿下はニコニコと浮かべていた笑顔を少しだけ寂しそうに変え、眉を下げて「残念」と口にした。
ゼン殿下は私の婚約者であるダニエル様の実弟である。
私やダニエル様とは年齢は一つしか離れておらず、ダニエル様にとって彼は弟だが、まだ王太子が決まってないこの国で王座を奪い合うライバルでもあるため正直なところあまり仲はよろしくない。
本来であればダニエル様の婚約者である私との関係も悪くなるはずなのだが、なぜかゼン殿下はこんな私に好意的に接してくださり話しかけてくださる。……それはきっとゼン殿下のお人柄なのだろう。
「そういえば聞きました、聖女様の話。苦労なさってるようですね」
「……そんなことはございません。聖女様は頑張っておられ──」
そこまで言って私は言葉を失った。私の視界に映る二人の姿。まるで鈍器で頭を殴られたようなそんな衝撃に、私はただ立ち尽くすことしかできなくなった。
「頑張って……、そうですか。ではなぜ聖女の授業中であるこの時間にルシア様がこんな場所を歩いていて、彼女は兄上といるのでしょう」
ゼン殿下の言葉に私は目を逸らしたくなった。……いや、耐えきれなくなって私は現実から目を逸らした。
もう何年も見ていなかったダニエル様の笑顔。それが今、目の前にある。しかしその笑顔が向けられているのは私ではなく、彼の隣に立つ聖女様だ。
庭園に二人並び花を愛で、楽しそうに話し、笑い合っている。私が彼とあんな風に笑い合ったのは思い出せないくらい前だというのに……。
「なんだ、お前たち。こんなところで逢引か?」
ハッと顔を上げれば、まるで軽蔑するかのように険しく冷たい視線を私に向け、婚約者でもない聖女に腕を組ませ体を密着させた‘‘私の’’婚約者・ダニエル様が目の前に立っていた。
「これは兄上、お久しぶりでございます。ですが逢引とは聞き捨てなりませんね。今一度その意味をお調べになってみてはいかがでしょう」
「はっ、何を言う。こんな人気のない場所で二人で会っていたのだ。そう捉えられても無理はないだろう」
「こんな人気のない場所……、そうですね。確かにそうかもしれません。でしたら兄上に対してもそのように捉えてよろしいと言うことですね。仮にも婚約者のいる身で‘‘こんな人気のない場所’’に他の女性とおられたのですから」
「はっ、俺はこの美しい庭園を見てみたいと言った彼女を案内していただけだが?」
「そうでしたか。ですが、兄上が僕たちのことをそう見たように、僕たちの目にもそう見えましたので今後は控えられた方がよろしいかと」
笑顔を崩すことなく話すゼン殿下と、彼の言葉に眉間にシワを寄せ怒りに肩を震わせるダニエル様。その後ろで聖女はわざとらしく瞳に涙を浮かべ、ダニエル様により体を密着させて体を震わせていた。
「お前、たかが第二王子が将来この国の王になる俺にそんな口を聞いていいと思ってるのか?」
「クス……兄上はもうご自分が王になったつもりでいらっしゃるのですか? まだ王太子は決まっていないというのに」
まるで煽るかのようにクスリと笑うゼン殿下に、ダニエル様の怒りは明白だった。
騒ぎを聞きつけた者がわらわらと集まり出していたが、今にもゼン様に殴りかかりそうなダニエル様と、未だ笑顔を崩さないゼン様の様子を伺うだけで誰もこの二人を止めることなどできない。
「おっと、そろそろ僕は行きますね。兄上と違い僕は仕事をこなさなければなりませんので」
極めて明るく、しかし言葉には刺を含めゼン殿下は軽くお辞儀をする。そして隣にいた私に掌を上に向け片手を差し出した。
「ルシア様、良ければお部屋までのエスコートの役目、僕にくださいませんか?」
さっきまでの煽るような笑顔ではなく、優しく頬を緩ませた表情を浮かべ乞うように私を見つめるゼン殿下。
「お前っ!! そいつは俺の婚約しゃ──」
「あっ、もしかして頭が高かったでしょうか」
すかさずダニエル様が声を荒げるも、まるで聞こえていないかのようにゼン様は無視し、流れるような動作で片膝をつき下から私の瞳をしっかりと捉える。
それはまるで子犬のように潤んだ瞳で……
「ぜ、ゼン殿下っ! いけません! わたくしなどにそのようなことは──」
「ではルシア様、お手をとってください。そしたらすぐにやめますので」
「で、ですが……」
私たちに向かって叫び続けるダニエル様などまるで気にしていないかのようにゼン様は優しい笑顔を浮かべ私だけをまっすぐに見つめる。
このままでは埒が明かないだろう。膝をつき立ち上がろうとしないゼン殿下に、私たちへの苛立ちを隠すことなく顕にし怒鳴り続けているダニエル様。
本来ならば、婚約者以外の男性の手をとることなどしない。でもこの時だけは一刻も早くこの場を離れたくて……私はそっと彼の手に自身の手を、重ねた。
「ありがとうございます。エスコートさせていただけるなんて光栄です」
そう言って彼は触れた私の手に一度、触れるだけのキスを落とす。
そしてしっかりと離さないように大きな手で包み込むとやっと腰を上げ、兄であるダニエル様の言葉を無視し私の手を引きその場を後にする。
「あ、あの、ゼン殿下……」
「どうされました?」
「よろしかったのでしょうか……、ダニエル様にあのような……」
静かな廊下に二人の足音だけが響く。はっきりと言えずに濁された言葉はすぐに空気に溶けるが、ゼン様はそんな私の心内を理解したのだろう。
「態度、の話でしょうか? それでしたら平気です。実際まだ王太子は決まっておりません。それに兄上は威張るだけで公務など一切行わない無能な第一王子です」
‘‘無能な第一王子’’
ダニエル様が陰でそう言われていることは何度も耳にしたことがあった。実際ダニエル様はほとんど公務を行わない。国に関する仕事はもっぱら第二王子であるゼン様に丸投げだ。
ではダニエル様は何をしているかというと、第一王子という肩書きから王太子の座は自分のものだと慢心し、好き勝手なことをしてお金と時間を浪費しているということだろうか。
だからこそゼン殿下の言葉に私は婚約者であろうがフォローなどできなかった。それが事実であるから。
「仮にこのまま兄上が王になったとしましょう。この国は一年とせずに地図からその名を消すことでしょう。国政に興味のない兄上に取り入ろうと汚い手を使うものも現れ、国庫は食い潰され、その結果国は内側から腐り破滅の道を辿る」
その言葉に、私は何も言い返せない。本当にその通りなのだ。しかし──
「──だからこそ、わたくしがおります。ダニエル様を支えるために……」
幼い頃から厳しい王妃教育を受けてきたのは全て王になったダニエル様を支えるためだ。そして、この国をより豊かにするため。国民が平和に、幸せに暮らせるような国を作るためだ。
「あなたが僕の婚約者だったらよかったのに……」
「え? 今なんと……」
「いえ、世界一美しく聡明であるルシア様をお部屋までエスコートさせていただけて光栄です、と改めて思っただけです」
「っ!」
ゼン殿下はずるい。時々そう思わずにはいられない。
優しく、御伽噺の中の王子様のような佇まいで常に笑顔を浮かべ、こんな私にも分け隔てなく接してくださり、さらにこのような言葉まで……。彼にこんな扱いをされてときめかない女性はきっと世界中探してもきっといないだろう。
「ありがとう、ございます……。ですが、そういった言葉は簡単に口にしてはなりませんわ。ゼン殿下には婚約者の方がまだいらっしゃらないので、自分が特別だと勘違いする女性が現れてしまいます」
「勘違い、ですか……。していただいて良いのですがね」
「えっ……?」
「あぁ、もう着いてしまいましたね。できることならもっと長くお話ししていたかったのですが……残念です」
いつの間にか私の部屋の前に到着しており、ゼン殿下はもう一度触れるだけのキスを私の手の甲に落とし背を向け後にした。
ダメだとわかっていても、この胸が高鳴ってしまう。珍しく赤く染まった顔を隠すように、私は慌てて部屋に入り心を鎮めたのだった。
◇ ◇ ◇
聖女の態度は日を増すごとに酷いものへと変わっていった。
「嫌だって言ってるでしょ! あんたほんと何様!? あたしは聖女なんだから!!」
「勉強なんてしなくていいの! だってそんなことしなくてもエル様はあたしにそのままでいいって言ってくれたんだから!」
「このドレス、エル様があたしに買ってくれたの! 可愛いでしょ! ……あぁ、あんたは買ってもらったことなんてないんだっけ?」
「ふふっ、婚約者のくせに……、なんかあたしばっかりごめんね?」
私を見下すような笑みを浮かべ、彼女は私に隠すことなく彼のことを‘‘エル’’様と愛称で呼ぶようになった。それは明らかな私への侮辱だった。
「たとえ聖女様でも、ダニエル様のことを愛称で呼ぶことは──」
「エル様がいいって言ったの! あんたには関係ない。それとも悔しいの? 婚約者のくせに愛称で呼ぶことを許されないのが」
「そうではありません」
「じゃあ何? 言えばいいじゃん、悔しいって! 自分は婚約者に相手にされないのに、聖女であるあたしには構っているのが悔しいって!」
何でも手に入れられる聖女。そして彼女はきっと、彼の心さえも手に入れた。だからこそこんなにも堂々と私を侮辱できるのだろう。
彼を味方につけた今、彼女を咎めるものは誰もいないから……。
「何の騒ぎだ」
二人きりの部屋にノックもなく突然入ってきた声に驚く私。反対に目の前の彼女はさっきまでのひどく歪んだ優越感に浸る表情から一転、可愛らしく庇護欲を掻き立てる表情へと瞬時に切り替える。その目には涙を浮かべて──。
「エル様っ! きてくれたのっ?」
「あぁ、今日は一緒に宝石を観に行く約束をしていたからな。なかなかこないから心配していたんだ。……しかし、さっきの騒ぎは一体なんだ? なぜアンが涙を浮かべている?」
抱きつくようにダニエル様の胸に飛び込み、ダニエル様もまた、彼女を守るように抱きしめる。優しい笑顔を浮かべ彼女を観ていた視線が私を捉えるとすぐに冷たい視線へと変わり、低い声には怒りがこもっているのがわかった。
「申し訳ございません。聖女様がダニエル様のことを愛称でお呼びになられておりましたので諌めておりました」
「諫めた、だと? アンにその名を呼ぶことを許可したのは俺だ。何の権利があってお前ごときが彼女に意見できるというのだ」
「……申し訳ございません」
「お前にアンのことを任せた俺が馬鹿だった。行こう、アン。キミに似合う宝石を俺が選んであげよう」
「やったぁ! エル様大好き!」
「あぁ、俺もだ」
深く頭を下げる私になど目もくれず、ダニエル様は彼女の肩を抱いて部屋から出て行った。
蓋の開いたインク瓶は今日も豪華な絨毯を真っ黒に染めている。
私はただボーッと立ち尽くし、ゆっくりとシミが広がるのを見ていた。明るい場所が少しずつ真っ黒に染められていく光景。それはまさにわたしの心そのものだった。
少しして部屋の片付けに数人の使用人が入ってくるが、いつも通りのひどく汚れた部屋を見て彼女たちは私を前にしても溜息を隠すことはなかった。
……舐められたものね。
第一王子の婚約者。しかし、今の私は婚約者から寵愛を受けることのできなかったただのお飾り同然の女。ダニエル様の気持ちが聖女に向いていることなど誰が見ても一目瞭然だった。だからこそ、私の権威が薄まるのはしょうがないこと。
静かに部屋を出れば、さっきまで静かだった室内から使用人たちの声が聞こえ出す。それはもっぱら私の悪口だ。
でももうどうでもよかった。使用人が私の悪口を言おうが、私のことを嫌おうが、もうどうでもいい。何もかも、誰もかも、全てが私にとってはどうでもいいのだ。
この地獄のような日々に私は慣れてしまったようだ。悲しい、つらい、苦しい、悔しい。そんな感情はいつしか生まれなくなっていた。ただ無心で頭を下げ、私はただ無心で命令に従うだけだ。
◇ ◇ ◇
そこは煌びやかな世界。
綺麗なドレス姿に身を包み、髪を美しく上品に纏め、大きく輝く宝石を付け着飾る女性。
反対に、きっちりとした落ち着いた色の服に身を包み、パートナーとなる女性を侍らせシャンパングラスを片手に談笑する男性たち。
しかし今、大きなホールに入場した私に多くの者が視線を向け、シンとした一瞬の静寂の後すぐにコソコソと聞こえない声量で話を繰り広げだした。
普通、パーティーでのパートナーは既婚者であれば旦那や子息が、未婚の女性も男家族や婚約者が務めるものだ。しかし今、私の隣には誰もいない。第一王子の婚約者である私がパートナーのエスコートなく入場する姿はひどく異様に彼らの目に映ったのだろう。もしくは滑稽に映ったに違いない。
いつもなら多くの者が未来の王妃になる可能性が最も高い私に媚び諂うように挨拶にきていた。しかし今日は私の実家である公爵家に縁のある一握りの者のみだけだった。
寵愛を受けられない私よりも、おそらくダニエル様にエスコートされ入場するであろう聖女に取り入った方がいいと思ったからだろう。
「ルシア様っ!」
「……ゼン殿下」
窓際で誰の視界にも入らないように大人しくしていた私に話しかけてきたのはいつもの優しい笑顔を浮かべたゼン殿下だった。
白と青を基調とした豪華な服に身を包んだ彼はまさに‘‘王子’’そのもの。
「そのドレス、とてもお似合いです。ルシア様にはやはり海のように光り輝く青が似合いますね!」
「……ありがとうございます。ゼン殿下もとてもよくお似合いですわ」
「ところで兄上はご一緒では……」
そこまで言って気が付いたのだろう。ゼン殿下は深い溜息を吐いた。
「どこまでも愚かな……。婚約者であるルシア様を一人にするなど」
「私は気にしておりませんので」
「そんなっ!」
声を上げた彼に私は小さく首を振った。大丈夫、何も気になどしていないと、心配などいらないと意味を込めて。
「……でしたら、僕がルシア様のパートナーになってはいけませんか?」
「え……?」
「見ての通り僕も独り身ですので」
そう両掌を私に向け笑いながら何もないことをアピールするゼン殿下。
「パーティーは楽しまなければ損です! 美味しい料理も、優雅な音楽もあります。まぁ、中には変な輩もおりますが、ルシア様のことは僕が守りますので!」
不思議な気持ちだった。どんなに真っ黒に心が染められようともゼン殿下がそばにいると、まるで浄化されていくかのように心がひどく穏やかになる。
守ると言いながら見えない的に向かって剣を振る様子を見せる殿下に、私は釣られて笑みを溢す。そして差し出された手に私は‘‘迷いなく’’手を伸ばすと、私が彼に触れるよりも先に彼が私の手に触れた。
「あらゆるものから僕が守ります。この命に変えても。例えば……兄上とか!」
「ふふっ、ありがとうございます」
「あなたにはハッピーエンド以外似合いません。だからどうか、笑っていてください」
優しく笑うゼン殿下につられ、私もつい頬を緩める。穏やかで幸せだと感じる時間。この時間がずっと続けばいいにと、願わずにはいられなかった──。
ゼン殿下のおかげでいつもよりも楽しい時間を過ごし、華やかなパーティーも終盤に差し掛かった頃。
「ルシア様はここで休んでいてください。僕は何か飲み物を取ってきますので」
そう言ってゼン殿下に案内されたホールの端で、私は穏やかで温かい気持ちに浸りながら一人休憩していた。
ある者たちは美しく舞い、ある者たちは会話に花を咲かせる。周りを見れば誰もが笑顔を浮かべている光景に、私も今はその中の一人なのだと不思議な気持ちになる。
パーティーを楽しいと感じたのはいつぶりだろうか。そう考えてしまうほど、その最後の記憶は遠いものだった。
普段、パーティーでの私は何も考えずにダニエル様の隣に立っているだけの人形のようなものだ。ダニエル様の隣に立ち、作り笑顔を貼り付けて彼の命に従うだけ。楽しいだなんて感情は、そこに少しもありはしなかった。
だからこそ、こんな風にパーティーを楽しめる時が来るなど思いもしなかった。
──なんて珍しく頬を緩めていると、アンを背中に隠しながら私の元までやってきたダニエル様は人目も憚らず突然声を荒げた。
「ルシア・プリエーミャ。今この時をもってお前との婚約は破棄させてもらう!」
瞬間、優雅に流れていた音楽はピタリと止まり、シン──とした静寂が会場を支配する。
「アンから全て聞いた。お前は聖女の力を持つ彼女に嫉妬し、酷い嫌がらせをしていたようだな!」
周りの空気など気にしないダニエル様は怒りを顕にしてそう言葉を続けた。
彼の後ろに隠れるように立っている聖女はか弱い小動物のように小さくなり、彼の服の裾をギュッと掴んでいる。
そして自分達は巻き込まれないようにと、さっきまで近くで踊っていた人たちは皆一定の距離を置き私たちを囲み見ている。
「誤解でございます。わたくしはそのようなことはしておりません」
「誰に口答えしているのだ! 聖女であるアンが嘘など吐くはずないだろう!」
彼の後ろに隠れたアンが口角を上げたのが見えた。ダニエル様はもう私が何を言おうと聞きはしないだろう。……いや、今更か。前からずっと彼は私の話など聞いてくれなかった。
「王妃になれるとでも思っていたのか? ハッ、残念だったな! 王妃になるのは聖女であるアンだ!! 今すぐ俺の前から消えろ! もう二度と俺の前へ姿を見せるな!!」
そんな彼にもう何を言っても無駄だろう。そんなこと私が一番わかっている。だから最後くらいは気高くいようと決めた。たとえここにいる全ての人の目に惨めに映っても、こんな風に惨めに婚約破棄を突き付けられようとも、私は公爵令嬢なのだから。
「……かしこまりました。失礼いたします」
私は目の前で顔を真っ赤にさせ怒りを顕にしている‘‘元’’婚約者と、そんな彼の腕にぴったりと自身の体をつけ潤んだ瞳で彼を見上げる少女──聖女・アンに一礼してその場を後にしようとした。……その時だった。パッと腕を掴まれ私は足を止め、顔を上げる。
「ゼン、殿下……?」
「遅くなり申し訳ございません」
「ハッ、ゼンと一緒だったのか! よかったな、俺に相手にされなくとも同じ王族であるゼンに相手してもらえて! そいつに未来はないとわかっていてもそこまでして王家に縋りたいか!」
突然現れたゼン殿下を見てダニエル様は一瞬ピクリと眉を動かすも、すぐにその軽く回る口を動かす。
「兄上。謹んでください。それ以上彼女を侮辱することは許しません」
「なに? お前、誰に向かってそんなことを言って──」
「何を騒いでおる」
突然部屋全体に響いた低く威厳のある声に、ダニエル様は口を塞ぎ、ホールにいた者も皆動きを止めた。さっきまで私たちの様子を見てザワザワとしていたざわめきは一瞬にして無くなる。
「今日は皆に報告があり来たのだがな、なんだこの騒ぎは」
王族専用の二階から並んで入場したダニエル様とゼン殿下の実の両親である国王陛下と王妃様は、騒がしいホールに気がつくとすぐに鋭い視線を私たちに向け、そしてダニエル様を捉えて止めた。
「ダニエル、答えよ。一体なんの騒ぎだ」
そう名指しされたダニエル様は一瞬肩を震わせたが、少し息を吸うとことの経緯を話し始めた。……が、その話は酷いものだった。
ダニエル様の話は客観的ではなく、自身の感情が先走っているものだった。そんな話を一通り話し終えたダニエル様は勝ち誇ったような表情を私たちに向ける。
しかし次の瞬間ホールに響いたのは、頭を抱えた国王陛下の呆れ果てた溜息だった。
「愚かな……」
その言葉は静かなホールに嫌でも響き渡った。
「……愚か、と仰ったのですか?」
「あぁ、お前にはそう聞こえなかったのか?」
低く吐き捨てられた言葉にダニエル様は信じられないという顔をして、それ以上何も言えずに口を噤んだ。
「ゼンよ、こちらへ。それからプリエーミャ嬢もこちらへ」
「はい、父上」
国王陛下の言葉にゼン殿下は返事をすると、「お手をどうぞ」と私に手を差し出し、私は戸惑いながらもその手に自身の手を重ねる。
そして王族のみが足を踏み入れることのできる豪華な階段をゼン殿下にエスコートされながら上れば、ダニエル様と聖女・アンが驚きつつも憎そうに私たちを見ているのが視界の隅に映る。
「今日皆に報告したいと言ったことは外でもない、王太子についてだ」
国王陛下の突然の言葉に、静寂が支配していた会場は一瞬にしてざわつきを取り戻す。
「長く、王太子を決めてこなかったのは相応しいかを見極めるためであった。私は二人の息子に平等にチャンスを与えた。そしてその結果がこれだ」
それはひどく呆れたように、国王陛下は言い放った。そして、一度息を吐き息を整えると……
「ホークス・フォン・クライフの名においてここに宣言する。王太子の地位はゼン・フォン・クライフに与えるものとする!」
瞬間、会場内は王太子となったゼン殿下を称える声で溢れた。しかし、そんな声をかき消すかのようにダニエル様の叫び声が響く。
「お待ちください父上!! これはいったいどういうことなのでしょう!!」
「……なにがだ」
「なぜ第一王子である私が王太子ではないのです!!」
「言ったであろう。私は平等にチャンスを与えた、と。第一王子という意味のない肩書きに胡坐をかき何もしなかったのはお前自身であろう」
「っ!! そ、それは……、で、ですが私には聖女である彼女を歓迎する役目が──」
「お前の言う‘‘歓迎’’とは自身の婚約者を蔑ろにし、聖女の欲しがるものをなんでも買い与え国庫を潰そうとする行為のことか?」
国王陛下のその言葉に再び反論しようとしたダニエル様だが、ギロリと国王陛下に睨まれると肩を震わせ口を閉ざした。
「お前には後日罰を与える。それまで自室を出ることは許さん。謹慎しておけ!!」
シン──としたホールに国王陛下の声が響き渡る。まさかこんな未来が来るなんて少しも想像していなかったダニエル様は、突き付けられた現実を受け止めきれず膝からその場に力なく崩れ落ちた。
「して、聖女よ。そなたは王子を惑わし国を乗っ取ろうと画策した」
「っ!! あたしはそんなことしてない! それにあたしは聖女でこの国の誰よりも偉いんだから、大切にされるのなんて当たり前でしょ!!」
「……愚かにも罪を重ねるか。聖女を地下牢へ!! 連れて行け!」
近づいてくる騎士たちから逃げようとするがすぐに捕まり、騒ぎ抵抗する聖女。しかし、大の男数人に小さな少女が力で敵うわけがなく、抵抗虚しく聖女はホールから連れ出された。
そしてダニエル様もフラフラした足取りで騎士に囲まれこの場を後にする。
突然のことに静まりかえったホール。しかし、その静寂もすぐにゼン殿下が王太子となった話題で溢れかえっていた。
私はその一瞬とも思える出来事を、国王陛下たちの後ろに控えるように立つゼン殿下の隣に並び、ただ見ていることしか出来なかった。
彼らに振り回された私の1ヶ月は国王陛下自らの手により一瞬にして片付けられてしまい、私は戸惑いを隠せない。しかし、そんな私に王妃様は近づくなり直ぐに申し訳なさそうに頭を下げた。
「あなたには迷惑をかけたわね。それにあの子のせいでたくさん傷つけてしまって、ごめんなさい」
「そ、そんな! 頭をあげてください」
「今この時を持ってあの子との婚約は破棄させていただきます。もしあなたが望むならゼンと──」
「は、母上っ!!」
「あら、わたくしったら余計なことを?」
慌てた様子で止めに入るゼン殿下に、王妃様はフフッと上品に笑ってみせる。
「それ以上は自分で伝えさせていただきますので」
「そうね。それがいいわ」
さっきまでと違い、ゼン殿下とそっくりな顔で優しく微笑む王妃様のおかげで穏やかな空気が流れ出す。
「ルシア様、よろしければ少し風に当たりませんか?」
もう私に男性の誘いに躊躇う理由はなかった。だから私は素直に頷き差し出された彼の手に自分の手を重ねた。
体を撫でる風が心地いい。静かなバルコニーにゼン殿下と二人きり。ここから見える中庭の小さな池には月や星が映し出されていてとても美しかった。
「綺麗です」
「えぇ、本当に。今夜は天気が良いですから」
「いえ、そうではなく……ルシア様が」
ゼン殿下の思いも寄らない言葉に、私は驚き顔を上げる。そして真っ直ぐに私を見つめる綺麗な瞳と視線が交わった。
「綺麗です、昔から変わらずずっと」
「ぜ、ゼン殿下!? 急に何を──」
「僕はルシア様をお慕いしております」
それは突然の告白だった。そして流れるように膝をついた彼は私の手を取り、手の甲に一つキスを落とす。──瞬間、私の心臓が激しく脈打ち出す。
「どうか僕に、あなたの隣にいる権利をくれませんか?」
そう切実に、乞うような視線を向けられ、私の胸は今にも壊れそうだ。聞こえてしまうのではないかと思うほど、体中に響く心臓の音は心臓が耳元にあるかのように近く感じる。
きっと顔はりんごのように真っ赤に染め上げられているだろう。しかし男性からこんな風に思いを伝えられたことなど生まれてから一度も経験したことがないのだから仕方のないことだ。そしてこんな時どうするのが正解なのか、私は知らない。
「私は……」
ただ、ついさっきまで私はダニエル様の婚約者だった。それなのにすぐにゼン殿下の手を取るなんてことしていいはずがないと私の中の冷静な部分が私に訴える。
呟かれた言葉はあっという間に空気に溶けて消えて無くなり、訪れる静寂。たった数秒が今はすごく長く感じる。
「では、チャンスをください」
「チャンス、でしょうか……?」
「はい。僕がどれだけルシア様を好きなのか言葉と行動で示します。これまでは兄上の婚約者でしたので遠慮していましたが、これからは遠慮は一切しません」
ゆっくりと立ち上がったゼン殿下は手始めに、と言わんばかりに「好きです」と言葉にした。
「触れてもいいですか?」
そう聞くと同時に私の頬へ伸ばされた手は優しく私の頬を撫でる。
「んっ……」
「可愛いすぎです、ルシア様」
くすぐったくて、恥ずかしくて、真っ直ぐにゼン殿下を見れなくて視線を逸らす。そんな私を見てゼン殿下はクスリと笑い──
──チュッ
と、静かに私の額にキスをした。それはまるで御伽噺のワンシーンのように、月に照らされた私たちの影が一つに重なった瞬間だった。
「ぜ、ゼン殿下っ!?」
「ルシア様、愛しています」
「っ!!」
いたずらっぽく笑う彼。そんな彼に、私はきっと一生ドキドキさせられるのだろうと、そんな予感がした。