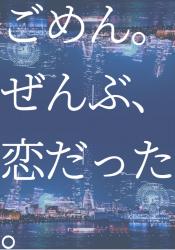桜新町ワンルーム
焦がれて、離れて、恋をして
ドイツ出身の思想家、フリードリヒ・ニーチェはこんな言葉を残している。
〝結婚するときはこう自問せよ。「年をとってもこの相手と会話ができるだろうか」そのほかは年月がたてばいずれ変化することだ〟
桜新町二丁目に住みはじめたのは、高校を卒業した春からだ。高校時代、渋谷、二子玉界隈で遊んでいた俺は品川にある大学に入った。渋谷までは九分、二子玉川までは十一分、品川までは二十六分の桜新町でワンルームを借りることは、俺にとって理想郷とも言えた。
「なあ、フジロック行かね? 今年はヤバいらしいんだよ」
うるさいと陽気を兼ね備えた俺の友人、早瀬は空を見ても、猫を見ても、旨いものを食っても『ヤバい』しか言わないようなやつだった。
「早瀬のヤバいは信用できないんだけど?」
「いや、今回はマジでヤバいんだって!」
俺はもみくちゃにされるフェスよりも、モルカルみたいな落ち着いたライブのほうが好きだったけれど、早瀬のしつこさに根負けする形でフジロックに初参戦することになった。
結果として、普通に楽しめた。音楽は世界共通なんて言うけれど、会場にいた人と全員友達になれると思ったくらいフェスは俺を陽キャに変える力を持っていた。
「うわ、バス待ちの列エグっ!」
満員電車を避けるためにバスを使おうという考えは、みんな同じだった。いつ乗れるのかわからないほど長く続いてる列は、早瀬のいうとおりエグかった。
「これ隣の駅まで歩いたほうが早くない?」
「だな!」
意見が一致した俺たちは、まるで勝ち誇ったように列の横を通りすぎる。その時に、フジロックのタオルを首から下げている女子ふたり組を見つけた。
ひとりはフェス常連感が漂う登山女子みたいな格好をしていて、もうひとりは綺麗めのセットアップを着ていた。肌の露出はなくてもスタイルの良さは洋服越しでも分かる。
脳内にモルカルではなく、アジカンの曲が流れはじめる。完全にフェスの影響だった。ロックに背中を押されるように、俺はセットアップ女子に声をかけた。
「俺たち隣の駅まで歩くんですけど、一緒にどうですか?」
ナンパと言っていいのか分からないけれど、下心は確実にあった。普段空気が読めない早瀬は、こういう時だけ察する能力に長けていて、俺とお目当ての女の子が並んで歩けるように、二対二に分かれてくれた。
「俺、森崎誠二っていう名前です」
「私は中野三加です」
「何歳ですか?」
「二十歳です」
「え、じゃあ、タメですね! 大学生ですか?」
「私は専門に通ってます。誠二くんは大学?」
声をかけて正解だと思うほど、三加は俺のタイプだった。見た目もそうだし、話し方も穏やかで、聞き上手。彼女もフェスには初めて参加したようで、そこにも勝手に運命を感じていた。
フェスの話、アーティストの話、学校の話、住んでる場所の話、俺たちの喋りは途切れなかった。まるで、昔から知っているような安心感で、俺は連絡先を聞いた。
今度四人でご飯食べに行きましょうよ、なんて、決してふたりきりではないですよということを強調した。警戒されたくなかった。彼女は『いいですよ』と笑って、ラインを教えてくれた。
それからすぐに四人の食事会が実現した。意気投合した俺たちはカラオケで朝まで歌った。コンビニでストロング缶を買って、河川敷で喋った夜もあった。
居酒屋のトイレに貼ってある九十九万円で行ける世界一周旅行をしよう。海に行って、シュノーケリングがしたい。秋にはブドウ狩り、冬はグランピングもいいねという話をした。
それは、毎日渋谷と二子玉に入り浸っていた高校の時のような、二度目の青春みたいだった。
早瀬は三加の友人、敦子ちゃんにすぐ手を出した。敦子ちゃんもまんざらではなかったらしく、すぐにふたりは付き合いはじめた。
「敦子ちゃんって、年上の彼氏いなかったっけ?」
「いたけど、早瀬くんと付き合いたいから別れたみたいだよ。早瀬くんこそ、年下の彼女がいたよね?」
「あいつも敦子ちゃんと付き合うために別れたらしい」
「似た者同士だね」
友人たちの展開の早さは、俺と三加の背中を押した。俺は早瀬みたいに手を出したりはしなかったけれど、ふたりだけのデートを重ねた折に、彼女になってくださいと告白した。
三加は年子の姉と一緒に草加に住んでいた。何回か彼女の家に遊びにいったけれど、いつお姉さんが帰ってくるか分からない家は、終始落ち着かなかった。だから、俺は言った。
『ここから専門に通うの大変じゃない?』『敦子ちゃんの家って、たしか新宿だったよね? 桜新町からだったら三十分もかからないよ』『映画館はないけど、ツタヤがあるから三加の好きなアバウト・タイムを借りよう』『スタバのコーヒーも用意するよ』
自分の家がいかにして住みやすいということを毎日アピールした。その甲斐もあって三加は俺の家で暮らすようになった。桜新町のワンルームは、俺にとってさらに理想郷と呼べるものになっていた。
「三加、準備できたよ」
「うん、ありがとう」
彼女がおそろいのお皿を持って、やってくる。テーブルには、近所のケーキ屋で買った四万十地栗のモンブラン。俺がカスタムしたスタバのコーヒーをその隣に置いて、プロジェクターのスイッチを入れた。
このプロジェクターは、敦子ちゃんの結婚式の二次会で三加が当てたものだ。敦子ちゃんが結婚したのは早瀬ではない。あのふたりは展開こそ早かったものの、その付き合いは半年も続かなかった。一方の俺たちは、あれから三年六カ月一緒にいる。
初々しさはなくても、安定感はある。スタバのカップを口に付けるタイミングも、手に取るタイミングも、飲むタイミングも、テーブルに戻すタイミングさえも同じだ。まるで長年連れ添った夫婦のように。
壁に投影されている映画が進む。場面はちょうど主人公がタイムトラベルの能力を父親から聞かされるシーンだった。
「三加は過去に戻れたら、なにがしたい?」と尋ねると、彼女は決まって同じ質問を返してくる。
俺は人生を楽しんできたほうだから、戻りたい過去はない。強いていうのであれば、仮想通貨の利益とか、上がる株の情報とか、宝くじの当選番号を過去の自分に教えて億万長者になりたいという願望はある。
「過去に戻れたら、俺たちはまた付き合うと思う?」
そう聞くと、三加はまた答えを言わずに質問を返してきた。
「誠二は、私が彼女で幸せだった?」
俺はもちろんと答えた。三加とだったら、これからも幸せでいられると思っている。なのに、彼女は一カ月前、突然別れを切り出してきた。
俺はすぐに三加に好きな人ができたのではないかと疑った。でも彼女は違うと言った。
「それなら、なんで別れるの?」
「私は誠二といることに慣れすぎちゃったと思う」
俺は納得できなかった。慣れることのなにがいけないのだろうか。
俺は三加の穏やかな空気が好きで、仕事の飲み会に行っても文句を言わないところ。急な用事が入ってデートに行けなくなっても、また今度行けばいいよって許してくれるところ。彼女よりも奥さんみたいに、俺を立ててくれる三加とずっと家族になりたいと思っていた。
だから俺は彼女を繋ぎ止めたかった。
家を出ていくという三加に、新居が決まるまではうちにいなよと言った。この一カ月間、ふたりで過ごした思い出の場所にたくさん行った。
そうすれば、幸せだった日々を思い返して、別れることをやめてくれると思っていた。
けれど、彼女の意志は固かった。住む場所も決まってしまって、今日が最後の日。三加の好きな映画を観て、ケーキを買って、スタバのコーヒーも用意した。俺はまだ諦めていなかった。
〝結婚するときはこう自問せよ。「年をとってもこの相手と会話ができるだろうか」そのほかは年月がたてばいずれ変化することだ〟
フリードリヒ・ニーチェの言葉のように、俺は三加とだったら、ずっと会話を重ねていける。
その他のことがいくら変わっていったとしても、思い出を増やしていけば、愛も増えていく。
お互いに年を取って、スキンシップがなくなっていったとしても、こうして好きな映画を観ればいい。
三加は最後の荷物を持って、玄関に立った。どうして、なんで、と言いたい気持ちを抑えた。ここで泣きつくような男にはなりたくなかった。三加の前では、堂々とした自分を見せたかった。
「もう、行くのか?」
「うん」
俺はポケットに手を入れる。今日までずっと、なんで三加が別れようと言ってきたのか分からなかった。
早瀬に聞いたら、お前が覚悟を決めるのが遅すぎたのではないかと言われた。女は早くプロポーズしてほしいものなんだと。
三年六カ月、三加にとっては長すぎたんだろうか。まだお互いに二十三歳だ。身を固めるには早すぎる年齢だけど、彼女にとっては違ったのかもしれない。そういう理由しか、俺には思い付かなかった。
もしも、三加が悲しい顔を見せたら、名残惜しそうな素振りをひとつでも感じたら、これを渡そう。
「誠二、今までありがとう」
だけど、彼女の表情は晴れやかだった。
もう俺を置いて、別の道へと進もうとしていた。ふたりで暮らしたワンルームのドアが閉まる。ひとり残された俺は、彼女が置いていったシューズボックスの上の鍵を見つめた。
――『誠二は、私が彼女で幸せだった?』
どうして俺は、その質問を三加にしなかったのだろうか。
三加こそ、俺が彼氏で幸せだった?
俺は三加の幸せを願えない。
他の男と一緒になることすら、想像したくない。
俺は鍵の横に、渡せなかった指輪を置いた。