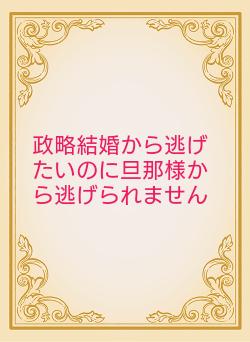異世界召喚 (聖女)じゃない方でしたがなぜか溺愛されてます
最終話 聖女(じゃなくても)溺愛されています②/②
それから二人でダンスをした。
自慢じゃ無いけど私のダンス経験。小さいときの盆踊りと幼稚園でのお遊戯しかない。
そんな私が踊るのだから、絶対アドルファスの足を踏むに決まっていた。
「ユイナ、かなり緊張していますね」
「ら、らっれ・・・・」
口も上手く回らないし、動きはすでにロボットになり、顔は石膏で固めたようになっている。
「あ、ごめんなさい」
既に足を踏んだ回数は片手では足りなくなっていた。
「大丈夫です。いざとなったら私が魔法で何とかしますから、あなたは笑顔で私だけを見つめていてください」
そう言って、アドルファスが強張った私の頬にキスをする。
「それにユイナが踏んだところで私の足はちっとも痛みませんよ」
「そんなわけないわ。踏んだら痛いでしょ」
「ですから、そんな痛みもあなたからなら、甘美な快感にしか思えません」
「マ、マゾ・・」
「マゾ?」
「えっと・・その苦痛を与えられて喜ぶ性癖のことです」
「ああ、そうですね。そうかも知れません。マゾ。きっとそうなんでしょう。あなたから与えられる刺激に限ってでしょうけど」
妙に納得して頷くのを見て、何だかアドルファスの新たな扉を開いてしまったかも知れないとおののく。
「ユイナ、この世界に来てあなたは良かったと思いますか」
本当は自分の力で踊りきりたかったけど、途中からアドルファスが風魔法を使って私を少し浮かせてくれた。
私はまだコントロールがうまくなく、長時間魔法を使うことはできない。
「はい。ここに来たからあなたに会えました」
力強く答えると、アドルファスが心の底から嬉しそうに微笑む。
「最近、生徒達に言われるんです。教官の表情がとても柔らかくなったと。きっとそんな時はあなたのことを想っているんでしょうね」
「それ、生徒達に言っていませんよね」
仮にそうだとしても、私を想っていたからとか、恋愛脳だと暴露しているようなものだ。しかも仕事中に。
「え、言ってはいけませんでしたか? もちろん仕事の手は抜いていませんよ」
「え、本当に言ったの!」
「事実ですから」
言葉を失って唖然としていると、更に彼は続けた。
「私の妻になる人は浄化の力があって、全属性の魔法が使えて、料理も上手でその上可愛い。正式に聖女とされているのはもう一人の異世界から来た女性だが、彼女はそれ以上、聖女じゃなく女神。私の人生に現われた奇跡だ。そんな人を妻に出来るなんて私ほど幸せな人間はいない。思わず笑みが溢れてしまうのは仕方の無いことだ。そう言ったら皆納得してくれた」
「・・・・・うそ」
「嘘では無い」
きっぱりとどや顔で言い切るアドルファスを、私は信じられない思いで見上げた。
(いや、いやいやいや、前半はいいとして途中から何だか私への認識がすごいことになっています。女神とか奇跡とか、アドルファスってそんなことを言う人だったの)
「そ、そんな大袈裟な・・」
どうりで士官学校の生徒達の私を見る目が最近変だと思っていた。
「大袈裟では無い事実だ。私にとってユイナはそういう存在だ」
「わ、私にとってもアドルファスは格好良くて勇気があって誰よりも優しくて、責任感があって頭も良くて背も高くて、私にはもったいないくらいの人だと思っているけど」
「そんな風に思ってくれているんだ。嬉しいよ」
「じゃなくて、でもそれは自分がそう思っているだけど、人には言いません」
人の惚気を聞かされても困るだけだ。それに実際に私のことを知っている人たちがそれを聞いたら絶対「え!」と思うだろう。
「それはそうだな」
少し考えてアドルファスが納得して頷く。私の気持ちが通じたと思った。
「皆がユイナのことを好きになったら困る。ユイナの素晴らしさは私だけが知っていれば良い。だが、それではユイナへの評価が上がらない」
などと真剣に悩まれまたもや唖然とする。
「だから・・」
「でも、やはりユイナがどんなに素晴らしいかを伝えるには・・」
「わ、わかった。わかったわ。アドルファス。私のこと、そこまで考えてくれてありがとう。でも、私は皆に評価されなくても、自分の周りの人たち、特にあなたに愛されればそれでいいの」
それは本心だ。元から万人に受け入れられるとは思っていない。
「ユイナ。そうですね。あなたの言うとおりです」
ふわりと体が浮いて、アドルファスと同じ目の高さになった。
アドルファスは浮き上がった私の腰を抱えて抱き寄せると、皆の前でキスをした。
その顔は私のことが好きでたまらないということを隠そうともしないくらい甘々だ。
周りの微笑ましい視線がちょっと恥ずかしかったが、今日は二人の結婚式なのだからイチャイチャも大目に見てもらえるだろう。
「愛しています、アドルファス」
「私もです。ユイナ」
わざと残している顔の傷に手を這わせ、そこにキスを落とす。
日本では愛しているとか言うこと自体恥ずかしい。こんな人前で抱き合ったりキスしたりするのも。
これもここだからだ。
それを見て誰も眉を顰めたりしない。
「これからもよろしくお願いします」
ぎゅっとアドルファスの首に腕を回して抱き寄せる。
「こちらこそ、よろしくお願いします」
異世界で出会った最愛の人。
私を大切にして溺愛してくれる人。
聖女・・じゃなくても、この人に溺愛されて、私はここで生きていく。
自慢じゃ無いけど私のダンス経験。小さいときの盆踊りと幼稚園でのお遊戯しかない。
そんな私が踊るのだから、絶対アドルファスの足を踏むに決まっていた。
「ユイナ、かなり緊張していますね」
「ら、らっれ・・・・」
口も上手く回らないし、動きはすでにロボットになり、顔は石膏で固めたようになっている。
「あ、ごめんなさい」
既に足を踏んだ回数は片手では足りなくなっていた。
「大丈夫です。いざとなったら私が魔法で何とかしますから、あなたは笑顔で私だけを見つめていてください」
そう言って、アドルファスが強張った私の頬にキスをする。
「それにユイナが踏んだところで私の足はちっとも痛みませんよ」
「そんなわけないわ。踏んだら痛いでしょ」
「ですから、そんな痛みもあなたからなら、甘美な快感にしか思えません」
「マ、マゾ・・」
「マゾ?」
「えっと・・その苦痛を与えられて喜ぶ性癖のことです」
「ああ、そうですね。そうかも知れません。マゾ。きっとそうなんでしょう。あなたから与えられる刺激に限ってでしょうけど」
妙に納得して頷くのを見て、何だかアドルファスの新たな扉を開いてしまったかも知れないとおののく。
「ユイナ、この世界に来てあなたは良かったと思いますか」
本当は自分の力で踊りきりたかったけど、途中からアドルファスが風魔法を使って私を少し浮かせてくれた。
私はまだコントロールがうまくなく、長時間魔法を使うことはできない。
「はい。ここに来たからあなたに会えました」
力強く答えると、アドルファスが心の底から嬉しそうに微笑む。
「最近、生徒達に言われるんです。教官の表情がとても柔らかくなったと。きっとそんな時はあなたのことを想っているんでしょうね」
「それ、生徒達に言っていませんよね」
仮にそうだとしても、私を想っていたからとか、恋愛脳だと暴露しているようなものだ。しかも仕事中に。
「え、言ってはいけませんでしたか? もちろん仕事の手は抜いていませんよ」
「え、本当に言ったの!」
「事実ですから」
言葉を失って唖然としていると、更に彼は続けた。
「私の妻になる人は浄化の力があって、全属性の魔法が使えて、料理も上手でその上可愛い。正式に聖女とされているのはもう一人の異世界から来た女性だが、彼女はそれ以上、聖女じゃなく女神。私の人生に現われた奇跡だ。そんな人を妻に出来るなんて私ほど幸せな人間はいない。思わず笑みが溢れてしまうのは仕方の無いことだ。そう言ったら皆納得してくれた」
「・・・・・うそ」
「嘘では無い」
きっぱりとどや顔で言い切るアドルファスを、私は信じられない思いで見上げた。
(いや、いやいやいや、前半はいいとして途中から何だか私への認識がすごいことになっています。女神とか奇跡とか、アドルファスってそんなことを言う人だったの)
「そ、そんな大袈裟な・・」
どうりで士官学校の生徒達の私を見る目が最近変だと思っていた。
「大袈裟では無い事実だ。私にとってユイナはそういう存在だ」
「わ、私にとってもアドルファスは格好良くて勇気があって誰よりも優しくて、責任感があって頭も良くて背も高くて、私にはもったいないくらいの人だと思っているけど」
「そんな風に思ってくれているんだ。嬉しいよ」
「じゃなくて、でもそれは自分がそう思っているだけど、人には言いません」
人の惚気を聞かされても困るだけだ。それに実際に私のことを知っている人たちがそれを聞いたら絶対「え!」と思うだろう。
「それはそうだな」
少し考えてアドルファスが納得して頷く。私の気持ちが通じたと思った。
「皆がユイナのことを好きになったら困る。ユイナの素晴らしさは私だけが知っていれば良い。だが、それではユイナへの評価が上がらない」
などと真剣に悩まれまたもや唖然とする。
「だから・・」
「でも、やはりユイナがどんなに素晴らしいかを伝えるには・・」
「わ、わかった。わかったわ。アドルファス。私のこと、そこまで考えてくれてありがとう。でも、私は皆に評価されなくても、自分の周りの人たち、特にあなたに愛されればそれでいいの」
それは本心だ。元から万人に受け入れられるとは思っていない。
「ユイナ。そうですね。あなたの言うとおりです」
ふわりと体が浮いて、アドルファスと同じ目の高さになった。
アドルファスは浮き上がった私の腰を抱えて抱き寄せると、皆の前でキスをした。
その顔は私のことが好きでたまらないということを隠そうともしないくらい甘々だ。
周りの微笑ましい視線がちょっと恥ずかしかったが、今日は二人の結婚式なのだからイチャイチャも大目に見てもらえるだろう。
「愛しています、アドルファス」
「私もです。ユイナ」
わざと残している顔の傷に手を這わせ、そこにキスを落とす。
日本では愛しているとか言うこと自体恥ずかしい。こんな人前で抱き合ったりキスしたりするのも。
これもここだからだ。
それを見て誰も眉を顰めたりしない。
「これからもよろしくお願いします」
ぎゅっとアドルファスの首に腕を回して抱き寄せる。
「こちらこそ、よろしくお願いします」
異世界で出会った最愛の人。
私を大切にして溺愛してくれる人。
聖女・・じゃなくても、この人に溺愛されて、私はここで生きていく。