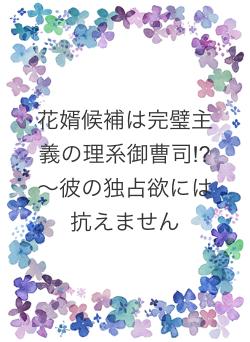あなたがそばにいるから
7.遥
目を開けたら、真っ白だった。
白銀の世界!
「はー……まっしろ……」
ため息と共に口から出た。
小学校の校庭。都会よりも確実に広いそこは、雪で真っ白、太陽に照らされてきらきら輝いている。
朝早いせいか、誰も足を踏み入れておらず、真っ白い絨毯を敷いたようだった。
「そんな珍しい?遥の実家だって、雪降るだろ?」
隣に立つ優太が苦笑している。
「降るけど。最近あんまり見てないもん、こんな一面の雪」
「そうだな、俺も久しぶりだった、そういえば」
「綺麗だねー……」
「やっぱ寒いな」
「うん、でも気持ちいい。空気が澄んでる」
でもやっぱり寒くて、私は優太の腕にくっついた。
吐く息は、当然白い。
私達は、優太の実家に来ている。
結局年末年始まで休みが取れず、年始の休みを2日延ばしてこちらに来た。
飛行機に乗ったのだけど、まず離陸しなかった。着陸先の空港が、大雪で安全確認が取れないとアナウンスがあった。
結局1時間遅れで、到着した。
空港までは、優太の両親が車で迎えに来てくれていた。
優太から事情を聞いていたらしく、笑顔で『初めまして』と挨拶してくれて、私は恐縮しっぱなしだった。
2ヶ月間の記憶は、なくなったまま。
思い出したいけど、ないものは仕方ない、と優太が言ってくれた。
もう一度、始めればいい。
優太のその言葉を、呪文のようにくり返している。
雪で高速道路も速度制限があり、時間をかけて、赤木家に着いた。
もう遅い時間だったので、すぐに寝る時間になって、案内されたのは優太の部屋。戸惑う私に、お母さんは驚いて言った。
「あれっ、結婚するんじゃなかったの?」
優太が苦い顔をする。
「……まだそこまで言ってない」
「なーんだ、結婚のご挨拶だと思った」
「あのさ、人の話ちゃんと聞いて」
「はいはいすいませんでした。でもいいよね、同じ部屋でも。駄目?」
「そんな風に言われたら『はい』としか言えないだろ」
「えーだって他は健太の部屋しかないし、あっためてないから寒いよ。あ、優太がそっちに行けばいいのか。そうする?」
健太というのは、優太の弟。2歳下。大学から家を出ていて、そのまま就職したんだそうだ。明後日、帰ってくる予定。
「あ、あの、私は一緒で大丈夫です」
優太が寒いのは嫌いらしい、とは最近わかったこと。
「良かったー。そうそう、優太はまだ言ってないみたいだけど、いつでもお嫁にきてね、遥ちゃん。待ってるから」
「は、はい」
「ウチ男ばっかりだから、遥ちゃんが来てくれて嬉しいわー」
うふふ、と笑って去っていくお母さん。楽しそうな人だ。
「ごめん、あの人ちょっと変な人だから……」
優太が脱力している。話には聞いてたけど、変というか、おもしろいと思うんだけど。
「仲良くなれると思うよ」
私がそう言ったら、優太は嬉しそうに笑った。
そして、次の日の朝。
早く目が覚めてしまって、窓の外を見たら、真っ白だった。
「うわあ……」
思わず声が出る。それに反応するように、優太も目を覚ました。
「すげー降ったんだな」
「凄いね。いい景色」
赤木家は少し高台にあって、優太の部屋からは周りがよく見える。
「寒そうだけど、気持ち良さそう」
お散歩行きたいな、と思ったら、優太が笑った。
「行くか、散歩」
窓からの朝陽に照らされて、凄くカッコよく見えた。
そうして来たのは、家から10分ほど歩いた小学校。優太の母校だ。
本当は入っちゃいけないらしいけど、近所の人は犬の散歩とかに来ているから大丈夫、と優太は言う。
真っ白なところに踏み出すのを躊躇していたら、優太が無造作に歩き始めた。
「1番乗りー、取った」
「あっずるい」
私も負けじと走り出した。真ん中に向かって。
でも、すぐに雪に足を取られてもつれて転びそうになる。
「ふわっ!」
「おっと……大丈夫か?」
追いついた優太が、腕をつかんで支えてくれた。
「ありがと」
えへへ、とごまかして笑うと、優太は優しく笑った。
ひとしきり、走ったり雪合戦をしたりして、子どもみたいに遊んだ。
楽しかった。
遊び疲れて、そろそろ帰ろうという時。
校門を出る直前に、優太が立ち止まった。
「どうかした?」
「あー……あのさ……」
言いにくそうに、うつむいている。
少し待っていたら、息を一つついて、私の手を取った。
「ここ」
指したのは、左手の、薬指。
「予約、するから」
「は……」
見上げると、優太の赤い顔があった。
「昨夜、母さんに先に言われちゃって、カッコ悪いんだけど……いずれちゃんと言うから。この指、予約させてくれ」
真面目に、まっすぐに、私を見ている。
お母さんに先に言われたって『お嫁にきてね』のこと?
そうだよね。いくら私でも、左手の薬指の意味くらいわかる。
「……遥?」
優太が怪訝そうな顔に変わった。
焦ってしまう。
「ああ、あの、はい。予約、受け付けました」
「……ほんとか?」
「うん。ごめん、びっくりして。大丈夫、ちゃんと予約したよ」
自分で言って、言っていることを理解した。
優太が、私の、左手の薬指を予約。
嬉しくなって、つい顔が笑ってしまう。
そして、照れくさくて仕方ない。
「……えへへ……」
変な声が出ちゃった、と思ったら、優太に手を引っ張られた。
頭を優太の胸に押しつけられる。ぽふん、とダウンの空気が抜けていった。
「馬鹿……その顔、誰にも見せんなよ」
どの顔?と思った瞬間、キスされた。
「わかったか?」
優太が笑う。
「うん」
本当はどの顔なんだかよくわからなかったけど、私も笑顔を返した。
「帰るか」
「うん」
手をつなぐ。手袋越しでも、優太のあったかさが伝わってくる。
「あ、そうだ。私も予約ね、ここ」
つないだ手を持ち上げて、指差した。左手の薬指。
優太はまた笑った。
「ばーか、そんなのもうずっと前から済マーク付きだ」
「え……なにそれ」
「いいから、行くぞ」
歩き出した優太の顔は、マフラーに半分隠れて、でも真っ赤だった。
「ねえ、ずっと前からって、いつから?」
「いいだろ別に、いつからでも」
「えー教えてよ」
「うるさい、もう聞くな」
手を引かれて、フェンス越しに見える校庭に私と優太の足跡が見えた。
この足跡を、忘れたくない。覚えていたい。
「どうした?」
私の足が止まったので、半歩先の優太が振り向く。
優太の顔を見て、思い出した。
『もう一度始めればいいって思ったんだ』
「……そっか」
忘れてもいい訳じゃない。
でも、もし忘れてしまったら、もう一度始めればいい。
優太がいてくれれば、もう一度始められる。
「なに1人で納得してんの」
優太がからかうように笑っている。
私も、笑顔を返した。
「なんでもない」
そして、2人で歩き出す。
きっと、長い道のりを。