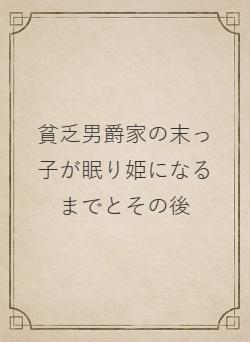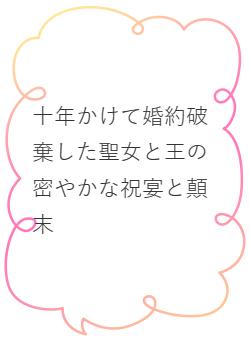家に帰ったら見知らぬ美形がいたんですが
家に帰ったら、見知らぬとんでもない美形が、堂々と粗末な椅子に鎮座していた。
「アーシャ、やっと会えた。あの日の約束を果たそう」
そのものが光り輝いているんじゃないかと思うようなご尊顔。座っていてもわかる均整のとれた体つき。足が長すぎて、我が家の年期の入った椅子だと完全に持て余している。
しかし先の通り、その人物はまったく見覚えのない顔をしていたので、私は即座に踵を返して警邏を呼びに行こうとした――のだけど。
(あ、開かない……!)
なぜかついさっき開閉したばかりの、外へと続く扉が開かない。取っ手を回してもガチャガチャと鳴るばかりで、押してもピクリとも動かないのだ。まるで塗り込められたかのように。
正体不明の不法侵入者(仮)と閉じ込められてしまった状況に焦る私の背後から、悠々と近づいてくる足音がした。
「何をしている、アーシャ。俺と同じ空間にいながら、俺に背を向けるなんて」
「人違いですので今すぐ出て行ってくれませんかね!?」
私の名前はセーラであり、アーシャではない。なぜ私の顔を見た時点で気付かなかったのかは謎だが、完全なる人違いだろう。
「俺がアーシャを――お前を間違うはずがない」
「いや現在進行形で間違ってますが!?」
いっこうに開かない扉にやけくそになって、よく見ろとばかりに光り輝く美貌の闖入者(仮)を振り仰ぐ。
しかし。
「ああ、やっとこちらを向いてくれたな」
語彙を失うような美貌を誇る闖入者(仮)は、蕩けるような笑みを浮かべて喜ぶばかりで、人違いに気付く様子が見受けられなかった。
(……ど、どういうこと?)
戸惑っている間にも、愛しさを煮詰めたような瞳で私を見下ろすその人は、そっと私のおとがいをとって、私の瞳を覗き込んだ。
「ああ――変わらない。器は変わっても、その魂を映す瞳はやはり変わらないな」
「え……?」
万感の思いを感じさせる声で紡がれた言葉に驚愕する。
「た、魂って、今……」
「? 何を驚いている?」
(魂を見極められるって、それは、つまり、この人は人ではない……『上位者』ってこと……!?)
『上位者』。この世界の運営に力を貸しているという人外の者たち。それらは様々な種族がいるが、総じて人よりも長く、永い生を生きるものだ。
「あなた、『上位者』なの……?」
「『上位者』? ああ、人が我らを呼ぶときの……。アーシャ、そんな呼び方は他人行儀に過ぎる。どうか、いつものように『フィデル』と呼んでくれ」
(『上位者』の真名!?)
伝えられた瞬間に、それが目の前の『上位者』を表す唯一の言霊だとわかった。
けれど呼べるはずなどない。いくら相手から伝えられたとはいえ、見知らぬ『上位者』の真名を不用意に呼べば、何が起こるかわからないのだから。
「あの、あなたは……」
「『フィデル』」
「あなたは、ここに何をしに……」
「『フィデル』と呼ばなければ答えない」
「…………フィ、フィデル」
大きな、とても大きな葛藤の末に、セーラはその名を呼んだ。呼んでしまった。
そうしなければ話が進まなさそうだというのもあったけれど、セーラが『あなた』と呼ぶ度に、『フィデル』と名乗った『上位者』の瞳に傷ついたような色が揺れるのに負けたのだった。
「! ああ、やはりアーシャに呼ばれる感覚は格別だ。私を歓喜に包んでくれる」
「……あの、私は『アーシャ』ではないのですが」
「? 何を言っている。俺がアーシャを間違えるはずがない」
「……それは、つまり、私の魂の以前の名前が『アーシャ』だったという意味ですか」
薄々、察してはいた。魂をその目にとらえられる『上位者』が、人違いをした様子もなく、セーラを『アーシャ』と呼ぶのだ。そして『上位者』は人間に比して長命。そこから導き出されるのは、セーラが『セーラ』として生を受ける前の魂が、『アーシャ』という名前で呼ばれていたのではないかという推測だ。
「……そうか。人間は魂に記憶を引き継がないのだったな」
得心したように、『上位者』は――フィデルは頷く素振りをした。
「お前はアーシャだ。私と出会い、愛し合い、共に生き、そして先立ってしまった――アーシャの魂を求めて俺はここに来た。約束を果たすために」
(そういえば、最初に『約束を果たそう』って……)
「その、約束というのは……?」
「アーシャは人間の中でも短命だった。だから俺は、アーシャを俺の力で生きさせようとした。だが、アーシャはそれを望まなかった」
(話し始めてくれるのはいいんだけど、この体勢どうにかならないかな……)
目の潰れそうなほどの美しいかんばせを至近距離に見ながら、吐息のかかるような距離で話されてしまっては正直集中できない。
でもそんなことを指摘できる雰囲気でもないので、セーラはとりあえず話の続きに耳を傾けた。
「アーシャは言った。自分は死にゆくけれど、魂はまたこの世界に生まれ出ずると。アーシャを、理を曲げてでも生きさせようとした俺の愛は、どうかこの先、また生まれ出ずる自分を育むこの世界に向けてくれと」
「……」
「それでも俺は納得できなかった。俺の愛したアーシャは、自分の寿命を受け入れはしていたけれど、死への恐怖が無かったわけじゃなかった。俺ならアーシャを苛むすべてを取り払えるのに、アーシャのためなら世界だって壊せるのに、アーシャはそれを望まなかった。ただ、約束を置いていった。――きっと、また愛してと。何度巡り会っても、そうしたらまた愛し合えると」
(それたぶん死に際に世界とか壊しかねないことを言い始めた相手をなだめるために言ったその場しのぎのやつ-!)
セーラは戦慄したが、それを口に出さないだけの分別はあったので、またもじっと言葉の続きを待った。
「だから俺は、約束を果たしに来た。さあ、アーシャ。俺たちは再び出会った。俺はお前を変わらず愛そう。だから――俺を、愛してくれ」
それが、当然のことを言っているような表情をして言われたのなら、セーラは「いや私とあなたは出会ったばかりですし」とやんわりいなしたが、どうしてか、彼は――フィデルは、今にも泣きそうな表情で、縋り付くような声音で伝えてきたので――。
「……まずは、間違いを正します」
「……アーシャ?」
「私は『アーシャ』じゃありません。記憶もありません。ただの『セーラ』です。その……約束についてだって、微塵も覚えがありません」
「アー……」
『アーシャ』と紡ぎたかったのだろう唇は、それを最後まで紡げずに――紡がずに、つぐまれた。
ああ、大丈夫、話が通じる、とセーラは思う。
「それでも、あなたが私の魂だけを見て、『アーシャ』と呼ぶのなら、私はあなたを愛せる気はしません。でも、もし、あなたが――『アーシャ』とそうしたように、私と時間を過ごして、心を近づけて……そういうふうに歩み寄ってくれるのなら。約束が果たされる可能性は、ゼロじゃないと思います」
「それは……」
何かを言いかけて、けれどまた口をつぐんで――。
「……わかった」
どこか迷子のような目をしていたフィデルが、セーラを初めて、しっかりと認識した――そう感じた。
「そうですね。まずは常識を、私に説かせてもらえますか?」
「……常識?」
「家主に無断で家に上がり込む行為は、犯罪ですから! 二度とやらないでください!」
セーラの勢いに押されたように、フィデルがこくこくと頷く。
そこでやっと、見知らぬ人物が家に上がり込んでいたことによるセーラの極度の緊張は、解かれたのだった。
それから、フィデルがセーラを『セーラ』として認識して、心通わせていくまでにも紆余曲折あったのだけど――それはまた、別の機会に。