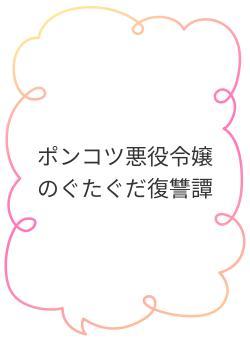悪役令嬢に捧ぐ献身
「うり!」
ひょこ、と扉の端から顔を出したシルヴィアが、喜色満面にラウリの名を呼ぶ。
公爵夫妻曰く、ラウリは先日の一件から三日ほど目を覚まさなかったらしい。
その深すぎる眠りの所以は恐らく、『ラウリ』の肉体で悪魔の力を行使したがゆえに体力を消耗したことに起因するのだろうが、そんなことを知る由もない公爵家の人々は「ラウリが意識を取り戻さない」と大慌てだったようだ。
とりわけ、あの日に何が起きたのかさっぱり理解していないシルヴィアは、何度会いに来ても眠っているラウリのことを段々と心配しはじめ、昨日は一日中そわそわとベッドのそばをうろついていたとか。
どうしてその様子を絵画に残していないのですかと真面目な表情で尋ねれば、公爵夫妻は可哀想なものを見る目でかぶりを振っていた。
「お嬢様、お久しぶりですね。あなたのラウリですよ」
「うり! こぇ、これたべる?」
「え?」
シルヴィアは小さなバスケットを持参しており、そこには彼女の大好きな焼き菓子が詰め込まれていた。
元気のないラウリに何かしてやらねばと、うんうん悩んで出した答えがお菓子のお裾分けとは、可愛さが天元突破している。ラウリは言葉にならない悲鳴を漏らしつつも、大人の笑みでかぶりを振った。
「大丈夫ですよ、そちらのお菓子はお嬢様がお召し上がりくださ」
「めーれ!」
「はい喜んで食べます」
ぬいぐるみに持たせるような小さなバスケットごと預かったラウリは、しかしおもむろに片足を上げてベッドによじ登ろうとするシルヴィアを見てぎょっとする。
「お嬢様ァ! 危のうございます! ラウリの腕にお掴まりください!」
「や!」
「いった」
ぺちっと彼の手を払ったシルヴィアは、険しい崖を登り切った登山家よろしく「ふう」と溜息をつくと、ちょこんとラウリの隣に腰を下ろした。
そして先程ラウリに渡したバスケットの中に手を突っ込み、ごそごそと何かを探す。やがて目当てのものを見付けたシルヴィアは、それをラウリの右手に乗せたのだった。
「ん!」
「うん……? ……雑草……?」
菓子に続いて贈られたのは、よれよれの雑草が複雑に絡み合った何か。
どこからどう見てもゴミだが、敬愛する主人から直々に下賜されたものをゴミなどと言うはずもないラウリは、これを押し花ならぬ押し草にして保管できないかと早急に思考を巡らせていたが。
「うり、およめしゃんね」
「え?」
「ちるびあのおよめしゃん!」
「ヒッ」
可愛いの二連コンボで危うく消滅しかけたが、いや待て待てとラウリは消し飛びそうになった意識を引っ張り戻した。
既にラウリにあげたことを忘れてバスケットから焼き菓子をつまんでいるシルヴィアと、手のひらに乗せられた雑草の塊を交互に見遣った彼は、やがて辿り着いた真相に悲鳴を上げる。
「え……も、もももっもしやお嬢様、こちら聖なるお草で作られた指輪だったりしますか!? そしてお嫁しゃんということは俺が娶られる側!?」
「ん、うり、およめしゃ」
「かぁ~っ参ったないや俺もちょうど左肩こんなことになって嫁の貰い手どうしようかなと思ってたところなんですよね~!」
開け放たれた窓の向こう、とうとうラウリの気が触れたのかもしれないと使用人たちがさめざめと泣いていることなど露知らず、この世で最も可愛い求婚を受けてしまったラウリはだらけまくった顔で雑草の指輪を眺めたのだった。
「ありがとうございますお嬢様、俺はこれからもお嬢様のために下僕として誠心誠意仕えていきますね」
「げぼ? およめしゃ……」
「当たり前だけど俺、おままごとでも求婚とかされたことなかったので新鮮ですねぇ。しかも初めてがお嬢様なんて、いやはやようやく報われた気分! お嬢様、これからもどうぞこの下僕をこき使ってくださ」
「んー!! げぼちがう! うり!!」
「痛ァ!? ちょちょちょお嬢様左肩は駄目ですさすがに!! どうして急にお怒りに!?」
何がシルヴィアの機嫌を損ねたのか、そのときばかりはさっぱり分からなかったラウリは、ひとまず彼女の気が済むまでぽかぽかと拳を受け止めた。
彼女が成年を迎えてもなお求婚が続くことを、このときのラウリはまだ知らない。
ひょこ、と扉の端から顔を出したシルヴィアが、喜色満面にラウリの名を呼ぶ。
公爵夫妻曰く、ラウリは先日の一件から三日ほど目を覚まさなかったらしい。
その深すぎる眠りの所以は恐らく、『ラウリ』の肉体で悪魔の力を行使したがゆえに体力を消耗したことに起因するのだろうが、そんなことを知る由もない公爵家の人々は「ラウリが意識を取り戻さない」と大慌てだったようだ。
とりわけ、あの日に何が起きたのかさっぱり理解していないシルヴィアは、何度会いに来ても眠っているラウリのことを段々と心配しはじめ、昨日は一日中そわそわとベッドのそばをうろついていたとか。
どうしてその様子を絵画に残していないのですかと真面目な表情で尋ねれば、公爵夫妻は可哀想なものを見る目でかぶりを振っていた。
「お嬢様、お久しぶりですね。あなたのラウリですよ」
「うり! こぇ、これたべる?」
「え?」
シルヴィアは小さなバスケットを持参しており、そこには彼女の大好きな焼き菓子が詰め込まれていた。
元気のないラウリに何かしてやらねばと、うんうん悩んで出した答えがお菓子のお裾分けとは、可愛さが天元突破している。ラウリは言葉にならない悲鳴を漏らしつつも、大人の笑みでかぶりを振った。
「大丈夫ですよ、そちらのお菓子はお嬢様がお召し上がりくださ」
「めーれ!」
「はい喜んで食べます」
ぬいぐるみに持たせるような小さなバスケットごと預かったラウリは、しかしおもむろに片足を上げてベッドによじ登ろうとするシルヴィアを見てぎょっとする。
「お嬢様ァ! 危のうございます! ラウリの腕にお掴まりください!」
「や!」
「いった」
ぺちっと彼の手を払ったシルヴィアは、険しい崖を登り切った登山家よろしく「ふう」と溜息をつくと、ちょこんとラウリの隣に腰を下ろした。
そして先程ラウリに渡したバスケットの中に手を突っ込み、ごそごそと何かを探す。やがて目当てのものを見付けたシルヴィアは、それをラウリの右手に乗せたのだった。
「ん!」
「うん……? ……雑草……?」
菓子に続いて贈られたのは、よれよれの雑草が複雑に絡み合った何か。
どこからどう見てもゴミだが、敬愛する主人から直々に下賜されたものをゴミなどと言うはずもないラウリは、これを押し花ならぬ押し草にして保管できないかと早急に思考を巡らせていたが。
「うり、およめしゃんね」
「え?」
「ちるびあのおよめしゃん!」
「ヒッ」
可愛いの二連コンボで危うく消滅しかけたが、いや待て待てとラウリは消し飛びそうになった意識を引っ張り戻した。
既にラウリにあげたことを忘れてバスケットから焼き菓子をつまんでいるシルヴィアと、手のひらに乗せられた雑草の塊を交互に見遣った彼は、やがて辿り着いた真相に悲鳴を上げる。
「え……も、もももっもしやお嬢様、こちら聖なるお草で作られた指輪だったりしますか!? そしてお嫁しゃんということは俺が娶られる側!?」
「ん、うり、およめしゃ」
「かぁ~っ参ったないや俺もちょうど左肩こんなことになって嫁の貰い手どうしようかなと思ってたところなんですよね~!」
開け放たれた窓の向こう、とうとうラウリの気が触れたのかもしれないと使用人たちがさめざめと泣いていることなど露知らず、この世で最も可愛い求婚を受けてしまったラウリはだらけまくった顔で雑草の指輪を眺めたのだった。
「ありがとうございますお嬢様、俺はこれからもお嬢様のために下僕として誠心誠意仕えていきますね」
「げぼ? およめしゃ……」
「当たり前だけど俺、おままごとでも求婚とかされたことなかったので新鮮ですねぇ。しかも初めてがお嬢様なんて、いやはやようやく報われた気分! お嬢様、これからもどうぞこの下僕をこき使ってくださ」
「んー!! げぼちがう! うり!!」
「痛ァ!? ちょちょちょお嬢様左肩は駄目ですさすがに!! どうして急にお怒りに!?」
何がシルヴィアの機嫌を損ねたのか、そのときばかりはさっぱり分からなかったラウリは、ひとまず彼女の気が済むまでぽかぽかと拳を受け止めた。
彼女が成年を迎えてもなお求婚が続くことを、このときのラウリはまだ知らない。