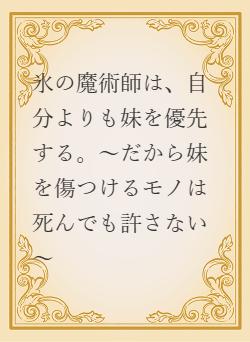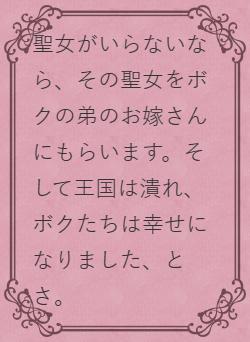婚約破棄された氷の令嬢と呼ばれた侯爵令嬢は、王位を放棄した第一王子と告白され、夫婦になる。
婚約破棄された氷の令嬢と呼ばれた侯爵令嬢は、王位を放棄した第一王子と告白され、夫婦になる。
「――好きな人が出来たんだ、リリア」
「……」
わかっていたことだったのに、こんなにあっさりとしてしまっていて大丈夫なのだろうかと、正直な所不安になってしまっているリリアの姿があったが、彼女は表情を引きつらせることなく、笑う事なく静かに頷きながら、一礼する。
「あなたがおっしゃる事でしたら……婚約破棄いたしましょう」
「すまない……けど、君だったら――」
「わたくし、だったら?」
「――君なら、一人でなんでもできるだろう?」
この男は一体何を言っているのだろうかと、不思議とぶん殴りたくなる気持ちを抑えながら、彼女は笑う事すらせずに再度、お辞儀をする。
これ以上、目の前の男の顔なんて見たくなかった。
見たくなかったからこそ、彼女は目線をそらしながら、再度、答える。
「それならば、私は父に報告させていただきます。そちらも、よろしいですわね?」
「ああ、わかった。本当に済まない、リリア」
(――そう思っているなら、そんな嬉しそうな顔をしないでほしい)
リリアと呼ばれた少女は顔が嬉しそうにしている青年に目を向けながら、再度苛立ちを覚えたのだった。
▽▽ ▽
「――で、その婚約者は堂々と浮気をしていた、という事なんだね、リリア」
「ええ、そうですよ……それより、何故こちらにいらっしゃるのですかウィンセント様」
「何って……今日は弟の見守りだよ。いやぁ、君の妹も相変わらず可愛くなっちゃってねぇーこれは将来美人になるね、絶対」
「妹にはお金を欠かさずおか――ゲフンゲフンッ、美しくなってもらうために勉強をさせているつもりです。将来、立派な妃になってもらうために」
そのように言いながら、リリアはまだ幼い妹、アンジェに力を入れていた。目的は将来の妃にする為でもある。
そんなアンジェの隣にいる少年はこの国の第二王子であり王太子であり、将来この国の国王になっていただく少年、クリストファー第二王子である。
二人の様子を見つめながら、目を輝かせているリリアの真正面に楽しそうに座っているのはウィンセント第一王子――クリストファー第二王子の母親違いの兄である。
アンジェとクリストファーは幼い頃からの婚約者同志であり、将来この国を背負っていく二人だからこそ、リリアはアンジェの教育に熱心に取り込んでいる。もちろん、金を使ってだが。
二人が遊ぶ光景を眺めながら、リリアは第一王子であるウィンセントにこの前の婚約の話をする。
「えっと、この前君が言っていた婚約者って、確か君と幼馴染なんだよね」
「ええ、一応そうなります。長年一緒に居たからでしょうか……昔の恋より、今の恋に行ってしまったようで、なんでも『真実の愛』に目覚めてしまったらしいですわ」
「ハハッ、し、真実の愛……クク、腹痛ェ……」
「……笑いすぎなのではないですが?」
「クク……いいじゃん別に。俺、君の所じゃないと、のんびり出来ないんだから」
「はぁ……」
笑顔で答えるウィンセントにリリアはため息しか出ない。
リリア・プロージェット。
ブロージェット侯爵の長女であり、彼女は貴族の中で『氷の令嬢』と呼ばれているほど、感情を表に出さない性格なのである。
幼い頃から徹底的に実の母親から教育され、笑う事すら忘れてしまったと言われるほど、彼女は笑う事はない。目の前にいる母親違いの妹、アンジェのように無邪気に笑う事すら出来なくなってしまっていた。
幼い頃は笑顔を見せる事はあったのかもしれない。幼馴染で元婚約者だった男、ディアスとは長い付き合いであり、この人の隣に立つのだと信じていたはずなのに――リリアは見事に裏切られたのである。
相手は一体どんな人物なのか、正直気になるところなのだがリリアは別に調べるつもりもないし、もう終わってしまった事なのだ。
詮索するつもりもないし、放っておくつもりなのだが、どうやら家族はそうもいかなかったらしい。
母親違いとは言え、年齢が少し離れた妹は自分の事のように怒ってくれて、将来弟になるこの国の第二王子も同じように怒ってくれた。
リリアの父は剣を握りしめ、家に乗り込もうとしたぐらいで、義理の母親は止めるどころか応戦しようとするぐらいだ。家族にはとても恵まれていると改めて実感した日だったのだが、止めるこちらの身にもなってほしいと少しだけ思ってしまった。
対し、第一王子であるウィンセントも同じように、怒ってくれた。
「にしても……浮気していたってことだろう?腹は立たなかったのか?」
「立った……と思います。というより、なんかわかり切っていたことなのかもしれないです」
「分かり切っていたこと?」
「……一度だけ、浮気現場を見た事があります」
遠い目をするように、リリアは数週間前の現場を思い出す。
妹のアンジェがケーキが食べたいと可愛い我儘を言ってきたので、美味しいと評判のケーキ屋に足を運んだ時、リリアは見てしまった。
嬉しそうに笑う元婚約者と、隣に立ち、同じように笑う一人の少女の姿を。
綺麗な金髪の髪に、美しいエメラルドの瞳。男たちを引き付ける、とても可愛らしいと言っていいほどの少女であった。
すぐにリリアは理解した――ああ、これは見てはいけないモノだと言う事を。
ディアスが話をしてくれるまで、黙っておくことにしたのだが、それでも彼女の心は深い傷を負った。
しかしそれでも、彼女は泣く事も、怒る事もせず、部屋に戻っても顔色一つも変わらなかった。同時に、ディアスの事はもう好きではなかったんだなと理解する。
『大きくなったらリリア、結婚してくれる?』
幼い頃、真剣な瞳でリリアに向けて言ってきたディアスの言葉が今でも胸に突き刺さる。その時はちゃんと笑う事が出来ていたのであろうかと不安になりながら。
結局はディアスの家から婚約破棄の申し出があり、了承する事にした。
きっと今頃は、新しい婚約者でも出来て、あの少女と一緒に楽しい一日を過ごしているのだろうかと思うと、正直腹が立って仕方がない――が、その感情すら、表に出す事はなかった。
マグカップを置き、ウィンセントに視線を向ける。
「これで良かったのです。私は邪魔者……あちらの方はその『真実の愛』と言うものに目覚めたのですから、祝福しなくてはいけません…………腹が立ちますが」
「ハハッ、相変わらずだなお前は……まぁ、腹は立っているのか?」
「表に出せないだけですが、一応」
「そうか……なるほどなるほど……おい、クリストファー!!」
突然、同じように年齢が離れた少年に声をかけたウィンセントはクリストファーを呼び、彼も兄の声に気づいたように、アンジェの手をしっかりと握りしめながら一緒にウィンセントとリリアの所に来る。
穢れを知らない大きな目で、クリストファーはウィンセントに目を向け、首をかしげる。
「兄上、どうかしましたか?」
「おう、今日もアンジェと良く遊んでいたな」
「はい!」
「おねえさま、今日はウィンセントさまとどんなお話をしたんですか?」
「ええ、婚約破棄の話をしただけですよ。アンジェ、顔に泥がついております」
「え、あ、ありがとうございますおねえさま……けど、聞くたびに許せません!おかあさまなんて、おとうさまと一緒にいつぶっ壊しに行きましょうかって昨日話してました!だからアンジェも参加したいと――」
「待って、お父様とお義母様がそんな話を……まずい、それはまずい……あの二人が手を組んだらこの国滅びますよ……」
「まぁ、元冒険者だからあの二人は!!お前の元婚約者の事はどうでもいいが、国が滅ぶのはまずいな!!」
笑顔で答えるアンジェの両耳を抑えながら、真顔で答えるリリアに対し、ウィンセントも笑ってはいたのだが正直笑える話ではなかった。
アンジェの母親は有名な魔術師の家系の元後継者であり、二人の父親は元有名な冒険者であり、前線で戦っていたほどの腕前の持ち主。その二人が手を組んでしまえば、この国は間違いなく滅びる。
(後でもう一度話をしよう……うん、絶対に止めなければいけない)
「……アンジェ、次お父様とお義母様がそのような話をしたら、絶対に止めてくださいね」
「ええ、どうしてですかおねえさま?」
「そんな事をしたら私が悲しむからです。アンジェは私を悲しませたいのですか?」
「え……そ、それは嫌です!わかりました!約束します!」
「ありがとう、アンジェ」
姉に嫌われたら――と言う言葉がアンジェの頭から離れなくなってしまったのか、彼女は涙目になりながら、リリアの身体を強く抱きしめる。その姿を見ながらリリアはアンジェの頭を優しく撫でながら、今度はクリストファーに視線を向ける。
視線を向けられた瞬間、クリストファーは驚いたような顔をしたのだが、同時に彼女から目を逸らす。
「クリストファー様……あなたも、アンジェと一緒に行ってはいけませんよ?」
「し、しかしリリアさま、僕も許せないのです……リリアさまはこんなにも優しくて、理想のおねえさまなのに……その男は、何がいけなかったのでしょう?」
「……」
――君なら、一人でなんでもできるだろう?
ふと、ディアスが言った言葉が胸に突き刺さる。
リリアの実の母親は厳しい人で、立派な淑女になる事を目標に、厳しく教育をしてくれた。嫌だったことは何度もあったが、頑張った後はいつも優しい母親で居てくれたから。母は死ぬまで家族の事を考えてくれた人だった。
父もリリアの事を大事に思ってくれているという事はわかっているし、義理の母親となったアンジェの母も、彼女の事を実の娘のように大事に育ててくれているし、最近は魔術について学ばせてもらっている。
自分の事は、いつも自分でやるようにしていたのだが、ディアスはそれが気に入らなかったのかもしれない。
浮気現場を見たあの少女は、いかにも守ってほしいと言う外形をしていた。
笑う事もしなければ、頼る事もしない――『氷の令嬢』なんて言われるのはしょうがない。
突然黙ってしまったリリアに対し、クリストファーとアンジェも少し困った表情を見せていたのだが、その時ウィンセントが声をかける。
「なぁ、リリア」
「――はい、何でしょうウィンセント様」
「お前、今は婚約者作るつもりはないんだろう?」
「え、ええ……父もしばらくは考えなくていいと言ってくれました……ですが、そこまで甘えるわけにはいかないと思いまして、こんな私でよろしければもらってくれる相手を探してみようかと――」
「で、決まったのか?」
「いいえ、そもそもまだ探しておりませんが……」
「そうか、それはよかった」
「え、よかった?」
良かったとの意味が全く理解できず、思わず表情が崩れそうになってしまったが、目の前の男であるウィンセントにとって、どうでもよい事らしい。
嬉しそうにしながら再度弟であるクリストファーに視線を向けた後、クリストファーも何かを悟ったかのように、兄に対して親指を立てながら、嬉しそうに微笑み。
同時に、ウィンセントの手が、リリアの手に触れる。
「――俺の妻になる気はないか、リリア?」
「……」
開いた口が塞がらない、と言う意味はこの事ではないのだろうかと思ってしまったリリアは呆然としながらウィンセントに視線を向けてしまう。同時に、リリアの隣に居た妹のアンジェも頬を赤く染めながら、嬉しそうに笑っている。
どうやらクリストファーとアンジェはウィンセントのその意味を理解しているらしく、応援しているらしい。お互い顔を見合わせながらはしゃいでいる姿がある。
だが、当の本人であるリリアは何も言えず、飲んでいた紅茶を思わず吹き出そうになってしまったなんて、死んでも言えない。
再度、咳き込みながら、リリアはウィンセントに声をかける。
「ゴホっ……う、ウィンセント様、そ、それは……」
「婚約破棄されてすぐに求婚するつもりはなかったのだが、俺の長年の夢でもある。俺はあの時、出会った時からリリアに対してこのような思いを抱いていた……鈍いから気づいていなかっただろう?」
「……お、おっしゃる通り……」
「俺は確かに第一王子だが既にクリストファーに王位継承権を譲っている。母上も父上も承知の上で、放棄した。将来冒険者になりたいと言う夢を叶えるためにな……だが、もし、侯爵家を継ぐと言う話になるなら、俺は婿入りする……だから、俺の告白を受けてくれないだろうか?」
「……」
リリアとウィンセントとの出会いは、クリストファーとアンジェが幼いながら婚約を結ぶと言う話になった時、侯爵家に訪れた時から、このような交流が始まった。
しかし、リリアはその時既に幼馴染と婚約を結んでおり、ウィンセントは諦めていたのだが、それでも彼女を想う気持ちは心の中にあった。
婚約を破棄されたのであるならば――と、クリストファーの押しもあり、ウィンセントは自分の気持ちを正直に伝え、同時に返事を待つ。心臓の音がウィンセントの中で徐々に大きくなっていくのを理解しながら。
一方のリリアは状況への理解が追い付かず、氷の表情も徐々に崩れだしてきている。確かにウィンセントとは数年の付き合いだが、まさかそのような下心があるなんて知らなかったため、どのように返事をすればいいのかわからない。放棄していると言っても、ウィンセントはこの国の第一王子だ。
しかし、リリアは別に嫌ではなかった。
同時に、真剣な表情を見せてくれるウィンセントの事を――しかし、それでもその答えに行きつくのが怖くてたまらない。
(……また、裏切られたら、嫌だわ)
元婚約者のように、好きな女性が出来たらどうしようと考えてしまう。自分は表情を豊かに出来ない、そんな女だ。きっと、普通の男ならば、可愛らしい性格の女性を好むに違いない。
だからこそ、目の前のウィンセントの言葉に頷く事が出来ない。歯を噛みしめるようにしながら言葉が出なかったリリアだったが、アンジェが不安そうな顔をしているリリアに向けて、優しく笑いかける。
「だいじょうぶだよ、おねえさま」
「え……」
「ウィンセントさまは、裏切らないよ。だって、クリストファーと二人で見てたけど、ウィンセントさま、おねえさまに一筋だもの」
「ちょ、アンジェ……」
笑顔で答えるアンジェに対し、ウィンセントは顔面真っ赤に染まりながらアンジェに声をかけたのだが、アンジェの言葉に対し、クリストファーはうんうんと頷いており、ウィンセントは両手で顔を隠しながら恥ずかしそうにしている。
不思議な気持ちになったリリアは、アンジェの言葉に救われた気持ちになってしまった。アンジェの言葉がとても積極的に信じられる言葉だったからである。
リリアはウィンセントに振り向き、いつもの表情で答えた。
「ウィンセント様」
「は、はい!」
「……私でよろしければ、どうぞよろしくお願いいたします。これからお父様にお話してきますわ」
「あ、な、なら俺も行く。クリストファー、お前はどうする?」
「僕も行きます!アンジェ!」
「おねえさま、わたしも説得するね!」
笑顔で答えるアンジェとクリストファーはお互いの姉と兄の手を握りしめながら、ウィンセントとリリアの婚約を認めてもらうために、四人で一緒に父親が居る部屋に向かうのである。
その姿をほほえましく、後ろで待機していた護衛やメイドたちが静かに見つめていたなど、四人は知らない。
▽▽ ▽
「リリア」
「おかえりなさいませ、ウィンセント様」
数年後、リリアはウィンセントと仲睦まじく、二人で森林の奥で小屋を建て、二人で暮らしている。
成人したウィンセントはリリアと一緒に国を出て、ウィンセントはなりたかった冒険者となり、リリアは家で家事などをしながら生活していた。
侯爵令嬢だった彼女だが、慣れない家事もようやく慣れるようになり、料理も上達し、幸せに暮らしている。
家に帰ってきたウィンセントはいつものように稼いだお金をリリアに渡す。
「今日はこのぐらいなんだけど、足りるか?」
「多いぐらいですよウィンセント様……楽しいのは別に良いのですが、ムリなく、出来れば危険な仕事はしないようにお願いしますね」
「ああ、わかってるよ……もうすぐ俺も父親だからなぁ……」
「ええ、この子の為にも、よろしくお願いしますね」
リリアはそのように言いながら、大きくなっているお腹をさすると、ウィンセントは急いで隣に座り、リリアの大きなお腹に触れる。
一年前、リリアの妊娠が発覚し、ウィンセントは夜には必ず帰るようになった。ケガもする事はあるが、それでも絶対に家に帰ると言う事を曲げずに、今まで頑張ってきている。
第一王子だった面影はどこに行ったのだろうか――リリアはそのように考え、思わずクスっと笑っていると、ウィンセントは思い出したかのように懐から一枚の封筒を取り出す。
「そうそう、これアンジェから手紙が届いてた。相変わらず分厚い手紙だなぁ」
「アンジェと、お父様とお義母様からお手紙ですね……あら?」
「ん、どうした?」
「……ディアスが家に来たそうで、私の事を探しているらしいですわ」
「は?」
瞬間、ウィンセントは不機嫌そうな顔をしながら手紙の内容を確認する。ディアスは数年前にリリアと婚約破棄をしてきた男だ。
既に未練もない、幼馴染の元婚約者なのだが、彼は愛する女性を見つけ、真実の愛に気づいたと言う事で可愛げのないリリアを捨て、可愛らしい、守ってあげたい少女の所に行ってしまった男で、既にリリアには関係のない男なのだが。
彼の名前を聞くと同時に不機嫌になってしまったウィンセントはちょっと驚きながらも、手紙の内容を読み続け、ため息を吐く。
「……なるほど、真実の愛は偽りだったと、言う話らしいな」
「どういう事ですの?」
「あれから結婚したらしいんだが、その女性、なんでも金遣いが荒かったらしいんだ。おかげで家は破綻、そんでもって、リリアの家に向かったらしいんだが、門前払いされたらしいな」
「あらまぁ……」
「……最初からリリアを選んでいたら、幸せな生活が出来たのになぁ」
ため息を吐きながら、大事そうに手紙を折りたたんだ後、リリアに手紙を返し、再度リリアは手紙の内容を読み、どうやら借金まで抱えてしまったディアスは妻と離縁し、リリアの家に頼って再度自分と婚約を結ぼうと思ったらしい。
数年前にリリアは既に家を出ているし、結婚もしている。愛する夫との子供ももうすぐ生まれる。
既に、ディアスはリリアの中ではどうでもよい存在となっているのだ。ため息を吐きながらディアスの所以外読みながら、彼女は話を続ける。
「しかし、ディアスも可哀そうですわ」
「え、なんで?」
「――きっと、お父様とお義母様が許しませんもの」
フフっと笑いながら遠い目をしている彼女の姿に対し、ウィンセントは納得してしまう。あの二人は婚約破棄された時からディアスの事を許していない。家に行ってしまった事でどのような仕打ちを受けたのだろうかと考えつつ、想像すると恐怖を感じながら、ウィンセントは考えないことにした。
そう、今はどうでも良い事。
ディアスの事など、リリアの中には入っていない――もう、彼女は『氷の令嬢』ではなく、もうすぐ母親になる女性なのだ。
「楽しみですわね、ウィンセント様」
「ああ、そうだなリリア……生まれたら、一度家に帰ろう。きっと、孫を見せたら喜ぶ」
「ええ、そうですね」
「――愛してる、俺のリリア」
「私もですわ、ウィンセント様」
数年経った今でも、彼女の表情は以前より緩やかになっているが、相変わらず無表情の方が多い。
しかしこの時だけ、彼女は満足そうな笑顔を、夫であるウィンセントに見せるのだった。