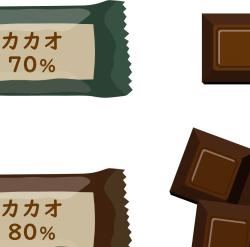バイバイ、リトルガール ーわたし叔父を愛していますー
番外編 悠の微熱
何かを訴えるような蝉達の鳴き声が聞こえる。
開け放たれた窓からは真夏の太陽と時折吹き抜けていく風。
汗が額から流れ落ちる。
それでも僕はエアコンの冷たい空気より、この自然な温度が心地よかった。
僕の部屋のベッドの上には、僕の初恋相手、綿貫直人がその持ち主よりもくつろぎながらヤングジャンプを読んでいる。
すっきりと切り揃えられた襟足に繋がるよく焼けた首。
白いTシャツの袖からのぞく筋肉のついた腕。
陸上競技で鍛えられたその体躯。
見慣れている直人の身体なのに、今日は何故か生々しい。
僕は壁にもたれ小説を読むフリをして、直人を盗み見る。
そんな僕の視線に気付きもしない直人は、ふいに僕に告げた。
「俺さあ、彼女と別れたんだよね。」
突然の直人の言葉に、僕の心臓は撥ねた。
けれど冷静を装いながら、僕は何でもないことのように言った。
「ふーん。そうなんだ。」
直人はヤングジャンプから目を離し、僕を見た。
「ふーん、ってそれだけ?」
「それ以外、何て言えばいいのさ。」
「理由とか聞かないのか?」
「・・・聞いてもいいの?」
直人は身体を起こし、ベッドサイドへ座った。
「なんだろう・・・思ってたのと違うっていうか・・・」
「・・・・・。」
「女の子は可愛いと思うよ?いい匂いがするし、身体は柔らかいし。でも・・・それだけだ。彼女が他の男と話そうが何をしようが俺の心は動かない。ああ、そうですかって感じ。それって好きって言えないだろ?」
「まあ・・・それはそうかもね。恋には独占欲が含まれているっていうし。」
「だよな。」
「その彼女とは相性が合わなかったんじゃない?直人に合う子がまた現れるよ。」
僕は思ってもいないことを口にした。
本当は直人が彼女と別れたことを誰よりも喜んでいるのに。
「悠は?」
「え?」
「悠は好きな人、いないのか?」
心臓が再びどきんと音を立てた。
鼓動が早くなり、口が渇いた。
喉の奥から絞り出すように、声を発した。
「・・・いないよ。」
「本当か?」
「そんなこと嘘ついてもしょうがないだろ?」
直人の目が僕をじっと凝視した。
「悠もやるよな。」
「は?」
「俺、悠のこと何もわかっていなかったんだなって。」
「・・・話が見えないんだけど。」
直人は一体なんの話をしているんだ?
「俺、見ちゃったんだよね。」
「見ちゃったって・・・なにを?」
直人の表情が歪んだ。
「悠さ・・・野口さんと付き合っているんだろ?」
「・・・え?」
「たまたま友達と飲みに行った居酒屋で、悠と野口さんが一緒にいるところを見た。悠はすごく嬉しそうな顔で野口さんと笑い合ってた。」
「・・・・・・。」
「野口さん、可愛いもんな。小動物系というか・・・性格も良さげだし。髪もサラサラで大きな瞳はいつも潤んでいて、でもミステリアスな魅力もあって。」
「直人・・・誤解だよ。僕と野口さんは直人が思っているような関係じゃない。」
「じゃあ、どういう関係だよ!」
直人の口調が荒くなった。
その目には怒りが含まれている。
僕と野口さんの関係を話すことは出来ない。
それを話すということは、僕の直人への想いを話すことになる。
「話せないほど親密な関係ってわけ?」
直人の強い視線に射抜かれそうになる。
「どうしたんだよ。らしくないね。」
「俺、悠と野口さんを見て、自分でも信じられないくらいイラついた。ムカついた。悠と野口さんを引き離したいと思った。」
どういうことだ?
僕は胸の動揺を悟られないように笑った。
「直人。なんだか野口さんに嫉妬してるように聞こえるよ?」
すると直人は立ち上がり、真正面から僕をきつく抱きしめた。
直人のいつも使うシャンプーの匂いがする。
「そうだよ。嫉妬だよ。それくらい判れよ。」
「直人・・・?」
僕の鼓動は早くなり、体温が急上昇した。
身体が震え、このあり得ない展開に、これは夢ではないかと思った。
「俺がお前の気持ちに気付いてないとでも思ってた?」
「!!」
「俺、余裕ぶっこいてた。結局悠には俺しかいないって高をくくっていた。でも悠に彼女が出来たって思ったら、気持ちを抑えきれなくなった。」
「直人。誤解だよ。僕と野口さんはただの友達だ。」
「・・・友達?」
「そう。彼女は誰にも言えない哀しくて・・・でも誰よりも純粋な恋をしているんだ。そして僕も・・・。」
「悠・・・?」
「直人への想いを野口さんに聞いてもらっていたんだ。」
僕は直人の腕を掴んだ。
「悠・・・好きだ。」
直人の低い声が僕の鼓膜を揺らした。
「僕も直人が・・・好き。」
「悠・・・俺だけを見てて。」
「もうずっと前からそうしてる。」
直人の唇が僕の唇に重なった。
真夏の風がちりんと風鈴を鳴らす。
僕の微熱は当分下がりそうもない。
fin
開け放たれた窓からは真夏の太陽と時折吹き抜けていく風。
汗が額から流れ落ちる。
それでも僕はエアコンの冷たい空気より、この自然な温度が心地よかった。
僕の部屋のベッドの上には、僕の初恋相手、綿貫直人がその持ち主よりもくつろぎながらヤングジャンプを読んでいる。
すっきりと切り揃えられた襟足に繋がるよく焼けた首。
白いTシャツの袖からのぞく筋肉のついた腕。
陸上競技で鍛えられたその体躯。
見慣れている直人の身体なのに、今日は何故か生々しい。
僕は壁にもたれ小説を読むフリをして、直人を盗み見る。
そんな僕の視線に気付きもしない直人は、ふいに僕に告げた。
「俺さあ、彼女と別れたんだよね。」
突然の直人の言葉に、僕の心臓は撥ねた。
けれど冷静を装いながら、僕は何でもないことのように言った。
「ふーん。そうなんだ。」
直人はヤングジャンプから目を離し、僕を見た。
「ふーん、ってそれだけ?」
「それ以外、何て言えばいいのさ。」
「理由とか聞かないのか?」
「・・・聞いてもいいの?」
直人は身体を起こし、ベッドサイドへ座った。
「なんだろう・・・思ってたのと違うっていうか・・・」
「・・・・・。」
「女の子は可愛いと思うよ?いい匂いがするし、身体は柔らかいし。でも・・・それだけだ。彼女が他の男と話そうが何をしようが俺の心は動かない。ああ、そうですかって感じ。それって好きって言えないだろ?」
「まあ・・・それはそうかもね。恋には独占欲が含まれているっていうし。」
「だよな。」
「その彼女とは相性が合わなかったんじゃない?直人に合う子がまた現れるよ。」
僕は思ってもいないことを口にした。
本当は直人が彼女と別れたことを誰よりも喜んでいるのに。
「悠は?」
「え?」
「悠は好きな人、いないのか?」
心臓が再びどきんと音を立てた。
鼓動が早くなり、口が渇いた。
喉の奥から絞り出すように、声を発した。
「・・・いないよ。」
「本当か?」
「そんなこと嘘ついてもしょうがないだろ?」
直人の目が僕をじっと凝視した。
「悠もやるよな。」
「は?」
「俺、悠のこと何もわかっていなかったんだなって。」
「・・・話が見えないんだけど。」
直人は一体なんの話をしているんだ?
「俺、見ちゃったんだよね。」
「見ちゃったって・・・なにを?」
直人の表情が歪んだ。
「悠さ・・・野口さんと付き合っているんだろ?」
「・・・え?」
「たまたま友達と飲みに行った居酒屋で、悠と野口さんが一緒にいるところを見た。悠はすごく嬉しそうな顔で野口さんと笑い合ってた。」
「・・・・・・。」
「野口さん、可愛いもんな。小動物系というか・・・性格も良さげだし。髪もサラサラで大きな瞳はいつも潤んでいて、でもミステリアスな魅力もあって。」
「直人・・・誤解だよ。僕と野口さんは直人が思っているような関係じゃない。」
「じゃあ、どういう関係だよ!」
直人の口調が荒くなった。
その目には怒りが含まれている。
僕と野口さんの関係を話すことは出来ない。
それを話すということは、僕の直人への想いを話すことになる。
「話せないほど親密な関係ってわけ?」
直人の強い視線に射抜かれそうになる。
「どうしたんだよ。らしくないね。」
「俺、悠と野口さんを見て、自分でも信じられないくらいイラついた。ムカついた。悠と野口さんを引き離したいと思った。」
どういうことだ?
僕は胸の動揺を悟られないように笑った。
「直人。なんだか野口さんに嫉妬してるように聞こえるよ?」
すると直人は立ち上がり、真正面から僕をきつく抱きしめた。
直人のいつも使うシャンプーの匂いがする。
「そうだよ。嫉妬だよ。それくらい判れよ。」
「直人・・・?」
僕の鼓動は早くなり、体温が急上昇した。
身体が震え、このあり得ない展開に、これは夢ではないかと思った。
「俺がお前の気持ちに気付いてないとでも思ってた?」
「!!」
「俺、余裕ぶっこいてた。結局悠には俺しかいないって高をくくっていた。でも悠に彼女が出来たって思ったら、気持ちを抑えきれなくなった。」
「直人。誤解だよ。僕と野口さんはただの友達だ。」
「・・・友達?」
「そう。彼女は誰にも言えない哀しくて・・・でも誰よりも純粋な恋をしているんだ。そして僕も・・・。」
「悠・・・?」
「直人への想いを野口さんに聞いてもらっていたんだ。」
僕は直人の腕を掴んだ。
「悠・・・好きだ。」
直人の低い声が僕の鼓膜を揺らした。
「僕も直人が・・・好き。」
「悠・・・俺だけを見てて。」
「もうずっと前からそうしてる。」
直人の唇が僕の唇に重なった。
真夏の風がちりんと風鈴を鳴らす。
僕の微熱は当分下がりそうもない。
fin