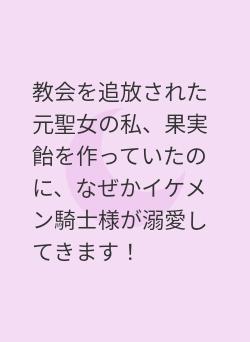妹に婚約者を奪われた私は、呪われた忌子王子様の元へ
未来へ
後日ランベール王によって、第一王子ユリウスの存在が公にされた。
ランベールは長きに渡る風習によって、王家で双子が産まれると、どちらか片方を「忌子」として隠し、ユリウスも例に漏れず今まで存在が公表されていなかった。
しかしユリウスは王家から忌子と称され、蔑ろにされながらも独自による魔法研究に人生を注いだ。その甲斐あってリドリスに掛けられていた呪いを解き、弟を救ったのだった。
ここ一、二年のリドリスの様子がおかしかったのは、王都の貴族内で噂になっていたことでもある。
そして呪いの効果により、精神を病んだリドリスと婚約破棄となっていたティアリーゼ。彼女をミルディンにいるユリウスと、新たな婚姻を結ぶよう提案したのは国王である。
ランベール王が全てを明るみにする覚悟が出来たのは、ユリウス、リドリス、ティアリーゼの未来のため。
その結果、自身が非難されることになろうと甘んじる覚悟だ。
王家に振り回されたティアリーゼは、ミルディンの地にて、ユリウスと心を通わせた。
ティアリーゼは以前、リドリスと入れ替わっていたユリウスと対面したことがあり、その頃から二人は惹かれあっていたのだという。
一方マリータやミランダについて、彼女達の事件への関与は未だ公表されていない。
マリータの取り調べは現在も慎重に行われている。
クルステア公爵は娘と妻の減罪を嘆願しながら、遠縁に爵位を譲ることを考えているのだという。
マリータは修道院にひっそりと送られる可能性が高く、ミランダは既に王都から離れてクルステア領の小さな町に身を寄せている。
彼女達はエルニア民族の血を引くことで、サイファーに利用されてしまった、ある意味被害者に近い立場でもある。だが、長年のティアリーゼに対する仕打ちは到底許されるものではない。
またエルニアの関与をどこまで公表するか、国王と重鎮の間で、幾度も話し合いが持たれた。ランベール国内にいるエルニア民族へ、差別的感情や怒りが向く可能性が懸念され、慎重にならざる得ない。
「行ってしまうのですか」
旅立とうとするユーノにティアリーゼは向き合う。
現在の彼の身長はティアリーゼより少しだけ高い。まだ少年らしさの残る面立ちから、成長過程であることが窺える。
最初は彼本来の姿に違和感を感じていたが、やはり妖精の姿も、猫の姿も、人間の姿もユーノであることに変わりない。
「俺みたいなのがこの国に留まっていたら、また悪巧みを考える奴等が集まってくるかもしれないからな。
それに俺は、修行を兼ねた放浪の旅が好きなんだ。
最古のエルニアは精霊の声を聞き、自然と共にあった遊牧の民族だ。それが国を持った途端王位争いとか色んなゴタゴタが起こった。
遊牧の民族は、国を持たない方がいいのは通説だよな」
ユーノ自身、エルニア民族としての誇りを持っていても、国の復興には興味がないらしい。
「また会えますよね?」
「当たり前だ。……というかユリウス!」
勢いよくユリウスに人差し指を突きつけると、彼は高らかに宣言する。
「また修行して、近々お前に勝負を挑んでやるからなっ」
また近々来る予定らしい。
「ミハエル殿下とイル様は……?」
ティアリーゼは視線を移し、二人を伺う。
何だか送り出す側のような立ち位置でユーノを見送っている二人だが、彼らも近々自国へと帰ることが決まっているらしい。
問われて「ユリウスを倒すまで居座る」と言い掛けたミハエルだが、そんな彼をイルが遮る。
「使節団を通して、陛下からの通達を受け取っております。即戻ってくるようにとのお達しでした。勝手に国を出たミハエル殿下に対して、国王夫妻や王太子殿下も相当お怒りのようですから」
「う、それは帰りたくなくなるな……」
頭を抱えるミハエルに、更にイルが追随する。
「そうですか?さっさと帰国しない方が、後が怖いと思われますよ」
「……」
顔面蒼白となったミハエルは、その後珍しい程静かになった。
現在見送る立場のティアリーゼとユリウスも、もう少ししたら王都を離れ、ミルディンへと帰還することになる。
帰りはレイヴンの力を使い、ミルディンまで転移出来るらしい。
レイヴンは高位精霊でありながら、人間のようにユリウスに仕えているのは、長い時を精霊として過ごすのに、単純に飽きたからと言っていた。
ユリウスの執事として仕えているのは、人間の振りをして楽しむ暇つぶしだそうだ。
それについてユリウスは「レイヴンは精霊の中でも変わり者なんだよ」と口にしていた。
レイヴンの正体が高位精霊と判明したことで、兼ねてから疑問だったユリウスに対する彼の慇懃無礼な態度に、ティアリーゼは納得したのだった。
ちなみに王都に来るまでの道のりを馬車にしたのは、ユリウスがティアリーゼと長旅をしてみたかったかららしい。
◇
銀糸の髪に赤紫の瞳をした王子、ユリウスが大理石の回廊を歩いていた。
王宮の人々は彼に気付くとすぐに端により、頭を垂れる。それは初対面の者でも同様である。
長年王宮で暮らしていなかったユリウスだが、誰しもが彼の姿を一目見ただけで、この国の王子であると理解する。
もう一人の王子、リドリスと瓜二つの顔を持つ双子だから。
突然公表された、もう一人のランベール王子の存在に、戸惑う者も中には当然のようにいた。
貴族特有の嫌がらせに有りがちな、細やかな礼儀を欠いた態度を取られようが、ユリウス本人はどこ吹く風。
持ち前の機転で躱したり、時には逆に相手を揶揄ったりもしたが、大抵は特段気にしたようすもなく王宮や王都での時間を楽しんでいる。
度々王都の町でもその姿は目撃され、店先の店主などと楽し気に会話していることさえあるのだという。ユリウスのその気さくな人柄が、世間に知れ渡っていくのは遅くはなかった。
かつて忌子として遠ざけられていたとは思えぬ程の彼の明るい内面に、惹きつけられる者は多い。
本宮殿を出て、歩みを続けるユリウスが辿り着いたのは、庭園の奥にある薔薇園。
ここは幼少児に初めてティアリーゼと言葉を交わした場所。
「ティア」
ユリウスはその後ろ姿に呼び掛ける。振り返った彼女の、ピンクブロンドの髪がサラサラと靡く。昔の面影を残しつつ美しく成長したティアリーゼを瞳に写し、ユリウスは微笑み掛けた。
「またティアとここに来れるなんてね、何と無く足を運んでみて良かったよ」
微笑み掛けるユリウスは、誰かに教えられた訳ではなく、偶然この場所に立ち寄ったらしい。
「そろそろミルディンに帰ることになるけど」
「はい」
「本当にこれから先、僕とミルディンでずっと暮らす未来をティアは受け入れてくれる?」
ユリウスの言葉に、ティリーゼは驚き目を見張る。
「陛下やリドリス殿下、お父様の前で宣言したあの時……とても緊張して恥ずかしかったんですからっ。なのにまだ、そのような質問をなさるのですか?」
「昔、もしティアが何らかの原因で婚約破棄になってしまったら、僕がティアの婚約者にして貰うことは可能かと、陛下に尋ねた過去がある。僕のこの一言が、ティアの運命を変えてしまう一因だったかもしれない……。だから、ティアの気持ちを優先するため、改めて確認が必要だと思った。
それに僕こそ、出会った子供の時からティアが欲しくて欲しくてたまらなかった」
ユリウスから初めて語られる過去の話を、ティアリーゼは真摯に聞き入った。
そして小さな唇を開く。
「嬉しいです……」
本当に昔出会った時から、自分を想っていてくれたのだと知り、その一言で不安は何処かへ消えていった。
嬉しくて堪らない。
次の瞬間、ふいにティリーゼの体が温もりに包まれる。気付けばユリウスに抱き寄せられていた。
「最後にティアの気持ちが確認出来たから、何があっても、もう絶対に離してあげられない」
優しく抱き締めてくるユリウスに、ティアリーゼはそのまま身を委ねた。
◇
結婚許可証に署名がされ、ユリウスとティアリーゼの婚約がランベール国内に発表された。
同時に正式に第一王子として認められたユリウスは、公爵位を与えられる運びとなった。
そしてティアリーゼとユリウスも、とうとうミルディンへ帰還する当日。
国王、リドリス、クルステア公爵といった限られた面々のみが、ユリウスとティアリーゼを見送るために、謁見の間へと集まっていた。
馬車は使わずに、予定通りレイヴンの転移魔法でミルディンへと帰還することとなっている。
まずはリドリスが、二人に向き合う。
すっかり体調が回復しつつあるその姿に、ティアリーゼの表情は喜色を浮かべた。
「兄上、ありがとうございました。兄上に助けて頂いたのを機に、生まれ変わったつもりでこれから頑張ります。また是非王都にいらして下さい、ティアリーゼも元気で」
「リドリス殿下も」
二人は婚約者ではなくなったが、良き友人に戻れたことが、ティアリーゼは心から嬉しかった。
それぞれが挨拶をすませると、レイヴンが背中に翼を出現させると、見送る者達は息を呑んだ。
──魔法自体はありふれた現象だとしても、人が一瞬で消えるなど、信じられない
それも王都から離れた地へ転移するとなると、現実的ではない話だった。
しかし高位精霊の存在がそれらを可能にする。
「よろしいですね?」
「頼む」とユリウスが返事をすると、三人の足下に魔法陣が出現し、次第に身体を光が包み込んでいく。
リドリス、クルステア公爵、ランベール王の目には何とも不思議で、幻想的な光景に映った。
そして漆黒の翼を広げたレイヴンは、高位精霊の名に違わぬ神々しさを纏っていた。
次第に消えてゆくティアリーゼとユリウスを見届けながらリドリスは呟く。
「さようならティアリーゼ……」
◇
ティアリーゼが瞼を開けると、目の前にはミルディン城の正面玄関。
見上げれば聳え立つ城、振り向けば辺りは雪景色の庭園。
それらを視界に写しながら、ティアリーゼは身体を震わせる。
外套を羽織っているとはいえ、王都より低いミルディンの気温を肌で感じ、とうとうこの地へと帰ってきたのだと実感した。
「冷えるから、中へと入ろう。温かいお茶が飲みたいな」
「お淹れ致しますね」
「本当?」
王都では飲むことの叶わなかったティアリーゼが淹れるお茶、それが久々に飲めるとは、つい思い浮かべてユリウスは破顔した。
そんな主人を尻目に、レイヴンがティアリーゼに問い掛ける。
「ティアリーゼ様、長旅でお疲れではありませんか?」
「距離的には確かに長旅ですが、一瞬だったので特に疲れてなどいませんわ」
ティアリーゼはくすくすと笑いながら答えた。
城に足を踏み入れると、既に揃っていた使用人達が出迎えてくれた。
「お帰りなさいませ」
「城を開けている間、大事なかったか?」
「特に、変わったことなどはございませんでした」
「そうか、ご苦労様だったな」
ユリウスの言葉に、年配の使用人は深々と頭を垂れた。
そんなユリウス達を尻目に、懐かしい顔ぶれの中からマシューとターニャの姿を見つけ、ティアリーゼは安堵する。
「お嬢様、無事お戻りになられてわたくしも安心致しました」
「ターニャは毎日、口を開けばお嬢様の話ばかりでしたよ」
「兄さんは黙ってて下さいっ」
ティアリーゼは兄妹の遣り取りに見ながら微笑む。
顔を真っ赤にさせるターニャだが、マシューの言葉を否定しない。
幾つか会話を交わし、ティアリーゼは着ていた外套を脱いで、ターニャに手渡した。
「わたしはユリウス様にお出しするお茶を淹れに、厨房へ行ってくるわね」
さっそくお茶を淹れようとしているティアリーゼの、相変わらずな言動にターニャは思わず苦笑せざるおえなかった。
ターニャの横をすり抜け、ユリウスが「僕も手伝うよ」と言いながらティアリーゼと並んで厨房の方へ向かう。
「え、旦那様もですか……いえ、殿下とお呼びした方が良いのでしょうか??えぇっと……」
頭を悩ませながらターニャは暫く、一人ぶつぶつと呟いていた。
さっそく厨房ではティアリーゼがお茶の準備をし、その間ユリウスが茶器をティーワゴンに乗せていく。
楽しげ気な二人の様子に、使用人達は敢えて手伝おうとせず、遠巻きに見守ることに徹している。
厨房でお茶の準備をする城主と、その婚約者の姿は、この先もミルディン城のありふれた光景となっていった。
ランベールは長きに渡る風習によって、王家で双子が産まれると、どちらか片方を「忌子」として隠し、ユリウスも例に漏れず今まで存在が公表されていなかった。
しかしユリウスは王家から忌子と称され、蔑ろにされながらも独自による魔法研究に人生を注いだ。その甲斐あってリドリスに掛けられていた呪いを解き、弟を救ったのだった。
ここ一、二年のリドリスの様子がおかしかったのは、王都の貴族内で噂になっていたことでもある。
そして呪いの効果により、精神を病んだリドリスと婚約破棄となっていたティアリーゼ。彼女をミルディンにいるユリウスと、新たな婚姻を結ぶよう提案したのは国王である。
ランベール王が全てを明るみにする覚悟が出来たのは、ユリウス、リドリス、ティアリーゼの未来のため。
その結果、自身が非難されることになろうと甘んじる覚悟だ。
王家に振り回されたティアリーゼは、ミルディンの地にて、ユリウスと心を通わせた。
ティアリーゼは以前、リドリスと入れ替わっていたユリウスと対面したことがあり、その頃から二人は惹かれあっていたのだという。
一方マリータやミランダについて、彼女達の事件への関与は未だ公表されていない。
マリータの取り調べは現在も慎重に行われている。
クルステア公爵は娘と妻の減罪を嘆願しながら、遠縁に爵位を譲ることを考えているのだという。
マリータは修道院にひっそりと送られる可能性が高く、ミランダは既に王都から離れてクルステア領の小さな町に身を寄せている。
彼女達はエルニア民族の血を引くことで、サイファーに利用されてしまった、ある意味被害者に近い立場でもある。だが、長年のティアリーゼに対する仕打ちは到底許されるものではない。
またエルニアの関与をどこまで公表するか、国王と重鎮の間で、幾度も話し合いが持たれた。ランベール国内にいるエルニア民族へ、差別的感情や怒りが向く可能性が懸念され、慎重にならざる得ない。
「行ってしまうのですか」
旅立とうとするユーノにティアリーゼは向き合う。
現在の彼の身長はティアリーゼより少しだけ高い。まだ少年らしさの残る面立ちから、成長過程であることが窺える。
最初は彼本来の姿に違和感を感じていたが、やはり妖精の姿も、猫の姿も、人間の姿もユーノであることに変わりない。
「俺みたいなのがこの国に留まっていたら、また悪巧みを考える奴等が集まってくるかもしれないからな。
それに俺は、修行を兼ねた放浪の旅が好きなんだ。
最古のエルニアは精霊の声を聞き、自然と共にあった遊牧の民族だ。それが国を持った途端王位争いとか色んなゴタゴタが起こった。
遊牧の民族は、国を持たない方がいいのは通説だよな」
ユーノ自身、エルニア民族としての誇りを持っていても、国の復興には興味がないらしい。
「また会えますよね?」
「当たり前だ。……というかユリウス!」
勢いよくユリウスに人差し指を突きつけると、彼は高らかに宣言する。
「また修行して、近々お前に勝負を挑んでやるからなっ」
また近々来る予定らしい。
「ミハエル殿下とイル様は……?」
ティアリーゼは視線を移し、二人を伺う。
何だか送り出す側のような立ち位置でユーノを見送っている二人だが、彼らも近々自国へと帰ることが決まっているらしい。
問われて「ユリウスを倒すまで居座る」と言い掛けたミハエルだが、そんな彼をイルが遮る。
「使節団を通して、陛下からの通達を受け取っております。即戻ってくるようにとのお達しでした。勝手に国を出たミハエル殿下に対して、国王夫妻や王太子殿下も相当お怒りのようですから」
「う、それは帰りたくなくなるな……」
頭を抱えるミハエルに、更にイルが追随する。
「そうですか?さっさと帰国しない方が、後が怖いと思われますよ」
「……」
顔面蒼白となったミハエルは、その後珍しい程静かになった。
現在見送る立場のティアリーゼとユリウスも、もう少ししたら王都を離れ、ミルディンへと帰還することになる。
帰りはレイヴンの力を使い、ミルディンまで転移出来るらしい。
レイヴンは高位精霊でありながら、人間のようにユリウスに仕えているのは、長い時を精霊として過ごすのに、単純に飽きたからと言っていた。
ユリウスの執事として仕えているのは、人間の振りをして楽しむ暇つぶしだそうだ。
それについてユリウスは「レイヴンは精霊の中でも変わり者なんだよ」と口にしていた。
レイヴンの正体が高位精霊と判明したことで、兼ねてから疑問だったユリウスに対する彼の慇懃無礼な態度に、ティアリーゼは納得したのだった。
ちなみに王都に来るまでの道のりを馬車にしたのは、ユリウスがティアリーゼと長旅をしてみたかったかららしい。
◇
銀糸の髪に赤紫の瞳をした王子、ユリウスが大理石の回廊を歩いていた。
王宮の人々は彼に気付くとすぐに端により、頭を垂れる。それは初対面の者でも同様である。
長年王宮で暮らしていなかったユリウスだが、誰しもが彼の姿を一目見ただけで、この国の王子であると理解する。
もう一人の王子、リドリスと瓜二つの顔を持つ双子だから。
突然公表された、もう一人のランベール王子の存在に、戸惑う者も中には当然のようにいた。
貴族特有の嫌がらせに有りがちな、細やかな礼儀を欠いた態度を取られようが、ユリウス本人はどこ吹く風。
持ち前の機転で躱したり、時には逆に相手を揶揄ったりもしたが、大抵は特段気にしたようすもなく王宮や王都での時間を楽しんでいる。
度々王都の町でもその姿は目撃され、店先の店主などと楽し気に会話していることさえあるのだという。ユリウスのその気さくな人柄が、世間に知れ渡っていくのは遅くはなかった。
かつて忌子として遠ざけられていたとは思えぬ程の彼の明るい内面に、惹きつけられる者は多い。
本宮殿を出て、歩みを続けるユリウスが辿り着いたのは、庭園の奥にある薔薇園。
ここは幼少児に初めてティアリーゼと言葉を交わした場所。
「ティア」
ユリウスはその後ろ姿に呼び掛ける。振り返った彼女の、ピンクブロンドの髪がサラサラと靡く。昔の面影を残しつつ美しく成長したティアリーゼを瞳に写し、ユリウスは微笑み掛けた。
「またティアとここに来れるなんてね、何と無く足を運んでみて良かったよ」
微笑み掛けるユリウスは、誰かに教えられた訳ではなく、偶然この場所に立ち寄ったらしい。
「そろそろミルディンに帰ることになるけど」
「はい」
「本当にこれから先、僕とミルディンでずっと暮らす未来をティアは受け入れてくれる?」
ユリウスの言葉に、ティリーゼは驚き目を見張る。
「陛下やリドリス殿下、お父様の前で宣言したあの時……とても緊張して恥ずかしかったんですからっ。なのにまだ、そのような質問をなさるのですか?」
「昔、もしティアが何らかの原因で婚約破棄になってしまったら、僕がティアの婚約者にして貰うことは可能かと、陛下に尋ねた過去がある。僕のこの一言が、ティアの運命を変えてしまう一因だったかもしれない……。だから、ティアの気持ちを優先するため、改めて確認が必要だと思った。
それに僕こそ、出会った子供の時からティアが欲しくて欲しくてたまらなかった」
ユリウスから初めて語られる過去の話を、ティアリーゼは真摯に聞き入った。
そして小さな唇を開く。
「嬉しいです……」
本当に昔出会った時から、自分を想っていてくれたのだと知り、その一言で不安は何処かへ消えていった。
嬉しくて堪らない。
次の瞬間、ふいにティリーゼの体が温もりに包まれる。気付けばユリウスに抱き寄せられていた。
「最後にティアの気持ちが確認出来たから、何があっても、もう絶対に離してあげられない」
優しく抱き締めてくるユリウスに、ティアリーゼはそのまま身を委ねた。
◇
結婚許可証に署名がされ、ユリウスとティアリーゼの婚約がランベール国内に発表された。
同時に正式に第一王子として認められたユリウスは、公爵位を与えられる運びとなった。
そしてティアリーゼとユリウスも、とうとうミルディンへ帰還する当日。
国王、リドリス、クルステア公爵といった限られた面々のみが、ユリウスとティアリーゼを見送るために、謁見の間へと集まっていた。
馬車は使わずに、予定通りレイヴンの転移魔法でミルディンへと帰還することとなっている。
まずはリドリスが、二人に向き合う。
すっかり体調が回復しつつあるその姿に、ティアリーゼの表情は喜色を浮かべた。
「兄上、ありがとうございました。兄上に助けて頂いたのを機に、生まれ変わったつもりでこれから頑張ります。また是非王都にいらして下さい、ティアリーゼも元気で」
「リドリス殿下も」
二人は婚約者ではなくなったが、良き友人に戻れたことが、ティアリーゼは心から嬉しかった。
それぞれが挨拶をすませると、レイヴンが背中に翼を出現させると、見送る者達は息を呑んだ。
──魔法自体はありふれた現象だとしても、人が一瞬で消えるなど、信じられない
それも王都から離れた地へ転移するとなると、現実的ではない話だった。
しかし高位精霊の存在がそれらを可能にする。
「よろしいですね?」
「頼む」とユリウスが返事をすると、三人の足下に魔法陣が出現し、次第に身体を光が包み込んでいく。
リドリス、クルステア公爵、ランベール王の目には何とも不思議で、幻想的な光景に映った。
そして漆黒の翼を広げたレイヴンは、高位精霊の名に違わぬ神々しさを纏っていた。
次第に消えてゆくティアリーゼとユリウスを見届けながらリドリスは呟く。
「さようならティアリーゼ……」
◇
ティアリーゼが瞼を開けると、目の前にはミルディン城の正面玄関。
見上げれば聳え立つ城、振り向けば辺りは雪景色の庭園。
それらを視界に写しながら、ティアリーゼは身体を震わせる。
外套を羽織っているとはいえ、王都より低いミルディンの気温を肌で感じ、とうとうこの地へと帰ってきたのだと実感した。
「冷えるから、中へと入ろう。温かいお茶が飲みたいな」
「お淹れ致しますね」
「本当?」
王都では飲むことの叶わなかったティアリーゼが淹れるお茶、それが久々に飲めるとは、つい思い浮かべてユリウスは破顔した。
そんな主人を尻目に、レイヴンがティアリーゼに問い掛ける。
「ティアリーゼ様、長旅でお疲れではありませんか?」
「距離的には確かに長旅ですが、一瞬だったので特に疲れてなどいませんわ」
ティアリーゼはくすくすと笑いながら答えた。
城に足を踏み入れると、既に揃っていた使用人達が出迎えてくれた。
「お帰りなさいませ」
「城を開けている間、大事なかったか?」
「特に、変わったことなどはございませんでした」
「そうか、ご苦労様だったな」
ユリウスの言葉に、年配の使用人は深々と頭を垂れた。
そんなユリウス達を尻目に、懐かしい顔ぶれの中からマシューとターニャの姿を見つけ、ティアリーゼは安堵する。
「お嬢様、無事お戻りになられてわたくしも安心致しました」
「ターニャは毎日、口を開けばお嬢様の話ばかりでしたよ」
「兄さんは黙ってて下さいっ」
ティアリーゼは兄妹の遣り取りに見ながら微笑む。
顔を真っ赤にさせるターニャだが、マシューの言葉を否定しない。
幾つか会話を交わし、ティアリーゼは着ていた外套を脱いで、ターニャに手渡した。
「わたしはユリウス様にお出しするお茶を淹れに、厨房へ行ってくるわね」
さっそくお茶を淹れようとしているティアリーゼの、相変わらずな言動にターニャは思わず苦笑せざるおえなかった。
ターニャの横をすり抜け、ユリウスが「僕も手伝うよ」と言いながらティアリーゼと並んで厨房の方へ向かう。
「え、旦那様もですか……いえ、殿下とお呼びした方が良いのでしょうか??えぇっと……」
頭を悩ませながらターニャは暫く、一人ぶつぶつと呟いていた。
さっそく厨房ではティアリーゼがお茶の準備をし、その間ユリウスが茶器をティーワゴンに乗せていく。
楽しげ気な二人の様子に、使用人達は敢えて手伝おうとせず、遠巻きに見守ることに徹している。
厨房でお茶の準備をする城主と、その婚約者の姿は、この先もミルディン城のありふれた光景となっていった。