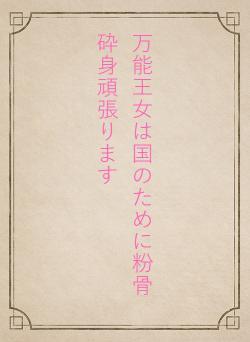ベテラン転生者エリザベス、完璧な令嬢になりました。今度こそ思い通りの人生になる…はず?
レディは失恋、こちらは初恋…かな?
その日は、なんとなく罪悪感を覚えたらしきアンドリューと、なぜか生き生きしているレオに励まされながら、リズは馬車に乗り込んで自邸へと戻っていった。
馬車は普通に走り、馬も心なしか元気がない。
「レディ・リズ、大丈夫かなぁ? 失恋なんてしたことなかっただろうに……」
と、レオ。
「おそらく生まれて初めての失恋でしょうね」
「だよなぁ……」
いつも余裕たっぷりのリズの萎んだ姿はある意味インパクト大であった。
「あんな姿、滅多に人に見せないんですよ、彼女……。ちょっと心配だなぁ」
アンドリューの心底心配そうな言葉に、そうだな、と、レオも頷く。そしてチラっとアンドリューを見た
「……アンドリューは……」
「はい、なんでしょう」
微妙な間が発生した。アンドリューはレオが喋るのを待ち、レオは口を開けては閉じる。
「なんだ、その……」
怪訝そうな表情を浮かべたアンドリューだが、すぐに察した。にっ、と口角を持ち上げ、わざと恭しい礼を取ってみせた。
「ご心配には及びません。彼女とはそんな関係ではありません」
ち、ち、違うし! とやたら慌てるレオであった。
「ところで……レオンハルト殿下!」
しんと教会が静まり返ったのを確認し、アンドリューがものすごい勢いでレオの腕を掴んだ。
「……なんだよ、レディが帰ったとたんに怖い顔だな。それに城の外では閣下と呼んでくれ」
「は、失礼しました。いえ、そうではなくて!」
じゃあ何だよ、とレオが拗ねた表情になる。
「仕事を放り出して夜な夜な遊びまわっているので見かけたら連れ戻してくれとお城から手配書が回っています。何日お留守になさっているのですか」
やかましい、と、レオは片手を振る。
「気にするな。たった……そうだな、三か月ほどだ」
「十分、いや、長すぎます!」
やれやれ、と、レオは肩を竦めた。
「城の煩い爺どもには辟易するんだ。いいじゃないか、父上は健在なんだし、俺の不在は側近たちでなんとかなってるわけだし、少しくらい拠点を城の外に移しても……」
とぼやき、アンドリューが「閣下!」と喚く。
「……わかったわかった、今宵は戻るよ」
今宵は、ということはまたすぐに城を飛び出してフラフラするつもりなのだろう。
「だいたい市井に交じって何をなさっているのですか? 花嫁候補探し……にも見えませんが……」
「念のため言っておくが、俺は彼女を騙してはいない」
神に誓って本当だ、と、レオは真顔で言う。
「わかっております。意図的に一部の情報を告げていないだけですよね。それも、聞かれなかったから答えてない。閣下のいつもの手段です」
うんうん、と、レオは頷く。
「そういうこと。さすがアンドリュー」
恐れ入ります、と、律儀にアンドリューが頭を下げる。
「それでも今回は自分の遊びのためじゃないぞ。なかなか結婚しようとしない腹心の部下に嫁をと思ってだな……」
「目論見が外れたかもしれませんね」
「そう、だな……」
シュテファンとレディ・リズ。
リズを始めて見た時から気になる存在だった。
完璧な美貌と完璧な肢体、完璧な知性と教養すべてを兼ね備えているのみならず、それらを隠すことなく使用して狙った男に突進していく。その、飢えた肉食獣のような逞しさに驚いたものだ。
大人しくて万事控えめなレディがよしとされている中、リズの勢いは眩かった。手段を選ばず突撃し、敵を蹴落とし獲物を我が物にするさまは、のちに戦の女神イシュタルに準えられるが、それを初めて聞いた時も納得したものだ。
「陛下がリズを初めて見かけたのは、サーラス伯爵主催の舞踏会でしたか」
「ああ。正式に社交界にデビューする前だったと思うが、年上の令嬢たちを蹴散らかして、どこぞの嫡男に肉薄し、巧みに駆け引きをしていた。その度胸に呆れた」
そうだろうそうだろう、とアンドリューも頷く。アンドリューもその会に参加していたが、扇の代わりに剣でも持たせたらいいだろうと思われるほどの、突進具合だったのを覚えている。
ちなみにその時のお相手は、リズの美貌と豊満な肉体に惑い、助平心を出し過ぎてリズにこっぴどくふられている。テラスに連れ出して口説きながら押し倒してキスを迫ったらしいがーーリズの悲鳴と罵声と殴打音が響いたのみならず、王都に「助平貴公子、レディは気をつけて!」と書かれた張り紙があちこちに貼られた。
やり過ぎという人もいたが、内心喜んだ令嬢も多いと聞いた。
兎にも角にも。
普通だったら、結婚するために多少のことは我慢したり醜聞を畏れて我慢したりするのだが、リズはきっぱりと、嫌です、と拒否する。そこも、レオがリズを気に入ったところだ。
美しいだけではない少し変わった令嬢と、将来有望なライセン侯爵家の嫡男シュテファン・ゾンマーフェルト・ライセン。とてもお似合いの二人に思えたのだ。
「俺の誘導というか計画通りに、レディはシュテファンに惹かれてくれたが……肝心のシュテファンがああではなぁ……」
「まったく興味を示さないとは想定外でしたね」
ちょっと悪いことをしたかな、と、レオが天井を仰ぐ。
「アンドリュー、レディ・リズの様子を気にかけておいてくれ」
「ほーう、殿下がそんなことをおっしゃるとは珍しいですね」
んあ? と、レオが首をかしげる。あどけない少年のような表情に、アンドリューはこの顔をリズに見せてやりたいと思った。
「いいえ、レディたちの心には無頓着、適当に弄んではポイ捨てするか、思わせぶりな態度をとっておいてほったらかし、の、どちらかが常套手段ですからねぇ……」
アンドリューが、にやにやと笑いながらレオの顔を覗き込む。見ればレオが呆気にとられたような表情で瞬きをしている。どうやら無自覚だったらしい。
「俺、はたから見たらひどい男じゃないか! まてよ、それはレディ・リズの耳にも入っているだろうか?」
「……お? もしや、レディ・リズのことがそんなに気になりますか? もしや、初恋だったり……」
「へ?」
「……リズのことが、お気に入りでしょう?」
「う?」
「もっと知りたい、構いたい、仲良くなりたいと思っていらっしゃる」
かかかーっ、とレオの白い頬が赤く染まった。
その変化にアンドリューは驚いたが敢えて触れずにおいた。
「アンドリュー! 俺をからかうとはいい度胸だ」
「あっはっは、殿下をからかえるのは、僕とシュテファンくらいでしょう」
「ま、確かにな……」
この筋骨たくましい神父と、将来有望なシュテファン、そしてレオ。三人は同じ寄宿学校にかよっていた学友なのである。生まれも育ちもバラバラだが、ともに成績優秀で妙に馬が合ってしまった。
しかも、三人寄ればなんとやら、あらん限りの悪戯をしてまわり、先生や生徒を悉く困らせ、ついには開校以来の悪童トリオとして名を馳せたのである。彼らが無事に卒業してくれたとき、教師陣は泣いて喜んだという。
「まぁ、レディ・リズの失恋……いや、恋の行方が気になるのはぼくも同じです。彼女の動向には気を配っておきますよ。きっと彼女は、明日か明後日にもここへ来るでしょうから」
「そうか、じゃあ俺も寄らせてもらうよ」
「承知いたしました」
ではまたな、と手を振って帰るレオを見送ったアンドリューは、ひとり小さく笑った。
「これは――もしかしたら……雨降って地固まる、になるかな?」
馬車は普通に走り、馬も心なしか元気がない。
「レディ・リズ、大丈夫かなぁ? 失恋なんてしたことなかっただろうに……」
と、レオ。
「おそらく生まれて初めての失恋でしょうね」
「だよなぁ……」
いつも余裕たっぷりのリズの萎んだ姿はある意味インパクト大であった。
「あんな姿、滅多に人に見せないんですよ、彼女……。ちょっと心配だなぁ」
アンドリューの心底心配そうな言葉に、そうだな、と、レオも頷く。そしてチラっとアンドリューを見た
「……アンドリューは……」
「はい、なんでしょう」
微妙な間が発生した。アンドリューはレオが喋るのを待ち、レオは口を開けては閉じる。
「なんだ、その……」
怪訝そうな表情を浮かべたアンドリューだが、すぐに察した。にっ、と口角を持ち上げ、わざと恭しい礼を取ってみせた。
「ご心配には及びません。彼女とはそんな関係ではありません」
ち、ち、違うし! とやたら慌てるレオであった。
「ところで……レオンハルト殿下!」
しんと教会が静まり返ったのを確認し、アンドリューがものすごい勢いでレオの腕を掴んだ。
「……なんだよ、レディが帰ったとたんに怖い顔だな。それに城の外では閣下と呼んでくれ」
「は、失礼しました。いえ、そうではなくて!」
じゃあ何だよ、とレオが拗ねた表情になる。
「仕事を放り出して夜な夜な遊びまわっているので見かけたら連れ戻してくれとお城から手配書が回っています。何日お留守になさっているのですか」
やかましい、と、レオは片手を振る。
「気にするな。たった……そうだな、三か月ほどだ」
「十分、いや、長すぎます!」
やれやれ、と、レオは肩を竦めた。
「城の煩い爺どもには辟易するんだ。いいじゃないか、父上は健在なんだし、俺の不在は側近たちでなんとかなってるわけだし、少しくらい拠点を城の外に移しても……」
とぼやき、アンドリューが「閣下!」と喚く。
「……わかったわかった、今宵は戻るよ」
今宵は、ということはまたすぐに城を飛び出してフラフラするつもりなのだろう。
「だいたい市井に交じって何をなさっているのですか? 花嫁候補探し……にも見えませんが……」
「念のため言っておくが、俺は彼女を騙してはいない」
神に誓って本当だ、と、レオは真顔で言う。
「わかっております。意図的に一部の情報を告げていないだけですよね。それも、聞かれなかったから答えてない。閣下のいつもの手段です」
うんうん、と、レオは頷く。
「そういうこと。さすがアンドリュー」
恐れ入ります、と、律儀にアンドリューが頭を下げる。
「それでも今回は自分の遊びのためじゃないぞ。なかなか結婚しようとしない腹心の部下に嫁をと思ってだな……」
「目論見が外れたかもしれませんね」
「そう、だな……」
シュテファンとレディ・リズ。
リズを始めて見た時から気になる存在だった。
完璧な美貌と完璧な肢体、完璧な知性と教養すべてを兼ね備えているのみならず、それらを隠すことなく使用して狙った男に突進していく。その、飢えた肉食獣のような逞しさに驚いたものだ。
大人しくて万事控えめなレディがよしとされている中、リズの勢いは眩かった。手段を選ばず突撃し、敵を蹴落とし獲物を我が物にするさまは、のちに戦の女神イシュタルに準えられるが、それを初めて聞いた時も納得したものだ。
「陛下がリズを初めて見かけたのは、サーラス伯爵主催の舞踏会でしたか」
「ああ。正式に社交界にデビューする前だったと思うが、年上の令嬢たちを蹴散らかして、どこぞの嫡男に肉薄し、巧みに駆け引きをしていた。その度胸に呆れた」
そうだろうそうだろう、とアンドリューも頷く。アンドリューもその会に参加していたが、扇の代わりに剣でも持たせたらいいだろうと思われるほどの、突進具合だったのを覚えている。
ちなみにその時のお相手は、リズの美貌と豊満な肉体に惑い、助平心を出し過ぎてリズにこっぴどくふられている。テラスに連れ出して口説きながら押し倒してキスを迫ったらしいがーーリズの悲鳴と罵声と殴打音が響いたのみならず、王都に「助平貴公子、レディは気をつけて!」と書かれた張り紙があちこちに貼られた。
やり過ぎという人もいたが、内心喜んだ令嬢も多いと聞いた。
兎にも角にも。
普通だったら、結婚するために多少のことは我慢したり醜聞を畏れて我慢したりするのだが、リズはきっぱりと、嫌です、と拒否する。そこも、レオがリズを気に入ったところだ。
美しいだけではない少し変わった令嬢と、将来有望なライセン侯爵家の嫡男シュテファン・ゾンマーフェルト・ライセン。とてもお似合いの二人に思えたのだ。
「俺の誘導というか計画通りに、レディはシュテファンに惹かれてくれたが……肝心のシュテファンがああではなぁ……」
「まったく興味を示さないとは想定外でしたね」
ちょっと悪いことをしたかな、と、レオが天井を仰ぐ。
「アンドリュー、レディ・リズの様子を気にかけておいてくれ」
「ほーう、殿下がそんなことをおっしゃるとは珍しいですね」
んあ? と、レオが首をかしげる。あどけない少年のような表情に、アンドリューはこの顔をリズに見せてやりたいと思った。
「いいえ、レディたちの心には無頓着、適当に弄んではポイ捨てするか、思わせぶりな態度をとっておいてほったらかし、の、どちらかが常套手段ですからねぇ……」
アンドリューが、にやにやと笑いながらレオの顔を覗き込む。見ればレオが呆気にとられたような表情で瞬きをしている。どうやら無自覚だったらしい。
「俺、はたから見たらひどい男じゃないか! まてよ、それはレディ・リズの耳にも入っているだろうか?」
「……お? もしや、レディ・リズのことがそんなに気になりますか? もしや、初恋だったり……」
「へ?」
「……リズのことが、お気に入りでしょう?」
「う?」
「もっと知りたい、構いたい、仲良くなりたいと思っていらっしゃる」
かかかーっ、とレオの白い頬が赤く染まった。
その変化にアンドリューは驚いたが敢えて触れずにおいた。
「アンドリュー! 俺をからかうとはいい度胸だ」
「あっはっは、殿下をからかえるのは、僕とシュテファンくらいでしょう」
「ま、確かにな……」
この筋骨たくましい神父と、将来有望なシュテファン、そしてレオ。三人は同じ寄宿学校にかよっていた学友なのである。生まれも育ちもバラバラだが、ともに成績優秀で妙に馬が合ってしまった。
しかも、三人寄ればなんとやら、あらん限りの悪戯をしてまわり、先生や生徒を悉く困らせ、ついには開校以来の悪童トリオとして名を馳せたのである。彼らが無事に卒業してくれたとき、教師陣は泣いて喜んだという。
「まぁ、レディ・リズの失恋……いや、恋の行方が気になるのはぼくも同じです。彼女の動向には気を配っておきますよ。きっと彼女は、明日か明後日にもここへ来るでしょうから」
「そうか、じゃあ俺も寄らせてもらうよ」
「承知いたしました」
ではまたな、と手を振って帰るレオを見送ったアンドリューは、ひとり小さく笑った。
「これは――もしかしたら……雨降って地固まる、になるかな?」