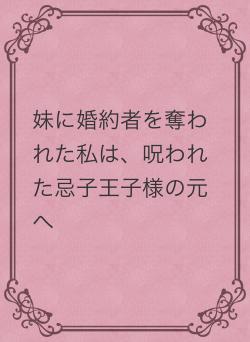新婚なのに旦那様と会えません〜公爵夫人は宮廷魔術師〜
66
シルヴィアは先に王都へと帰還していた。
そして償いも兼ねてのつもりなのか、公爵家の書類仕事を以前よりもこなしている。
頼まれれば茶会などにも参加するようになり、公爵夫人として極普通の生活を送っていた。
一週間と少し過ぎた頃、ようやく王太子とその婚約者、レティシアが王都に帰還。ギルバートを護衛していたアレクセルも、邸へと戻った。
ちなみに、彼らがグランヴェール王都へと戻る前に、ブルゴー侯爵が失脚する事態となっていた。
レティシアの首飾りに呪いをかけようとした、ブルゴー侯爵の次男マシュー。
彼は以前留学の経験があり、そこで邪神イルザーブを信仰する邪教と出会い、信者になるまでとなっていた。
以前ブルゴー侯爵は、邪教に身を落とした時点でマシューを侯爵家から勘当したと言っていたが、どうやらそれは調べによると真実らしい。
ブルゴー侯爵はとても敬虔な人物だった。
そして勘当された事により、貧しく暮らしていたマシューの元にやってきた侯爵は「邪教の呪いをレティシアの首飾りにかけろ。計画が成功すれば報酬と邸の一つをやる」と持ち掛けたが、失敗に終わったためマシューは捕らえられ、父侯爵からそのまま見捨てられてしまった。
そして今回、レティシアを賊の襲撃に紛れて襲うはずだった黒髪の騎士の名は、ルース・フォートレル。フォートレル子爵領は葡萄酒の産地であり、上客であったブルゴー家から出荷直前に、ワインの発注を取り止めるよう申し出を受けた。突然の事で事情を聞くと、レティシアを襲撃する計画を持ちかけられ、言う事を聞くなら発注は取り止めないと言われる。
脅されたフォートレル家は、計画に乗ってしまった。
また捕らえた賊はフレリアの有名な盗賊団の格好をしていたが、体の刺青はブルゴー領に生息する山賊の物と一致した。彼らも口を揃えて、ブルゴー侯爵に話を持ちかけられたという。
その他にも言い逃れ出来ない証拠や証言が、次々に出てきた事により、侯爵は捕らえられる事となった。
こうしてレティシアに危害を加えていた、ブルゴー侯爵を排除し、グランヴェールに迎え入れる手筈を整える事が出来た。
**
アレクセルが、邸に戻った夜。
晩餐を終えたシルヴィアとアレクセルは、寝室のバルコニーにて、夜の庭園や空を眺めて過ごしていた。
バルコニーに備え付けられた、白い丸テーブルを挟んで、左右に設置した椅子に腰掛ける。
シルヴィアに話しかけたアレクセルは、飾りのついた箱を取り出し、差し出した。
「シルヴィアのために作らせていた首飾りが出来上がりました」
「私に……ですか?」
「勿論です。受け取って頂けますか?」
「頂いてもよろしいのですか……?」
遠慮気味なシルヴィアの顔を、アレクセルは覗き込むようにする。
「どうしました?」
「えっと、今回の任務の事で……。私は公爵家の奥様を、クビになる可能性を考えていまして……。いつか旦那様直々に、言い渡されるのではないかと……」
しどろもどろ話すシルヴィアに、アレクセルの瞳が見開かれる。
「もしかして、シルヴィアは私の妻でいる事が嫌ですかっ?」
「えっ、そんな事は……」
シルヴィアは驚き顔を上げた。
「シルヴィア、私の側から離れようとしないでください……!私は、シルヴィアがいなくなってしまったり、もしもの事があったら生きていけませんっ」
立ち上がったアレクセルが、座ったままのシルヴィアへと距離を詰め、肩を強く掴んだ。
アレクセルの端正な顔が、苦痛に歪み、必死に訴えてくる。
「旦那様……?」
思ってもいなかった反応に、シルヴィアは虚を突かれてしまった。
「旦那様は、殿下から私を押し付けられた筈なのに、どうして?」
「違います!押し付けられたのでは無く、私がシルヴィアを妻にと望んだのです」
「え?」
驚き、停止しているシルヴィアにアレクセルは、縋るように強く抱きしめた。
「ずっと好きでした。婚約する前から。シルヴィアが嫁いで来てくれて、一緒に過ごすようになって、もっと好きになりました。初めて女性を好きになったんです、妻になって貰えてようやく手が届いたと思ったのに……いつか手の届かない所へ行ってしまいそうで、不安で堪らない……っ」
「婚約する前……?殿下と三人で顔を合わせた、あの時より前ですか?」
「はい」
「えっ、私達何処かで会ってましたっけ?」
記憶を必死で探るも、やはり心当たりはなく、シルヴィアは焦る一方だった。
「王宮の廊下を歩いていたら、上の階の窓から飛び降りてきた、シルヴィアと出会いました」
「えっ!?」
「私は柱の陰に隠れて見ていたので、シルヴィアは気付いていませんでしたが」
それは一方的すぎて、出会ったと言うのだろうか。しかし王宮の窓から飛び降りた前科は、何度かあるのでシルヴィアも、当然心当たりはある。
出会いというよりむしろ、遭遇に近いかもしれない。
「一目惚れといえば一目惚れですが、下町で買い食いする姿なども見かけていました。容姿だけでなく、シルヴィアのありのままの姿を好きになったのです!」
ポカーンとした表情で力説をを聞くシルヴィアを見て、今度はアレクセルが慌て始めた。
「あ、付き纏っていた訳ではありませんよ!?夜会などで、探したりはしていましたが。たまたま私の行く所でシルヴィアを目撃出来た時は、運命を感じていましたっ」
付き纏ってはいないかもしれないが、いそうな場所や、足を運びそうな場所へと積極的に探しに行っていた。そして見かけると、隠れて見守っていたので、やはり近いものがある。
「い、嫌ですか……?もしかして、嫌いになりましたか?」
不安の色に染まる、端正なアレクセルの顔を見て、シルヴィアは頬がゆるんでしまった。
国の筆頭貴族であり、誰もが羨むような美貌や才能を持つ彼が、妻に嫌われたくなくて不安そうに見つめてくる。
そして窓から飛び降りたら、それを見ていた公爵様から、自分が好意を寄せられるとは。
それを思うと、なんだか可笑しくなってしまった。
「嫌いになんて、なるはずがありません。もし、それが本当ならとても嬉しいです」
「嘘じゃありません、ずっと見ていました!……愛しているんです」
シルヴィアの華奢な両手を握り締めて、跪き懇願する。そんな夫を見てシルヴィアはポツリポツリと話し始めた。
「旦那様……私は、この国で産まれた人間ではないのです。そして親がいなくて魔力の強かった私を、レイノール家の両親は養女にして下さいました。
レイノール家は過去に、魔法国家ジールから降嫁した、王女様を迎えられた事があります。
その為か特殊な魔力を持つ方々が多くて、元の私は遠縁の子供だった、という事にされました。私は、レイノールの血すら入っていないのです。
それなのに、家族もこの国の方々は皆んな優しくて、いつかこの魔力で国に恩返しがしたいと、そう思って生きて来ました。私はずっと生き急いでいたのかもしれません。
身元のしれない私が、公爵家に嫁いでいいものかとも思っておりました」
「シルヴィア、私はシルヴィアの身分や出自など、どうでも良いんです。シルヴィアが良いんです」
アレクセルの真摯な眼差しにシルヴィアは応えようと決心した。
「旦那様。これからは、黙って任務についたりなど致しません。だから……このまま旦那様の妻でいさせて頂いても、よろしいでしょうか?」
「勿論です。私はシルヴィアを絶対に離したりはしません」
アレクセルから渡された箱に入っていた首飾りは、月と蝶と薔薇のモチーフ。
銀細工の月に、アメジストの羽の蝶が飛び、薔薇とサファイヤが添えられている。
シルヴィアが特に気に入った石やモチーフばかり。やはりアレクセルは、シルヴィアの反応を常に観察しているから、出来る技だった。
**
二週間後。フランベルク地方で売られていた生地で作った、草花モチーフのワンピースがルクセイア邸へと届けられた。
とても可愛い服だが、何故公爵家に平服が届けられたのかと、シルヴィアは首を傾げる。
「町で見かけそうな、可愛いお洋服ですね!でも、このお洋服はどうなさったんですか?」
「その服でなら、町を一緒に散策が出来ると思いまして。シルヴィアがその生地を眺めていたから、王都に戻る前に買っておいたのです。仕立て終わるまで秘密にしていました。気に入りましたか?」
「はい、とっても!」
(旦那様……。なぜ毎回そのような、女心を知り尽くしているような言動を……いえ、疑ってません。信じてます、信じてますよ?)
「では、次の休みにはこれを来て、王都の町を一緒に回りましょうか」
「はいっ」
国内でも評判の美しきルクセイア公爵夫妻。
グランヴェールの王都の町では、仲睦まじく寄り添い合って歩く、夫婦の姿が頻繁に見られるようになった。
そして償いも兼ねてのつもりなのか、公爵家の書類仕事を以前よりもこなしている。
頼まれれば茶会などにも参加するようになり、公爵夫人として極普通の生活を送っていた。
一週間と少し過ぎた頃、ようやく王太子とその婚約者、レティシアが王都に帰還。ギルバートを護衛していたアレクセルも、邸へと戻った。
ちなみに、彼らがグランヴェール王都へと戻る前に、ブルゴー侯爵が失脚する事態となっていた。
レティシアの首飾りに呪いをかけようとした、ブルゴー侯爵の次男マシュー。
彼は以前留学の経験があり、そこで邪神イルザーブを信仰する邪教と出会い、信者になるまでとなっていた。
以前ブルゴー侯爵は、邪教に身を落とした時点でマシューを侯爵家から勘当したと言っていたが、どうやらそれは調べによると真実らしい。
ブルゴー侯爵はとても敬虔な人物だった。
そして勘当された事により、貧しく暮らしていたマシューの元にやってきた侯爵は「邪教の呪いをレティシアの首飾りにかけろ。計画が成功すれば報酬と邸の一つをやる」と持ち掛けたが、失敗に終わったためマシューは捕らえられ、父侯爵からそのまま見捨てられてしまった。
そして今回、レティシアを賊の襲撃に紛れて襲うはずだった黒髪の騎士の名は、ルース・フォートレル。フォートレル子爵領は葡萄酒の産地であり、上客であったブルゴー家から出荷直前に、ワインの発注を取り止めるよう申し出を受けた。突然の事で事情を聞くと、レティシアを襲撃する計画を持ちかけられ、言う事を聞くなら発注は取り止めないと言われる。
脅されたフォートレル家は、計画に乗ってしまった。
また捕らえた賊はフレリアの有名な盗賊団の格好をしていたが、体の刺青はブルゴー領に生息する山賊の物と一致した。彼らも口を揃えて、ブルゴー侯爵に話を持ちかけられたという。
その他にも言い逃れ出来ない証拠や証言が、次々に出てきた事により、侯爵は捕らえられる事となった。
こうしてレティシアに危害を加えていた、ブルゴー侯爵を排除し、グランヴェールに迎え入れる手筈を整える事が出来た。
**
アレクセルが、邸に戻った夜。
晩餐を終えたシルヴィアとアレクセルは、寝室のバルコニーにて、夜の庭園や空を眺めて過ごしていた。
バルコニーに備え付けられた、白い丸テーブルを挟んで、左右に設置した椅子に腰掛ける。
シルヴィアに話しかけたアレクセルは、飾りのついた箱を取り出し、差し出した。
「シルヴィアのために作らせていた首飾りが出来上がりました」
「私に……ですか?」
「勿論です。受け取って頂けますか?」
「頂いてもよろしいのですか……?」
遠慮気味なシルヴィアの顔を、アレクセルは覗き込むようにする。
「どうしました?」
「えっと、今回の任務の事で……。私は公爵家の奥様を、クビになる可能性を考えていまして……。いつか旦那様直々に、言い渡されるのではないかと……」
しどろもどろ話すシルヴィアに、アレクセルの瞳が見開かれる。
「もしかして、シルヴィアは私の妻でいる事が嫌ですかっ?」
「えっ、そんな事は……」
シルヴィアは驚き顔を上げた。
「シルヴィア、私の側から離れようとしないでください……!私は、シルヴィアがいなくなってしまったり、もしもの事があったら生きていけませんっ」
立ち上がったアレクセルが、座ったままのシルヴィアへと距離を詰め、肩を強く掴んだ。
アレクセルの端正な顔が、苦痛に歪み、必死に訴えてくる。
「旦那様……?」
思ってもいなかった反応に、シルヴィアは虚を突かれてしまった。
「旦那様は、殿下から私を押し付けられた筈なのに、どうして?」
「違います!押し付けられたのでは無く、私がシルヴィアを妻にと望んだのです」
「え?」
驚き、停止しているシルヴィアにアレクセルは、縋るように強く抱きしめた。
「ずっと好きでした。婚約する前から。シルヴィアが嫁いで来てくれて、一緒に過ごすようになって、もっと好きになりました。初めて女性を好きになったんです、妻になって貰えてようやく手が届いたと思ったのに……いつか手の届かない所へ行ってしまいそうで、不安で堪らない……っ」
「婚約する前……?殿下と三人で顔を合わせた、あの時より前ですか?」
「はい」
「えっ、私達何処かで会ってましたっけ?」
記憶を必死で探るも、やはり心当たりはなく、シルヴィアは焦る一方だった。
「王宮の廊下を歩いていたら、上の階の窓から飛び降りてきた、シルヴィアと出会いました」
「えっ!?」
「私は柱の陰に隠れて見ていたので、シルヴィアは気付いていませんでしたが」
それは一方的すぎて、出会ったと言うのだろうか。しかし王宮の窓から飛び降りた前科は、何度かあるのでシルヴィアも、当然心当たりはある。
出会いというよりむしろ、遭遇に近いかもしれない。
「一目惚れといえば一目惚れですが、下町で買い食いする姿なども見かけていました。容姿だけでなく、シルヴィアのありのままの姿を好きになったのです!」
ポカーンとした表情で力説をを聞くシルヴィアを見て、今度はアレクセルが慌て始めた。
「あ、付き纏っていた訳ではありませんよ!?夜会などで、探したりはしていましたが。たまたま私の行く所でシルヴィアを目撃出来た時は、運命を感じていましたっ」
付き纏ってはいないかもしれないが、いそうな場所や、足を運びそうな場所へと積極的に探しに行っていた。そして見かけると、隠れて見守っていたので、やはり近いものがある。
「い、嫌ですか……?もしかして、嫌いになりましたか?」
不安の色に染まる、端正なアレクセルの顔を見て、シルヴィアは頬がゆるんでしまった。
国の筆頭貴族であり、誰もが羨むような美貌や才能を持つ彼が、妻に嫌われたくなくて不安そうに見つめてくる。
そして窓から飛び降りたら、それを見ていた公爵様から、自分が好意を寄せられるとは。
それを思うと、なんだか可笑しくなってしまった。
「嫌いになんて、なるはずがありません。もし、それが本当ならとても嬉しいです」
「嘘じゃありません、ずっと見ていました!……愛しているんです」
シルヴィアの華奢な両手を握り締めて、跪き懇願する。そんな夫を見てシルヴィアはポツリポツリと話し始めた。
「旦那様……私は、この国で産まれた人間ではないのです。そして親がいなくて魔力の強かった私を、レイノール家の両親は養女にして下さいました。
レイノール家は過去に、魔法国家ジールから降嫁した、王女様を迎えられた事があります。
その為か特殊な魔力を持つ方々が多くて、元の私は遠縁の子供だった、という事にされました。私は、レイノールの血すら入っていないのです。
それなのに、家族もこの国の方々は皆んな優しくて、いつかこの魔力で国に恩返しがしたいと、そう思って生きて来ました。私はずっと生き急いでいたのかもしれません。
身元のしれない私が、公爵家に嫁いでいいものかとも思っておりました」
「シルヴィア、私はシルヴィアの身分や出自など、どうでも良いんです。シルヴィアが良いんです」
アレクセルの真摯な眼差しにシルヴィアは応えようと決心した。
「旦那様。これからは、黙って任務についたりなど致しません。だから……このまま旦那様の妻でいさせて頂いても、よろしいでしょうか?」
「勿論です。私はシルヴィアを絶対に離したりはしません」
アレクセルから渡された箱に入っていた首飾りは、月と蝶と薔薇のモチーフ。
銀細工の月に、アメジストの羽の蝶が飛び、薔薇とサファイヤが添えられている。
シルヴィアが特に気に入った石やモチーフばかり。やはりアレクセルは、シルヴィアの反応を常に観察しているから、出来る技だった。
**
二週間後。フランベルク地方で売られていた生地で作った、草花モチーフのワンピースがルクセイア邸へと届けられた。
とても可愛い服だが、何故公爵家に平服が届けられたのかと、シルヴィアは首を傾げる。
「町で見かけそうな、可愛いお洋服ですね!でも、このお洋服はどうなさったんですか?」
「その服でなら、町を一緒に散策が出来ると思いまして。シルヴィアがその生地を眺めていたから、王都に戻る前に買っておいたのです。仕立て終わるまで秘密にしていました。気に入りましたか?」
「はい、とっても!」
(旦那様……。なぜ毎回そのような、女心を知り尽くしているような言動を……いえ、疑ってません。信じてます、信じてますよ?)
「では、次の休みにはこれを来て、王都の町を一緒に回りましょうか」
「はいっ」
国内でも評判の美しきルクセイア公爵夫妻。
グランヴェールの王都の町では、仲睦まじく寄り添い合って歩く、夫婦の姿が頻繁に見られるようになった。