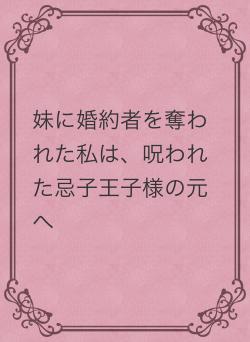婚約者と男性の逢瀬現場を目撃してしまいました。
フォンテーヌ伯爵家の令嬢アリスは近頃悩んでいた。
婚約者であるウィルム伯爵家の令息、リーンハルトと会えない日々が続いている。
(観劇の約束も守られず仕舞いでした……)
二人で観ようと約束していた流行りの歌劇は、とうとう数日前に最終公演を迎え、結局行けず仕舞いだった。
本日王宮へ来た目的は、王女殿下主催のお茶会への参加。そのお茶会も終了し、時間を持て余したアリスはそのまま、庭園へと向かう。
物思いにふけりながら歩いていると、庭園の更に奥の方から、聞き馴染みのある声が聞こえてきた気がした。
(今リーンハルト様の声が……)
アリスの婚約者リーンハルトは騎士であり、遠征中のため今現在は、王都から遠く離れた場所にいる筈である。
それなのに彼の声が耳に届いた気がするなんて。彼恋しさに、とうとう幻聴まで起こり始めたのかと、アリスは自身を案じた。しかし──
「受け取って欲しい」
「何?」
若い黒髪の騎士──アリスの婚約者、リーンハルトが首を傾げる。彼の癖のない艶やかな黒髪がさらりと風に靡く。
そんなリーンハルトに向き合う金髪の騎士、ライネルが何かを取り出した。
「これを……」
「取り敢えず貰うよ」
「でも、やはり止めておこうかな。いらないだろうし……」
「なんだそれは、お前が俺の為に用意してくれたんだろ?だったら貰うよ」
ライネルの手の中で何かが光る。
(あれは、指輪……?)
植木と花壇で身を隠し、アリスは二人の様子を窺うことにした。
「でもお前こういうの渡されても迷惑だろうし持て余すかなって……ぶっちゃけ趣味でもないだろうし」
「言い出しておいてなんだ?お前から貰った物なら、取り敢えず持っておくから」
ライネルの手の上に、リーンハルトの掌が優しく重ねられる。
僅かに驚いたライネルが、リーンハルトの青の瞳を逡巡してから、視線を落とした。
「婚約者殿に貰った物だって……」
突然自身の話題に触れられ、アリスの鼓動はどきりと揺れ動く。
音を立ててしまわぬように後退り、アリスはその場を離れた。
(どうしましょう……!?)
もじもじと、恥じらう麗しいライネルに対し、優しく受け止めようとする、クールな美形リーンハルト。
(どうしましょう、何だかわたくし新しい世界を知ってしまったかもしれませんわ……)
アリスは今まで見たどの歌劇よりも、リーンハルトとライネルのやり取りを真剣に、食い入るように見ていた。お陰で脳裏に焼き付いて先程の情景が離れない。
「まさかライネル様はリーンハルト様のことが……、そしてリーンハルト様もライネル様のことを……」
ぽつりと呟き、最後まで言い切る前に口を噤む。しかしリーンハルトはアリスの婚約者だ。
リーンハルトといえば今まで、アリスへ送ってくる手紙は短文でそっけなかったが、彼は感情をあまり表に出さないタイプである。きっと文章も苦手なのだろう。
それでも実際に会って時間を共有している時は、優しく紳士的に扱ってくれていると、アリスは感じている。
このまま無事リーンハルトと結婚すれば、自分は理解ある妻として──それはつまり……。
(お二方のやり取りを、身近で拝見出来る機会が増えるのでは!?)
◇
夜が深まる頃、私室の寝台で横になっているアリスは中々寝付けないでいた。
脳裏に焼き付けた、王宮でのリーンハルトとライネルのやり取り──あの光景を鮮明に呼び起こしたはいいが、その後どうなったのか気になって仕方がない。
(リーンハルト様は無事、指輪をお受け取りになられたのでしょうか……?それにしてもお二人の距離はとても近かったですし……もしかしてあのまま……!!?)
アリスは胸の高鳴りを抑えきれず、思わず上半身をガバリと勢いよく起こし、しばし悶えた。
「ま、まあ……どうしましょう?」
その夜、アリスの妄想はとどまることを知らなかった。
お陰で次の日のアリスは、見事に寝不足だった。
それでも出掛けるため、支度を終えて馬車に乗り込んだ。屋敷の者には「王立図書館に用事があるので、王宮へ行って参ります」と言い添えて。
読書が好きなアリスは、王宮敷地内に併設される王立図書館には定期的に足を運んでいる。
馬車から降り立ち、王宮へと足を踏み入れる。しかしアリスは図書館とは違う方向へ歩みを進めた。
(図書館の前に……)
リーンハルトに会えるかもしれない、という期待を淡く抱きながら。
今日もリーンハルトが登城しているといった確証はない。彼からは帰還を知らせる手紙すら、送られて来ていないのだから。
その上この広大な王宮敷地内で、偶然姿を見つけられる可能性は低い。
そう思いながら騎士団修練場の方へ歩みを進めていた、その時──
リーンハルトの後ろ姿を発見した。
(いたーーー!!)
思わず柱に隠れて様子を窺うと、視線の先にはライネルの姿もあった。
(今日もご一緒だなんて、本当にお二人は仲が良いのですねっ)
腕組みをしながら、壁にもたれ掛かるリーンハルトと、どこか落ち着かない様子のライネル。
自身の婚約者とライネルとの組み合わせに、アリスは心をときめかせる。
アリス曰く、焦ったい距離感もまた堪らないらしい。
(やはりリーンハルト様は素敵ですわ……)
反面、何故王都にいるはずのないリーンハルトが王宮にいるのか、疑問が残る。
騎士職に就く彼故に、きっと自分には言えない事情があるのだ。そう言い聞かせ、アリスは柱の影にかくれながら、こっそり二人を生ぬるく見守ることにした。
「そういえば、くれるって言ってた指輪は?」
「一応、今日も持って来てる」
レオネルの言葉に、リーンハルトは短く息を吐きながら「だったら早くくれ」と催促した。
(まさかの、昨日の続きが展開されている!?)
昨日は結局指輪は渡せず仕舞いだったらしい。
宝石や、宝飾品収集を好む貴族男性は多くいるが、リーンハルトはそれらに当て嵌まらない。
確かに指輪をプレゼントしたところで、彼が身に着けるとは考えられない。
(でもライネル様からの贈り物なら、どのような物でも嬉しい筈。そして何より、リーンハルト様もご所望されているのですし!!)
一人脳内で盛り上がるアリス。
だがそんなアリスが見守る二人のやり取りに、新たなる人物が加わった。
「まだやってるのか、さっさと渡せばいいだろう」
「フェルグス……っ」
リーンハルトとライネルの所属する騎士団の同僚フェルグスだ。
(お二人の関係はフェルグス様も知っていらしたのですねっ。……まさか、騎士団公認だったりするのでしょうかっ!?)
リーンハルトとライネルの仲を、微笑ましく見守る騎士団の図を想像し「それもまた良いですわ」と頭の中で呟くアリスの顔はニヤけていた。
「さあ、ライネル」
リーンハルトに促され、ライネルは指輪を取り出す。
(二人きりの構図ではなくなってしまいましたが……ついにこの瞬間が……!)
その時だった。
パチリ
感極まったアリスが思わず拍手をしかけ、パチリと手を打った。
何とか思い止まって、一回きりの手打ちに留めたアリスだったが、後の祭りだ。
アリスの存在に気付いた三人の騎士は、一斉にこちらの方へと振り返った。
「アリス……?」
(覗き現場などという、とんでも無く、はしたない姿を見せてしまいました……!このままだとリーンハルト様に嫌われてしまうかも……!?)
覗きは明らかな現行犯であり、言い逃れ出来ない事態にアリスは震えた。
気付けばリーンハルトは、既にアリスとの距離を詰めている。
不思議そうな表情で自分を見つめてくる彼に対し、罪悪感や羞恥心に襲われたアリスは、足早にその場を去って行っていった。
「早い!?急いで去っていくのに、スカートの裾は翻さないだと?流石リーンハルトの婚約者だっ」
何故か実況し始めたフェルグスの隣で、面食らったリーンハルトが唖然と、遠ざかっていくアリスの華奢な背中を見つめる。
「アリス、どうしたんだ……」
「急いで行ってしまったぞ、スカートの裾を翻さずにな」
「彼女は淑女の鑑だからな」
「悠長に惚気ている場合か!?これはヤバイぞっ」
「何が……?」
狼狽するフェルグスに対し、状況を理解出来ないでいるリーンハルトが訝しみの表情を向ける。
「きっとリーンハルトとライネルを恋仲と疑ったに違いない」
ぶっ飛んだ返答に到底理解が及ばず、リーンハルトの思考が停止する。
だが意味を理解すると、次は自分が声を荒げる番だった。
「そんな訳あるかっ!?」
リーンハルトは婚約者を追うため、駆け出した。
アリスは急いで去って行ったが、当然足の速さは自分の方が上である。
内心狼狽しつつも、頭は状況を整理しようとしていた。
ライネルとの仲をアリスが誤解しているかはさて置き、自分は重大な失態を犯している。
アリスに王都へ帰還したと告げていなかった──この弁明こそ、必ずしなければならない。
庭園に足を踏み入れ、薔薇園に差し掛かった辺りで陽光に照らされれ、光り輝く金糸の頭を発見した。
(いた……!)
「アリス」
呼ばれてアリスはびくりと体を震わせる。
「君は何か……」
誤解をしていないか?そう紡ぎ掛けたリーンハルトより先に、アリスが声を発した。
「もうお帰りになられていたのですね」
「っ……!いや……」
やはり、アリスは変な誤解などしておらず、連絡を怠ったことを気にしていたのか。もしかしたら彼女を傷付けたかもしれないと、今更リーンハルトの胸中を焦燥感が支配する。
(アリスは俺とライネルとの関係を疑うような思考など持ち合わせない、純粋で清らかな女性だ)
リーンハルトはアリスから思いっきり自分達の妄想を繰り広げられているなどとは、露程も疑っていない。
何故、リーンハルトがアリスへの連絡を怠っていたのか──逐一手紙を送り続けたらアリスから鬱陶しがられるかもしれない、という葛藤を抱き、出すのは憚られていた。
そもそもリーンハルトは手紙を書くのも不得手であり、短文が基本である。
考えれば考える程、言い訳のようなことばしか思いつかないが、きちんと弁明して謝罪しなければ──
「任務が予定より早く終わって、昨日と今日は報告のため登城していた」
「そうだったのですか」
「家族、そして婚約者には任務の詳細を伝えても良いとの決まりだっんだが、アリスに伝えるのは躊躇っていた。任務はドラゴンの討伐だったんだ」
「ドラっ!?」
「ドラゴン」などという恐ろしい響きに驚いたアリスは、慌てて両手で口を覆った。
「無事今回もドラゴン討伐は完了したから、安心していい」
「そのような重要な任務に就いていらしたなんて……」
「今回も」ということは、リーンハルトは今までも何度かドラゴン討伐任務を経験していると、推察出来る。
「余計な混乱を招かないよう、公には伏せられているものの、婚約者には話せる状況だったが……。しかしアリスは怖がりだろ?ニール山脈にドラゴンが出現したなんて伝えるのは憚られてしまった。アリスには出来るだけ、心穏やかに日々を過ごしていて欲しいから」
「……」
確かに恐ろしい話である。
ニール山脈とは、隣国から続く巨大な山脈だ。
一体何故そんな場所にドラゴンが出現したのか、アリスには見当も付かない。
「アリスは雷も怖がっているし」
「そ、それは子供の頃の話ですわっ。それに、騎士様の妻になる予定のわたくしが、ドラゴンくらいで怖気付いたり致しませんっ」
「騎士の妻……」
(よかった、婚約を止めるなどと言われなくて……)
リーンハルトは安堵のため息を吐いた。
「帰還するのは来週になると手紙を出したものの、次の日に駐屯地近くの距離までドラゴンが襲来し、結果作戦が早まってしまった。
討伐後は速やかに報告に上がるため、直接作戦に参加した数名で帰還した。手紙は今日屋敷に戻ったら書くつもりだった、本当だ」
「そうでしたの……」
「きちんと手紙をマメに出すべきか悩んだんだ……。いやしかし、手紙を送った次の日に再び出すなんて、しつこいと思われる気がして」
リーンハルト曰く、同僚が毎日恋人に長文の手紙を送っていたら「流石に辟易する」と言われてしまったらしい。
リーンハルトはアリスが思ってた以上に色々と悩み、考えていた。
(何より、そのような命懸けの任務に参加していたのを知らなかったとはいえ、一緒に歌劇へ行けなくて寂しいだなんて……自分の能天気さが恥ずかしくて、むしろ恐ろしいですわっ)
危険と隣り合わせの日々の中にいたリーンハルト。そんな彼に対し、自分はなんて能天気だったのだろう。
羞恥と申し訳なさで顔を真っ赤にしながらも、アリスは自身の思いを口にする。
「わたくし、リーンハルト様がそのような危険な任務に着いていらっしゃるなど、思いもよらなくて……。王都にいるわたし達が平穏に日々を過ごせていたのも、リーンハルト様達のお陰です。心から感謝致します。
お手紙はリーンハルト様のお手隙の際で構いません。仮に毎日のようにお手紙を頂けたら、わたくしなら嬉しくて舞い上がってしまいますが……」
「ありがとう」
「お帰りなさいませ、無事に帰って来て下さって嬉しいです」
少し照れながら微笑む彼女に、リーンハルトは釘付けとなっていた。
「そ、それで……」
恥ずかしそうに口籠るアリスに、リーンハルトは首を傾げる。
「どうした?」
「あの、ライネル様からの指輪は……お受け取りになられたのですか?」
その話題がアリスの口から出て、しばし虚を付かれたリーンハルトだが、先程のやり取りを見られていたのだと思い至った。
「ああ、あの指輪か。前回の討伐の際に、倒したドラゴンの額に付いていた石を使って、作った指輪らしい。
指輪だと小振りだし家で保管するにも、持ち運ぶにも邪魔にならないと、ライネルが記念に揃いで作ってくれたんだ」
「お二人はとても仲が良ろしいのですね」
「まぁ、子供の頃から共に育って来て、ドラゴン討伐を任せられる様になって……無事生還出来たからな。友情以上に、あいつなら安心して背中を預けられると、今では強く思うよ」
二人は友情を超えて、戦友となったようだ。
(そんなお二人に対して、いかがわ……いいえ!決して如何わしい妄想など繰り広げてなどいません。決して)
脳内で必死に否定するアリスの側、リーンハルトはぽつりと呟いた。
「なのに、中々くれないんだ」
「俺の分も作ったくせに」「くれるって言ったのに」などと言いいながら、拗ねたような表情をする彼が年齢よりも幼なく映った。
(何だか可愛らしいですわ、リーンハルト様。……もしかしなくても、指輪を受け取れなかったのは、今さっきわたしが邪魔をしてしまったから……!?きっとそうなのだわ!!)
二人が見つめ合う中、とうとうライネルが指輪を渡す筈だった。
という都合の良い妄想を繰り広げつつ、何という罪深きことをしてしまったんだと、アリスは自分に憤っていた。
その時、リーンハルトが短く発する。
「おい」
「はいっ!?」
先程までとは打って変わって、リーンハルトの冷ややかな声音に驚いてしまったが、彼はアリスではなく遠くを見つめていた。
リーンハルトの視線の先を注視していると、ライネルが姿を現した。
「すまない、なんだか心配になってしまって、つい……」
(もしかしてライバル……!?)
新しい扉を開いてしまったものの、自分がリーンハルトに愛されないのはやはり悲しい。
トキメキと焦りという異なった感情が流れていた。
「すまない、気になって……邪魔をする気はなかったんだが。アリス嬢も、申し訳ない」
「えっ」
ライネルから謝罪を受け、アリスは戸惑う。
(そもそも先に覗いていたのはわたしなのですが)
「では行くよ」
「ライネル様、お待ち下さいっ」
「え?」
「あ、あの、指輪をリーンハルト様に下さいませんかっ?」
「えっ、指輪っ!?」
アリスから指輪の話題を振られ、ライネルは面を食らう。
「アリスもこういってるんだから、観念して俺に渡せ」
どう見ても物を貰う態度ではないリーンハルトだが、ライネルは観念したように指輪を取り出す。
「そうだな、アリス嬢に言われてしまっては……」
アリスが見守る目の前、そして庭園の花々を背景にしてライネルはリーンハルトに指輪を手渡した。
照れながら指輪を手渡してくるライネルを、リーンハルトは優しい眼差しで見つめている。
そしてその様子を食い入る様に見つめ、瞳を潤ませるアリス。
(美形同士の友情は素晴らしいですわ……、やはりどんな歌劇よりも感動してしまいます……!)
「わたくし、このような素晴らしい場面に居合わせる事が出来て、感無量ですわっ」
「何故泣く!?」
何故か涙を流し始めたアリスの肩を抱こうとした瞬間、何かに気付いたリーンハルトが顔を上げる。するとライネルがにやりと、こちらを見ていた。
「にやにやするなっ」
「悪い悪い、邪魔者は退散するよ」
リーンハルトがライネルに詰め寄り抗議する、そんな様子を見てアリスは脳内で黄色い歓声を上げる。
(ち、ちかっ、近いですわ!お二方の距離がとっても近いですわっ、どうしましょう、キャー!ご馳走様です!)
ライネルが場を去った後も、アリスが余韻に浸っていると、頬に温かな何かが触れた。
リーンハルトの手だ。そのまま彼の指がアリスの頬を撫で、涙を拭ってくれる。
「っ!?リーンハルト様っ……」
「君は本当に優しい人だな」
「え?」
「些細なことで泣くなんて、情緒が豊かで優しい証だ」
(なんか、ごめんなさい)
何だか急激に申し訳なくなって来た。
◇
本日、アリスはフォンテーヌ家の庭園にリーンハルトと共に、ライネルを招待していた。
庭園の花々は盛りを迎えている。
ライネルは隣国のショコラが好きと記憶しており、取り寄せた物をお茶会に用意した。
庭園のガーデンテーブルの上には、三人分のティーセットにショコラ、果物を載せた小ぶりのタルトなどが並ぶ。
リーンハルトが意外に甘い物好きなのは、婚約者であるアリスは当然把握している。
椅子に腰掛けるリーンハルトとライネル──の二人を木の陰から生暖かく見守るアリス。
(ああ、このままずっと、お二人のやり取りを眺めていたい……。覗きではないです、断じて違います。観察です)
欲望のまま延々と観察していたいのは山々だが、ずっとお客様をお待たせする訳にはいかない。
(邪魔はしたくありませんが、致し方ありませんわ。ゆっくり近づくことにしましょう。ゆ〜っくり)
微妙な速度でアリスが進み出した瞬間、ライネルがリーンハルトの方へ身を乗り出した。
「あ、珍しい小鳥」
「何処?」
「ほらあそこ」
リーンハルトにぴたりと密着したライネルは、地面を啄む青い小鳥を指差した。
(ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうます)
アリスは神に感謝した。
◇
お茶会を終え、ライネルが一足先にフォンテーヌ家の屋敷を出た後も、リーンハルトとアリスは二人の時間を過ごしていた。
「今日はライネルまで持て成してくれて、ありがとう」
「リーンハルト様の大切なご友人ですから」
「あいつに、そこまで気を使わなくても……でも、喜んでたよ」
言いながら頬を染めて、視線を逸らすリーンハルト。そんな彼の様子を見たアリスは、必死に自身の興奮を抑えようと奮闘していた。
(ツンデレ!?ここに来てツンデレ属性まで発揮して下さいますの!?お可愛いらしいですわ!)
脳内がやかましいアリスに、リーンハルトの真摯な声が落ちてくる。
「そういえば、もう一つ謝らなくてはいけないことがあるんだ」
「何でしょう?」
「ドラゴン討伐の最中、アリスから貰ったハンカチを落としてしまって……。お守りとして大切に肌身離さず身に着けていたんだけど、せっかく贈ってくれたのに申し訳ないっ」
頭を下げるリーンハルトに、アリスは穏やかに微笑む。
「まあ、そうでしたの。リーンハルト様のためなら、何十枚でも刺繍致しますわ。だからどうかお気になさらないで」
「本当か!?ありがとう!」
勢いよく両手を握られたアリスは、虚を付かれたのち顔を真っ赤にさせながら狼狽した。
「ふぁ、はいっ」
(ち、ちちちちちかっ、近いですわ!距離が近すぎますわー!)
いざ自分の元へリーンハルトが距離を詰めてくると、ライネルとのやり取りを生温かく見守っていた時とは、比べ物にならない程心臓が早鐘を打ちつけてくる。
もはや壊れてしまうのではないかと、心配になる程だ。
「それと、もし良ろしければ……ライネル様から頂いた指輪を入れるための小袋も、刺繍を添えて贈らせて頂きたいと……」
「アリスは何で優しいんだ」
感極まったリーンハルトに強く抱きしめられたアリスは、身体を硬直させた。
我に返ったリーンハルトは、そんな婚約者に申し訳なさそうに尋ねる。
「ごめん、思わず……嫌じゃなかった……?」
「幸せすぎて死にそうです」
「死!?」
(やはりライネル様には申し訳ないですが、リーンハルト様の一番はわたくしじゃないと絶対に嫌です)
アリスは幸せを噛み締めつつ──
これからもリーンハルトとライネルの友情を生暖かく、見守っていくのであった。