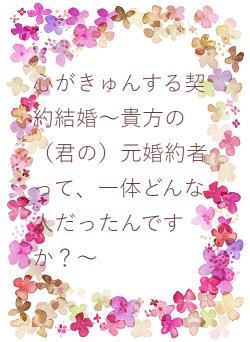雪解けの白い結婚 〜触れることもないし触れないでほしい……からの純愛!?〜
最終話 そして、ここから
私たちは次の休日にフォーウッド家に訪れた。お姉様やリリーも駆けつけてくれて、夕食を皆で食べる。ただそれだけのことだったけれど、両親とリリーが大泣きするものだから面食らってしまった。
「セレンは愛されて育ったんだね」
私たちに用意された客室に案内された後、レインは嬉しそうに言った。
「でも私は今までその気持ちを返せていなかったわ」
「そうかな?セレンが思うよりも、彼らはずっとセレンのことを知ってくれているよ」
「……本当にそうね」
レインに出会ったから。だから人を愛することができた。
前世の私の苦しみが心の奥に凍って刺さったままだった。ずっと溶けずに固まっていた気持ちを、誠実に丁寧にあたためてくれたのはレインの愛だ。
でも彼に出会う前から、少しずつ溶かされていたものがあったのかもしれない。
職場の人や、家族。私が知ろうとしなかっただけで。
「ああでも。セレンが頼りにすればもっと喜ばれそうだね」
「そうね」
私は先程のお父様の表情を思い出して笑った。
リスター領の騒動で色々と依頼したことを父は大変喜んでいた。
人生で私が父にねだったものは、王都の学校に通いたいということと、護衛と、ジェイデン様を尾行する人材と、アプリコット鉱石の見積もりだけだったらしいのだ。それは娘としては全く可愛げのないものたちばかりなのにあれほど喜んでくれるとは。素直に甘えることも親孝行なんだ。
今まで気持ちを返せていなかった分、これからたくさん返そう。きっと今夜のように受け入れてくれるはずだ。
「学校については二人とも賛成してくれたわね。お祖父様はまだまだ死ねん!って生きる希望になっていたわ」
お祖父様が喜びそうな案だとは思っていたけど、こちらの予想以上に喜んでいて。いつも寡黙なお祖父様しか見たことのない姉妹たちは少し驚いていた。
「そうだ。そろそろジェイコブ様の部屋に行こうか」
「そうしましょう」
私たちはそれぞれお祖父様にお土産を持って帰ってきていたのだ。
私からのお土産は、この数か月大活躍してくれた卵!エピソードも添えればますます喜んでくれるだろう。ずっと勉強と仕事ばかりしていた私にとっては冒険譚のような物なのだから。
・・
いつ帰ってきてもお祖父様の部屋は私をあたたかく出迎えてくれる。
幼い頃からのクッションはいつもの定位置にいて私を歓迎してくれた。
棚に並んでいる魔法具たちも、ひときわ丁寧に飾られている私が制作に関わった魔法具たちも、積まれた論文や専門書も、お祖父様のロッキングチェアも。全てが私におかえりと囁いてくれている。
紙と少し埃っぽい匂いがするこの部屋は、いつまでたっても私の心の基地だ。
「レイン、久しぶりだな」
お祖父様はロッキングチェアから立ち上がって、私たちを出迎えてくれた。
「お祖父様。レインは夕食の席にもいたわよ」
まさか覚えていないのだろうか。年齢に不安を感じて私が尋ねると、お祖様は心外だと文句を返した。
「老いぼれジジイにするな。覚えているに決まっているだろう。レインがこの部屋に来たのが久しぶり、という意味だ」
「どういうこと?」
「十年ぶりですかね」
レインは部屋を懐かしそうに見渡した。
「レイン、来たことがあるの?」
「以前言っただろう?魔法の楽しさをジェイコブ様に教えていただいたって」
「レインは一度セレンの婚約者候補にあがったこともあるんだ」
お祖父様が楽しげな顔になる。普段は表情をあまり変えないお祖父様が魔法のことでもないのにやけに楽しそうだ。
「私とレインは会ったことがあったの?」
「いや、ないよ。フォーウッド家には何度か来たけれど、ご令嬢を紹介してもらったことはないから。
父が商談で他領を訪れる時、よく同行させられたんだ。領地を継がせるつもりはなかったから、他領の婿にできないか考えていたらしい。アメリアはセオドアと結婚するから、私を使って他家と縁を結ぼうとしていたみたいだね」
「そうそう、フォーウッド家にも何度も来ていたな。我が家にはちょうど婚約者がいないセレンがいたから。お前の両親はお茶会にレインを招待していて引き合わせようとしていたな」
「まあ……」
私が誰とも会いたがらず、お茶会にも参加しないでいた裏にレインがいたとは。
その時に出会っていたとしても、私とレインは何も始まらなかったとは思うけれど。
「私はご令嬢に振られて――それがセレンだとは知らなかったけど――振られたおかげで、ジェイコブ様に魔法の楽しさを教えてもらえたよ。あの時のセレンに感謝だね」
レインもお祖父様と同じいたずらっ子な表情になる。
レインが魔法のことに関しては子供っぽくなるのはお祖父様の影響だったのか。――私もそうだけれど。
「父の商談を待っている時にジェイコブ様が魔法書を貸してくださったのがきっかけ。振られたから暇だったしね」
「それでレインはお祖父様を知っていたのね」
「うん。だからセレンに結婚を持ちかけたのは、フォーウッド家のご令嬢だったからだというのも正直ある。フォーウッド家にはいい思い出があったから」
白状するようにレインは言った。最初に話しかけてくれたきっかけがお祖父様だったとは。それはさすがに申し訳なくて言えなかったともレインは付け加えた。
「どこかでセレンを見たことがあると思っていたんだ。仕事関係だと思っていたけれど、この館のどこかですれ違っていたのかもしれないね」
レインの言葉にお祖父様は声を出して笑った。
「この館のどこかではなく、お前たちはこの部屋で出会っていたよ!まさか覚えていなかったのか!」
これにはレインも驚いたようにお祖父様を見た。もちろん私も一切覚えはない。お祖父様はおかしそうに私たちを見比べる。
「お前たちは子供の頃から本当に魔法バカだったようだな。
まあ……そうだな。この部屋は物も多いし、気づかないということもあるか……。セレンはいつものクッションのあたりで、レインはこっちのソファで本を読んでいたかな」
「まさか……」
「同じ空間にはいたけれどお互い存在を認識していなかったとは。本当に魔法のことしか考えていなかったんだな。五回は居合わせただろうに!」
お祖父様は一人おかしくて仕方ないと言った様子。レインを見ると口をあけて間抜け面になっているけれど、きっと私も同じ顔をしているに違いない。でも、そうだ。私もレインも夢中になると周りは一切見えなくなるのだから。
「それでお祖父様はレインとの結婚に反対しなかったのね」
「二人とも、何かに傷ついている気がした。それを和らげてくれる相手がいればいいなとはずっと思っていたんだ」
一人でしばらく笑っていたお祖父様は、優しく私たちを見た。
「その相手が見つかったんだな」
レインが大きく頷くとお祖父様は目を細めた。
この部屋は私の心の基地だ、それはずっと変わらない。でも、私の心を預ける場所は広がっていく。もう怖くなかった。
・・
目の前には小さな教会があった。
翌日、王都に帰る前に寄りたいところがあるとレインが言い、メインの公道を曲がった。
住宅地をさらに進んでいった先に小さな林があり木々をかき分けるように木造の教会があった。目的地にしなければ見落として通り過ぎてしまうほどの小さな教会だ。
「ここもレイン少年の思い出の地だったりする?」
「いや、初めて来た場所だよ」
「じゃあどうしてここに?」
「……許可はもらっているから入ろうか」
レインは答えてくれずに扉を開いた。
中に入ると木の香りが身体に入り込んでくる。中は薄暗いけれど、窓から差し込んだ光が木材の建物を優しく照らしていた。
レインは奥まで進み、小さな十字架の祭壇までたどり着いた。私も彼の後に続き、私たちは向かい合うように並んだ。
「セレン、二人だけの挙式をもう一度しないか」
「えっ?」
「ドレスも何もないけれど」
差し込んだ光がレインのことも包む。その日差しのように暖かな瞳で私を見つめる。
「挙式をもう一度?」
「うん。以前の挙式は簡単に済ませてしまったし。偽りの愛を誓ってしまったから」
真面目なレインらしい提案だ、彼は区切りをつけたがるところがある。
「今日からまた始めるのね」
「うん。ああ、今日までが嘘だったと言いたいわけじゃないよ」
「わかっているわ」
どこまでも誠実なレインがおかしくて笑みがこぼれてしまう。
「……それに、先日セオドアとアメリアの挙式でうらやましそうな顔をしていた気がしたから」
「そ、そうね……」
まさかキスが羨ましかったなどは言えず曖昧に返す。あの表情を見られていたとは恥ずかしい。
照れている私には気づかずレインは真面目な顔をして私を見つめるから、私も姿勢をピンと正した。
「誰かが証人にならなくていい。セレンに誓うよ、ずっとこの命ある限り、貴女を愛し大切にすることを」
誰もいない小さな森の教会で。誰かに宣言することもなく、レインは私だけに誓ってくれる。
「私も。レインをずっと愛し続けます」
二人の小さな誓いは、静かな教会に響いて溶けた。
「セレン、目を閉じてくれる?」
「ええ」
戸惑いながらも目を閉じると、私の肩にレインの手が乗せられた。
彼の足が一歩出て私のつま先に当たるのを感じる。目を瞑っていて何も見えないけれど、彼がどのように私に触れてくれているか全て伝わってくる。
まずは額に温度を感じる。ああ、先日私が羨ましく見ていたキスをレインは気付いていたのかもしれない。
次に唇にそっと熱が伝わる。すぐ離された後、もう一度だけ触れた。
目を開けると、潤んだ瞳のレインがいる。私はたまらなくなって思わず彼の頬に手を伸ばした。
「やっと触れられた」
レインがこぼす言葉に胸がどうしようもなく痛い。
胸の一番奥にある刺さったままの氷が全て溶け切る音がした。
そしてそれは柔らかく私の胸に広がっていき、溶けた気持ちは涙に変わる。
私の心を溶かして、涙をぬぐってくれる人がそこにいた。
レインが瞼を閉じると、彼の睫毛から涙が一粒転がって。私の指がそれを掬った。
……やっと私もレインの全部に触れられた気がした。
「嬉しい」
おでこがこつんと当たる。「あの時セレンが目を閉じるから我慢するのが大変だった」
「あの時って、花火の時……?」
恥ずかしさで顔から火が出てしまいそうだ。キスしたい気持ちはやっぱり見抜かれていたんだ。
「そんな……我慢しなくても。してくれたらよかったのに……」
「期待してくれてた?でもこうして誓い直してからにしたかったから」
「ふふ、真面目過ぎるわ」
笑って目を細めるとまた涙がこぼれた。レインといると泣いたり、笑ったり忙しい。でもそんな自分が好きだ。
「大好きだよ」
もう焦らなくてもいい。急いで治療をしなくてもいい。
心に触れて、触れてもらえた。それが何より嬉しい。
柔らかな光が眩しくて、私はもう一度だけ目を閉じた。
fin