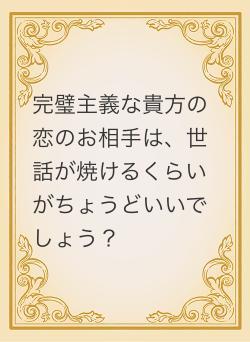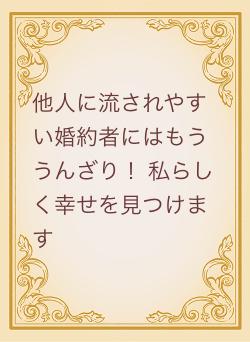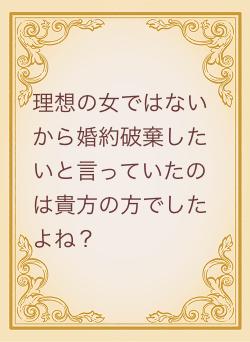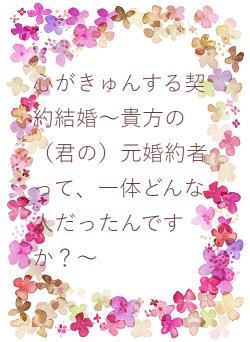最強騎士様は素直じゃないけど、どうやら私は溺愛されているようです
15.雨が上がったら
「父ので良かったら着る? 少し大きいかもしれないけど」
コレットが大きなシャツを持ってリアムに見せた。
「大丈夫、すぐ乾くさ。……それよりコレット、君の方が濡れてるじゃないか」
コレットの髪を雨の雫が伝い落ちている。貸して、とタオルを手に取ると、リアムはコレットの髪を乱暴に拭いた。
「まったく……風邪を引いたらどうするんだ」
「また怒るのね」
「私は君が心配なんだ」
無防備な顔を覗き込むと、ぐりぐりと大きな丸い瞳が揺らぐのが見えた。リアムは短く、唇を重ねた。コレットは一瞬驚いたように目を見開いて、すぐに照れたように笑った。
「私は本気だよ、コレット。さっき言ってただろう、揶揄っていたんじゃないかって」
リアムはポツリポツリと話し始めた。
「初めて君を見たのは、実は決闘の日じゃないんだ」
ふっと、思い出したようにリアムは笑った。
「仕事仲間から評判のパン屋があると聞いてね。そこに君がいた」
やはりアベラの言う通り以前から店に通ってくれていたのだ。全く気付くことが出来なかった。
「こんな仕事だから、心が酷く荒んでしまう日もある。でも君の笑顔に癒されていた。誰にでも屈託なく笑い掛ける君は、天使のようだった。遠くから見てるだけで十分だったよ」
確かめるように、コレットの頬を優しく撫でた。
「……あの決闘の日、君がいたことに気付いた。泣いている君を見て心が痛かったよ。君のような心の美しい人間が見るようなものじゃない。……薔薇を贈ったとき、君がハンカチを差し出してくれただろう。それで決めたんだ。これは神様がくれたチャンスだって」
目を見て優しく微笑んだ。綺麗な深い緑色の瞳にコレットが映っている。
「君の笑顔を守りたい」
リアムはそう言って、小さく溜息を吐いた。
「いつもそう思ってるのに、いざ君を目の前にすると上手い言葉も見つからない。怒ってるなんて言われる始末さ。本当に情けないよ」
「上手い言葉じゃなくてもいいわ。でもたまには優しくして」
「ああ、もちろんだ。君も何でも話してほしい、分かっただろう。私がどれほど、君を愛してるか」
コレットの手にその手をそっと重ねると、左手の薬指に優しく唇を落とした。
「ええ、とっても」
コレットは返事をするのもやっとだった。さっきとは違う、嬉しさからまた涙が溢れてしまった。
「……そうだ、君にカードを書いたんだ」
リアムはポケットから小さなカードを取り出して、コレットにそっと差し出した。
「なかなか口に出して愛を囁けないから……今はこれで許して欲しい。どうか私が帰った後に読んでくれ」
コレットはカードを受け取ると、流れるようにカードを開けて顔をくしゃくしゃにさせて笑った。
「ああ、もう! 私が帰ってからだと……」
「私も愛してるわ、リアム」
そう言って、コレットはリアムの頬に優しくキスをした。
窓の外の雨はいつの間にか止んでいる。
雲の切れ間から、二人を未来を照らすような暖かい光が差し込んでいた。
コレットが大きなシャツを持ってリアムに見せた。
「大丈夫、すぐ乾くさ。……それよりコレット、君の方が濡れてるじゃないか」
コレットの髪を雨の雫が伝い落ちている。貸して、とタオルを手に取ると、リアムはコレットの髪を乱暴に拭いた。
「まったく……風邪を引いたらどうするんだ」
「また怒るのね」
「私は君が心配なんだ」
無防備な顔を覗き込むと、ぐりぐりと大きな丸い瞳が揺らぐのが見えた。リアムは短く、唇を重ねた。コレットは一瞬驚いたように目を見開いて、すぐに照れたように笑った。
「私は本気だよ、コレット。さっき言ってただろう、揶揄っていたんじゃないかって」
リアムはポツリポツリと話し始めた。
「初めて君を見たのは、実は決闘の日じゃないんだ」
ふっと、思い出したようにリアムは笑った。
「仕事仲間から評判のパン屋があると聞いてね。そこに君がいた」
やはりアベラの言う通り以前から店に通ってくれていたのだ。全く気付くことが出来なかった。
「こんな仕事だから、心が酷く荒んでしまう日もある。でも君の笑顔に癒されていた。誰にでも屈託なく笑い掛ける君は、天使のようだった。遠くから見てるだけで十分だったよ」
確かめるように、コレットの頬を優しく撫でた。
「……あの決闘の日、君がいたことに気付いた。泣いている君を見て心が痛かったよ。君のような心の美しい人間が見るようなものじゃない。……薔薇を贈ったとき、君がハンカチを差し出してくれただろう。それで決めたんだ。これは神様がくれたチャンスだって」
目を見て優しく微笑んだ。綺麗な深い緑色の瞳にコレットが映っている。
「君の笑顔を守りたい」
リアムはそう言って、小さく溜息を吐いた。
「いつもそう思ってるのに、いざ君を目の前にすると上手い言葉も見つからない。怒ってるなんて言われる始末さ。本当に情けないよ」
「上手い言葉じゃなくてもいいわ。でもたまには優しくして」
「ああ、もちろんだ。君も何でも話してほしい、分かっただろう。私がどれほど、君を愛してるか」
コレットの手にその手をそっと重ねると、左手の薬指に優しく唇を落とした。
「ええ、とっても」
コレットは返事をするのもやっとだった。さっきとは違う、嬉しさからまた涙が溢れてしまった。
「……そうだ、君にカードを書いたんだ」
リアムはポケットから小さなカードを取り出して、コレットにそっと差し出した。
「なかなか口に出して愛を囁けないから……今はこれで許して欲しい。どうか私が帰った後に読んでくれ」
コレットはカードを受け取ると、流れるようにカードを開けて顔をくしゃくしゃにさせて笑った。
「ああ、もう! 私が帰ってからだと……」
「私も愛してるわ、リアム」
そう言って、コレットはリアムの頬に優しくキスをした。
窓の外の雨はいつの間にか止んでいる。
雲の切れ間から、二人を未来を照らすような暖かい光が差し込んでいた。