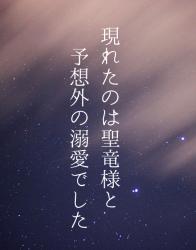前奏曲にしては重すぎる執着愛でした
「律さん、起きていたのか」
「はっ……はい、すみません」
何を謝っているのか自分でもよくわからないまま、ばっと身を起こして袷の前で両手を握りしめる。その仕草に橘さんは僅かに眉を八の字にした。
「……怯えさせるつもりはなかったんだが、な」
「あ、あああの、桃次郎くんが探していた懐中時計って、橘さんのですか」
気まずさを誤魔化すように早口でそう問えば、彼は一瞬だけ疑問を顔に浮かべたものの、何か察したように顎をさすった。
「……ああ。あれはきみの顔を知らなかったからな。私と同じものを持つ女性をお連れするようにと、きみの職場がある、あのビルの前で張らせていた」
「どうして……」
それはいろんな疑問をすべて含んだ問いかけだった。
何故私を探していたのか。
何故私の職場を知っているのか。
何故私を助けてくれたのか。
何故私に──好意を抱いているような触れ方をしたのか。
「まずは礼を言おう。律さんはこの時計をいたく気に入ってくれているようだな。感謝する」
にこりと微笑まれて一瞬毒気を抜かれた。
しかし、続いての言葉にまたもや身を固くすることになる。
「私は幾つか事業を手がけているのだが、一般大衆向けの、それも女性向けの品には縁がなくてね。どうにも行き詰まったことがあったのさ」
いわゆるシノギというヤツですか、と口から出かかったものの、真一文字に唇を引き結んで飲み込んだ。肯定されるのはやはり怖い。
「知人のツテで展示会の枠を貰った。そこであるひとりの女性が──後は言わずともきみも知っている話だな」
思い出しかけていた記憶と、彼の語りが二重写しのようにダブって重なって──ぴたりと嵌る。
「え……?」
「無論、接客は他の者に任せていたが……バックヤードからきみの様子は見て取れた。何やら楽しげに頬を紅潮させて試着している笑顔は──非常に魅力的だった」
見ていた、の? あの時?
「音楽をモチーフにしたデザインを発注したのは偶然だったが、律さんの反応を見て本腰を入れることにした。本家の紳士物にも取り入れたが、これが好評でね。男女問わず、旋律で装うことは心を浮き立たせるようだ」
そこで言葉を切った橘さんは私の手首に目を向ける。
「一目惚れとは言え、私にも立場がある。きみのひととなりを充分に調べ終わり、初めは食事にでも誘うつもりだった。しかしきみが倒れていたのは予想外でね……こうして我が家においで頂くことになったのだが、嬉しい誤算だったな」
「ご、誤算って」
「ああ、きみにしてみれば体調が万全でないのだから嬉しくは無いな。だが、それも含めて面倒は見るつもりだから安心しなさい。隣の部屋に医師を呼んである。この後診てもらうといい」
上機嫌なのか饒舌になる橘さんの口からは、私を絡め取ろうとする言葉が重なり合っていくつも結び目を作り、雁字搦めの罠が張り巡らされていく。
「ま、待ってください。私、もうお暇します。病院も自分で行けます。薬もそこで処方してもらいますから」
「遠慮するな。別に闇医者じゃない。腕は確かだよ。それとも」
すうと瞳が細められる。
「私の好意を無碍にするのか」
立ち上がりかけた腰が抜けて、すとんと落ちる。
微笑んでいるのに威圧感で潰されそうだ。
「……ああ、震えているな」
この震えがぶり返した発熱なのか、はたまた怯えなのか、わからないひとではないはずだ。
「きみのことは、きみが思う以上に調べてある。最近、後輩との接し方に悩んでいるらしいな」
はっと顔を上げて彼を見る。
彼は表情ひとつ変えずに言葉を続ける。
「勤務体系、及び評価にもご不満かな。才能があっても使い潰されては元も子もない。どうにも律さんは、他人の仕事を押しつけられるきらいがあるようだな。こなせてしまうのだから重宝されるのも道理だが、見合った対価が無ければ一方的な搾取だ」
「な、なんで、それを」
「言っただろう? いくつか事業を手がけていると」
そう言われて、最近本部の視察担当者が変わっていたことを思い出す。評価に第三者の目を入れるため、外部委託に切り替えたと説明を受けたのだ。
そしてその担当者に後輩指導の現場を見られていたのは、記憶に新しい。
「見張って……いたんですか」
「心外だな。見守っていたと言ってくれ。だからこそ、きみにとって好条件での仕事も紹介できるのだからな」
背筋にゾワゾワしたものが駆け上がっては、うなじのあたりでひっきりなしに爆ぜている。
プライベートも仕事も、全部知っているというの?
「し、仕事に不満があるのは確かにそうですけど、100パーセント満足できる職場なんてありえません。仮にあったとしたって、転職なら自分でなんとかします」
「そうか。自立心旺盛なのは頼もしいな」
はは、と乾いた笑みを向けられる。
距離を保っているはずなのに、丸裸にされている錯覚で落ち着かない。
「……律」
ひとこと、名前を呼ばれる。
どくんと跳ねた鼓動を、胸の前で組んだ手で抑え込む。
「響きの良い、凛とした名前だ。ご両親の教養と愛情が感じられる」
「…………あ……」
単なる虚仮威しか、それともそこまで手中に収めているのか。判断する術を持たない私は、彼の唇がそれ以上を紡がないように祈りながら見つめるしかない。
目の前がチカチカしてくる。
うまく息が吸えない。
耳の後ろでどくどくと鼓動が逃げ出そうと暴れている。
ぐらりと橘さんの姿が歪んで──
視界が回った。
「おっと」
ふらついた後頭部を抱き寄せられて、橘さんの胸板に額を寄せる。
「病人には刺激が強すぎたな。もう今日は休みなさい」
「……は…………」
ここで頷いてはだめだ。
突き飛ばしてでも、噛みついてでも、この腕から逃げなくては。
懸命に手を胸板から突っ張ってかぶりを振る。
目眩がして力が緩むと、そっと手首を握られた。
おそるおそる開いた視界に映る彼の骨ばった長い指は、腕時計の上から手首を掴んでもまだ余裕がある。
聞こえるはずのない秒針の音がカウントダウンのように頭に響く。
「律」
「や……」
「許してくれるなら、私はきみにすべてを──」
何を許せと請われているのか、曖昧すぎる懇願に彼の傲慢さと狡猾さを感じ取って、ただひたすらに首を振る。
体重をかけられて傾く視界の隅で、厚い胸板を懸命に拒んでいた手が袷をずらしてしまう。
非日常を生きるひとの証にふるりと怯えて、反った首に唇が寄せられて──ひくん、とわなないた首は、静かに上下した。
覆い被さってきた鷹は侵蝕を始める。
腕時計の文字盤に描かれた旋律は、知らないメロディを奏で始めた。
「はっ……はい、すみません」
何を謝っているのか自分でもよくわからないまま、ばっと身を起こして袷の前で両手を握りしめる。その仕草に橘さんは僅かに眉を八の字にした。
「……怯えさせるつもりはなかったんだが、な」
「あ、あああの、桃次郎くんが探していた懐中時計って、橘さんのですか」
気まずさを誤魔化すように早口でそう問えば、彼は一瞬だけ疑問を顔に浮かべたものの、何か察したように顎をさすった。
「……ああ。あれはきみの顔を知らなかったからな。私と同じものを持つ女性をお連れするようにと、きみの職場がある、あのビルの前で張らせていた」
「どうして……」
それはいろんな疑問をすべて含んだ問いかけだった。
何故私を探していたのか。
何故私の職場を知っているのか。
何故私を助けてくれたのか。
何故私に──好意を抱いているような触れ方をしたのか。
「まずは礼を言おう。律さんはこの時計をいたく気に入ってくれているようだな。感謝する」
にこりと微笑まれて一瞬毒気を抜かれた。
しかし、続いての言葉にまたもや身を固くすることになる。
「私は幾つか事業を手がけているのだが、一般大衆向けの、それも女性向けの品には縁がなくてね。どうにも行き詰まったことがあったのさ」
いわゆるシノギというヤツですか、と口から出かかったものの、真一文字に唇を引き結んで飲み込んだ。肯定されるのはやはり怖い。
「知人のツテで展示会の枠を貰った。そこであるひとりの女性が──後は言わずともきみも知っている話だな」
思い出しかけていた記憶と、彼の語りが二重写しのようにダブって重なって──ぴたりと嵌る。
「え……?」
「無論、接客は他の者に任せていたが……バックヤードからきみの様子は見て取れた。何やら楽しげに頬を紅潮させて試着している笑顔は──非常に魅力的だった」
見ていた、の? あの時?
「音楽をモチーフにしたデザインを発注したのは偶然だったが、律さんの反応を見て本腰を入れることにした。本家の紳士物にも取り入れたが、これが好評でね。男女問わず、旋律で装うことは心を浮き立たせるようだ」
そこで言葉を切った橘さんは私の手首に目を向ける。
「一目惚れとは言え、私にも立場がある。きみのひととなりを充分に調べ終わり、初めは食事にでも誘うつもりだった。しかしきみが倒れていたのは予想外でね……こうして我が家においで頂くことになったのだが、嬉しい誤算だったな」
「ご、誤算って」
「ああ、きみにしてみれば体調が万全でないのだから嬉しくは無いな。だが、それも含めて面倒は見るつもりだから安心しなさい。隣の部屋に医師を呼んである。この後診てもらうといい」
上機嫌なのか饒舌になる橘さんの口からは、私を絡め取ろうとする言葉が重なり合っていくつも結び目を作り、雁字搦めの罠が張り巡らされていく。
「ま、待ってください。私、もうお暇します。病院も自分で行けます。薬もそこで処方してもらいますから」
「遠慮するな。別に闇医者じゃない。腕は確かだよ。それとも」
すうと瞳が細められる。
「私の好意を無碍にするのか」
立ち上がりかけた腰が抜けて、すとんと落ちる。
微笑んでいるのに威圧感で潰されそうだ。
「……ああ、震えているな」
この震えがぶり返した発熱なのか、はたまた怯えなのか、わからないひとではないはずだ。
「きみのことは、きみが思う以上に調べてある。最近、後輩との接し方に悩んでいるらしいな」
はっと顔を上げて彼を見る。
彼は表情ひとつ変えずに言葉を続ける。
「勤務体系、及び評価にもご不満かな。才能があっても使い潰されては元も子もない。どうにも律さんは、他人の仕事を押しつけられるきらいがあるようだな。こなせてしまうのだから重宝されるのも道理だが、見合った対価が無ければ一方的な搾取だ」
「な、なんで、それを」
「言っただろう? いくつか事業を手がけていると」
そう言われて、最近本部の視察担当者が変わっていたことを思い出す。評価に第三者の目を入れるため、外部委託に切り替えたと説明を受けたのだ。
そしてその担当者に後輩指導の現場を見られていたのは、記憶に新しい。
「見張って……いたんですか」
「心外だな。見守っていたと言ってくれ。だからこそ、きみにとって好条件での仕事も紹介できるのだからな」
背筋にゾワゾワしたものが駆け上がっては、うなじのあたりでひっきりなしに爆ぜている。
プライベートも仕事も、全部知っているというの?
「し、仕事に不満があるのは確かにそうですけど、100パーセント満足できる職場なんてありえません。仮にあったとしたって、転職なら自分でなんとかします」
「そうか。自立心旺盛なのは頼もしいな」
はは、と乾いた笑みを向けられる。
距離を保っているはずなのに、丸裸にされている錯覚で落ち着かない。
「……律」
ひとこと、名前を呼ばれる。
どくんと跳ねた鼓動を、胸の前で組んだ手で抑え込む。
「響きの良い、凛とした名前だ。ご両親の教養と愛情が感じられる」
「…………あ……」
単なる虚仮威しか、それともそこまで手中に収めているのか。判断する術を持たない私は、彼の唇がそれ以上を紡がないように祈りながら見つめるしかない。
目の前がチカチカしてくる。
うまく息が吸えない。
耳の後ろでどくどくと鼓動が逃げ出そうと暴れている。
ぐらりと橘さんの姿が歪んで──
視界が回った。
「おっと」
ふらついた後頭部を抱き寄せられて、橘さんの胸板に額を寄せる。
「病人には刺激が強すぎたな。もう今日は休みなさい」
「……は…………」
ここで頷いてはだめだ。
突き飛ばしてでも、噛みついてでも、この腕から逃げなくては。
懸命に手を胸板から突っ張ってかぶりを振る。
目眩がして力が緩むと、そっと手首を握られた。
おそるおそる開いた視界に映る彼の骨ばった長い指は、腕時計の上から手首を掴んでもまだ余裕がある。
聞こえるはずのない秒針の音がカウントダウンのように頭に響く。
「律」
「や……」
「許してくれるなら、私はきみにすべてを──」
何を許せと請われているのか、曖昧すぎる懇願に彼の傲慢さと狡猾さを感じ取って、ただひたすらに首を振る。
体重をかけられて傾く視界の隅で、厚い胸板を懸命に拒んでいた手が袷をずらしてしまう。
非日常を生きるひとの証にふるりと怯えて、反った首に唇が寄せられて──ひくん、とわなないた首は、静かに上下した。
覆い被さってきた鷹は侵蝕を始める。
腕時計の文字盤に描かれた旋律は、知らないメロディを奏で始めた。