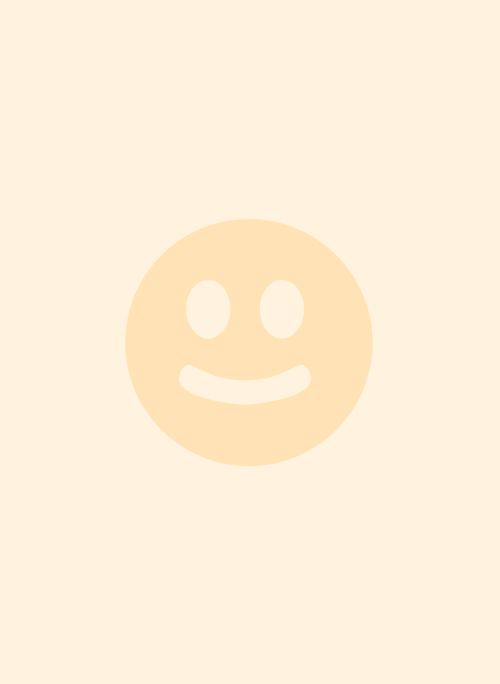七夕の日の恋「一年に一度の恋」
平成28年の、夏である。
その日は、7月6日だった。
連日の、猛暑で、夏バテで、僕は、まいっていた。
子供の頃は、夏が来ると、単純に嬉しかった。
しかし、大人になると、夏になるのは、子供の時と、同様に、嬉しかったが、連日の猛暑で、夏バテして、いささか、夏の到来を、素直には、喜べなくなっていた。
それと、もう一つ、嫌なことが、あった。
二年に一度の、車の車検の期限が、1週間後の、7月14日で、切れるからである。
今年は、車検が切れる年だった。
だいたい、車検にかかる費用は、10万円くらいだろう、と思っていた。
いつも、そうだったからだ。
しかし、去年、ある時、バックした時に、電信柱に、車をぶつけてしまい、車の後ろが、少し凹んでしまった。その時から、電気系統が故障したのか、ドライブにギアチェンジすると、「D」の、ランプが点かなくなった。
しかし、運転には、問題ないので、そのまま、乗っていた。
僕の車は、旧型マーチだった。
今回の車検は、いくら、かかるのだろうか、と、日産のディーラー店に、入ってみた。
車検は、7月14日で、切れるから、あと、1週間である。
「車検にかかる費用、見積もってもらえませんか?」
と僕は聞いた。
「はい。わかりました」
と、店の人が言った。
店では、新車を売っているが、店の裏に、修理場があって、修理工が、働いている。
僕は、自動車の、修理工を立派だと思っていた。
毎日、油にまみれ、汚れた服で働いて。
働く、とは、ああいうことを、言うものだ、と僕は思っていた。
一時間、くらいして、店の人が、やって来た。
それで、見積もりの明細を見せてくれた。
部品交換と、工賃が、バーと、並んでいて、合計で、18万円だった。
僕は、あせった。
僕は、車検にかかる費用が、10万、程度なら、買い替えることなく、乗り継ごうと思っていた。
僕は、車の事情については、素人だか、それでも。18万ともなれば、もう少し、金を出せば、中古車が買える。
ボロボロになった、車を、18万も出して、乗り続けるよりは、あらたに中古車を買い替えようと、思った。
僕は、スズキのラバンが欲しかったので、スズキのディーラー系の中古車店に行くことに決めた。
ディーラー系の中古車店は、アフターサービスがいいからである。
そのぶん、値段が、高目だが、表示価格10万とかの、激安車は、諸経費が10万円、くらい、かかって、合計20万円くらいになり、1年、以内に、色々と、故障個所が出てきて、結局は、修理に次ぐ、修理となってまう。
なので、多少、高目でも、信頼できる、ディーラー系の中古車店の中古車を買った方が、いいと信じ込んでいた。
国道467号線は、中古車通り、と、言われるくらい、道路の左右に、無数の中古車店がある。
しかし、ある中古車店で、表示価格1万円の、激安中古車が目に止まった。
ラパンだった。
激安中古車なんて、走行距離は長いし、年式も古いし、色々と、性能に問題があって、修理しなくてはならないから、結局は、高くつく。
しかし、そのラパンは、車検2年つき、で、年式も、平成26年式で、走行距離も、1万km、と、信じられないくらい、いい条件だった。
僕は、一応、店に入ってみることにした。
僕は、中古車店に車を入れた。
「こんにちはー」
僕が、大きな声で、呼ぶと、中から、男が出てきた。
「はい。私が、この店の店長です。ご用は何でしょうか?」
男が言った。
「店頭にある、表示価格1万円のラパン、なんですけど。諸経費は、いくらですか?」
僕は、聞いた。
大体、中古車なんて、表示価格は、下げて、安く見えるようにして、諸経費は、最低でも、10万は、かかるものである。
その諸経費に、ある程度の金額を水増しして、諸経費で、儲けているのだろう。
ガリバーなんて、諸経費が、40万もする。
「あの、ラパンは、本体と諸経費、込みの、全額で、一万円です」
これは、ちょっと、安すぎる、と、僕は、おどろいた。
「どうして、そんなに安いのですか?」
「まあ。ちょっと、事情があって」
そう言って、店長は、へへへ、と笑った。
どうせ、事故車とか、性能に問題のある車だろうと思った。
僕は、性能が気になった。
たとえ、安くても、性能が、悪くて、すぐに、故障してしまうのでは、意味がない。
それで。
「ちょっと、試運転しても、いいですか?」
と、店長に聞いた。
「ええ。いいですよ」
と、店長は、言ってくれた。
僕は、すぐに、ラパンに乗り、店を出た。
乗り心地は快適だった。
僕は、すぐに車買い取り店、ガリバーに行って、車の性能を見てもらった。
「別に、問題は、ありませんよ。ほとんど、新車同様です。事故を起こさなければ、5年間は、修理なしで、乗れるでしょう」
と店員は、言った。
「あのー。売るとしたら、いくらで買ってくれますか?」
僕は聞いた。
「そうですねー。新車同様ですから、大体、50万円で、買いますよ」
ガリバーの人は、そう言った。
僕は、中古車店にもどった。
僕は、車を買うことにした。
「じゃあ、このラパン、買います」
僕は、そう言って、一万円札を、渡した。
「毎度、ありがとうございます」
店長は、やけに、嬉しそうに言った。
「今、乗っているマーチ。廃車にしたいんですけれど・・・」
僕は言った。
「ええ。廃車の処理は、やっておきますよ」
店長は、やけに、嬉しそうだった。
こうして、僕は、一日で、マーチから、ラパンに乗り換えることが出来た。
(やった。もうけものだ)
と僕は思った。
僕は、事故車だの、何だのには、関心がなかった。
(どうせ、こんな激安車だ。そのうち、故障が起こるかもしれない。しかし、故障が起こっても、たかが、一万円の損だ。それに、ガリバーの人も、新車同様と言ってくれた。一ヶ月でも、乗れれば、御の字だ。故障した時、修理代が、10万円、以下だったら、修理して乗ろう。修理代が高かったら、ガリバーで、売るなり、廃車にして、別の車を買うなりすれば、いいや)
と、僕は思った。
○
翌日。
さっそく、僕は、新しく買ったラパンで、大磯ロングビーチに行くことにした。
僕は、朝の8時に、アパートを出た。
大磯ロングビーチは、朝9時から、入場開始である。
途中、日焼け止めのオイルを買うために、僕は、コンビニに、入った。
そして、日焼け止めのオイルと、ついでに、ポカリスエットを買って、車にもどって、エンジンを駆けて、車を走らせた。
僕は、鼻歌を歌いながら、いい気分で、走っていた。
そのうち、赤信号の交差点になった。
僕は、ふと、バックミラーを見た。
20代に間違いない、きれいな、女の人が、後部座席に乗っていた、からだ。
僕は、びっくりした。
「あなたは、誰ですか?」
僕は聞いた。
「佐藤由香里といいます」
彼女は答えた。
「どうして、この車に乗っているのですか。というか、どうやって、この車に乗ったのですか?」
僕は聞いた。
「あ、あの。さっき、あなたが、コンビニの駐車場に、車をとめた時に、勝手に、入ってしまいました。ごめんなさい」
彼女は答えた。
僕は、さっき、コンビニに、入った時、車にキーをかけるのが、面倒なので、キーを、かけずに、コンビニに入った。
彼女は、僕が、コンビニに、入った隙に、車に、乗り込んだんだろう。
「でも、どうして、僕の車に乗り込んだんですか?」
僕は、疑問に思って、聞いた。
「あ、あの。私。あのコンビニで、親指を上げて、ヒッチハイクしていたんです。でも、どの車も、止まってくれなくて・・・。それで、勝手に、あなたの車に乗り込んでしまったんです。ごめんなさい」
と、彼女は言った。
「そうですか。でも、あなたのような、きれいな人なら、止まってくれる車も、あったんじゃないでしょうか?」
僕は、疑問に思って、聞いた。
「いえ。男の人が、運転している車は、みんな、助手席に、彼女が、乗っていて・・・止まってくれませんでした」
と、彼女は言った。
それは、もっともなことだ、と、僕は、思った。
彼女とのドライブなら、たとえ、美人であっても、見知らぬ女を、男は、乗せたりはしない。
彼女との、二人きりの、アツアツを、楽しみたいからだ。
「でも、車の数は多いです。男一人の車も、何台かは、あったのでは、ないでしょうか?」
僕は聞いた。
「ええ。確かに、男の人が一人で運転している車も、数台は、ありました」
「では、なぜ、その車に、ヒッチハイクの合図をして、乗らなかったのですか?」
「男の人が、なんだか、みんな、エッチなこと、してきそうに思われて、こわかったんです」
彼女は答えた。
「僕は違うんですか?」
「ええ。あなたは、真面目で、優しそうに、見えたので・・・」
「そうですか。そう言ってもらえると、嬉しいです」
人間は、なかなか、自分を客観視できないものである。
僕は、女性に、そのように、見られていることに、嬉しくなった。
「ところで、あなたは、どこに、行くのが目的なんですか?」
僕は聞いた。
「えっ」
と、彼女は、言葉を詰まらせた。
「ヒッチハイクするっていうのは、行く目的地があるからじゃないですか。それを、教えてもらえないと、あなたを、目的地に連れていけないじゃないですか」
僕は聞いた。
「私を、私の目的地まで、連れていって下さるのですか?」
「ええ」
「でも、あなたも、どこかに、行く予定があるんじゃないんでしょうか?」
彼女が聞いた。
「え、ええ。そりゃー。ありますけれど、急ぐ用でもないし、あなたを、あなたの、目的地まで、連れていきますよ」
僕は言った。
「やっぱり、思った通り、優しい方なんですね」
彼女は、嬉しそうに言った。
「そうでしょうか?」
僕は、聞き返した。
「そうですわ。男なんて、女を、ヒッチハイクしたら、みんな、呈のいいことを言って、結局は、100%、ラブホテルに、連れ込みますわ。それが、こわいから、女は、ヒッチハイクがこわくて、出来にくいんです」
彼女が言った。
「そんなものですか?」
僕は、友達づきあい、が、ほとんどないので、彼女がいないのは、もちろんのこと、世の男が、どういうことを、考えているのかも、あまり知らなかった。
「ええ。そんなものです」
彼女は言った。
「ともかく、あなたの行く目的地を教えて下さい」
僕は彼女に聞いた。
「あ、あの。私の目的地なんて、ないです」
彼女は、あっさり、言った。
僕は、おどろいた。
「じゃあ、なんで、僕の車に乗り込んだんですか?」
「あなたと、ドライブして、少し、お話しがしたかったからです」
「ええっ。本当ですか?」
僕は、耳を疑った。
「ええ。本当です」
彼女は、あっさり、言った。
「じゃあ。あなたが、僕の車に、乗り込んだのは、僕と、ドライブするためですか?」
僕は聞いた。
「ええ。そうです」
僕は、信じられない思いだった。
なにか、裏があるんじゃないか、とも、考えた。
しかし、まあ、ともかく、彼女の言うことを、素直に信じることにした。
「うわー。嬉しいなー。あなたのような、きれいな人と、ドライブ出来るなんて・・・。夢のようだ。僕、女の人と、つきあったことが一度もないんです。僕は、岡田純と言います」
僕は、飛び上がらんばかりに、喜んで、そう言った。。
「ところで、あなたは、どこへ行く予定だったんですか?」
彼女が聞いた。
「僕は、大磯ロングビーチに、行こうと、思っていました」
僕は、答えた。
「じゃあ、私も、大磯ロングビーチに、連れて行って下さい」
彼女が言った。
「本当に、いいんですか?」
僕は彼女に確かめた。
「ええ」
彼女は、あっさり、言った。
「うわー。嬉しいな。僕、女の人と、大磯ロングビーチに、行くのが、夢だったんです」
僕は、信じがたい思いだった。
しかし、バックミラーから、見える彼女の顔は、嬉しそうに、ニッコリ笑っていた。
しばし行くと、道の左手に、コンビニが、見えてきた。
「そうとわかれば・・・」
僕は、そう言って、左のウィンカーランプを点けて、左折して、コンビニの駐車場に入った。
そして、車を止めた。
「さあ。佐藤由香里さん。後部座席ではなく、助手席に乗って下さい」
そう言って、僕は、ドアロックを解き、助手席のドアを開けた。
「はい」
彼女は、僕の要求どおり、後部座席から出て、助手席に乗った。
「由香里さん。飲み物は、何がいいですか?」
僕は彼女に聞いた。
「何でも、いいです」
彼女は、答えた。
「では、オレンジジュースで、いいですか?」
「はい」
僕は、コンビニに、入って、500mlの、ペットボトルの、オレンジジュースを買い、ストローを一本、貰って、車にもどった。
「はい」
と言って、僕は、彼女に、オレンジジュースを渡した。
「ありがとう。純さん」
と、彼女は、礼を言って、オレンジジュースを、受けとった。
僕は、エンジンを駆けて、車を走らせた。
「咽喉が、渇いたでしょう。オレンジジュースを飲んで下さい」
僕は、運転しながら言った。
「はい」
彼女は、ペットボトルの蓋を開け、ストローを、その中に入れ、オレンジジュースを飲んだ。
コクコクと、彼女の咽喉が、動く様子が、可愛らしかった。
「僕も、咽喉が、渇いたなあ」
僕は、思わせ振りに言った。
「あ、あの。純さん。私が口をつけてしまった、オレンジジュースですが、飲まれますか?」
彼女が聞いた。
「ええ。飲みたいです。でも、僕は、運転しているから、手を離せません。片手運転は危険です」
僕は、思わせ振りに言った。
「で、では・・・」
そう言って、彼女は、ストローの入った、オレンジジュースを、僕の口の所に持ってきた。
僕は、ストローを口に含み、オレンジジュースを、啜った。
「ふふふ。これで、由香里さんと、間接キスしちゃった」
僕は、そんなことを言って、笑った。
彼女は、少し、恥ずかしそうに、顔を赤らめた。
「由香里さん。何か、歌を歌ってくれませんか?」
僕は彼女に頼んだ。
「何がよろしいでしょうか?」
「何でもいいです。由香里さんの、好きな歌を歌って下さい」
「わかりました。では、小坂明子の、あなた、を歌います」
そう言って、彼女は、小坂明子の、あなた、を歌い出した。
「もーしもー。わたしがー、家をー、建てたなら―。小さな家を建てたでしょう・・・♪」
彼女の歌は、上手かった。
「いやー。由香里さん。歌。上手いですね。歌手になれますよ」
僕は、感心して言った。
お世辞ではない。
「い、いえ。そんなに・・・」
彼女は謙遜して、顔を赤らめた。
○
そうこうしている、うちに、大磯ロングビーチに、ついた。
僕たちは、車を降りた。
「純さん」
「はい。何ですか?」
「あ、あの。私。水着、持っていないんです」
彼女は言った。
「ははは。大丈夫ですよ。場内で売っていますから」
「大人二人。一日券」
と言って、僕は、入場券を買い、大磯ロングビーチに入った。
僕は、場内にある、水着売り場で、彼女に、セクシーな、ビキニを買ってあげた。
ビキニ姿の、彼女は、ものすごくセクシーだった。
僕は、スマートフォンで、彼女の、ビキニ姿を、何枚も撮った。
そして、僕と彼女が、手をつないでいる写真も、何枚も撮った。
僕と彼女は、ウォータースライダーや、流れるプールで、うんと、楽しんだ。
「今日は、僕の人生で、最高に幸せな一日です」
僕は彼女に、そう言った。
し、実際、その通りだった。
○
12時を過ぎ、1時に近くなった。
「由香里さん。何か、食べましょう。由香里さんは、何が食べたいですか?」
僕は彼女に聞いた。
「私は、何でも、いいです。純さんと、同じ物でいいです」
と、彼女は言った。
「そうですか。じゃあ、焼きソバでいいですか?」
「ええ」
僕は、焼きそば、を、二人分、買った。
そして、彼女と一緒に食べた。
「あ、あの。純さん」
「はい。何ですか?」
「私。純さんに、言わなくてはならないことがあるんです。そして、謝らなくてはならないことがあるんです」
彼女は、あらたまった口調で、言った。
「はい。何でしょうか?」
「このことは、最初に言うべきだったんです。ですが、純さんが、優しくて、私も楽しくて、つい、言いそびれてしまいました。本当に、申し訳ありません」
と、彼女は、深刻な口調で言った。
「はい。それは、一体、何でしょうか?」
僕には、どういうことか、さっぱり、わからなかった。
彼女に、何か、謝るべきことなど、僕には、さっぱり思いつかなかった。
「あ、あの。私。実は、幽霊なんです」
彼女は言った。
「そうですか」
僕は、あっさりと言った。
「あ、あの。純さんは、幽霊がこわくないんですか?」
彼女は聞いた。
「こわくありませんね。僕は、幽霊の存在なんて、信じていません。し、仮に、幽霊がいたとしても、こわくありません」
僕は、キッパリと言った。
「僕は、唯物主義を信じていて、精神も、脳の神経回路の活動によるものだと、確信しています。物質によらない、精神の存在など、無いと、信じています。なので、もちろん、無神論者だし、「神」だの、死後の、「天国」だの、「地獄」だのも、もちろん、存在しない、と、確信しています。それらは、人間の想像力が、生み出した、産物だと確信しています」
と、僕は、自分の信念を、言った。
「そうですか。でも、本当に、私は、幽霊なんです」
と、彼女は言った。
「由香里さん。それにですよ。仮に、あなたが、幽霊だとしても、あなたは、僕に、何の危害も加えません。なので、由香里さん、が、仮に、幽霊だとしても、僕はこわくは、ありません」
と、僕は、キッパリと言った。
「純さん、や、多くの人々が、唯物論を信じるのは、無理のないことだと思います。だって、神さまは、幽霊や、霊魂や、死後の世界などを、知らせると、人間が、こわがって、しまって、人間世界が、混乱してしまう、ことを、心配して、人間には、それらのことは、知らせませんもの」
と、彼女は言った。
「そうですか」
と、僕は、言った。
なるほど、彼女の言い分にも、一理あるな、と思った。
人間は、一度、死んだら、生きかえることは、出来ない。
死んで、その後、生きかえって、死後、人間は、どうなるのか、その体験を、語った人間は、いないのだから。
だから、人間は、死後、どうなるのかは、本当は、わからないのである。
物質に全く依存しないで、独立して、存在する、精神、というものも、無い、と、科学的に、証明されてはいない。
僕は、証明されていない事は、信じることも、否定することも、しない主義である。
なので、彼女の言うことを、僕は、頭から、否定する気には、なれなかった。
彼女の言うことを、傾聴しようと思った。
「あなたが、幽霊だと、言うのなら、一応、それを信じましょう」
僕は、言った。
「信じてくれて、ありがとうございます」
と、彼女は言った。
「ところで、あなたは、さっき、僕に、謝らなくてはならないことが、ある、と、言いましたよね。それは、一体、何なのですか?」
僕は、彼女に聞いた。
「そのことなんです。単刀直入に、率直に、正直に言います。私は、幽霊です。そして幽霊である、私と一日、付き合った人間は、一年間、寿命が短くなるんです。もう、私は、純さんと、一日、つきあいましたから、純さんの寿命は、一年間、短くなっているんです。これは、最初に言うべきでした。ごめんなさい」
と、彼女は、涙を流しながら、謝った。
「そうですか。でも、別に、僕は、それでも構いませんよ」
僕は言った。
「どうしてですか。純さんは、寿命が短くなることが、こわくは、ないのですか?」
彼女は聞いた。
「こわくは、ないですね。人間は、いつかは、死にます。それが、一年、短くなったからといって、僕は、別に気にしません。僕は、人間の価値は、いかに長く生きるか、ではなく、生きている間に、何事をなすか、だと思っています。今日、あなたと、楽しく過ごすことが出来た、一日は、歳をとって、寝たきりになって、何も出来ないで、過ごす、一年間より、はるかに、価値があると、思っています。それに、あなたが、幽霊だという主張は、僕は、一応、信じることにしているだけで、僕は、あなたが、幽霊だという主張を、完全には、信じては、いませんし、僕の寿命が一年、短くなった、という、あなたの、主張も、完全には、信じることは、出来ませんから」
と、僕は言った。
「ありがとうございます。そう言って、いただけると、この上なく嬉しいです」
と、言って、彼女は、また、泣いた。
「由香里さん。ところで、あなたは、どうして幽霊になってしまったのですか?」
僕が聞くと、彼女は、また、ポロポロと、涙を流し出した。
そして、語り出した。
「私は、純さん、が、買った車に、はねられて、死にました。大学を卒業して、晴れて、ある、アパレル会社に就職した、社会人一年目の年です。真夜中に、あの車を運転していた人に、はねられて、死んでしまったのです。はねた人は、真夜中で、誰も周りに人はいませんでしたが、すぐに、車を止めて、警察と、消防に、連絡してくれました。でも、私は、アスファルトの道路に、頭を強くぶつけていて、即死でした。ですから、私は、彼を怨んではいません。でも、私も、男の人と、一度もつき合ったことが、なく、どうしても、優しい男の人と、楽しい恋愛を、楽しみたい、という願望が、あまりにも、強くあって、それが、心残りで、どうしても、成仏できないのです。それで、成仏できずに、あの車に、幽霊として、居続けることになってしまったのです」
と、彼女は語った。
僕の心は、彼女の主張を信じる方に、かなり傾いた。
中古車店の、店長が、あんなに、新車に近い、いい、車を、ほとんど、タダに近い、安い金額で、売ってくれたことの理由が、彼女の訴えによって、説明が、つくからだ。
僕は、彼女の言うことを、一応、信じることにした。
「そうだったんですか。それは、気の毒ですね。あなたは、今まで、とても、つらい思いをしてきたんですね。でも、さっき、言った通り、僕は、年老いて、寝たきりになってからの、一年、より、今日の、あなたとの楽しい一日の方が、はるかに、価値があるんです。ですから、気にしないで下さい。今日は、うんと、楽しみましょう」
と、僕は言った。
「ありがとうございます。純さん」
そう言って、彼女は、涙をポロポロ流した。
○
その後は、もう、彼女とは、辛気臭い、暗い話はせず、波のプール、や、流れるプールで、彼女と、水をかけあったり、つかまえっこをしたりと、うんと、夏の楽しい、一日を過ごした。
○
時計を見ると、もう、4時30分だった。
大磯ロングビーチは、以前は、6時まで、営業していたが、最近は、不況で、経営が厳しく、午後5時で、閉館となっていた。
もう、あと、30分しかない。
昨日から、平塚七夕まつり、が、始まって、今日は、2日目だった。
「由香里さん。今日は、平塚七夕まつり、を、やっています。行きませんか?」
僕は、彼女に聞いた。
「ええ。ぜひ、行きたいわ」
彼女は、ニコッと、笑って答えた。
僕と彼女は、大磯ロングビーチを、出た。
そして、国道1号線を、走って、平塚駅に向かった。
東海道線の下りで、平塚の次が、大磯で、一駅、だけで、距離も、4kmなので、すぐに、平塚に着いた。
平塚七夕まつり、は、関東三大七夕まつり、の一つである。
来場者は、145万人と、大規模である。
平塚駅の北口の、駅前の、三つの、大通りには、隙間の無いほど、びっしりと、露店が、並んでいた。
大勢の人が、賑やかに行き来していた。
僕と彼女は、金魚すくい、を、したり、焼きトウモロコシ、や、綿アメを、食べたりした。
「金魚すくいって、可哀想ですね」
と、彼女は、言った。
「どうしてですか?」
僕は聞いた。
「だって、金魚は、弱って、動きの鈍い、金魚ばかりが、狙われるんですもの」
と、彼女は、言った。
「そうですね。でも、すくった金魚を、家に持ち帰りたい人は、元気な金魚を狙うんじゃないんですか」
と、僕は言った。
こんな、他愛もないことでも、お祭りは、楽しいのである。
僕は、彼女と、手をつないで、露店を見ながら歩いた。
彼女が、浴衣でないのが、ちょっと残念だった。
通りの中には、お化け屋敷、があった。
入場料、500円と書いてある。
「由香里さん。あれに入って、みませんか?」
僕は、彼女に言った。
「え、ええ。でも、なんだか、こわそうだわ」
彼女は言った。
「何を言ってるんですか。お化け屋敷なんて、人間を、こわがらせるために、巧妙に、わざと、こわく見えるように、作った偽物であって、本当の、お化け、なんかじゃないですよ。その点、あなたは、幽霊じゃないですか」
と、僕は言った。
「でも、本当に、こわいんですもの」
と、彼女は言った。
「ともかく、入りましょう」
と、言って、僕は、二人分の、入場料の、1000円を、払って、彼女と、お化け屋敷、に、入った。
彼女は、入る前から、こわいのか、私の腕をガッシリと、握っていた。
お化け屋敷、の中は、うす暗かった。
お岩さん、や、ろくろ首、や、フランケンシュタイン、や、ドラキュラ、や、化け猫、や、ミイラ、などが、バッと、いきなり、出てきた。
その度に、彼女は、
「うわー」
「きゃー」
「ひいー。こ、こわいー」
と、大声で、叫んで、僕に、ガッシリと、しがみついた。
僕は、こんなのは、全然、こわくなかったので、平然としていた。
そして、やっと、お化け屋敷、を出た。
「ああ。こわかったわ。こわくて、ショック死するかと思ったわ」
と、彼女は、ハアハアと、息を荒くしながら、言った。
僕は、ははは、と、笑った。
「何を言ってるんですか。あなたは、幽霊で、もう、死んでいるんじゃないですか。死んでいる幽霊が、死ぬかと思った、なんて、発言は、矛盾していますよ」
僕は、やはり、彼女は、幽霊ではないのではないか、と思った。
「でも、本当に、こわかったんですもの」
と、彼女は言った。
「そうですか」
幽霊とは、そんなものなのか、と、僕は、ちょっと、違和感を感じた。
お化け、を、こわがる幽霊というのも、変なものだと思った。
「本当に、こわいのは、あなたの方ですよ。だって、あなたは、幽霊なんですから」
と、僕は彼女に言った。
「じゃあ、純さんは、何で、私を、こわがらないんですか?」
彼女は僕に聞いた。
「それは、あなたが、こわい容貌ではなく、美人で、可愛いからです。それと、僕は、あなたが、幽霊であるとは、完全には、信じ切っていません。車の値段が、安すぎるのが、いまだに、不思議ですが、あなたが、幽霊だというのなら、車の値段が、安かった説明が、あなたの主張によって、つくから、一応、信じることに、しているだけ、だからです」
と、僕は言った。
○
「由香里さん。もう、帰りましょう」
「はい」
僕と、彼女は、駐車場に停めておいた、車にもどった。
「純さん。今日は、楽しかったです。ありがとうございました」
「僕も、楽しかったです。今日は、最高に楽しい一日でした。ありがとうございます。由香里さん」
「あ、あの。純さん」
「はい。何でしょうか?」
「これからも、私と、つきあってくれますか?」
「ええ。大歓迎です」
「でも、私は、幽霊ですから、一日、私とつきあうと、純さんの寿命が一年、縮まりますよ。それでも、つきあって下さいますか?」
「僕は、あなたを、まだ、完全に、幽霊だと、信じ切ることが、出来ないのです。だから、その質問には、答えようが、ありません。あなたが、幽霊だということを、証明することが、出来ますか?」
「わかりました。では、証明します。それでは、一度、車から、降りて、私の写真を撮って下さい」
彼女は、そう言った。
僕は、彼女に、言われた通り、車から、降りた。
彼女も車から出た。
彼女は、車の前に、立った。
「さあ。純さん。車を背にして、立っている、私の、写真を、たくさん、撮って下さい」
彼女は言った。
「はい。わかりました」
僕は、車を背にして、立っている、彼女の、写真を、たくさん、撮った。
「純さん。私の顔写真も、たくさん、撮って下さい」
彼女は言った。
「はい。わかりました」
僕は、彼女の、顔写真も、たくさん、撮った。
彼女は、口を、アーンと、大きく開いた。
「純さん。口を開けている、私の顔も、撮って下さい」
彼女に言われて、僕は、口を開けている、彼女の顔も、撮った。
こんな事をして、何になるのかと、僕は、疑問に思いながら。
「では、AKB48の、ヘビーローテーションを、踊りながら、歌いますので、その動画も、撮って下さい」
彼女は言った。
「はい。わかりました」
彼女は、車の前で、踊りながら、歌い出した。
「ポップコーンが、弾けるように、好きという文字が躍る・・・・♪」
彼女の歌は、上手かった。
しかし、こんな事をして、何になるのかと、僕は、疑問に思っていた。
歌い終わると、彼女は、
「では。車にもどりましょう」
と、彼女が言った。
僕と、彼女は、車にもどった。
彼女は、助手席に座った。
「純さん。私の指紋をとって下さい」
彼女が言った。
僕は、彼女の指紋をとった。
「純さん。私の髪の毛を、数本、とって下さい」
彼女が言った。
僕は、彼女の、髪の毛を、数本、とった。
「では。私が、幽霊だということを、証明します。茅ヶ崎に、私の実家がありますので、そこへ行って下さい。場所は、私が、案内します」
「わかりました」
僕は、車のエンジンを駆けた。
そして、国道一号線を、藤沢の方に、向けて、走り出した。
彼女は、「そこの交差点を左に」とか、「そこの交差点を右に」とか、言った。
僕は、彼女の言う通りに、車を運転した。
○
「純さん。車を止めて下さい」
彼女が言ったので、僕は、車を止めた。
「あそこの、二階建ての、青い屋根の家が、私の実家です」
そう言って、彼女は、少し先にある、二階建ての、青い屋根の家を指差した。
「では。純さん。私の家族に、さっき、スマートフォンで、撮った、写真や、動画を、見せて下さい。そうすれば、私の言っていることが、本当だということが、証明できます。私は、ここで待っています」
彼女は、自信に満ちた口調で言った。
「わかりました」
そう言って、僕は車を降りた。
そして、二階建ての、青い屋根の家の前に行った。
表札には、「佐藤圭介」、と、書いてある。
彼女の苗字は、「佐藤」だから、合っている。
僕は、チャイムを押した。
ピンポーン。
家の中で、チャイムの音が、響くのが、聞こえた。
「はーい」
女性の声が聞こえて、パタパタ、走ってくる音が聞こえた。
すぐに、玄関が開いた。
一人の、中年の、女性が姿を現した。
「どちらさまでしょうか。ご用は何でしょうか?」
女性は、僕を見ると、そう聞いた。
「あの。ここは、佐藤由香里さんの、お宅でしょうか?」
僕は聞いた。
「由香里は死にました。あなたは、どなたでしょうか?」
女性が聞いた。
「ちょっと、由香里さん、と、縁のある者です。由香里さんに関して、お聞きしたいことが、あります。なので、少し、お話しを聞かせて欲しいのです」
僕は言った。
「由香里の、生前の、お友達ですか?それなら、どうぞ、お入り下さい」
そう言って、彼女は、僕を家に入れてくれた。
僕は、居間に通された。
「どうぞ。お座り下さい」
僕は、彼女に勧められて、居間のソファーに座った。
「あなたは、由香里さん、と、どういう関係の人でしょうか?」
僕は聞いた。
「私は、死んだ由香里の母です」
と、彼女は言った。
「そうですか」
と僕は、言った。
確かに、顔が、彼女と、似ている。
「ところで、あなたは、由香里と、どういう関係の人でしょうか?」
今度は、彼女が僕に、聞いた。
「僕は、由香里さん、の友達です」
僕は言った。
「そうですか」
彼女は、少し、憔悴ぎみの顔で言った。
○
「あの。これを見て欲しいのです」
そう言って、僕は、スマートフォンを、テーブルの上に置き、さっき、撮った、写真や、動画を再生して見せた。
「ああっ。由香里だわ。これは、いつ、撮られたのですか?」
母親は聞いた。
「少し前です」
僕はそう言った。
「この人は、本当に、あなたの、娘さんの、由香里さん、ですか?」
僕は、念を押すように聞いた。
「間違いありません。これは、娘の由香里です。母親の私が、娘を間違うはずなど、ありません。右足の甲に、由香里の、ほくろ、も、ありますし、右の眉毛の所に、子供の頃、怪我をして、縫った小さな傷痕もありますし、口を開けている写真では、右下の奥から二本目に、治療した、銀歯も、ありますし。娘が、得意だった、ヘビーローテーションの、踊り方も、声も、娘に間違いありません」
母親は、昔を思い出して、少し涙ぐんで言った。
「それに、由香里が着ている服は、由香里が、事故で死んだ時に、着ていた服です」
母親は言った。
「でも、不思議ですわ」
母親が言った。
「何がですか?」
「由香里が背にしている車は、由香里が、はねられた車です。青のラパンです」
「そうですか。でも、青のラパンなど、いくらでも、走っています。由香里さん、が、はねられた車か、どうかは、わからないでは、ないですか?」
「それは、その通りですね。ところで、こういう写真を持っているということは、あなたは、由香里と、かなり、親しい仲だったんですね?」
「え、ええ。まあ、そうです」
と、僕は言った。
○
「ところで、由香里さん、の写真は、ありますか?」
僕は聞いた。
「ええ。あります。ちょっと、待っていて、下さい。由香里の部屋に行って、とってきます」
そう言って、母親は、階段を昇っていった。
そして、母親は、すぐに、アルバムと、パソコンを、持って、もどってきた。
「これが、由香里の写真です」
そう言って、母親は、アルバムを開いた。
アルバムには、彼女の子供の頃から、大学の卒業式、や、会社に入社した時の、写真が、たくさん、載っていた。
確かに、それは、由香里さん、だった。
高校生の頃の、彼女の写真も、今の、彼女の面影がある。
「これも、見て下さい」
母親は、そう言って、パソコンのディスプレイを、表示させた。
「これは、由香里が、友達と、飲み会をした時に、カラオケ喫茶で、由香里の友達が、撮影してくれた動画です」
そう言って、母親は、スタートボタンを押した。
パソコンのディスプレイに、彼女が、AKB48の、ヘビーローテーションを、踊りながら、歌っている、動画が、映し出された。
その、声も、踊り方も、さっき、見た、彼女の、ヘビーローテーション、と、全く、同じだった。
「うーん」
僕は、唸った。
やはり、彼女は、彼女が言うように、幽霊なのかも、しれないな、と、僕は、思うようになった。
「あなたは、由香里と、親しかった人なんですね?だって、一緒に、レジャープールに行くほどなんですから」
母親が聞いた。
「ええ。そうです」
僕は答えた。
「では。由香里の冥福を、祈って、焼香してやって下さい」
母親が言った。
僕は、二階の、由香里さん、の部屋に入った。
由香里さん、の、写真が祀られた、額縁と、由香里さん、の、位牌が、あった。
僕は、手を合わせて、由香里さん、の、冥福を祈った。
「由香里さん、が、死んだ、ということを、僕は、最近、知りました。ちょっと、変わった、お願いがあるんですが・・・」
僕は言った。
「はい。何でしょうか?」
母親は、聞き返した。
「由香里さん、が、死んだ、ということを、証明できる、ものが、他に何か、あるでしょうか?」
僕は聞いた。
「由香里は、本名で、ブログをやっていました。由香里が死んでも、ブログは、残してあります」
母親は、そう言って、彼女のブログを、見せてくれた。
ブログには、彼女の写真も、たくさん、載っていた。
そして、最後のブログの記事のコメントには、「由香里。悲しいわ。でも、あなたは、立派に生きたわ。私。あなたを、いつまでも、忘れないわ」、などと、いう、友達のメッセージが、たくさん、載っていた。
そして、パソコンで、「佐藤由香里」で、検索すると、「茅ヶ崎市に住む、東海大学、文学部教授の、一人娘の、佐藤由香里さん、が、昨日、自動車事故で亡くなられました」という、記事が、いくつも、出てきた。
「うーん」
と、僕は、唸った。
ここまで、物的証拠があれば、彼女が、本当に、幽霊だということを、信じるしか、ないな。
と、僕は思った。
「どうも、色々と、ありがとうございました」
そう言って、僕は、彼女の家を出た。
○
そして、車にもどった。
助手席には、彼女が、座っていた。
「どう。私が、幽霊だということが、確信できましたか?」
彼女は僕に聞いた。
僕は、黙っていた。
「まだ、信じられない、というのなら、私の部屋には、私の指紋が、いっぱい、ついているから、私の指紋と、照合しても、いいわよ」
と、彼女は言った。
「由香里さん。あなたは、幽霊になったのなら、どうして、お母さんと、会わないのですか?」
僕は聞いた。
「それは。幽霊と、出会うと、寿命が、一年、縮まるからですよ。私。お母さんの寿命を、縮めたくないもの。それに、私が、成仏できないで、幽霊になってしまった、ということを、おかあさん、が、知ったら、驚くし、不安になるでしょ。それに、幽霊が、本当に、存在する、などと、わかったら、世間を騒がせて、混乱させてしまうでしょ。私、世間を混乱させたくないもの」
と、彼女は、飄々と言った。
「なるほど」
と、僕は言った。
「指紋を照合しても、また、信じられない、というのなら、私の髪の毛で、DNA解析して、調べて下さい。母は、私の遺髪として、私の髪の毛を、持っていますから。DNAが、一致したら、確実に、私だと、証明されるでしょ」
と、彼女は言った。
「いや。由香里さん。その必要はありません。ここまで、確かな証拠が、そろっていれば、僕は、あなたが、幽霊だということを、100%、確信しました」
と、僕は言った。
「ありがとうございます。やっと、信じていただけて、嬉しいです」
と、彼女は、嬉しそうに言った。
「僕は、唯物論を信じ切っていません。確かに、この世の事のほとんどは、唯物論で、説明できます。しかし、人間は、時間、というものを、説明することが出来ません。時計の針の、動きは、時間を、便宜的に、図るための道具に過ぎません。宇宙に、上下があるのかも、説明できません。し、宇宙のはて、は、どうなっているのか、も、わかりません。死後、人間は、どうなるのか、物質によらない精神というものは、存在しない、ということも、科学的に証明されていません。僕は、証明されていないことは、否定しない主義です。ですから、ここまで、証拠が、そろえば、僕は、あなたが、幽霊だということを、信じます」
と僕は言った。
「ありがとうございます。やっと、信じていただけて、嬉しいです」
と、彼女は、嬉しそうに言った。
○
「あ、あの。純さん」
「はい。何でしょうか?」
「私が、幽霊だと、信じてもらえましたが、こんな私でも、これからも、つきあってくれますか?」
「ええ。大歓迎です」
「でも、私は、幽霊ですから、一日、私とつきあうと、純さんの寿命が一年、縮まりますよ。それでも、つきあって下さいますか?」
「ええ。構いませんよ」
「嬉しいわ」
そう言って、彼女は、涙を流した。
「ところで、由香里さん」
「はい。何でしょうか?」
「あなたと、一日、つきあうと、僕の寿命が一年、縮まるんですよね」
「ええ。そうです」
「僕は、今、二十歳です。僕が、何歳まで、生きられるのかは、わかりませんけれど、平均寿命から考えて、80歳まで、生きられる、と、仮定しましょう。すると、あなたと、これから、毎日、つきあうと、60日後、つまり、二ヶ月後に、僕は、死ぬことになりますね」
「ええ。そうです」
「そこで、僕に提案があるんです。あなたと、つきあう一日は、充実した、一日にしたいですね。毎日、つきあうと、僕は、60日で、死ぬことになります。しかし、月に一度だけ、会う、というように、すれば、60/12=5年、あなたと、結婚生活を、送れることが出来ます。月に、一度でなくても、月に二度でも、構いませんし、あるいは、逆に、二ヶ月に、一度、会う、と、いうように、しても、いいんでは、ないでしょうか。二ヶ月に、一度、会う、とすれば、60/6=10年、あなたと、結婚生活を、送れます。どのくらいの、頻度で会うかは、あなたに任せます」
「なるほど。そういう方法もありますね。気がつきませんでした」
と、彼女は言った。
「結婚生活なんて、毎日、顔を見ていると、惰性で、だんだん、新鮮味が、なくなるものですよ。ささいなことで、夫婦ケンカになったりも、しますしね。芸能人でも、一般の人でも、アツアツの想いで、結婚しても、その半分ちかくは離婚しています。毎日は、会えず、時たま、会える、という方が、いつまでも、新鮮でいられると、思います。毎日、会っていると、厭き、も、来やすいものです。会えない期間があった方が、会いたい、という、情熱が、強くなります。七夕にしたって、織姫と牽牛は、一年に一度しか、会えないから、二人の愛は、激しく燃えあがるのでは、ないですか。一年に一度、会うとすれば、僕は、あと、30年、生きられます。ゲーテも、「ふたりの愛を深くするにはふたりを遠く引き離しさえすればよい」、と言っています。プブリウス・オウィディウス・ナソも、「満ちたりてしまった恋は、すぐに退屈になってしまうものである」、と言っています。シェイクスピアも、「ほどほどに愛しなさい。長続きする恋はそういう恋です」、と言っています。どうでしょうか?」
「わかりました。純さん、って、理性的な方なんですね。ちょっと、拍子抜けしてしまいました。でも・・・」
と、言い出して、彼女は、少し、渋い顔になった。
僕は、彼女の思っている事をすぐに、察知した。
そのため、僕は、先手を打った。
「ははは。由香里さん。あなたが、不安に思っていることは、わかりますよ。会わない期間が長いと、僕が、心変わりして、他の女性と、つきあうように、なってしまうんではないかと、心配しているんでしょう?」
彼女は、黙っている。
「由香里さん。答えて下さい」
僕は、強気の口調で、問い詰めた。
「・・・え、ええ。恥ずかしいですけれど、その通りです・・・」
彼女は、顔を赤くして言った。
「その点は、大丈夫です。安心して下さい」
僕は、自信をもって言った。
「どうして、ですか。それを、証明して下さい」
今度は、彼女が、僕に証明を求めるようになった。
「だって、僕は、内気で、無口で、ネクラで、友達なんて、一人もいませんから。彼女をつくることなんて、不可能です。僕は、憶病ですから、女性に、声をかけることなんて、出来ません。僕は、今まで、一度も、彼女、というものを、つくることが出来ませんでした。これからも、つくれないしょう。だから、あなたと、会った時、僕は、有頂天になって、喜んだじゃないですか。僕が、女性と、デートするのは、今日が、生まれて初めてだと、言ったじゃありませんか。僕の、パソコンでも、スマートフォンでも、調べてもらえば、わかりますが、僕が、女性と、楽しそうにしている、写真なんて、一枚もありません。ですから、それが、僕の証明です。科学的には、証明できませんが、あとは、由香里さん、が、信じてくれる、か、どうかに、かかっています」
と、僕は言った。
「僕のスマートフォンを、見て下さい。もし、僕に、恋人が、いるのなら、スマートフォンに、恋人との、メールのアドレスや、恋人との、メールのやりとり、や、恋人と撮った写真が、のっているでしょう」
そう言って、僕は、彼女に、スマートフォンを渡した。
彼女は、スマートフォンを、受けとると、一心に、カチャカチャ操作した。
「どうです。何もないでしょう?」
僕は、彼女に聞いた。
「確かに、何もありません。わかりました。純さんを信じます」
と、彼女は言った。
「ところで、由香里さん」
「はい。なんでしょうか?」
「一日、つきうと、と、寿命が一年、縮まる、と、あなたは、言いましたが、一日というのは、24時間、ちょうど、ですか?」
「いえ。12時間です」
「そうですか。それなら、早く、アパートにもどらないと」
僕は、車のエンジンを駆け、アクセルをグンと踏んだ。
急いで、アパートに帰らねば、と思った。
なぜなら、今日一日、彼女と、つきあってしまったのだから、僕は、一年、寿命が、縮まってしまったのだ。
それなら、彼女と、少し、ペッティングも、したいと思ったからだ。
「ところで、由香里さん」
僕は、車を運転しながら聞いた。
「はい。なんでしょうか?」
「この次は、いつ、会う予定ですか?」
「それは、まだ、決めていません」
「そうですか。できれば、日曜日に、出てきてくれると、助かります。今度、あなたと、会う時は、ディズニーランドに、行きましょう」
「はい。ありがとうございます。楽しみだわ」
彼女は、嬉しそうに言った。
○
途中に、コンビニがあった。
「ちょっと、トイレに行ってきます。すぐ、もどってきます」
そう言って、僕は、コンビニに入った。
僕は、コンビニのトイレで、オシッコをして、すぐに、コンビニを出た。
急いで、車に入ったが、彼女は、いなかった。
そして、車の中には、彼女の服があった。
そして、メモがあった。
それには、こう書いてあった。
「純さん。ちょうど、12時間、経ちました。私は、消えます。この次は、いつ、お会いするかは、考えておきます。もしかすると、成仏できるかもしれません。由香里」
彼女と、今日、会ったのは、午前、8時頃で、今、ちょうど、午後8時である。
ちょうど、12時間、経ってしまったのだ。
僕は、ちょっと、残念だった。
○
それから、三ヶ月経った。
彼女は、現れない。
僕が、言ったように、彼女は、気をきかせて、くれているのだろう。
もしかすると、一年は、現れないかも、しれない。
さらに、もしかすると、彼女は、成仏できたのかもしれない。
まあ、しかし、僕としては、彼女がまた現われて、彼女と、ディズニーランドに行くのが、楽しみである。
○
しかし、日が経つにつれ、僕は、だんだん彼女が恋しくなった。
あんな、きれいな人と、出会えたんだから、ペッティングしておけば、良かった、と、僕は後悔した。
(もう、現れてくれないだろうか?)
僕は、彼女の、ビキニ姿の写真を見ながら、何回も、オナニーした。
彼女が、僕と会いたがっている、のと、同様に、僕も、彼女に会いたくなった。
だが、いつまで、経っても、彼女は、現れなかった。
「きっと、彼女は、成仏してしまったんだろう」
と、僕は、思って、あきらめだした。
○
それから、一年が経った。
僕は、由香里さん、のことなど、忘れていた。
もちろん、僕は、シャイで、憶病なので、彼女など、つくれない。
町で、手をつないで、歩いているカップルを、うらやましく、眺めるだけである。
七月七日になった。
「純さん。お久しぶり」
そう言って、ひょっこり、由香里さん、が、現れた。
びっくりすると、同時に、僕は、嬉しくなった。
「ああ。由香里さん。会いたかったよ」
僕は言った。
「私もよ」
彼女も言った。
僕は彼女を、ガッシリと抱きしめて、キスした。
「じゃあ、今日は、ディズニーランドに行きましょう」
「ええ」
こうして、僕と、由香里さん、は、ディズニーランドに行き、一年ぶりに、楽しい一日を過ごした。
前回、出来なかったので、一日、ディズニーランドで楽しんだ後は、近くのホテルに、入り、うんと、彼女と、ペッティングした。
「一年に、一回、くらいの、割り合が、良さそうだと思います。では。来年の、七月七日に、お会い致しましょう」
そう言って、12時間、経つと、彼女は、姿を消した。
僕は、来年の、七月七日が、待ち遠しい。
平成28年8月18日(木)擱筆
その日は、7月6日だった。
連日の、猛暑で、夏バテで、僕は、まいっていた。
子供の頃は、夏が来ると、単純に嬉しかった。
しかし、大人になると、夏になるのは、子供の時と、同様に、嬉しかったが、連日の猛暑で、夏バテして、いささか、夏の到来を、素直には、喜べなくなっていた。
それと、もう一つ、嫌なことが、あった。
二年に一度の、車の車検の期限が、1週間後の、7月14日で、切れるからである。
今年は、車検が切れる年だった。
だいたい、車検にかかる費用は、10万円くらいだろう、と思っていた。
いつも、そうだったからだ。
しかし、去年、ある時、バックした時に、電信柱に、車をぶつけてしまい、車の後ろが、少し凹んでしまった。その時から、電気系統が故障したのか、ドライブにギアチェンジすると、「D」の、ランプが点かなくなった。
しかし、運転には、問題ないので、そのまま、乗っていた。
僕の車は、旧型マーチだった。
今回の車検は、いくら、かかるのだろうか、と、日産のディーラー店に、入ってみた。
車検は、7月14日で、切れるから、あと、1週間である。
「車検にかかる費用、見積もってもらえませんか?」
と僕は聞いた。
「はい。わかりました」
と、店の人が言った。
店では、新車を売っているが、店の裏に、修理場があって、修理工が、働いている。
僕は、自動車の、修理工を立派だと思っていた。
毎日、油にまみれ、汚れた服で働いて。
働く、とは、ああいうことを、言うものだ、と僕は思っていた。
一時間、くらいして、店の人が、やって来た。
それで、見積もりの明細を見せてくれた。
部品交換と、工賃が、バーと、並んでいて、合計で、18万円だった。
僕は、あせった。
僕は、車検にかかる費用が、10万、程度なら、買い替えることなく、乗り継ごうと思っていた。
僕は、車の事情については、素人だか、それでも。18万ともなれば、もう少し、金を出せば、中古車が買える。
ボロボロになった、車を、18万も出して、乗り続けるよりは、あらたに中古車を買い替えようと、思った。
僕は、スズキのラバンが欲しかったので、スズキのディーラー系の中古車店に行くことに決めた。
ディーラー系の中古車店は、アフターサービスがいいからである。
そのぶん、値段が、高目だが、表示価格10万とかの、激安車は、諸経費が10万円、くらい、かかって、合計20万円くらいになり、1年、以内に、色々と、故障個所が出てきて、結局は、修理に次ぐ、修理となってまう。
なので、多少、高目でも、信頼できる、ディーラー系の中古車店の中古車を買った方が、いいと信じ込んでいた。
国道467号線は、中古車通り、と、言われるくらい、道路の左右に、無数の中古車店がある。
しかし、ある中古車店で、表示価格1万円の、激安中古車が目に止まった。
ラパンだった。
激安中古車なんて、走行距離は長いし、年式も古いし、色々と、性能に問題があって、修理しなくてはならないから、結局は、高くつく。
しかし、そのラパンは、車検2年つき、で、年式も、平成26年式で、走行距離も、1万km、と、信じられないくらい、いい条件だった。
僕は、一応、店に入ってみることにした。
僕は、中古車店に車を入れた。
「こんにちはー」
僕が、大きな声で、呼ぶと、中から、男が出てきた。
「はい。私が、この店の店長です。ご用は何でしょうか?」
男が言った。
「店頭にある、表示価格1万円のラパン、なんですけど。諸経費は、いくらですか?」
僕は、聞いた。
大体、中古車なんて、表示価格は、下げて、安く見えるようにして、諸経費は、最低でも、10万は、かかるものである。
その諸経費に、ある程度の金額を水増しして、諸経費で、儲けているのだろう。
ガリバーなんて、諸経費が、40万もする。
「あの、ラパンは、本体と諸経費、込みの、全額で、一万円です」
これは、ちょっと、安すぎる、と、僕は、おどろいた。
「どうして、そんなに安いのですか?」
「まあ。ちょっと、事情があって」
そう言って、店長は、へへへ、と笑った。
どうせ、事故車とか、性能に問題のある車だろうと思った。
僕は、性能が気になった。
たとえ、安くても、性能が、悪くて、すぐに、故障してしまうのでは、意味がない。
それで。
「ちょっと、試運転しても、いいですか?」
と、店長に聞いた。
「ええ。いいですよ」
と、店長は、言ってくれた。
僕は、すぐに、ラパンに乗り、店を出た。
乗り心地は快適だった。
僕は、すぐに車買い取り店、ガリバーに行って、車の性能を見てもらった。
「別に、問題は、ありませんよ。ほとんど、新車同様です。事故を起こさなければ、5年間は、修理なしで、乗れるでしょう」
と店員は、言った。
「あのー。売るとしたら、いくらで買ってくれますか?」
僕は聞いた。
「そうですねー。新車同様ですから、大体、50万円で、買いますよ」
ガリバーの人は、そう言った。
僕は、中古車店にもどった。
僕は、車を買うことにした。
「じゃあ、このラパン、買います」
僕は、そう言って、一万円札を、渡した。
「毎度、ありがとうございます」
店長は、やけに、嬉しそうに言った。
「今、乗っているマーチ。廃車にしたいんですけれど・・・」
僕は言った。
「ええ。廃車の処理は、やっておきますよ」
店長は、やけに、嬉しそうだった。
こうして、僕は、一日で、マーチから、ラパンに乗り換えることが出来た。
(やった。もうけものだ)
と僕は思った。
僕は、事故車だの、何だのには、関心がなかった。
(どうせ、こんな激安車だ。そのうち、故障が起こるかもしれない。しかし、故障が起こっても、たかが、一万円の損だ。それに、ガリバーの人も、新車同様と言ってくれた。一ヶ月でも、乗れれば、御の字だ。故障した時、修理代が、10万円、以下だったら、修理して乗ろう。修理代が高かったら、ガリバーで、売るなり、廃車にして、別の車を買うなりすれば、いいや)
と、僕は思った。
○
翌日。
さっそく、僕は、新しく買ったラパンで、大磯ロングビーチに行くことにした。
僕は、朝の8時に、アパートを出た。
大磯ロングビーチは、朝9時から、入場開始である。
途中、日焼け止めのオイルを買うために、僕は、コンビニに、入った。
そして、日焼け止めのオイルと、ついでに、ポカリスエットを買って、車にもどって、エンジンを駆けて、車を走らせた。
僕は、鼻歌を歌いながら、いい気分で、走っていた。
そのうち、赤信号の交差点になった。
僕は、ふと、バックミラーを見た。
20代に間違いない、きれいな、女の人が、後部座席に乗っていた、からだ。
僕は、びっくりした。
「あなたは、誰ですか?」
僕は聞いた。
「佐藤由香里といいます」
彼女は答えた。
「どうして、この車に乗っているのですか。というか、どうやって、この車に乗ったのですか?」
僕は聞いた。
「あ、あの。さっき、あなたが、コンビニの駐車場に、車をとめた時に、勝手に、入ってしまいました。ごめんなさい」
彼女は答えた。
僕は、さっき、コンビニに、入った時、車にキーをかけるのが、面倒なので、キーを、かけずに、コンビニに入った。
彼女は、僕が、コンビニに、入った隙に、車に、乗り込んだんだろう。
「でも、どうして、僕の車に乗り込んだんですか?」
僕は、疑問に思って、聞いた。
「あ、あの。私。あのコンビニで、親指を上げて、ヒッチハイクしていたんです。でも、どの車も、止まってくれなくて・・・。それで、勝手に、あなたの車に乗り込んでしまったんです。ごめんなさい」
と、彼女は言った。
「そうですか。でも、あなたのような、きれいな人なら、止まってくれる車も、あったんじゃないでしょうか?」
僕は、疑問に思って、聞いた。
「いえ。男の人が、運転している車は、みんな、助手席に、彼女が、乗っていて・・・止まってくれませんでした」
と、彼女は言った。
それは、もっともなことだ、と、僕は、思った。
彼女とのドライブなら、たとえ、美人であっても、見知らぬ女を、男は、乗せたりはしない。
彼女との、二人きりの、アツアツを、楽しみたいからだ。
「でも、車の数は多いです。男一人の車も、何台かは、あったのでは、ないでしょうか?」
僕は聞いた。
「ええ。確かに、男の人が一人で運転している車も、数台は、ありました」
「では、なぜ、その車に、ヒッチハイクの合図をして、乗らなかったのですか?」
「男の人が、なんだか、みんな、エッチなこと、してきそうに思われて、こわかったんです」
彼女は答えた。
「僕は違うんですか?」
「ええ。あなたは、真面目で、優しそうに、見えたので・・・」
「そうですか。そう言ってもらえると、嬉しいです」
人間は、なかなか、自分を客観視できないものである。
僕は、女性に、そのように、見られていることに、嬉しくなった。
「ところで、あなたは、どこに、行くのが目的なんですか?」
僕は聞いた。
「えっ」
と、彼女は、言葉を詰まらせた。
「ヒッチハイクするっていうのは、行く目的地があるからじゃないですか。それを、教えてもらえないと、あなたを、目的地に連れていけないじゃないですか」
僕は聞いた。
「私を、私の目的地まで、連れていって下さるのですか?」
「ええ」
「でも、あなたも、どこかに、行く予定があるんじゃないんでしょうか?」
彼女が聞いた。
「え、ええ。そりゃー。ありますけれど、急ぐ用でもないし、あなたを、あなたの、目的地まで、連れていきますよ」
僕は言った。
「やっぱり、思った通り、優しい方なんですね」
彼女は、嬉しそうに言った。
「そうでしょうか?」
僕は、聞き返した。
「そうですわ。男なんて、女を、ヒッチハイクしたら、みんな、呈のいいことを言って、結局は、100%、ラブホテルに、連れ込みますわ。それが、こわいから、女は、ヒッチハイクがこわくて、出来にくいんです」
彼女が言った。
「そんなものですか?」
僕は、友達づきあい、が、ほとんどないので、彼女がいないのは、もちろんのこと、世の男が、どういうことを、考えているのかも、あまり知らなかった。
「ええ。そんなものです」
彼女は言った。
「ともかく、あなたの行く目的地を教えて下さい」
僕は彼女に聞いた。
「あ、あの。私の目的地なんて、ないです」
彼女は、あっさり、言った。
僕は、おどろいた。
「じゃあ、なんで、僕の車に乗り込んだんですか?」
「あなたと、ドライブして、少し、お話しがしたかったからです」
「ええっ。本当ですか?」
僕は、耳を疑った。
「ええ。本当です」
彼女は、あっさり、言った。
「じゃあ。あなたが、僕の車に、乗り込んだのは、僕と、ドライブするためですか?」
僕は聞いた。
「ええ。そうです」
僕は、信じられない思いだった。
なにか、裏があるんじゃないか、とも、考えた。
しかし、まあ、ともかく、彼女の言うことを、素直に信じることにした。
「うわー。嬉しいなー。あなたのような、きれいな人と、ドライブ出来るなんて・・・。夢のようだ。僕、女の人と、つきあったことが一度もないんです。僕は、岡田純と言います」
僕は、飛び上がらんばかりに、喜んで、そう言った。。
「ところで、あなたは、どこへ行く予定だったんですか?」
彼女が聞いた。
「僕は、大磯ロングビーチに、行こうと、思っていました」
僕は、答えた。
「じゃあ、私も、大磯ロングビーチに、連れて行って下さい」
彼女が言った。
「本当に、いいんですか?」
僕は彼女に確かめた。
「ええ」
彼女は、あっさり、言った。
「うわー。嬉しいな。僕、女の人と、大磯ロングビーチに、行くのが、夢だったんです」
僕は、信じがたい思いだった。
しかし、バックミラーから、見える彼女の顔は、嬉しそうに、ニッコリ笑っていた。
しばし行くと、道の左手に、コンビニが、見えてきた。
「そうとわかれば・・・」
僕は、そう言って、左のウィンカーランプを点けて、左折して、コンビニの駐車場に入った。
そして、車を止めた。
「さあ。佐藤由香里さん。後部座席ではなく、助手席に乗って下さい」
そう言って、僕は、ドアロックを解き、助手席のドアを開けた。
「はい」
彼女は、僕の要求どおり、後部座席から出て、助手席に乗った。
「由香里さん。飲み物は、何がいいですか?」
僕は彼女に聞いた。
「何でも、いいです」
彼女は、答えた。
「では、オレンジジュースで、いいですか?」
「はい」
僕は、コンビニに、入って、500mlの、ペットボトルの、オレンジジュースを買い、ストローを一本、貰って、車にもどった。
「はい」
と言って、僕は、彼女に、オレンジジュースを渡した。
「ありがとう。純さん」
と、彼女は、礼を言って、オレンジジュースを、受けとった。
僕は、エンジンを駆けて、車を走らせた。
「咽喉が、渇いたでしょう。オレンジジュースを飲んで下さい」
僕は、運転しながら言った。
「はい」
彼女は、ペットボトルの蓋を開け、ストローを、その中に入れ、オレンジジュースを飲んだ。
コクコクと、彼女の咽喉が、動く様子が、可愛らしかった。
「僕も、咽喉が、渇いたなあ」
僕は、思わせ振りに言った。
「あ、あの。純さん。私が口をつけてしまった、オレンジジュースですが、飲まれますか?」
彼女が聞いた。
「ええ。飲みたいです。でも、僕は、運転しているから、手を離せません。片手運転は危険です」
僕は、思わせ振りに言った。
「で、では・・・」
そう言って、彼女は、ストローの入った、オレンジジュースを、僕の口の所に持ってきた。
僕は、ストローを口に含み、オレンジジュースを、啜った。
「ふふふ。これで、由香里さんと、間接キスしちゃった」
僕は、そんなことを言って、笑った。
彼女は、少し、恥ずかしそうに、顔を赤らめた。
「由香里さん。何か、歌を歌ってくれませんか?」
僕は彼女に頼んだ。
「何がよろしいでしょうか?」
「何でもいいです。由香里さんの、好きな歌を歌って下さい」
「わかりました。では、小坂明子の、あなた、を歌います」
そう言って、彼女は、小坂明子の、あなた、を歌い出した。
「もーしもー。わたしがー、家をー、建てたなら―。小さな家を建てたでしょう・・・♪」
彼女の歌は、上手かった。
「いやー。由香里さん。歌。上手いですね。歌手になれますよ」
僕は、感心して言った。
お世辞ではない。
「い、いえ。そんなに・・・」
彼女は謙遜して、顔を赤らめた。
○
そうこうしている、うちに、大磯ロングビーチに、ついた。
僕たちは、車を降りた。
「純さん」
「はい。何ですか?」
「あ、あの。私。水着、持っていないんです」
彼女は言った。
「ははは。大丈夫ですよ。場内で売っていますから」
「大人二人。一日券」
と言って、僕は、入場券を買い、大磯ロングビーチに入った。
僕は、場内にある、水着売り場で、彼女に、セクシーな、ビキニを買ってあげた。
ビキニ姿の、彼女は、ものすごくセクシーだった。
僕は、スマートフォンで、彼女の、ビキニ姿を、何枚も撮った。
そして、僕と彼女が、手をつないでいる写真も、何枚も撮った。
僕と彼女は、ウォータースライダーや、流れるプールで、うんと、楽しんだ。
「今日は、僕の人生で、最高に幸せな一日です」
僕は彼女に、そう言った。
し、実際、その通りだった。
○
12時を過ぎ、1時に近くなった。
「由香里さん。何か、食べましょう。由香里さんは、何が食べたいですか?」
僕は彼女に聞いた。
「私は、何でも、いいです。純さんと、同じ物でいいです」
と、彼女は言った。
「そうですか。じゃあ、焼きソバでいいですか?」
「ええ」
僕は、焼きそば、を、二人分、買った。
そして、彼女と一緒に食べた。
「あ、あの。純さん」
「はい。何ですか?」
「私。純さんに、言わなくてはならないことがあるんです。そして、謝らなくてはならないことがあるんです」
彼女は、あらたまった口調で、言った。
「はい。何でしょうか?」
「このことは、最初に言うべきだったんです。ですが、純さんが、優しくて、私も楽しくて、つい、言いそびれてしまいました。本当に、申し訳ありません」
と、彼女は、深刻な口調で言った。
「はい。それは、一体、何でしょうか?」
僕には、どういうことか、さっぱり、わからなかった。
彼女に、何か、謝るべきことなど、僕には、さっぱり思いつかなかった。
「あ、あの。私。実は、幽霊なんです」
彼女は言った。
「そうですか」
僕は、あっさりと言った。
「あ、あの。純さんは、幽霊がこわくないんですか?」
彼女は聞いた。
「こわくありませんね。僕は、幽霊の存在なんて、信じていません。し、仮に、幽霊がいたとしても、こわくありません」
僕は、キッパリと言った。
「僕は、唯物主義を信じていて、精神も、脳の神経回路の活動によるものだと、確信しています。物質によらない、精神の存在など、無いと、信じています。なので、もちろん、無神論者だし、「神」だの、死後の、「天国」だの、「地獄」だのも、もちろん、存在しない、と、確信しています。それらは、人間の想像力が、生み出した、産物だと確信しています」
と、僕は、自分の信念を、言った。
「そうですか。でも、本当に、私は、幽霊なんです」
と、彼女は言った。
「由香里さん。それにですよ。仮に、あなたが、幽霊だとしても、あなたは、僕に、何の危害も加えません。なので、由香里さん、が、仮に、幽霊だとしても、僕はこわくは、ありません」
と、僕は、キッパリと言った。
「純さん、や、多くの人々が、唯物論を信じるのは、無理のないことだと思います。だって、神さまは、幽霊や、霊魂や、死後の世界などを、知らせると、人間が、こわがって、しまって、人間世界が、混乱してしまう、ことを、心配して、人間には、それらのことは、知らせませんもの」
と、彼女は言った。
「そうですか」
と、僕は、言った。
なるほど、彼女の言い分にも、一理あるな、と思った。
人間は、一度、死んだら、生きかえることは、出来ない。
死んで、その後、生きかえって、死後、人間は、どうなるのか、その体験を、語った人間は、いないのだから。
だから、人間は、死後、どうなるのかは、本当は、わからないのである。
物質に全く依存しないで、独立して、存在する、精神、というものも、無い、と、科学的に、証明されてはいない。
僕は、証明されていない事は、信じることも、否定することも、しない主義である。
なので、彼女の言うことを、僕は、頭から、否定する気には、なれなかった。
彼女の言うことを、傾聴しようと思った。
「あなたが、幽霊だと、言うのなら、一応、それを信じましょう」
僕は、言った。
「信じてくれて、ありがとうございます」
と、彼女は言った。
「ところで、あなたは、さっき、僕に、謝らなくてはならないことが、ある、と、言いましたよね。それは、一体、何なのですか?」
僕は、彼女に聞いた。
「そのことなんです。単刀直入に、率直に、正直に言います。私は、幽霊です。そして幽霊である、私と一日、付き合った人間は、一年間、寿命が短くなるんです。もう、私は、純さんと、一日、つきあいましたから、純さんの寿命は、一年間、短くなっているんです。これは、最初に言うべきでした。ごめんなさい」
と、彼女は、涙を流しながら、謝った。
「そうですか。でも、別に、僕は、それでも構いませんよ」
僕は言った。
「どうしてですか。純さんは、寿命が短くなることが、こわくは、ないのですか?」
彼女は聞いた。
「こわくは、ないですね。人間は、いつかは、死にます。それが、一年、短くなったからといって、僕は、別に気にしません。僕は、人間の価値は、いかに長く生きるか、ではなく、生きている間に、何事をなすか、だと思っています。今日、あなたと、楽しく過ごすことが出来た、一日は、歳をとって、寝たきりになって、何も出来ないで、過ごす、一年間より、はるかに、価値があると、思っています。それに、あなたが、幽霊だという主張は、僕は、一応、信じることにしているだけで、僕は、あなたが、幽霊だという主張を、完全には、信じては、いませんし、僕の寿命が一年、短くなった、という、あなたの、主張も、完全には、信じることは、出来ませんから」
と、僕は言った。
「ありがとうございます。そう言って、いただけると、この上なく嬉しいです」
と、言って、彼女は、また、泣いた。
「由香里さん。ところで、あなたは、どうして幽霊になってしまったのですか?」
僕が聞くと、彼女は、また、ポロポロと、涙を流し出した。
そして、語り出した。
「私は、純さん、が、買った車に、はねられて、死にました。大学を卒業して、晴れて、ある、アパレル会社に就職した、社会人一年目の年です。真夜中に、あの車を運転していた人に、はねられて、死んでしまったのです。はねた人は、真夜中で、誰も周りに人はいませんでしたが、すぐに、車を止めて、警察と、消防に、連絡してくれました。でも、私は、アスファルトの道路に、頭を強くぶつけていて、即死でした。ですから、私は、彼を怨んではいません。でも、私も、男の人と、一度もつき合ったことが、なく、どうしても、優しい男の人と、楽しい恋愛を、楽しみたい、という願望が、あまりにも、強くあって、それが、心残りで、どうしても、成仏できないのです。それで、成仏できずに、あの車に、幽霊として、居続けることになってしまったのです」
と、彼女は語った。
僕の心は、彼女の主張を信じる方に、かなり傾いた。
中古車店の、店長が、あんなに、新車に近い、いい、車を、ほとんど、タダに近い、安い金額で、売ってくれたことの理由が、彼女の訴えによって、説明が、つくからだ。
僕は、彼女の言うことを、一応、信じることにした。
「そうだったんですか。それは、気の毒ですね。あなたは、今まで、とても、つらい思いをしてきたんですね。でも、さっき、言った通り、僕は、年老いて、寝たきりになってからの、一年、より、今日の、あなたとの楽しい一日の方が、はるかに、価値があるんです。ですから、気にしないで下さい。今日は、うんと、楽しみましょう」
と、僕は言った。
「ありがとうございます。純さん」
そう言って、彼女は、涙をポロポロ流した。
○
その後は、もう、彼女とは、辛気臭い、暗い話はせず、波のプール、や、流れるプールで、彼女と、水をかけあったり、つかまえっこをしたりと、うんと、夏の楽しい、一日を過ごした。
○
時計を見ると、もう、4時30分だった。
大磯ロングビーチは、以前は、6時まで、営業していたが、最近は、不況で、経営が厳しく、午後5時で、閉館となっていた。
もう、あと、30分しかない。
昨日から、平塚七夕まつり、が、始まって、今日は、2日目だった。
「由香里さん。今日は、平塚七夕まつり、を、やっています。行きませんか?」
僕は、彼女に聞いた。
「ええ。ぜひ、行きたいわ」
彼女は、ニコッと、笑って答えた。
僕と彼女は、大磯ロングビーチを、出た。
そして、国道1号線を、走って、平塚駅に向かった。
東海道線の下りで、平塚の次が、大磯で、一駅、だけで、距離も、4kmなので、すぐに、平塚に着いた。
平塚七夕まつり、は、関東三大七夕まつり、の一つである。
来場者は、145万人と、大規模である。
平塚駅の北口の、駅前の、三つの、大通りには、隙間の無いほど、びっしりと、露店が、並んでいた。
大勢の人が、賑やかに行き来していた。
僕と彼女は、金魚すくい、を、したり、焼きトウモロコシ、や、綿アメを、食べたりした。
「金魚すくいって、可哀想ですね」
と、彼女は、言った。
「どうしてですか?」
僕は聞いた。
「だって、金魚は、弱って、動きの鈍い、金魚ばかりが、狙われるんですもの」
と、彼女は、言った。
「そうですね。でも、すくった金魚を、家に持ち帰りたい人は、元気な金魚を狙うんじゃないんですか」
と、僕は言った。
こんな、他愛もないことでも、お祭りは、楽しいのである。
僕は、彼女と、手をつないで、露店を見ながら歩いた。
彼女が、浴衣でないのが、ちょっと残念だった。
通りの中には、お化け屋敷、があった。
入場料、500円と書いてある。
「由香里さん。あれに入って、みませんか?」
僕は、彼女に言った。
「え、ええ。でも、なんだか、こわそうだわ」
彼女は言った。
「何を言ってるんですか。お化け屋敷なんて、人間を、こわがらせるために、巧妙に、わざと、こわく見えるように、作った偽物であって、本当の、お化け、なんかじゃないですよ。その点、あなたは、幽霊じゃないですか」
と、僕は言った。
「でも、本当に、こわいんですもの」
と、彼女は言った。
「ともかく、入りましょう」
と、言って、僕は、二人分の、入場料の、1000円を、払って、彼女と、お化け屋敷、に、入った。
彼女は、入る前から、こわいのか、私の腕をガッシリと、握っていた。
お化け屋敷、の中は、うす暗かった。
お岩さん、や、ろくろ首、や、フランケンシュタイン、や、ドラキュラ、や、化け猫、や、ミイラ、などが、バッと、いきなり、出てきた。
その度に、彼女は、
「うわー」
「きゃー」
「ひいー。こ、こわいー」
と、大声で、叫んで、僕に、ガッシリと、しがみついた。
僕は、こんなのは、全然、こわくなかったので、平然としていた。
そして、やっと、お化け屋敷、を出た。
「ああ。こわかったわ。こわくて、ショック死するかと思ったわ」
と、彼女は、ハアハアと、息を荒くしながら、言った。
僕は、ははは、と、笑った。
「何を言ってるんですか。あなたは、幽霊で、もう、死んでいるんじゃないですか。死んでいる幽霊が、死ぬかと思った、なんて、発言は、矛盾していますよ」
僕は、やはり、彼女は、幽霊ではないのではないか、と思った。
「でも、本当に、こわかったんですもの」
と、彼女は言った。
「そうですか」
幽霊とは、そんなものなのか、と、僕は、ちょっと、違和感を感じた。
お化け、を、こわがる幽霊というのも、変なものだと思った。
「本当に、こわいのは、あなたの方ですよ。だって、あなたは、幽霊なんですから」
と、僕は彼女に言った。
「じゃあ、純さんは、何で、私を、こわがらないんですか?」
彼女は僕に聞いた。
「それは、あなたが、こわい容貌ではなく、美人で、可愛いからです。それと、僕は、あなたが、幽霊であるとは、完全には、信じ切っていません。車の値段が、安すぎるのが、いまだに、不思議ですが、あなたが、幽霊だというのなら、車の値段が、安かった説明が、あなたの主張によって、つくから、一応、信じることに、しているだけ、だからです」
と、僕は言った。
○
「由香里さん。もう、帰りましょう」
「はい」
僕と、彼女は、駐車場に停めておいた、車にもどった。
「純さん。今日は、楽しかったです。ありがとうございました」
「僕も、楽しかったです。今日は、最高に楽しい一日でした。ありがとうございます。由香里さん」
「あ、あの。純さん」
「はい。何でしょうか?」
「これからも、私と、つきあってくれますか?」
「ええ。大歓迎です」
「でも、私は、幽霊ですから、一日、私とつきあうと、純さんの寿命が一年、縮まりますよ。それでも、つきあって下さいますか?」
「僕は、あなたを、まだ、完全に、幽霊だと、信じ切ることが、出来ないのです。だから、その質問には、答えようが、ありません。あなたが、幽霊だということを、証明することが、出来ますか?」
「わかりました。では、証明します。それでは、一度、車から、降りて、私の写真を撮って下さい」
彼女は、そう言った。
僕は、彼女に、言われた通り、車から、降りた。
彼女も車から出た。
彼女は、車の前に、立った。
「さあ。純さん。車を背にして、立っている、私の、写真を、たくさん、撮って下さい」
彼女は言った。
「はい。わかりました」
僕は、車を背にして、立っている、彼女の、写真を、たくさん、撮った。
「純さん。私の顔写真も、たくさん、撮って下さい」
彼女は言った。
「はい。わかりました」
僕は、彼女の、顔写真も、たくさん、撮った。
彼女は、口を、アーンと、大きく開いた。
「純さん。口を開けている、私の顔も、撮って下さい」
彼女に言われて、僕は、口を開けている、彼女の顔も、撮った。
こんな事をして、何になるのかと、僕は、疑問に思いながら。
「では、AKB48の、ヘビーローテーションを、踊りながら、歌いますので、その動画も、撮って下さい」
彼女は言った。
「はい。わかりました」
彼女は、車の前で、踊りながら、歌い出した。
「ポップコーンが、弾けるように、好きという文字が躍る・・・・♪」
彼女の歌は、上手かった。
しかし、こんな事をして、何になるのかと、僕は、疑問に思っていた。
歌い終わると、彼女は、
「では。車にもどりましょう」
と、彼女が言った。
僕と、彼女は、車にもどった。
彼女は、助手席に座った。
「純さん。私の指紋をとって下さい」
彼女が言った。
僕は、彼女の指紋をとった。
「純さん。私の髪の毛を、数本、とって下さい」
彼女が言った。
僕は、彼女の、髪の毛を、数本、とった。
「では。私が、幽霊だということを、証明します。茅ヶ崎に、私の実家がありますので、そこへ行って下さい。場所は、私が、案内します」
「わかりました」
僕は、車のエンジンを駆けた。
そして、国道一号線を、藤沢の方に、向けて、走り出した。
彼女は、「そこの交差点を左に」とか、「そこの交差点を右に」とか、言った。
僕は、彼女の言う通りに、車を運転した。
○
「純さん。車を止めて下さい」
彼女が言ったので、僕は、車を止めた。
「あそこの、二階建ての、青い屋根の家が、私の実家です」
そう言って、彼女は、少し先にある、二階建ての、青い屋根の家を指差した。
「では。純さん。私の家族に、さっき、スマートフォンで、撮った、写真や、動画を、見せて下さい。そうすれば、私の言っていることが、本当だということが、証明できます。私は、ここで待っています」
彼女は、自信に満ちた口調で言った。
「わかりました」
そう言って、僕は車を降りた。
そして、二階建ての、青い屋根の家の前に行った。
表札には、「佐藤圭介」、と、書いてある。
彼女の苗字は、「佐藤」だから、合っている。
僕は、チャイムを押した。
ピンポーン。
家の中で、チャイムの音が、響くのが、聞こえた。
「はーい」
女性の声が聞こえて、パタパタ、走ってくる音が聞こえた。
すぐに、玄関が開いた。
一人の、中年の、女性が姿を現した。
「どちらさまでしょうか。ご用は何でしょうか?」
女性は、僕を見ると、そう聞いた。
「あの。ここは、佐藤由香里さんの、お宅でしょうか?」
僕は聞いた。
「由香里は死にました。あなたは、どなたでしょうか?」
女性が聞いた。
「ちょっと、由香里さん、と、縁のある者です。由香里さんに関して、お聞きしたいことが、あります。なので、少し、お話しを聞かせて欲しいのです」
僕は言った。
「由香里の、生前の、お友達ですか?それなら、どうぞ、お入り下さい」
そう言って、彼女は、僕を家に入れてくれた。
僕は、居間に通された。
「どうぞ。お座り下さい」
僕は、彼女に勧められて、居間のソファーに座った。
「あなたは、由香里さん、と、どういう関係の人でしょうか?」
僕は聞いた。
「私は、死んだ由香里の母です」
と、彼女は言った。
「そうですか」
と僕は、言った。
確かに、顔が、彼女と、似ている。
「ところで、あなたは、由香里と、どういう関係の人でしょうか?」
今度は、彼女が僕に、聞いた。
「僕は、由香里さん、の友達です」
僕は言った。
「そうですか」
彼女は、少し、憔悴ぎみの顔で言った。
○
「あの。これを見て欲しいのです」
そう言って、僕は、スマートフォンを、テーブルの上に置き、さっき、撮った、写真や、動画を再生して見せた。
「ああっ。由香里だわ。これは、いつ、撮られたのですか?」
母親は聞いた。
「少し前です」
僕はそう言った。
「この人は、本当に、あなたの、娘さんの、由香里さん、ですか?」
僕は、念を押すように聞いた。
「間違いありません。これは、娘の由香里です。母親の私が、娘を間違うはずなど、ありません。右足の甲に、由香里の、ほくろ、も、ありますし、右の眉毛の所に、子供の頃、怪我をして、縫った小さな傷痕もありますし、口を開けている写真では、右下の奥から二本目に、治療した、銀歯も、ありますし。娘が、得意だった、ヘビーローテーションの、踊り方も、声も、娘に間違いありません」
母親は、昔を思い出して、少し涙ぐんで言った。
「それに、由香里が着ている服は、由香里が、事故で死んだ時に、着ていた服です」
母親は言った。
「でも、不思議ですわ」
母親が言った。
「何がですか?」
「由香里が背にしている車は、由香里が、はねられた車です。青のラパンです」
「そうですか。でも、青のラパンなど、いくらでも、走っています。由香里さん、が、はねられた車か、どうかは、わからないでは、ないですか?」
「それは、その通りですね。ところで、こういう写真を持っているということは、あなたは、由香里と、かなり、親しい仲だったんですね?」
「え、ええ。まあ、そうです」
と、僕は言った。
○
「ところで、由香里さん、の写真は、ありますか?」
僕は聞いた。
「ええ。あります。ちょっと、待っていて、下さい。由香里の部屋に行って、とってきます」
そう言って、母親は、階段を昇っていった。
そして、母親は、すぐに、アルバムと、パソコンを、持って、もどってきた。
「これが、由香里の写真です」
そう言って、母親は、アルバムを開いた。
アルバムには、彼女の子供の頃から、大学の卒業式、や、会社に入社した時の、写真が、たくさん、載っていた。
確かに、それは、由香里さん、だった。
高校生の頃の、彼女の写真も、今の、彼女の面影がある。
「これも、見て下さい」
母親は、そう言って、パソコンのディスプレイを、表示させた。
「これは、由香里が、友達と、飲み会をした時に、カラオケ喫茶で、由香里の友達が、撮影してくれた動画です」
そう言って、母親は、スタートボタンを押した。
パソコンのディスプレイに、彼女が、AKB48の、ヘビーローテーションを、踊りながら、歌っている、動画が、映し出された。
その、声も、踊り方も、さっき、見た、彼女の、ヘビーローテーション、と、全く、同じだった。
「うーん」
僕は、唸った。
やはり、彼女は、彼女が言うように、幽霊なのかも、しれないな、と、僕は、思うようになった。
「あなたは、由香里と、親しかった人なんですね?だって、一緒に、レジャープールに行くほどなんですから」
母親が聞いた。
「ええ。そうです」
僕は答えた。
「では。由香里の冥福を、祈って、焼香してやって下さい」
母親が言った。
僕は、二階の、由香里さん、の部屋に入った。
由香里さん、の、写真が祀られた、額縁と、由香里さん、の、位牌が、あった。
僕は、手を合わせて、由香里さん、の、冥福を祈った。
「由香里さん、が、死んだ、ということを、僕は、最近、知りました。ちょっと、変わった、お願いがあるんですが・・・」
僕は言った。
「はい。何でしょうか?」
母親は、聞き返した。
「由香里さん、が、死んだ、ということを、証明できる、ものが、他に何か、あるでしょうか?」
僕は聞いた。
「由香里は、本名で、ブログをやっていました。由香里が死んでも、ブログは、残してあります」
母親は、そう言って、彼女のブログを、見せてくれた。
ブログには、彼女の写真も、たくさん、載っていた。
そして、最後のブログの記事のコメントには、「由香里。悲しいわ。でも、あなたは、立派に生きたわ。私。あなたを、いつまでも、忘れないわ」、などと、いう、友達のメッセージが、たくさん、載っていた。
そして、パソコンで、「佐藤由香里」で、検索すると、「茅ヶ崎市に住む、東海大学、文学部教授の、一人娘の、佐藤由香里さん、が、昨日、自動車事故で亡くなられました」という、記事が、いくつも、出てきた。
「うーん」
と、僕は、唸った。
ここまで、物的証拠があれば、彼女が、本当に、幽霊だということを、信じるしか、ないな。
と、僕は思った。
「どうも、色々と、ありがとうございました」
そう言って、僕は、彼女の家を出た。
○
そして、車にもどった。
助手席には、彼女が、座っていた。
「どう。私が、幽霊だということが、確信できましたか?」
彼女は僕に聞いた。
僕は、黙っていた。
「まだ、信じられない、というのなら、私の部屋には、私の指紋が、いっぱい、ついているから、私の指紋と、照合しても、いいわよ」
と、彼女は言った。
「由香里さん。あなたは、幽霊になったのなら、どうして、お母さんと、会わないのですか?」
僕は聞いた。
「それは。幽霊と、出会うと、寿命が、一年、縮まるからですよ。私。お母さんの寿命を、縮めたくないもの。それに、私が、成仏できないで、幽霊になってしまった、ということを、おかあさん、が、知ったら、驚くし、不安になるでしょ。それに、幽霊が、本当に、存在する、などと、わかったら、世間を騒がせて、混乱させてしまうでしょ。私、世間を混乱させたくないもの」
と、彼女は、飄々と言った。
「なるほど」
と、僕は言った。
「指紋を照合しても、また、信じられない、というのなら、私の髪の毛で、DNA解析して、調べて下さい。母は、私の遺髪として、私の髪の毛を、持っていますから。DNAが、一致したら、確実に、私だと、証明されるでしょ」
と、彼女は言った。
「いや。由香里さん。その必要はありません。ここまで、確かな証拠が、そろっていれば、僕は、あなたが、幽霊だということを、100%、確信しました」
と、僕は言った。
「ありがとうございます。やっと、信じていただけて、嬉しいです」
と、彼女は、嬉しそうに言った。
「僕は、唯物論を信じ切っていません。確かに、この世の事のほとんどは、唯物論で、説明できます。しかし、人間は、時間、というものを、説明することが出来ません。時計の針の、動きは、時間を、便宜的に、図るための道具に過ぎません。宇宙に、上下があるのかも、説明できません。し、宇宙のはて、は、どうなっているのか、も、わかりません。死後、人間は、どうなるのか、物質によらない精神というものは、存在しない、ということも、科学的に証明されていません。僕は、証明されていないことは、否定しない主義です。ですから、ここまで、証拠が、そろえば、僕は、あなたが、幽霊だということを、信じます」
と僕は言った。
「ありがとうございます。やっと、信じていただけて、嬉しいです」
と、彼女は、嬉しそうに言った。
○
「あ、あの。純さん」
「はい。何でしょうか?」
「私が、幽霊だと、信じてもらえましたが、こんな私でも、これからも、つきあってくれますか?」
「ええ。大歓迎です」
「でも、私は、幽霊ですから、一日、私とつきあうと、純さんの寿命が一年、縮まりますよ。それでも、つきあって下さいますか?」
「ええ。構いませんよ」
「嬉しいわ」
そう言って、彼女は、涙を流した。
「ところで、由香里さん」
「はい。何でしょうか?」
「あなたと、一日、つきあうと、僕の寿命が一年、縮まるんですよね」
「ええ。そうです」
「僕は、今、二十歳です。僕が、何歳まで、生きられるのかは、わかりませんけれど、平均寿命から考えて、80歳まで、生きられる、と、仮定しましょう。すると、あなたと、これから、毎日、つきあうと、60日後、つまり、二ヶ月後に、僕は、死ぬことになりますね」
「ええ。そうです」
「そこで、僕に提案があるんです。あなたと、つきあう一日は、充実した、一日にしたいですね。毎日、つきあうと、僕は、60日で、死ぬことになります。しかし、月に一度だけ、会う、というように、すれば、60/12=5年、あなたと、結婚生活を、送れることが出来ます。月に、一度でなくても、月に二度でも、構いませんし、あるいは、逆に、二ヶ月に、一度、会う、と、いうように、しても、いいんでは、ないでしょうか。二ヶ月に、一度、会う、とすれば、60/6=10年、あなたと、結婚生活を、送れます。どのくらいの、頻度で会うかは、あなたに任せます」
「なるほど。そういう方法もありますね。気がつきませんでした」
と、彼女は言った。
「結婚生活なんて、毎日、顔を見ていると、惰性で、だんだん、新鮮味が、なくなるものですよ。ささいなことで、夫婦ケンカになったりも、しますしね。芸能人でも、一般の人でも、アツアツの想いで、結婚しても、その半分ちかくは離婚しています。毎日は、会えず、時たま、会える、という方が、いつまでも、新鮮でいられると、思います。毎日、会っていると、厭き、も、来やすいものです。会えない期間があった方が、会いたい、という、情熱が、強くなります。七夕にしたって、織姫と牽牛は、一年に一度しか、会えないから、二人の愛は、激しく燃えあがるのでは、ないですか。一年に一度、会うとすれば、僕は、あと、30年、生きられます。ゲーテも、「ふたりの愛を深くするにはふたりを遠く引き離しさえすればよい」、と言っています。プブリウス・オウィディウス・ナソも、「満ちたりてしまった恋は、すぐに退屈になってしまうものである」、と言っています。シェイクスピアも、「ほどほどに愛しなさい。長続きする恋はそういう恋です」、と言っています。どうでしょうか?」
「わかりました。純さん、って、理性的な方なんですね。ちょっと、拍子抜けしてしまいました。でも・・・」
と、言い出して、彼女は、少し、渋い顔になった。
僕は、彼女の思っている事をすぐに、察知した。
そのため、僕は、先手を打った。
「ははは。由香里さん。あなたが、不安に思っていることは、わかりますよ。会わない期間が長いと、僕が、心変わりして、他の女性と、つきあうように、なってしまうんではないかと、心配しているんでしょう?」
彼女は、黙っている。
「由香里さん。答えて下さい」
僕は、強気の口調で、問い詰めた。
「・・・え、ええ。恥ずかしいですけれど、その通りです・・・」
彼女は、顔を赤くして言った。
「その点は、大丈夫です。安心して下さい」
僕は、自信をもって言った。
「どうして、ですか。それを、証明して下さい」
今度は、彼女が、僕に証明を求めるようになった。
「だって、僕は、内気で、無口で、ネクラで、友達なんて、一人もいませんから。彼女をつくることなんて、不可能です。僕は、憶病ですから、女性に、声をかけることなんて、出来ません。僕は、今まで、一度も、彼女、というものを、つくることが出来ませんでした。これからも、つくれないしょう。だから、あなたと、会った時、僕は、有頂天になって、喜んだじゃないですか。僕が、女性と、デートするのは、今日が、生まれて初めてだと、言ったじゃありませんか。僕の、パソコンでも、スマートフォンでも、調べてもらえば、わかりますが、僕が、女性と、楽しそうにしている、写真なんて、一枚もありません。ですから、それが、僕の証明です。科学的には、証明できませんが、あとは、由香里さん、が、信じてくれる、か、どうかに、かかっています」
と、僕は言った。
「僕のスマートフォンを、見て下さい。もし、僕に、恋人が、いるのなら、スマートフォンに、恋人との、メールのアドレスや、恋人との、メールのやりとり、や、恋人と撮った写真が、のっているでしょう」
そう言って、僕は、彼女に、スマートフォンを渡した。
彼女は、スマートフォンを、受けとると、一心に、カチャカチャ操作した。
「どうです。何もないでしょう?」
僕は、彼女に聞いた。
「確かに、何もありません。わかりました。純さんを信じます」
と、彼女は言った。
「ところで、由香里さん」
「はい。なんでしょうか?」
「一日、つきうと、と、寿命が一年、縮まる、と、あなたは、言いましたが、一日というのは、24時間、ちょうど、ですか?」
「いえ。12時間です」
「そうですか。それなら、早く、アパートにもどらないと」
僕は、車のエンジンを駆け、アクセルをグンと踏んだ。
急いで、アパートに帰らねば、と思った。
なぜなら、今日一日、彼女と、つきあってしまったのだから、僕は、一年、寿命が、縮まってしまったのだ。
それなら、彼女と、少し、ペッティングも、したいと思ったからだ。
「ところで、由香里さん」
僕は、車を運転しながら聞いた。
「はい。なんでしょうか?」
「この次は、いつ、会う予定ですか?」
「それは、まだ、決めていません」
「そうですか。できれば、日曜日に、出てきてくれると、助かります。今度、あなたと、会う時は、ディズニーランドに、行きましょう」
「はい。ありがとうございます。楽しみだわ」
彼女は、嬉しそうに言った。
○
途中に、コンビニがあった。
「ちょっと、トイレに行ってきます。すぐ、もどってきます」
そう言って、僕は、コンビニに入った。
僕は、コンビニのトイレで、オシッコをして、すぐに、コンビニを出た。
急いで、車に入ったが、彼女は、いなかった。
そして、車の中には、彼女の服があった。
そして、メモがあった。
それには、こう書いてあった。
「純さん。ちょうど、12時間、経ちました。私は、消えます。この次は、いつ、お会いするかは、考えておきます。もしかすると、成仏できるかもしれません。由香里」
彼女と、今日、会ったのは、午前、8時頃で、今、ちょうど、午後8時である。
ちょうど、12時間、経ってしまったのだ。
僕は、ちょっと、残念だった。
○
それから、三ヶ月経った。
彼女は、現れない。
僕が、言ったように、彼女は、気をきかせて、くれているのだろう。
もしかすると、一年は、現れないかも、しれない。
さらに、もしかすると、彼女は、成仏できたのかもしれない。
まあ、しかし、僕としては、彼女がまた現われて、彼女と、ディズニーランドに行くのが、楽しみである。
○
しかし、日が経つにつれ、僕は、だんだん彼女が恋しくなった。
あんな、きれいな人と、出会えたんだから、ペッティングしておけば、良かった、と、僕は後悔した。
(もう、現れてくれないだろうか?)
僕は、彼女の、ビキニ姿の写真を見ながら、何回も、オナニーした。
彼女が、僕と会いたがっている、のと、同様に、僕も、彼女に会いたくなった。
だが、いつまで、経っても、彼女は、現れなかった。
「きっと、彼女は、成仏してしまったんだろう」
と、僕は、思って、あきらめだした。
○
それから、一年が経った。
僕は、由香里さん、のことなど、忘れていた。
もちろん、僕は、シャイで、憶病なので、彼女など、つくれない。
町で、手をつないで、歩いているカップルを、うらやましく、眺めるだけである。
七月七日になった。
「純さん。お久しぶり」
そう言って、ひょっこり、由香里さん、が、現れた。
びっくりすると、同時に、僕は、嬉しくなった。
「ああ。由香里さん。会いたかったよ」
僕は言った。
「私もよ」
彼女も言った。
僕は彼女を、ガッシリと抱きしめて、キスした。
「じゃあ、今日は、ディズニーランドに行きましょう」
「ええ」
こうして、僕と、由香里さん、は、ディズニーランドに行き、一年ぶりに、楽しい一日を過ごした。
前回、出来なかったので、一日、ディズニーランドで楽しんだ後は、近くのホテルに、入り、うんと、彼女と、ペッティングした。
「一年に、一回、くらいの、割り合が、良さそうだと思います。では。来年の、七月七日に、お会い致しましょう」
そう言って、12時間、経つと、彼女は、姿を消した。
僕は、来年の、七月七日が、待ち遠しい。
平成28年8月18日(木)擱筆
< 1 / 1 >