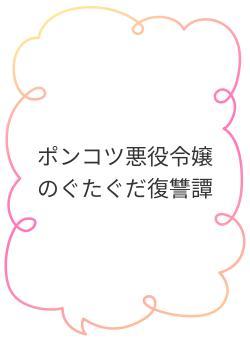フィナーレにくちづけを
1.夏空とビール
ついに、来てしまった。
愛実は多大なる緊張と、早くも心を侵食しつつある後悔と共に、駅のホームへと降り立った。
慣れない大きなサングラスを下にずらし、メモに記した地名と駅名標が一致していることを確かめる。その瞬間ぐっと重たくなったキャリーケースを転がし、人の流れに従って改札口を抜けた。真っ白なリボンのミュールでエスカレーターを降りていくと、むわりとした熱気が頬に触れる。つばの広いキャペリンハットを被り直しつつ、ゆっくりと外へ踏み出した。
そうして愛実が真っ先に捉えたのは、快晴の空と真っ青な海に浮かぶ、日差しを照り返す白が美しい豪華客船。
どっしりとした、されど気品を感じさせる巨大な方舟は、そこに招かれた乗客をさぞかし素敵な旅に連れ出してくれるであろう。
……が、しかし。
「──帰りたい……」
それを見た愛実の口からこぼれたのは、弱弱しい帰宅願望であった。
豪華客船の手前に広がる海の街を呆然と見渡し、ごろごろとキャリーケースを引っ張って木陰に入る。ショルダーバッグからスマホを取り出し、この一か月で何度消そうかと思った連絡先をタップした。
トーク画面を開くと、見計らったようにメッセージが届く。
『どこにいる?』
愛実が億劫な気分で「駅前のロータリーにいます」と返したときだった。
「何だ、合ってたのか」
「わあ!!」
真後ろから声を掛けられ、飛び上がるほど驚いてしまった。
慌ただしく振り返ると、そこには愛実をこの街へ呼び出した張本人が立っていた。
決まりすぎない程度に整えた黒髪、日本人にしては彫りの深い目元。飾らない白の開襟シャツに、腰を絞るベルトからすらりと伸びた黒いデニム。鎖骨に光るシンプルなチェーンネックレスが、彼の逞しい胸元をやけに扇情的に見せていた。
「ひと月ぶりだな、県愛実さん」
鼻の下までズレたサングラスを、大きな手にそっと直される。彼が口角を上げて囁いたなら、愛実もハッと我に返って咳ばらいをした。
「……お久しぶりです、松方鷹介さん。近くにいたなら普通に声をかけてください」
「仕方ないだろ、別人かと思ったんだ」
愛実のキャペリンハットを指先で軽く弾き、鷹介は彼女の装いに視線を遣る。
ネイビーにレモン柄を散りばめたノースリーブのシェルトップに、裾がふわりと広がる真っ白なロングスカート。大きめの帽子とサングラス、踵のあるミュールで元の高身長を更に底上げした愛実の出で立ちは、普段と比べれば確かに別人と言われても仕方ないだろう。
鷹介は愛実の姿を眺めながら顎を摩ると、満足げに笑った。
「良いな。──詐欺師っぽくて、実に良い」
そう見えるようコーディネートしたとは言え、なんとも不名誉で嬉しくない評価を貰ってしまった愛実は、ぶすっと唇を尖らせつつ「どうも」と返したのだった。
◇
遡ること一ヶ月ほど前。
愛実はその日、球場でビール販売のバイトに勤しんでいた。
大学を卒業して二年。一般企業への就職も考えたが、悩みに悩んだ末に彼女は自身の夢を優先した。
いや、夢と呼ぶには些か輝きが足りないかもしれない。憧れも、熱量も、がむしゃらな気持ちも、何もかも。
自分の中にあるものが燻った不満と執着ということに気付きながらも、彼女は目標を達成すべく忙しない日々を送っていた。
「おい姉ちゃん、ビール二つちょうだい」
「あっはい! ありがとうございます!」
強い日差しに目を眇めつつ階段を下りていくと、中年の男性に呼び止められる。愛実はすぐにその場に膝をつき、カップに生ビールを注いだ。
しゅわしゅわと音を立てる黄金色と、濃密な真っ白な泡。きちんと美味しそうに注げたところで、愛実はにっこりと笑みを浮かべてカップを渡そうとした。
「お待たせいたしま……」
「こら! はるくん! 走らないの! あ!!」
「え?」
ドッ、と愛実の体に振動が伝わり、背負ったビールサーバーに全身が引っ張られる。
はっとして後ろを見てみれば、ビールサーバーに正面衝突したであろう小さな男の子が尻もちをついていて。
男の子、目の前にいる男性、階段、ビール──一瞬の間に懸念事項がぐるぐると愛実の頭を駆け巡る。
そうして咄嗟に踏み出した片足で、まずは愛実自身が階段を転がり落ちないよう気合いで踏ん張る。続いて男性にビールをぶっかけてしまわぬよう、大きく揺れたビールカップをぐいと他所へ向けた。
愛実の瞬時の判断に、固唾をのんで見守っていた周囲の人達から「おお」と歓声が上がったのもつかの間。
「あ」
ばしゃ。
宙へと飛び出したビールは、階段を上ってきた一人の男性の顔面へと着地していた。
「あ……」
ずぶ濡れの呆けた顔。中途半端にこちらへ伸ばされた両手。
彼が愛実を助けようとしていたのは、一目瞭然であった。
「おっ、お客様!! 申し訳ございません!!」
愛実の悲鳴にも似た謝罪は、ホームランの歓声によって掻き消された。
「はは、いやぁびっくりした。ビールを顔面に食らったのは初めてだ」
──私も他人様の顔にビールをぶっかけたのは初めてです。
愛実は死刑宣告を待つ罪人よろしく、色を失ったまま突っ立っていた。
先ほどまで彼女の隣には球場の従業員を取りまとめるチーフが謝罪を繰り返していたのだが、責任者であるはずの彼はなぜか早々に退室させられ、愛実だけがここに取り残されている。
球場全体を悠々と見下ろすことのできる、高級感あふれるロイヤルレストラン。開放的な大窓のすぐ側、シャワーを浴びて身綺麗になった男性が、くつくつと肩を震わせて笑う。
「座ると良い。あんなに重いものを背負ってたんだから疲れただろう?」
「え……ですが、その……」
「別に君を叱りつけるために呼んだわけじゃない。安心してくれ」
てっきり土下座でもさせられるのかと思っていた愛実は、その言葉にまばたきを繰り返してしまった。正直すぎる反応だったのだろう、彼はまたおかしげに笑って「どうぞ」と席を勧める。
恐る恐る腰を下ろせば、まるで褒めるように彼の目が細められ、愛実は慌てて瞼を伏せておいた。
「さて。まずは自己紹介かな。俺は松方鷹介。こう見えて社長なんてものをやっていてね」
「え、しゃちょ……?」
「はいコレ名刺」
「あ、ご丁寧にどうもありがとうございます……」
鷹介はローテーブルに置かれた一枚の名刺を、すっと愛実の方へと滑らせる。
名刺には彼の名前と、松方商事──あまり経済方面に明るくない愛実でも聞いたことのある有名な商社の名前が印字されていた。
確か旧財閥系の会社だったような、とおぼろげな記憶を引っ張り出したのもつかの間、会社と同じ苗字を持つ目の前の人物を二度見する。
愛実の言わんとしていることを察してか、鷹介はにこりと口角を上げた。
「親の七光り野郎がって思った?」
「とっとんでもないです、苗字が一緒だなぁとか思っただけです」
「冗談冗談。俺が仕事をする上で、松方家の恩恵を受けてるのは本当だしな」
松方家。やはり彼はとんでもない大金持ちの家に生まれた人なのだと、そんな人に自分はビールをぶっかけてしまったのかと、愛実は天を仰ぎたい気分だった。かろうじて虚空を見つめるに留めたが。
愛実が己の行く末を憂いていることなど知らぬ素振りで、鷹介は「それで」と本題に入る姿勢を見せた。
「君は県愛実さんで合ってるかな?」
「えっ、は、はい」
「──十数年前よくテレビに出てた、県愛実さん?」
唐突に古傷を抉られたような気分になったが、ここで否定したところで何か意味があるわけでもなし、愛実は素直に、しかしぎこちなく頷く。
「ええと……はい。その県愛実ですね……」
天才子役、県愛実。
それが彼女の、早すぎた全盛期の呼び名だ。
とある映画に出演した際、彼女は僅か六歳で数々の賞を受賞した。監督から一発OKを貰ったシーンは、たったの三分。後に「奇跡の三分」とまで称されたそのシーンが、見る人全てを魅了した──らしい。
愛実からすれば既に十八年も前のことで、当時世間がどれだけ盛り上がっていたかなど、残念ながら彼女自身は全く知らない。
だが、おかげでさまざまな番組に引っ張りだこだったのは確かで、そのときの大変さはよく覚えていた。
……まぁそれも過去の栄光に過ぎず、今や愛実が巷の話題になることなど皆無である。
「やっぱりそうか! 大きくなったな」
何とも言えない気まずさに気分が沈みかけたとき、鷹介の毒気のない笑みと柔らかな声音がそれを吹き飛ばした。
愛実はつい呆けてしまった後、むず、と鼻がくすぐったくなった。
小さな頃からテレビに映っていたおかげで、見知らぬ人から「大きくなったね」と言われる機会は少なくない。それらはいつも、近所に住む幼子の成長を喜ぶような、温かい感情を乗せたものばかりだ。
愛実としても、大勢の人から見守られていた事実を実感できて嬉しく思うのが常なのだが──。
(……何だろ。年の近い人にあんまり言われたことないからかな。ちょっと変な感じ……しかももうとっくに成人してるし)
照れ臭さを隠しながらも小さく頭を下げれば、その仕草を見ていた鷹介がくすりと笑う。不意の優しい表情にうっかり見惚れてしまったせいで、愛実は次に放たれた言葉をすぐに理解できなかった。
「県愛実さん、ここで会ったのも何かの縁だ。ひとつ仕事を頼みたい」
「へ? お仕事、ですか?」
「そう。詐欺の仕事」
沈黙。
カキーン、と外から小気味よい音が響いたかと思えば、わっと歓声が上がる。愛実の時間が止まっている間に、打者は一塁を走り抜け二塁へと滑り込みを決めていた。
「……あの、家族と縁を切ってきてもいいでしょうか」
「うーん今のは俺が悪かった、冗談だ」
これが大富豪にビールをかけた代償ならやるしかないと覚悟を決めてしまいそうになったところで、すぐさま鷹介がストップをかける。
彼は軽く手招きをすると、前のめりになった愛実に囁いた。
「正確に言うと、君に詐欺師を演じてほしい」
「詐欺師を演じる……? ……えっと、舞台のお仕事ですか?」
愛実は高校や大学で演劇部に所属していた上に、今も単発アルバイトをしながら稽古に通い、小さな劇団で舞台に上がっている。
昨日も稽古に行っては、やれ演技が小さいだの地味だのと座長から指導を受けてダメージを負ったが、それでも舞台の仕事は続けていた。
それはさておき、詐欺師の役なんていうのは初めてだ。一体どんな脚本なのだろうと愛実が首を傾げていると。
「まぁ舞台のようなものかな。あそこは」
鷹介はジーンズのポケットからスマホを取り出すと、さっと何かを検索しては画面をスクロールする。
「ここ、知ってるかい」
くるりと反転したスマホに写っていたのは、真っ青な空を背景にした緑豊かな街並み。まるで海外のリゾート地よろしく美しい海、そこに浮かぶ真っ白な豪華客船や、太陽の光を照り返す真新しいビルの群れなど、写真映えする景色が次々と流れていく。
愛実は暫し呆けていたが、やがて見覚えのある駅が映し出されたことで「あっ」と目を丸くした。
「知ってます。テレビで見ました。何かあの……とんでもないお金持ちが集まるセレブ街ですよね」
「はは、そうそう。来月、ここで取引先の創立記念パーティーが開かれるんだ。俺も出席する予定でね」
「はあ。凄そうですね」
漠然とした感想を口にすると、鷹介はにこりと口角を上げる。
「そこが君の舞台だ」
「はい?」
「この創立記念パーティーで、君には俺の妻として出席してもらいたい」
再び訪れる沈黙。
球場はこれ以上にないほどの盛り上がりを見せていたが、愛実と鷹介のいるレストランはしんと静まり返っている。
意味が分からずに呆ける愛実を見て、鷹介は更に言葉を続けた。
「さっきも言ったが、ただの妻じゃあない。君は『俺にかけられた莫大な保険金を受け取るために結婚した女詐欺師』になって、周囲をこれでもかというほど搔き乱してほしい」
「え、はぁっ……!? そ、それ何か迷惑行為とかになりませんか!?」
「大丈夫、警察には話を通してある」
「警察!? ……警察?」
一度目の反芻には驚きを、二度目には懐疑を含めて聞き返す。
愛実が眉を顰めていると、鷹揚な動きで鷹介が頷いた。
「あまり驚かないで聞いてほしいんだが、俺は親戚から命を狙われていてね」
「驚きますし初対面の人間に話す内容でもないですよコレ」
「まぁそう言わずに。俺が狙われる理由は何だと思う?」
鷹介は何とも軽い調子で問いかけ、アイスコーヒーを一口飲む。
命を狙われている人間にしては焦りも恐怖も全く伝わってこないが、愛実は「ええと」と頬を掻いた。
「……松方さんのおうちって、その、やっぱり大家族です?」
「まぁな。それなりに古い家だから顔も知らない親戚が大量にいる」
「じゃあ、あー……遺産相続とか、でしょうか」
ドラマや映画の見過ぎだと、笑われるか叱られるのを期待していた愛実だったが、鷹介が褒めるように目を細めたのを見て頭を抱えてしまう。
「本当にあるんだ、そんなの……」
「困ったものだよな」
「他人事みたいに言うのやめてもらっていいですか」
危機感に欠ける鷹介はその返しにも笑っていたが、愛実の咎めるような視線を受けては肩を竦める。
「誰かが俺を殺そうとしていると知って、恐怖を感じるよりも呆れたのは事実さ。たかが金のために殺人を企てるなんて、どうかしているだろう」
「それは同意しますけど……。もしかして、もう既に身の危険を感じるような場面があったんですか?」
「会社に爆発物が届いた」
「ひっ……」
曰く、松方商事のオフィスに差出人不明の包みが届き、それを受け取った秘書は「中から妙な音がする」と言って警察に連絡したそうだ。
警察による調査の結果、中身が爆発物であったことが判明。包みを開封した瞬間に起爆するよう設計された、いわゆる郵便爆弾と呼ばれるものだった。
そして、その包みは松方商事の社長──すなわち鷹介に宛てたものだったことから、標的が会社ではなく彼個人であったことは明白だという。
「ちょうどその頃、闘病中の祖父から遺産の話をされててね。ああこれは身内の犯行だなと思ったわけさ」
「で、でもさすがにそんな……親戚って言っても、家族ですよね……?」
「さっき言っただろう? 顔も知らない奴が大勢いるって」
彼らはうっすらと血が繫がっているだけの他人に過ぎない。鷹介の言わんとしていることを理解した愛実は、ひとまず事実を飲み込んでおく。
「えっと、じゃあ……松方さんが狙われてるのは、お祖父様の遺産を手放させたいとか横取りしたいから、ということですね」
「ああ。俺の両親はずいぶん前に事故で亡くなったから、相続順位は俺が一番上になってるそうだ」
「え、あ、そうなんですか……」
先ほど命を狙われていると話したときもそうだったが、何故この男は自分の不幸をさらりと口に出せるのだろう。同情を誘おうとしているわけでもなく、ただ淡々と語る姿に愛実は戸惑ってしまう。
しかし初対面の人間があまりそこを突っ込むのも何だか図々しい気がして、言葉に詰まる。
愛実が何とも言えない表情を浮かべていると、それに気付いた鷹介が片方の眉を上げ、苦笑した。
「……他人に共感しやすいタイプか?」
「す、すみません。事故は、辛いなって……」
「はは。俺はまだ四歳だったからな。あまり覚えてないだけだから気にしないでくれ」
そう言って瞼を伏せた彼は、どこかで見たことがあるような気がした。
ふと脳裏をよぎった誰かの面影に、愛実は微かに目を眇める。だがその正体は到底掴めそうになく、感じた違和感はあえなく霧散した。
「両親が死んだ後、祖父が俺を引き取ってくれてね。それ以降、ずっとあの人が俺の父親代わりだった」
鷹介の祖父、松方藤次郎は旧財閥の松方家を受け継いだ人物であり、類稀な商才をもってして莫大な財産を築き上げた傑物として広く知られている。
一人息子の治輝には、松方家の次期当主としての心構えから企業を率いる経営者としてのノウハウに至るまで、非常に厳しく教育をしていたそうだ。
だが、その治輝が若くしてこの世を去ったことは、厳格な藤次郎にも深い傷を与えた。残された幼い孫に同様の教育を強いるなど出来るはずもなく、鷹介が高校に上がるまでは祖父の顔しか見せなかったという。
「そのおかげで、祖父は俺に全財産を譲ると聞かなくてだな。親戚から不満の声が上がってもお構いなしなんだ」
「な、なるほど……負い目を感じていらっしゃるんでしょうか」
「だろうな。頑固な人だから」
鷹介はそう言って笑ったが、決して悪い意味ではないのだろう。彼にとって藤次郎は父親同然で、もちろん藤次郎にとっても鷹介は大切な存在に違いない。
老い先短い自分が残せるもの──つまり巨額の財産を、愛する孫に相続させたいと考えるのは不思議ではなかった。
「……犯人の目星はついてるんですか?」
愛実が小さく尋ねると、鷹介はかぶりを振る。
「候補はいるが、絞り切れてない。俺としてはまた物騒な物を送り付けられる前に、さっさと特定してしまいたいんだが──残念ながら尻尾は掴めないままだ」
郵便爆弾が届けられて以降、松方商事に届く荷物は慎重なチェックを入れなければならなくなった。鷹介の警護に掛かるコストも然ることながら、社員の不安を取り除くためにも早急に片付けておきたい、と彼は語る。
「お祖父様本人を脅迫する可能性だってありますしね」
「そう。そこで君の出番だ」
「えっ」
そういえばさっき何か依頼されたんだった、何だったかなと愛実は現実逃避をしつつ頬を引きつらせた。
彼女のそんな心境は察しているだろうに、鷹介は気付かない素振りでにっこりと笑みを浮かべる。
「遺産相続とは全く別の切り口から、松方家の財産を狙う第三者……君の登場によって、犯人を誘き出したい」
「誘き出す……」
「ああ。たとえば君が犯人の立場だとして、急に俺が如何にも怪しい女に骨抜きにされて、湯水のごとく金を使い込んでると知ったらどうする?」
愛実は少し考えて、ぼそりと答えた。
「……その女を仲間に引き込めないか、画策しますかね……? 同じ金目当てということで」
口にしてから、はっとする。
鷹介の言う「犯人を誘き出す」とは、こういうことかと。
愛実が窺うように視線を持ち上げれば、彼は答え合わせをするように頷いたのだった。
「どうかな、県愛実さん。俺を助けると思って、一芝居打ってくれないか」
◇
──鷹介の突拍子もない依頼に対して愛実がどのような返事をしたのかは、彼女がこの街に来ている時点で想像がつくことだろう。
自身とは全く無関係な相続争いに首を突っ込むなど、普段の愛実ならば考えられないことだが──人命が懸かっていると聞いて、はいそうですかと切り捨てられるほど薄情にもなれなかった。
加えて、鷹介の話では既に何人か妻役の候補を集めていたそうなのだが、顔を合わせるなり彼に見惚れてしまったり、緊張して自然な振る舞いができなかったり、挙げ句には役を忘れ本気で妻の座を狙いかねない者も出る始末で、なかなか適任が見つからない状況だったという。
「君は芝居が本職で、松方の人間とも繋がりがない。ついでに俺にビールをかけたお詫びがしたいけど社長と聞いて気後れして何をすればいいか分からず途方に暮れている」
「はいその通りです」
「そういう真面目さも好ましい」
やわらかな笑顔で急に性格を褒められ、狼狽えたのも束の間。
「昔ほど世間に顔も割れてないしな」
コイツ……と心の中で汚い言葉を吐きそうになったが、愛実は辛うじて耐えた。
「先程も言ったが、君には危害が及ばないよう徹底する。報酬も当然用意するとして──県さん、つかぬことを聞くが現在恋人は?」
「へ。い、いません」
「ふむ」
鷹介は少しの間押し黙り、愛実の前に人差し指を立てる。
「なら、一年間。来月の創立記念パーティーで犯人が動かない可能性も考えて、一年は夫婦として振る舞ってほしい」
「……じ、実際に籍を入れるということで……?」
「ああ。もちろんご両親にも挨拶に伺うし、一年後の離婚に関しては君の経歴に傷がつかないよう最大限配慮すると約束しよう」
それから、と彼は微笑を浮かべた。
「この仕事で生じる経費は全て俺の負担だ。俺から贈るもの以外にも、何か必要なものがあれば遠慮せず請求してくれて構わない」
「後で返せとか」
「言わないよ。後日また契約書を作るから、君の要望も盛り込んでおいてくれ」
他に何か気になることはあるかと問われ、愛実は暫し黙考する。
これは松方藤次郎の遺産を狙う物騒な親類の目を欺くための、いわば偽装結婚という形になるだろう。その上で愛実が求められる働きは──彼らの注目を集め、味方に引き入れたい、もしくは手駒にしたいと思わせること。
当然ただの考えなしの女ではいけない。鷹介の新妻として振る舞いつつ、彼の資産目当てであることがほんの僅かに滲み出るような、強かで狡猾な女を演じなくてはならないだろう。
そこまで考えたとき、愛実の中に生じたのは疼きのようなものだった。
今まで一度も演じたことのない役柄ゆえに、自分では力不足だと思う一方で、未知への挑戦を望む心が確かにあったのだ。
──それは、もう久しく感じていなかった演技への情熱だったのかもしれない。
「いえ……分かりました。私で良いなら……頑張ります」
愛実の返答に、鷹介は「ありがとう」と言って深く頭を下げた。
◇
夕焼けに染まった病室。
ベッドに横たわる女性は小さな嗚咽で目を覚まし、うつろな瞳をさまよわせた。
ふと視線を手前に落とせば、そこには痩せた手を握りしめ、俯いたままポロポロと涙を溢れさせる少女がいる。
「おかあさん……おかあさん」
「リナ……ごめんね。おかあさん、リナと一緒にお出かけ、できないみたい……」
「おかあさ」
「ずっと、リナのこと、見守ってるからね」
女性はそのまま、眠るように息を引き取った。
残ったのは呆然と母を見つめる幼い少女だけ。
真っ赤に腫れた瞼を瞬かせ、繋いだ手を何度も揺らす。しかし何をしても母からの答えはなく、その手が握り返されることもなかった。
「おかあさん」
長い長い沈黙の後、ぽつりと呼びかける少女の声で──暗転。
このシーンこそが、天才子役として一世を風靡した「県愛実」のデビュー作である。
母親の死という厳しい現実を受け入れられない幼子の、息苦しさすら覚える生々しい演技が高く評価され、彼女は六歳で多くの賞を受賞した。
ドラマや映画はもちろん、バラエティ番組にも引っ張りだことなった彼女は、老若男女問わず幅広い世代に親しまれた。
しかし悲しいかな、その華やかな活躍は長く続かなかった。
各芸能事務所が「第二の県愛実」を発掘せんと、子役募集を活発に行うようになったのだ。
愛実よりも年下の子役が登場すれば、世間の目はそちらへと向き。愛実よりも目鼻立ちの整ったハーフの美少女が現れたなら、メディアがこぞって取り上げる。さらに愛実よりも弁の立つ社交性の高い子たちが、バラエティ番組の席を独占した。
天才子役「県愛実」は、あっという間に過去の人となっていった。
「『最近見かけなくなった現在が悲惨な子役ランキング』……悪趣味なブログを書く人間は尽きないな」
隣でつらつらと読み上げられる自身の過去に、愛実は少々惨めな気分で顔を背けた。
「そんな記事のアクセス数に貢献しないでください」
「はは、悪い悪い」
乗り込んだ車はその大きさに反して、存外静かに街のBCストリートを走行していた。
愛実と鷹介が当然のように後部座席に並んで腰掛けたなら、運転席には見知らぬ男性がいつの間にか着席していて。互いに小さく会釈した後、車は彼の運転によってゆるやかに発進した。
一方、ふかふかのシートに身を預け、優雅に組んだ長い脚の上でタブレットを操作していた鷹介は、笑いまじりに画面を消す。
「いや何、君のことを知っておかなくてはと、俺も一応いろいろと調べてたんだよ」
「い、いいですよ別にそんなことしなくて……松方さんが見てるものが私の全てです」
「鷹介」
「…………鷹介さん」
渋々と呼び方を改めれば、鷹介がにこりと笑う。
「この街に来たら即座に舞台が始まると思え──そう伝えたはずだろう?」
「う……あ、あの」
「何だ? 愛実」
馴れ馴れしい。でもどこにも不快感がないのは何故だ。愛実は困惑しつつも、車の外を流れていく街並みに視線を投じる。
「……本当にその、この設定でやるんですか?」
「ああ。君は今から『保険金目当てに松方鷹介を篭絡し、妻の座に収まって殺害を企てる女詐欺師』だ」
改めて告げられてしまった自身のアクの強い役柄に、愛実はゴッと窓に額をぶつけた。
「帰っちゃだめですか」
「つれないことを言うな愛実。君の行きたがっていたホテルを既に予約してしまったんだ。楽しみだと言ってただろ」
「言ってない言ってない」
捏造された記憶にげんなりと否定を入れれば、鷹介は短く哄笑した。
「そう不安がらないで良い。決して君を危険な目に遭わせることはないから」
流し目にこちらを見た彼が、ぱちりと片目を瞑って見せる。
気障な仕草だというのにどうしてこうも様になるのか。ああ、普段から女性相手に甘い言葉ばかり振りまいているからかと、愛実は胡乱げな眼差しを返したのだった。
「──愛実」
コンクリートから立ちのぼる熱気と、肌を焼く陽射し。
車から降りてわずか数秒、瞬く間に体力が削られていくのを感じながら視線を移せば、鷹介が左手を差し伸べていた。
愛実はにこりと口角を持ち上げ、その大きな手に指先を乗せる。
「ホテルに行くんじゃなかった?」
先程までの他人行儀な口調を取っ払い、気安い調子で尋ねれば、鷹介が少しばかり目を見開いた。
しかしそれも一瞬のこと、繋いだ手を引き寄せた彼は笑い混じりに囁く。
「少し話がしたくてね」
形の良い眉が僅かに持ち上がり、ヘーゼルの瞳が甘く細められる。ふわりと鼻腔をくすぐったのは、夏の蒸し暑さを和らげる爽やかなサンダルウッドの香り。
同年代の男性にはない大人の雰囲気に尻込みしつつも、それを悟らせない動きで愛実は逞しい腕に自身の手を添えた。
二人がやって来たのは、広々とした港湾を右手に据えながら散歩ができるプロムナードだった。淡い色合いのタイルによって整備されたその道には、見上げるほど背の高いヤシの木が並び、海風が吹くたびに波のような音を立てている。
如何にも高級そうな海辺のホテルに目を留めれば、愛実の視線を追った鷹介が口を開いた。
「泊まりたい?」
「えっ」
何となしに眺めていただけだった愛実が小刻みにかぶりを振ると、彼がくつくつと肩を揺らして笑う。
「泊まりたくなったら言ってくれ。ついでに花火大会の席でも取ろうか」
「花火大会?」
「パーティーの翌日にあるんだ。ホテルの最上階から見る花火はなかなか良いぞ」
ふぅん、と生返事をした愛実はしかし、一体いくら積めば既に満室であろうホテルに融通を利かせられるのかと遠い目をしてしまった。
彼女の表情は大きなサングラスで上手いこと隠れていたはずだが、鷹介は見透かしたようにその腰をぐいと抱き寄せる。
「これぐらいのおねだりは朝飯前じゃないと」
「なるほど。何となく規模は分かりました」
ぼそりと短く言葉を交わしつつ、愛実は周囲に誰もいないことを確認してから「それで」と本題を促した。
「お話って?」
「ああ。用意していたものを渡そうと思って」
プロムナードに沿って点々と設置された東屋の一つに入るや否や、鷹介が本革のセカンドバッグから何かを取り出す。
そしておもむろに彼が片膝をついたので、愛実はぎょっとして立ち上がるように言いかけたが。
「指輪を貰うなら、誰もいない綺麗な海が良いって言ってただろ? 愛実」
言ってない。
愛実は頬を引きつらせながら、差し出されたケースの中身──日陰にあっても煌めくプラチナの指輪を見遣る。
シンプルな形でありながら、細やかな装飾が施された一対の指輪。パートナーがこれからの人生を互いに支え生きていく、誓いの証。
しかし、二人にとってこれは愛の誓いなどではない。
「舞台へ上がる覚悟は出来たかな」
契約の証を差し出したまま、鷹介が静かに囁く。
愛実は彼の瞳をまっすぐに見返すと、ゆるりと唇に弧を描いて見せた。
「私、困ってる人は放っておけないタイプなんです。あと──本番にも強いと思います」
左手を持ち上げれば、大きな手に恭しく掬われる。薬指にゆっくりと嵌められた指輪を見つめ、愛実は静かに息を吐いた。
そうして残る一つの指輪を手に取り、自らも鷹介の左手に指輪を嵌める。
互いの指に揃いの輝きを灯した瞬間、何とも言えない羞恥に襲われてパッと手を離す。窺うように視線を上げれば、彼のからかうような笑みに迎えられた。
「な、何ですか」
「うん? いや、短い髪も似合うなと思って」
「……そういうのは会ってすぐ言うべきですよ」
ふいと顔を背けて文句を垂れれば、彼はやはり上機嫌に笑ったのだった。
愛実は多大なる緊張と、早くも心を侵食しつつある後悔と共に、駅のホームへと降り立った。
慣れない大きなサングラスを下にずらし、メモに記した地名と駅名標が一致していることを確かめる。その瞬間ぐっと重たくなったキャリーケースを転がし、人の流れに従って改札口を抜けた。真っ白なリボンのミュールでエスカレーターを降りていくと、むわりとした熱気が頬に触れる。つばの広いキャペリンハットを被り直しつつ、ゆっくりと外へ踏み出した。
そうして愛実が真っ先に捉えたのは、快晴の空と真っ青な海に浮かぶ、日差しを照り返す白が美しい豪華客船。
どっしりとした、されど気品を感じさせる巨大な方舟は、そこに招かれた乗客をさぞかし素敵な旅に連れ出してくれるであろう。
……が、しかし。
「──帰りたい……」
それを見た愛実の口からこぼれたのは、弱弱しい帰宅願望であった。
豪華客船の手前に広がる海の街を呆然と見渡し、ごろごろとキャリーケースを引っ張って木陰に入る。ショルダーバッグからスマホを取り出し、この一か月で何度消そうかと思った連絡先をタップした。
トーク画面を開くと、見計らったようにメッセージが届く。
『どこにいる?』
愛実が億劫な気分で「駅前のロータリーにいます」と返したときだった。
「何だ、合ってたのか」
「わあ!!」
真後ろから声を掛けられ、飛び上がるほど驚いてしまった。
慌ただしく振り返ると、そこには愛実をこの街へ呼び出した張本人が立っていた。
決まりすぎない程度に整えた黒髪、日本人にしては彫りの深い目元。飾らない白の開襟シャツに、腰を絞るベルトからすらりと伸びた黒いデニム。鎖骨に光るシンプルなチェーンネックレスが、彼の逞しい胸元をやけに扇情的に見せていた。
「ひと月ぶりだな、県愛実さん」
鼻の下までズレたサングラスを、大きな手にそっと直される。彼が口角を上げて囁いたなら、愛実もハッと我に返って咳ばらいをした。
「……お久しぶりです、松方鷹介さん。近くにいたなら普通に声をかけてください」
「仕方ないだろ、別人かと思ったんだ」
愛実のキャペリンハットを指先で軽く弾き、鷹介は彼女の装いに視線を遣る。
ネイビーにレモン柄を散りばめたノースリーブのシェルトップに、裾がふわりと広がる真っ白なロングスカート。大きめの帽子とサングラス、踵のあるミュールで元の高身長を更に底上げした愛実の出で立ちは、普段と比べれば確かに別人と言われても仕方ないだろう。
鷹介は愛実の姿を眺めながら顎を摩ると、満足げに笑った。
「良いな。──詐欺師っぽくて、実に良い」
そう見えるようコーディネートしたとは言え、なんとも不名誉で嬉しくない評価を貰ってしまった愛実は、ぶすっと唇を尖らせつつ「どうも」と返したのだった。
◇
遡ること一ヶ月ほど前。
愛実はその日、球場でビール販売のバイトに勤しんでいた。
大学を卒業して二年。一般企業への就職も考えたが、悩みに悩んだ末に彼女は自身の夢を優先した。
いや、夢と呼ぶには些か輝きが足りないかもしれない。憧れも、熱量も、がむしゃらな気持ちも、何もかも。
自分の中にあるものが燻った不満と執着ということに気付きながらも、彼女は目標を達成すべく忙しない日々を送っていた。
「おい姉ちゃん、ビール二つちょうだい」
「あっはい! ありがとうございます!」
強い日差しに目を眇めつつ階段を下りていくと、中年の男性に呼び止められる。愛実はすぐにその場に膝をつき、カップに生ビールを注いだ。
しゅわしゅわと音を立てる黄金色と、濃密な真っ白な泡。きちんと美味しそうに注げたところで、愛実はにっこりと笑みを浮かべてカップを渡そうとした。
「お待たせいたしま……」
「こら! はるくん! 走らないの! あ!!」
「え?」
ドッ、と愛実の体に振動が伝わり、背負ったビールサーバーに全身が引っ張られる。
はっとして後ろを見てみれば、ビールサーバーに正面衝突したであろう小さな男の子が尻もちをついていて。
男の子、目の前にいる男性、階段、ビール──一瞬の間に懸念事項がぐるぐると愛実の頭を駆け巡る。
そうして咄嗟に踏み出した片足で、まずは愛実自身が階段を転がり落ちないよう気合いで踏ん張る。続いて男性にビールをぶっかけてしまわぬよう、大きく揺れたビールカップをぐいと他所へ向けた。
愛実の瞬時の判断に、固唾をのんで見守っていた周囲の人達から「おお」と歓声が上がったのもつかの間。
「あ」
ばしゃ。
宙へと飛び出したビールは、階段を上ってきた一人の男性の顔面へと着地していた。
「あ……」
ずぶ濡れの呆けた顔。中途半端にこちらへ伸ばされた両手。
彼が愛実を助けようとしていたのは、一目瞭然であった。
「おっ、お客様!! 申し訳ございません!!」
愛実の悲鳴にも似た謝罪は、ホームランの歓声によって掻き消された。
「はは、いやぁびっくりした。ビールを顔面に食らったのは初めてだ」
──私も他人様の顔にビールをぶっかけたのは初めてです。
愛実は死刑宣告を待つ罪人よろしく、色を失ったまま突っ立っていた。
先ほどまで彼女の隣には球場の従業員を取りまとめるチーフが謝罪を繰り返していたのだが、責任者であるはずの彼はなぜか早々に退室させられ、愛実だけがここに取り残されている。
球場全体を悠々と見下ろすことのできる、高級感あふれるロイヤルレストラン。開放的な大窓のすぐ側、シャワーを浴びて身綺麗になった男性が、くつくつと肩を震わせて笑う。
「座ると良い。あんなに重いものを背負ってたんだから疲れただろう?」
「え……ですが、その……」
「別に君を叱りつけるために呼んだわけじゃない。安心してくれ」
てっきり土下座でもさせられるのかと思っていた愛実は、その言葉にまばたきを繰り返してしまった。正直すぎる反応だったのだろう、彼はまたおかしげに笑って「どうぞ」と席を勧める。
恐る恐る腰を下ろせば、まるで褒めるように彼の目が細められ、愛実は慌てて瞼を伏せておいた。
「さて。まずは自己紹介かな。俺は松方鷹介。こう見えて社長なんてものをやっていてね」
「え、しゃちょ……?」
「はいコレ名刺」
「あ、ご丁寧にどうもありがとうございます……」
鷹介はローテーブルに置かれた一枚の名刺を、すっと愛実の方へと滑らせる。
名刺には彼の名前と、松方商事──あまり経済方面に明るくない愛実でも聞いたことのある有名な商社の名前が印字されていた。
確か旧財閥系の会社だったような、とおぼろげな記憶を引っ張り出したのもつかの間、会社と同じ苗字を持つ目の前の人物を二度見する。
愛実の言わんとしていることを察してか、鷹介はにこりと口角を上げた。
「親の七光り野郎がって思った?」
「とっとんでもないです、苗字が一緒だなぁとか思っただけです」
「冗談冗談。俺が仕事をする上で、松方家の恩恵を受けてるのは本当だしな」
松方家。やはり彼はとんでもない大金持ちの家に生まれた人なのだと、そんな人に自分はビールをぶっかけてしまったのかと、愛実は天を仰ぎたい気分だった。かろうじて虚空を見つめるに留めたが。
愛実が己の行く末を憂いていることなど知らぬ素振りで、鷹介は「それで」と本題に入る姿勢を見せた。
「君は県愛実さんで合ってるかな?」
「えっ、は、はい」
「──十数年前よくテレビに出てた、県愛実さん?」
唐突に古傷を抉られたような気分になったが、ここで否定したところで何か意味があるわけでもなし、愛実は素直に、しかしぎこちなく頷く。
「ええと……はい。その県愛実ですね……」
天才子役、県愛実。
それが彼女の、早すぎた全盛期の呼び名だ。
とある映画に出演した際、彼女は僅か六歳で数々の賞を受賞した。監督から一発OKを貰ったシーンは、たったの三分。後に「奇跡の三分」とまで称されたそのシーンが、見る人全てを魅了した──らしい。
愛実からすれば既に十八年も前のことで、当時世間がどれだけ盛り上がっていたかなど、残念ながら彼女自身は全く知らない。
だが、おかげでさまざまな番組に引っ張りだこだったのは確かで、そのときの大変さはよく覚えていた。
……まぁそれも過去の栄光に過ぎず、今や愛実が巷の話題になることなど皆無である。
「やっぱりそうか! 大きくなったな」
何とも言えない気まずさに気分が沈みかけたとき、鷹介の毒気のない笑みと柔らかな声音がそれを吹き飛ばした。
愛実はつい呆けてしまった後、むず、と鼻がくすぐったくなった。
小さな頃からテレビに映っていたおかげで、見知らぬ人から「大きくなったね」と言われる機会は少なくない。それらはいつも、近所に住む幼子の成長を喜ぶような、温かい感情を乗せたものばかりだ。
愛実としても、大勢の人から見守られていた事実を実感できて嬉しく思うのが常なのだが──。
(……何だろ。年の近い人にあんまり言われたことないからかな。ちょっと変な感じ……しかももうとっくに成人してるし)
照れ臭さを隠しながらも小さく頭を下げれば、その仕草を見ていた鷹介がくすりと笑う。不意の優しい表情にうっかり見惚れてしまったせいで、愛実は次に放たれた言葉をすぐに理解できなかった。
「県愛実さん、ここで会ったのも何かの縁だ。ひとつ仕事を頼みたい」
「へ? お仕事、ですか?」
「そう。詐欺の仕事」
沈黙。
カキーン、と外から小気味よい音が響いたかと思えば、わっと歓声が上がる。愛実の時間が止まっている間に、打者は一塁を走り抜け二塁へと滑り込みを決めていた。
「……あの、家族と縁を切ってきてもいいでしょうか」
「うーん今のは俺が悪かった、冗談だ」
これが大富豪にビールをかけた代償ならやるしかないと覚悟を決めてしまいそうになったところで、すぐさま鷹介がストップをかける。
彼は軽く手招きをすると、前のめりになった愛実に囁いた。
「正確に言うと、君に詐欺師を演じてほしい」
「詐欺師を演じる……? ……えっと、舞台のお仕事ですか?」
愛実は高校や大学で演劇部に所属していた上に、今も単発アルバイトをしながら稽古に通い、小さな劇団で舞台に上がっている。
昨日も稽古に行っては、やれ演技が小さいだの地味だのと座長から指導を受けてダメージを負ったが、それでも舞台の仕事は続けていた。
それはさておき、詐欺師の役なんていうのは初めてだ。一体どんな脚本なのだろうと愛実が首を傾げていると。
「まぁ舞台のようなものかな。あそこは」
鷹介はジーンズのポケットからスマホを取り出すと、さっと何かを検索しては画面をスクロールする。
「ここ、知ってるかい」
くるりと反転したスマホに写っていたのは、真っ青な空を背景にした緑豊かな街並み。まるで海外のリゾート地よろしく美しい海、そこに浮かぶ真っ白な豪華客船や、太陽の光を照り返す真新しいビルの群れなど、写真映えする景色が次々と流れていく。
愛実は暫し呆けていたが、やがて見覚えのある駅が映し出されたことで「あっ」と目を丸くした。
「知ってます。テレビで見ました。何かあの……とんでもないお金持ちが集まるセレブ街ですよね」
「はは、そうそう。来月、ここで取引先の創立記念パーティーが開かれるんだ。俺も出席する予定でね」
「はあ。凄そうですね」
漠然とした感想を口にすると、鷹介はにこりと口角を上げる。
「そこが君の舞台だ」
「はい?」
「この創立記念パーティーで、君には俺の妻として出席してもらいたい」
再び訪れる沈黙。
球場はこれ以上にないほどの盛り上がりを見せていたが、愛実と鷹介のいるレストランはしんと静まり返っている。
意味が分からずに呆ける愛実を見て、鷹介は更に言葉を続けた。
「さっきも言ったが、ただの妻じゃあない。君は『俺にかけられた莫大な保険金を受け取るために結婚した女詐欺師』になって、周囲をこれでもかというほど搔き乱してほしい」
「え、はぁっ……!? そ、それ何か迷惑行為とかになりませんか!?」
「大丈夫、警察には話を通してある」
「警察!? ……警察?」
一度目の反芻には驚きを、二度目には懐疑を含めて聞き返す。
愛実が眉を顰めていると、鷹揚な動きで鷹介が頷いた。
「あまり驚かないで聞いてほしいんだが、俺は親戚から命を狙われていてね」
「驚きますし初対面の人間に話す内容でもないですよコレ」
「まぁそう言わずに。俺が狙われる理由は何だと思う?」
鷹介は何とも軽い調子で問いかけ、アイスコーヒーを一口飲む。
命を狙われている人間にしては焦りも恐怖も全く伝わってこないが、愛実は「ええと」と頬を掻いた。
「……松方さんのおうちって、その、やっぱり大家族です?」
「まぁな。それなりに古い家だから顔も知らない親戚が大量にいる」
「じゃあ、あー……遺産相続とか、でしょうか」
ドラマや映画の見過ぎだと、笑われるか叱られるのを期待していた愛実だったが、鷹介が褒めるように目を細めたのを見て頭を抱えてしまう。
「本当にあるんだ、そんなの……」
「困ったものだよな」
「他人事みたいに言うのやめてもらっていいですか」
危機感に欠ける鷹介はその返しにも笑っていたが、愛実の咎めるような視線を受けては肩を竦める。
「誰かが俺を殺そうとしていると知って、恐怖を感じるよりも呆れたのは事実さ。たかが金のために殺人を企てるなんて、どうかしているだろう」
「それは同意しますけど……。もしかして、もう既に身の危険を感じるような場面があったんですか?」
「会社に爆発物が届いた」
「ひっ……」
曰く、松方商事のオフィスに差出人不明の包みが届き、それを受け取った秘書は「中から妙な音がする」と言って警察に連絡したそうだ。
警察による調査の結果、中身が爆発物であったことが判明。包みを開封した瞬間に起爆するよう設計された、いわゆる郵便爆弾と呼ばれるものだった。
そして、その包みは松方商事の社長──すなわち鷹介に宛てたものだったことから、標的が会社ではなく彼個人であったことは明白だという。
「ちょうどその頃、闘病中の祖父から遺産の話をされててね。ああこれは身内の犯行だなと思ったわけさ」
「で、でもさすがにそんな……親戚って言っても、家族ですよね……?」
「さっき言っただろう? 顔も知らない奴が大勢いるって」
彼らはうっすらと血が繫がっているだけの他人に過ぎない。鷹介の言わんとしていることを理解した愛実は、ひとまず事実を飲み込んでおく。
「えっと、じゃあ……松方さんが狙われてるのは、お祖父様の遺産を手放させたいとか横取りしたいから、ということですね」
「ああ。俺の両親はずいぶん前に事故で亡くなったから、相続順位は俺が一番上になってるそうだ」
「え、あ、そうなんですか……」
先ほど命を狙われていると話したときもそうだったが、何故この男は自分の不幸をさらりと口に出せるのだろう。同情を誘おうとしているわけでもなく、ただ淡々と語る姿に愛実は戸惑ってしまう。
しかし初対面の人間があまりそこを突っ込むのも何だか図々しい気がして、言葉に詰まる。
愛実が何とも言えない表情を浮かべていると、それに気付いた鷹介が片方の眉を上げ、苦笑した。
「……他人に共感しやすいタイプか?」
「す、すみません。事故は、辛いなって……」
「はは。俺はまだ四歳だったからな。あまり覚えてないだけだから気にしないでくれ」
そう言って瞼を伏せた彼は、どこかで見たことがあるような気がした。
ふと脳裏をよぎった誰かの面影に、愛実は微かに目を眇める。だがその正体は到底掴めそうになく、感じた違和感はあえなく霧散した。
「両親が死んだ後、祖父が俺を引き取ってくれてね。それ以降、ずっとあの人が俺の父親代わりだった」
鷹介の祖父、松方藤次郎は旧財閥の松方家を受け継いだ人物であり、類稀な商才をもってして莫大な財産を築き上げた傑物として広く知られている。
一人息子の治輝には、松方家の次期当主としての心構えから企業を率いる経営者としてのノウハウに至るまで、非常に厳しく教育をしていたそうだ。
だが、その治輝が若くしてこの世を去ったことは、厳格な藤次郎にも深い傷を与えた。残された幼い孫に同様の教育を強いるなど出来るはずもなく、鷹介が高校に上がるまでは祖父の顔しか見せなかったという。
「そのおかげで、祖父は俺に全財産を譲ると聞かなくてだな。親戚から不満の声が上がってもお構いなしなんだ」
「な、なるほど……負い目を感じていらっしゃるんでしょうか」
「だろうな。頑固な人だから」
鷹介はそう言って笑ったが、決して悪い意味ではないのだろう。彼にとって藤次郎は父親同然で、もちろん藤次郎にとっても鷹介は大切な存在に違いない。
老い先短い自分が残せるもの──つまり巨額の財産を、愛する孫に相続させたいと考えるのは不思議ではなかった。
「……犯人の目星はついてるんですか?」
愛実が小さく尋ねると、鷹介はかぶりを振る。
「候補はいるが、絞り切れてない。俺としてはまた物騒な物を送り付けられる前に、さっさと特定してしまいたいんだが──残念ながら尻尾は掴めないままだ」
郵便爆弾が届けられて以降、松方商事に届く荷物は慎重なチェックを入れなければならなくなった。鷹介の警護に掛かるコストも然ることながら、社員の不安を取り除くためにも早急に片付けておきたい、と彼は語る。
「お祖父様本人を脅迫する可能性だってありますしね」
「そう。そこで君の出番だ」
「えっ」
そういえばさっき何か依頼されたんだった、何だったかなと愛実は現実逃避をしつつ頬を引きつらせた。
彼女のそんな心境は察しているだろうに、鷹介は気付かない素振りでにっこりと笑みを浮かべる。
「遺産相続とは全く別の切り口から、松方家の財産を狙う第三者……君の登場によって、犯人を誘き出したい」
「誘き出す……」
「ああ。たとえば君が犯人の立場だとして、急に俺が如何にも怪しい女に骨抜きにされて、湯水のごとく金を使い込んでると知ったらどうする?」
愛実は少し考えて、ぼそりと答えた。
「……その女を仲間に引き込めないか、画策しますかね……? 同じ金目当てということで」
口にしてから、はっとする。
鷹介の言う「犯人を誘き出す」とは、こういうことかと。
愛実が窺うように視線を持ち上げれば、彼は答え合わせをするように頷いたのだった。
「どうかな、県愛実さん。俺を助けると思って、一芝居打ってくれないか」
◇
──鷹介の突拍子もない依頼に対して愛実がどのような返事をしたのかは、彼女がこの街に来ている時点で想像がつくことだろう。
自身とは全く無関係な相続争いに首を突っ込むなど、普段の愛実ならば考えられないことだが──人命が懸かっていると聞いて、はいそうですかと切り捨てられるほど薄情にもなれなかった。
加えて、鷹介の話では既に何人か妻役の候補を集めていたそうなのだが、顔を合わせるなり彼に見惚れてしまったり、緊張して自然な振る舞いができなかったり、挙げ句には役を忘れ本気で妻の座を狙いかねない者も出る始末で、なかなか適任が見つからない状況だったという。
「君は芝居が本職で、松方の人間とも繋がりがない。ついでに俺にビールをかけたお詫びがしたいけど社長と聞いて気後れして何をすればいいか分からず途方に暮れている」
「はいその通りです」
「そういう真面目さも好ましい」
やわらかな笑顔で急に性格を褒められ、狼狽えたのも束の間。
「昔ほど世間に顔も割れてないしな」
コイツ……と心の中で汚い言葉を吐きそうになったが、愛実は辛うじて耐えた。
「先程も言ったが、君には危害が及ばないよう徹底する。報酬も当然用意するとして──県さん、つかぬことを聞くが現在恋人は?」
「へ。い、いません」
「ふむ」
鷹介は少しの間押し黙り、愛実の前に人差し指を立てる。
「なら、一年間。来月の創立記念パーティーで犯人が動かない可能性も考えて、一年は夫婦として振る舞ってほしい」
「……じ、実際に籍を入れるということで……?」
「ああ。もちろんご両親にも挨拶に伺うし、一年後の離婚に関しては君の経歴に傷がつかないよう最大限配慮すると約束しよう」
それから、と彼は微笑を浮かべた。
「この仕事で生じる経費は全て俺の負担だ。俺から贈るもの以外にも、何か必要なものがあれば遠慮せず請求してくれて構わない」
「後で返せとか」
「言わないよ。後日また契約書を作るから、君の要望も盛り込んでおいてくれ」
他に何か気になることはあるかと問われ、愛実は暫し黙考する。
これは松方藤次郎の遺産を狙う物騒な親類の目を欺くための、いわば偽装結婚という形になるだろう。その上で愛実が求められる働きは──彼らの注目を集め、味方に引き入れたい、もしくは手駒にしたいと思わせること。
当然ただの考えなしの女ではいけない。鷹介の新妻として振る舞いつつ、彼の資産目当てであることがほんの僅かに滲み出るような、強かで狡猾な女を演じなくてはならないだろう。
そこまで考えたとき、愛実の中に生じたのは疼きのようなものだった。
今まで一度も演じたことのない役柄ゆえに、自分では力不足だと思う一方で、未知への挑戦を望む心が確かにあったのだ。
──それは、もう久しく感じていなかった演技への情熱だったのかもしれない。
「いえ……分かりました。私で良いなら……頑張ります」
愛実の返答に、鷹介は「ありがとう」と言って深く頭を下げた。
◇
夕焼けに染まった病室。
ベッドに横たわる女性は小さな嗚咽で目を覚まし、うつろな瞳をさまよわせた。
ふと視線を手前に落とせば、そこには痩せた手を握りしめ、俯いたままポロポロと涙を溢れさせる少女がいる。
「おかあさん……おかあさん」
「リナ……ごめんね。おかあさん、リナと一緒にお出かけ、できないみたい……」
「おかあさ」
「ずっと、リナのこと、見守ってるからね」
女性はそのまま、眠るように息を引き取った。
残ったのは呆然と母を見つめる幼い少女だけ。
真っ赤に腫れた瞼を瞬かせ、繋いだ手を何度も揺らす。しかし何をしても母からの答えはなく、その手が握り返されることもなかった。
「おかあさん」
長い長い沈黙の後、ぽつりと呼びかける少女の声で──暗転。
このシーンこそが、天才子役として一世を風靡した「県愛実」のデビュー作である。
母親の死という厳しい現実を受け入れられない幼子の、息苦しさすら覚える生々しい演技が高く評価され、彼女は六歳で多くの賞を受賞した。
ドラマや映画はもちろん、バラエティ番組にも引っ張りだことなった彼女は、老若男女問わず幅広い世代に親しまれた。
しかし悲しいかな、その華やかな活躍は長く続かなかった。
各芸能事務所が「第二の県愛実」を発掘せんと、子役募集を活発に行うようになったのだ。
愛実よりも年下の子役が登場すれば、世間の目はそちらへと向き。愛実よりも目鼻立ちの整ったハーフの美少女が現れたなら、メディアがこぞって取り上げる。さらに愛実よりも弁の立つ社交性の高い子たちが、バラエティ番組の席を独占した。
天才子役「県愛実」は、あっという間に過去の人となっていった。
「『最近見かけなくなった現在が悲惨な子役ランキング』……悪趣味なブログを書く人間は尽きないな」
隣でつらつらと読み上げられる自身の過去に、愛実は少々惨めな気分で顔を背けた。
「そんな記事のアクセス数に貢献しないでください」
「はは、悪い悪い」
乗り込んだ車はその大きさに反して、存外静かに街のBCストリートを走行していた。
愛実と鷹介が当然のように後部座席に並んで腰掛けたなら、運転席には見知らぬ男性がいつの間にか着席していて。互いに小さく会釈した後、車は彼の運転によってゆるやかに発進した。
一方、ふかふかのシートに身を預け、優雅に組んだ長い脚の上でタブレットを操作していた鷹介は、笑いまじりに画面を消す。
「いや何、君のことを知っておかなくてはと、俺も一応いろいろと調べてたんだよ」
「い、いいですよ別にそんなことしなくて……松方さんが見てるものが私の全てです」
「鷹介」
「…………鷹介さん」
渋々と呼び方を改めれば、鷹介がにこりと笑う。
「この街に来たら即座に舞台が始まると思え──そう伝えたはずだろう?」
「う……あ、あの」
「何だ? 愛実」
馴れ馴れしい。でもどこにも不快感がないのは何故だ。愛実は困惑しつつも、車の外を流れていく街並みに視線を投じる。
「……本当にその、この設定でやるんですか?」
「ああ。君は今から『保険金目当てに松方鷹介を篭絡し、妻の座に収まって殺害を企てる女詐欺師』だ」
改めて告げられてしまった自身のアクの強い役柄に、愛実はゴッと窓に額をぶつけた。
「帰っちゃだめですか」
「つれないことを言うな愛実。君の行きたがっていたホテルを既に予約してしまったんだ。楽しみだと言ってただろ」
「言ってない言ってない」
捏造された記憶にげんなりと否定を入れれば、鷹介は短く哄笑した。
「そう不安がらないで良い。決して君を危険な目に遭わせることはないから」
流し目にこちらを見た彼が、ぱちりと片目を瞑って見せる。
気障な仕草だというのにどうしてこうも様になるのか。ああ、普段から女性相手に甘い言葉ばかり振りまいているからかと、愛実は胡乱げな眼差しを返したのだった。
「──愛実」
コンクリートから立ちのぼる熱気と、肌を焼く陽射し。
車から降りてわずか数秒、瞬く間に体力が削られていくのを感じながら視線を移せば、鷹介が左手を差し伸べていた。
愛実はにこりと口角を持ち上げ、その大きな手に指先を乗せる。
「ホテルに行くんじゃなかった?」
先程までの他人行儀な口調を取っ払い、気安い調子で尋ねれば、鷹介が少しばかり目を見開いた。
しかしそれも一瞬のこと、繋いだ手を引き寄せた彼は笑い混じりに囁く。
「少し話がしたくてね」
形の良い眉が僅かに持ち上がり、ヘーゼルの瞳が甘く細められる。ふわりと鼻腔をくすぐったのは、夏の蒸し暑さを和らげる爽やかなサンダルウッドの香り。
同年代の男性にはない大人の雰囲気に尻込みしつつも、それを悟らせない動きで愛実は逞しい腕に自身の手を添えた。
二人がやって来たのは、広々とした港湾を右手に据えながら散歩ができるプロムナードだった。淡い色合いのタイルによって整備されたその道には、見上げるほど背の高いヤシの木が並び、海風が吹くたびに波のような音を立てている。
如何にも高級そうな海辺のホテルに目を留めれば、愛実の視線を追った鷹介が口を開いた。
「泊まりたい?」
「えっ」
何となしに眺めていただけだった愛実が小刻みにかぶりを振ると、彼がくつくつと肩を揺らして笑う。
「泊まりたくなったら言ってくれ。ついでに花火大会の席でも取ろうか」
「花火大会?」
「パーティーの翌日にあるんだ。ホテルの最上階から見る花火はなかなか良いぞ」
ふぅん、と生返事をした愛実はしかし、一体いくら積めば既に満室であろうホテルに融通を利かせられるのかと遠い目をしてしまった。
彼女の表情は大きなサングラスで上手いこと隠れていたはずだが、鷹介は見透かしたようにその腰をぐいと抱き寄せる。
「これぐらいのおねだりは朝飯前じゃないと」
「なるほど。何となく規模は分かりました」
ぼそりと短く言葉を交わしつつ、愛実は周囲に誰もいないことを確認してから「それで」と本題を促した。
「お話って?」
「ああ。用意していたものを渡そうと思って」
プロムナードに沿って点々と設置された東屋の一つに入るや否や、鷹介が本革のセカンドバッグから何かを取り出す。
そしておもむろに彼が片膝をついたので、愛実はぎょっとして立ち上がるように言いかけたが。
「指輪を貰うなら、誰もいない綺麗な海が良いって言ってただろ? 愛実」
言ってない。
愛実は頬を引きつらせながら、差し出されたケースの中身──日陰にあっても煌めくプラチナの指輪を見遣る。
シンプルな形でありながら、細やかな装飾が施された一対の指輪。パートナーがこれからの人生を互いに支え生きていく、誓いの証。
しかし、二人にとってこれは愛の誓いなどではない。
「舞台へ上がる覚悟は出来たかな」
契約の証を差し出したまま、鷹介が静かに囁く。
愛実は彼の瞳をまっすぐに見返すと、ゆるりと唇に弧を描いて見せた。
「私、困ってる人は放っておけないタイプなんです。あと──本番にも強いと思います」
左手を持ち上げれば、大きな手に恭しく掬われる。薬指にゆっくりと嵌められた指輪を見つめ、愛実は静かに息を吐いた。
そうして残る一つの指輪を手に取り、自らも鷹介の左手に指輪を嵌める。
互いの指に揃いの輝きを灯した瞬間、何とも言えない羞恥に襲われてパッと手を離す。窺うように視線を上げれば、彼のからかうような笑みに迎えられた。
「な、何ですか」
「うん? いや、短い髪も似合うなと思って」
「……そういうのは会ってすぐ言うべきですよ」
ふいと顔を背けて文句を垂れれば、彼はやはり上機嫌に笑ったのだった。