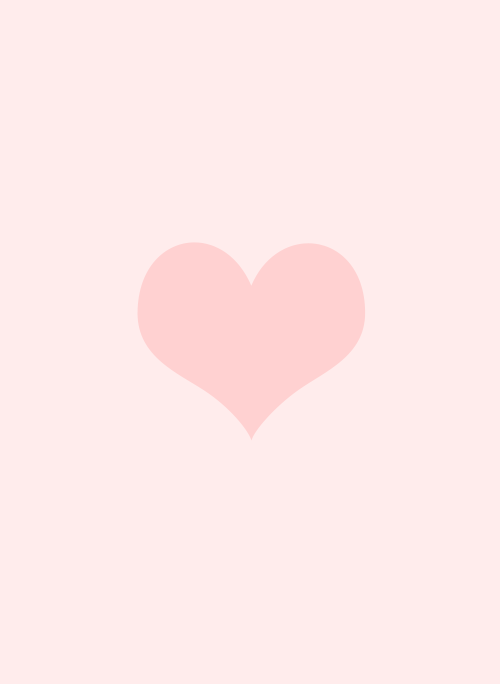答えのない朝
1
通い慣れた彼の部屋がある最寄駅で電車から降りる。
秋から冬に変わる季節は肌寒く、薄手の服を着て来たことを後悔した。
「あ、雨」
冷たい雨が頬を濡らした。
付き合いたての時は、彼が心配だからと駅まで迎えに来てくれたがここ最近はそれすらもなくなっている。
楽しかった時期は過ぎ去り、安定という名の惰性の日々を感じる。
きっと、それすらも幸せな事なのに、「慣れた」私は、それが許せなかった。
長い恋を引きずる彼に、同じく長い恋を募らせた私が言い寄るような形で始まった関係だというのに。
付き合い。大切にされる事になれた私は、軽く扱われる事に今もなれない。
最近では身体を繋げるためだけに部屋に呼び出される事ばかりだ。
「付き合わなきゃよかったんだ」
身体だけの関係なら今のままでも、私は幸せでいられたと思う。
彼は誠実で優しくて真面目で、許してはくれなかった。
あの時は嬉しくて仕方なかったけれど、今はそれが苦しい。
始まりがあれば終わりは必ず来て、始まりがなければ終わりはずっと来ない。
「久しぶり」
部屋の呼び鈴を鳴らすと、彼が部屋のドアを開けてくれた。
笑うことすらなく無表情だ。
本当は知ってる。彼の長い恋の相手が最近失恋していることを、私という存在が煩わしくて仕方ないことを、優しいからこそ何も言えずにいることを。
それも今日で終わりだ。
彼には新しい季節を迎えさせてあげたい。私なんかではなく、長い月日を恋した人と。
「少し濡れてるね。シャワー浴びて来たら?」
彼は私の肩が少しだけ濡れていた事に気がついたようだ。
好きでもない女なのに、よく気がつくものだ。
「行く前に浴びて来たから大丈夫」
苦笑い混じりにそう答えると、彼の目が細められた。
欲にまみれた目は濁っている。
「そっか、じゃあ脱いでよ」
「うん」
私は恥じらいすらなく、言われるままに服を脱ぎ捨てて、彼のベッドの上に横たわる。
目頭が熱くなるのを感じながら彼に目線を向けると、乱雑に服を脱ぎ捨てて私の上にのしかかって来た。
「んっ」
噛み付くように唇を塞がれる。
口付けをしているというのに、甘さなどあったものではない。
熱く濡れた舌が唇の中に入り込むと、これからの行為の予行演習かのように乱雑にかき混ぜられた。
身体を繋げる事に慣れなかった時は、素肌を見せることすら恥ずかしくて、優しい言葉をかけられながら、もどかしいほどにゆっくりと一枚一枚服を脱がされていた。
もう、そんなことすらないのだけれど。
唇が離れると、透明な蜘蛛の糸が伸びてふつりと切れた。
「……」
欲にまみれた濁った目で彼は私を見据える。
「ねえ、脚を開いて」
「んっ」
言われるままに脚を広げると、彼の目が鈍く光る。
彼はきっと、長い恋の相手にはこんなことを言わない。私にだけだ。
でも、私にだけの特別だなんて思いはしない。彼は獣のように身体を繋げて欲を吐き出す事しか考えていないのだから。
私ではない。別の誰かにも同じことを言うのだろう。
「あっ、んっ」
息づく場所に指先で触れられて、期待でそこはすでに濡れていた。
「濡れてきた。ここ、舐められるの好きだよね」
陰核に舌が絡みつき、長い指が蜜壺の蜜を掻き出すように蠢く。
「あっ」
私の身体を手にとるようによく理解している彼は、私をすぐに追い詰める。
「あぁっ!あぁ」
呆気なく絶頂を迎えた私は、もう、何も考えられなくなる。
教え込まれた快楽を振り払う術を私は知らない。
「もっと、触って」
幼子のような高く甘えた声で強請ると、彼は含み笑いを浮かべる。
「いいの?そんな事言って」
「うん、いいの」
視界が暗くなり私は目を閉じる。
「あぁっ、やっ」
また、絶頂を迎えて頭がぼんやりとする。
陰核は、痛みを伴うほどに痺れている。彼の剛直を受け入れているそこは、潤滑油のように愛液を溢れさせていた。
今は獣のように四つん這いになり彼を受け入れている。
彼が陰茎を押し込むたびに、尻を打たれたような痛みが走る。
獣のように、というよりも、獣のそのものだ。
「やだ、もう出来ないよ」
グズグズと泣き言を言うと、彼は苛立ったように舌打ちをした。
「焚き付けておいて泣くとかタチが悪いよ」
ガツンと骨が当たるように強く腰を打ち付けられると、私の意識がぼやける。
「あっ、あぁ!」
痛烈な快楽の終わりは、心地よい微睡を伴う。
「まだ寝るな」
彼の咎める声を聞きながら、私の意識は濁った色の雨空の夜に包まれた。
「……」
目が覚めると、外は薄明るい。
雨は降っていないようだ。
きっと、空は晴れていて私の気分とは真逆なのだろう。
「……っ」
起き上がると体が軋むように痛い。
ベッドに背を向けて眠る彼に気づかれないように、そっと起き上がる。
痛みに耐えながら服を身につけて向かう場所は一つだけ。
私の持ち物が置かれているスペースだ。
彼の別れを決めた日から少しずつ荷物を持ち帰っていた。
幸い彼は私のことなどどうでも良いようで、それに全く気がついていない様子だった。
「これで最後」
最後の荷物を手に取ると、私は立ち上がった。
彼が眠っている時に勝手に帰っても、もう、何も言われない。咎められることも。何も。
何の感情もないのだと嫌という程に思い知らされるのだ。
もう二度と会わないから。いまだけ。と、心に決めて、最後に彼の顔を見る。
この気安い関係に別れを告げられない彼は狡くて、そして、優しい。
傷つけまいとして言わない事が、かえって私を傷つけていると彼は知らない。
「最後に答えが欲しかった」
私は結局彼がどう思っているのかも知らずに身を引くのだ。
「さようなら」
頬にそっと別れの口付けを落とすと、彼の瞼がほのかに動いた気がした。