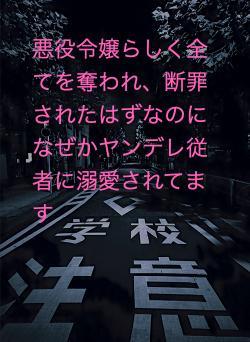義弟に婚約者を奪われ、悪女として断罪されましたがなぜか邪神に溺愛されハッピーエンド?を迎えることになりました🐍
32.邪神は唯一の存在を手に入れた
目を覚ますと、そこは一面の花畑だった。
「・・・・ここは?」
「目を覚ました、フィオナ」
「クロヴィス?」
私は草原の上でクロヴィスに膝枕をされた状態で寝ていた。
「気分はどう?」
「なんだか、とても穏やかな感じ。こんなに心が穏やかになったのは久しぶりね」
さらりと彼の細くて、長い指が私の前髪をすく。相変わらず、体温を感じさせない手だ。
「ここには君を煩わせる者も、害する者もいないからね。だから、これからは俺だけのことを考えて過ごしてね。フィオナ」
それはお願いの体裁を装っているが、一切の拒絶を許さない命令に近いものだった。
そんなことをしなくても、クロヴィス以外のことを考えるつもりなんてないのに。彼は初めて会った時から変わらない。相変わらずの嫉妬深さに私は苦笑した。
「そうだ!ねぇ、君の家族やお友達、婚約者がどうなったか知りたい?」
「・・・・興味ないわ」
「全く?」
「ええ。もう、私には関係のないことだもの。あなた以外のことを考えるのは億劫だし、頭の隅にすら残しておきたくないわ」
私がそう言うと彼は笑みを深めて、腰を曲げる。徐々に近づいてくる顔に何をされるのかを悟った私は静かにその行為を受け入れた。
何度か啄むような口付けをした後、クロヴィスの手が私のスカートの中に入ってくる。死人のように冷たい手が私の太ももと優しく撫でる。もどかしい感覚に足を擦り合わせるとクロヴィスは分かっていると言わんばかりにキスを深めた。
深く、長いキスで意識が朦朧としていると急に景色が変わり、部屋の中に移動していた。
私はベッドの上で仰向けの状態になっている。クロヴィスは私の体を両足で挟み、膝立ちの体勢で私を見下ろす。
「もう、戻れないよ」と私を放す気もないのに、クロヴィスは確認するように言ってくる。
彼は私とこの先の行為をここでしようとしているのだ。彼は人ではない。世間の人々が畏れ、忌み嫌う存在・・・・邪神。彼と繋がるということは私も人間ではなくなるということ。
私は自分の手を見る。
黒い蛇の紋様が肩まで刻まれていた。これは「所有印」だとクロヴィスが教えてくれた。これがあれば、私がどこにいるのかが分かるそうだ。
彼に私を逃す気はない。そして私も彼の元から逃げる気はない。元の世界に未練はない。
「初めて会った時から、幼い頃、庭であなたに会ったあの時から私はあなたのモノよ」
ニヤリとクロヴィスは笑う。彼の目はまるで獲物を見つけたこのようにギラギラと鋭くなる。少しだけ怖い。でも、愛しい。
「私を完全にあなたのモノにして。二人、溶け合うまで愛し合いましょう」
求めるように手を伸ばすと彼は私を抱きしめてくれた。すると、なぜか何もしていないのに私と彼の着ていた服が消滅した。
触れ合う地肌は冷たく、生者の気配が全くない。この体温の低さは彼が人でないことの証。
「境目が分からなくなるまで、溶け合い、一つになろう」
そう言ってクロヴィスは私を抱いた。言葉通り、本当に体がクロヴィスと融合してしまったんじゃないかと思うほど、深く、そして執拗に彼は私を愛した。まるで今まで一緒にいられなかった時間を埋めるように。
◇◇◇
目を覚ますと私を大きな黒い蛇が抱きしめるように眠っていた。これがクロヴィスの本当の姿。だからなのか、怖くはない。
クロヴィスの蛇体に抱かれた状態で私は窓の外を見る。外は真っ暗だ。これは時間が遅いからではない。
ここはクロヴィスが作り出した私と彼のための”巣”だ。そのため、ここでは時間の流れがない。クロヴィスが昼間のような明るさを望めばそうなるし、夜のような暗さを望めば夜になる。
『どうした?』
蛇の姿の時は、声が直接脳に響く。蛇の体内構造と人間の体内構造は違うため、蛇体の時は声を発することができないからだ。
「眼が覚めてしまって」
『起きるなら昼間にするぞ』
「ううん。夜のままでいい」
「ならば、夜の散歩をしよう」
クロヴィスは人の姿を取る。そして「夜のデートをしよう」と少年のような無邪気な顔をしながら私に手を差し出す。
「なんだか、ロマンチックね」
屋敷の敷地内でも貴族令嬢は基本的に、夜に外に出ることはない。だから、恋人と夜間外出なんて背徳的でドキドキする。
「夜の庭って、少し不気味なのね」
「スリルがあっていいでしょう」
薔薇の生垣で作った迷路。その横を進む噴水がある。少し先にはガゼボがある。
音が何もない。人の気配もない。だから夜は不気味なのかもしれない。もっとも、ここはクロヴィスが作った巣なので私たち以外の生き物は存在しない。
夜の庭を堪能しているとクロヴィスが後ろから抱きついてきた。
「んっ」
どうしたのかと視線を向けようとするとクロヴィスが私の胸に触れてきた。
「月明かりに照らされながらってのもいいね」
「・・・・・ここは外よ」
「俺たち以外、誰もいないからいいじゃん」
「そういう問題じゃないでしょう」
「そう言う問題だよ。それに、蛇の交尾って三日間繋がりっぱなしなんだよ」
それは初耳だ。私には到底できない行為だ。いやと言うわけではない。体力的な問題だ。それにいくら蛇の化身だからといって邪神を普通の蛇の枠に当てはめて考えてもいいのだろうか。
「もちろん、俺は邪神で普通の蛇とは違うから、それ以上の期間を要するけどね」
「・・・・・」
にっこりと笑いながらとんでもないことをぶち込んできた。
「・・・・・クロヴィス」
「大丈夫だよ」
「無理だ」と言おうとしたら先回りをするようにクロヴィスは言う。
「フィオナの体は邪神の番として作り変えているから。それに一度繋がったでしょう。ここで俺の精を受け止められたということは、人間じゃなくなっているということ」
「でないと、俺の毒に当てられて死ぬからね」と何やらボソボソ言っているけどよく聞き取れなかった。
クロヴィスは聞き返そうとする私の下腹部を撫でる。
「俺のをたくさん、受け止めてくれるでしょう」
・・・・・圧がすごい。
あと、そんな恥ずかしいことを平然と言わないでほしい。恥ずかしくて、茹蛸になりそう。
「きゃっ」
クロヴィスが真っ赤になった私の耳を口に咥えて、はむりだした。彼はここで本当にする気なのだ。
「クロヴィスせめて、部屋の中で」
「じゃあ、あそこの温室でしようか。そこにもベッドはあるから」
・・・・・なぜ?
いや、突っ込むのはやめておこう。
外でするよりはマシだ。観念した私をクロヴィスは嬉しそうに見つめる。
「たくさん、たくさん、愛し合おうね。二人、溶けてなくなるまで」
・・・・・小休憩時間は何とか確保できるように交渉しておかないと。
「・・・・ここは?」
「目を覚ました、フィオナ」
「クロヴィス?」
私は草原の上でクロヴィスに膝枕をされた状態で寝ていた。
「気分はどう?」
「なんだか、とても穏やかな感じ。こんなに心が穏やかになったのは久しぶりね」
さらりと彼の細くて、長い指が私の前髪をすく。相変わらず、体温を感じさせない手だ。
「ここには君を煩わせる者も、害する者もいないからね。だから、これからは俺だけのことを考えて過ごしてね。フィオナ」
それはお願いの体裁を装っているが、一切の拒絶を許さない命令に近いものだった。
そんなことをしなくても、クロヴィス以外のことを考えるつもりなんてないのに。彼は初めて会った時から変わらない。相変わらずの嫉妬深さに私は苦笑した。
「そうだ!ねぇ、君の家族やお友達、婚約者がどうなったか知りたい?」
「・・・・興味ないわ」
「全く?」
「ええ。もう、私には関係のないことだもの。あなた以外のことを考えるのは億劫だし、頭の隅にすら残しておきたくないわ」
私がそう言うと彼は笑みを深めて、腰を曲げる。徐々に近づいてくる顔に何をされるのかを悟った私は静かにその行為を受け入れた。
何度か啄むような口付けをした後、クロヴィスの手が私のスカートの中に入ってくる。死人のように冷たい手が私の太ももと優しく撫でる。もどかしい感覚に足を擦り合わせるとクロヴィスは分かっていると言わんばかりにキスを深めた。
深く、長いキスで意識が朦朧としていると急に景色が変わり、部屋の中に移動していた。
私はベッドの上で仰向けの状態になっている。クロヴィスは私の体を両足で挟み、膝立ちの体勢で私を見下ろす。
「もう、戻れないよ」と私を放す気もないのに、クロヴィスは確認するように言ってくる。
彼は私とこの先の行為をここでしようとしているのだ。彼は人ではない。世間の人々が畏れ、忌み嫌う存在・・・・邪神。彼と繋がるということは私も人間ではなくなるということ。
私は自分の手を見る。
黒い蛇の紋様が肩まで刻まれていた。これは「所有印」だとクロヴィスが教えてくれた。これがあれば、私がどこにいるのかが分かるそうだ。
彼に私を逃す気はない。そして私も彼の元から逃げる気はない。元の世界に未練はない。
「初めて会った時から、幼い頃、庭であなたに会ったあの時から私はあなたのモノよ」
ニヤリとクロヴィスは笑う。彼の目はまるで獲物を見つけたこのようにギラギラと鋭くなる。少しだけ怖い。でも、愛しい。
「私を完全にあなたのモノにして。二人、溶け合うまで愛し合いましょう」
求めるように手を伸ばすと彼は私を抱きしめてくれた。すると、なぜか何もしていないのに私と彼の着ていた服が消滅した。
触れ合う地肌は冷たく、生者の気配が全くない。この体温の低さは彼が人でないことの証。
「境目が分からなくなるまで、溶け合い、一つになろう」
そう言ってクロヴィスは私を抱いた。言葉通り、本当に体がクロヴィスと融合してしまったんじゃないかと思うほど、深く、そして執拗に彼は私を愛した。まるで今まで一緒にいられなかった時間を埋めるように。
◇◇◇
目を覚ますと私を大きな黒い蛇が抱きしめるように眠っていた。これがクロヴィスの本当の姿。だからなのか、怖くはない。
クロヴィスの蛇体に抱かれた状態で私は窓の外を見る。外は真っ暗だ。これは時間が遅いからではない。
ここはクロヴィスが作り出した私と彼のための”巣”だ。そのため、ここでは時間の流れがない。クロヴィスが昼間のような明るさを望めばそうなるし、夜のような暗さを望めば夜になる。
『どうした?』
蛇の姿の時は、声が直接脳に響く。蛇の体内構造と人間の体内構造は違うため、蛇体の時は声を発することができないからだ。
「眼が覚めてしまって」
『起きるなら昼間にするぞ』
「ううん。夜のままでいい」
「ならば、夜の散歩をしよう」
クロヴィスは人の姿を取る。そして「夜のデートをしよう」と少年のような無邪気な顔をしながら私に手を差し出す。
「なんだか、ロマンチックね」
屋敷の敷地内でも貴族令嬢は基本的に、夜に外に出ることはない。だから、恋人と夜間外出なんて背徳的でドキドキする。
「夜の庭って、少し不気味なのね」
「スリルがあっていいでしょう」
薔薇の生垣で作った迷路。その横を進む噴水がある。少し先にはガゼボがある。
音が何もない。人の気配もない。だから夜は不気味なのかもしれない。もっとも、ここはクロヴィスが作った巣なので私たち以外の生き物は存在しない。
夜の庭を堪能しているとクロヴィスが後ろから抱きついてきた。
「んっ」
どうしたのかと視線を向けようとするとクロヴィスが私の胸に触れてきた。
「月明かりに照らされながらってのもいいね」
「・・・・・ここは外よ」
「俺たち以外、誰もいないからいいじゃん」
「そういう問題じゃないでしょう」
「そう言う問題だよ。それに、蛇の交尾って三日間繋がりっぱなしなんだよ」
それは初耳だ。私には到底できない行為だ。いやと言うわけではない。体力的な問題だ。それにいくら蛇の化身だからといって邪神を普通の蛇の枠に当てはめて考えてもいいのだろうか。
「もちろん、俺は邪神で普通の蛇とは違うから、それ以上の期間を要するけどね」
「・・・・・」
にっこりと笑いながらとんでもないことをぶち込んできた。
「・・・・・クロヴィス」
「大丈夫だよ」
「無理だ」と言おうとしたら先回りをするようにクロヴィスは言う。
「フィオナの体は邪神の番として作り変えているから。それに一度繋がったでしょう。ここで俺の精を受け止められたということは、人間じゃなくなっているということ」
「でないと、俺の毒に当てられて死ぬからね」と何やらボソボソ言っているけどよく聞き取れなかった。
クロヴィスは聞き返そうとする私の下腹部を撫でる。
「俺のをたくさん、受け止めてくれるでしょう」
・・・・・圧がすごい。
あと、そんな恥ずかしいことを平然と言わないでほしい。恥ずかしくて、茹蛸になりそう。
「きゃっ」
クロヴィスが真っ赤になった私の耳を口に咥えて、はむりだした。彼はここで本当にする気なのだ。
「クロヴィスせめて、部屋の中で」
「じゃあ、あそこの温室でしようか。そこにもベッドはあるから」
・・・・・なぜ?
いや、突っ込むのはやめておこう。
外でするよりはマシだ。観念した私をクロヴィスは嬉しそうに見つめる。
「たくさん、たくさん、愛し合おうね。二人、溶けてなくなるまで」
・・・・・小休憩時間は何とか確保できるように交渉しておかないと。